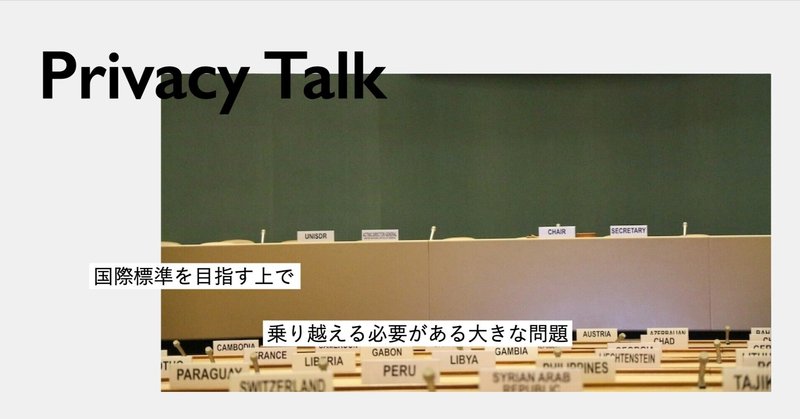
国際標準を目指す上で乗り越える必要がある大きな問題
※このインタビューは2024年3月20日に収録されました
今では当たり前のソーシャルメディアも、インターネット初期にはプライバシーに配慮した機能を前提に開発されていました。
今回はインターネット初期から様々なサービスを展開し、ソーシャルメディアの走りとなるデルファイインターネットサービスを開発したヴェスさんに、ソーシャルメディアの歴史とインフラの重要性についてお伺いしました。

前回の記事より
デルファイと呼ばれるプロジェクトの立ち上げに関わっていたと思うのですが、そのプロジェクトについても教えていただけませんか?
デジタル空間に生み出された世界初の百科事典
Wes: デルファイはデジタル空間の百科事典をコンセプトとして設計されました。ただ、百科事典のビジネスモデルはあまり上手く機能しませんでしたね。デルファイを開発したのが1981年で、当時は親が子供にコンピューター教育を行うことを好ましく思わない時期でもありました。
ただ、コンピューター教育は非常に人気で、誰でも2つはコンピューターに関連したコースを取得していました。
私たちが開発した百科事典はパーソナルコンピューターでの利用を推奨していました。主にApple2かTandy Color Computer(RadioShack Tandy Color Computerも含まれます)を選択することが多く、サポートも充実していました。
(動画:The Story of the Tandy Color Computer 2 - Tandy Lab #septandy)
ただサポートを充実させた分、電話での問い合わせが一気に増えてしまいました。
開発当初はコンピューターについて学びたい親御さんとその子供を対象としていたので、サポートを充実させることで利用者を増やしていくことを考えていましたが、これがビジネスモデル上の大きな課題になりました。
そこで、我々がサポートするよりもソーシャル機能を加えて相互にサポートし合う関係性が作れないかと思い、問い合わせ方法としてメールを準備したり、掲示板やフォーラム機能を導入するようになりました。
関心がある人のコミュニティ(SIGs)も機能に加えたりして、参加者がそれぞれオープンに繋がり合える場所を設計したりもしました。
こういったソーシャル性を持った機能を実装することで、デジタル上の百科事典は紙の百科事典同様に知見を共有する場へと変化していきました。利用者は安くはない金額で事典を購入し、数ヶ月は頻繁に利用する人たちも出てきました。

ただ、紙の事典と同じく徐々にオンライン百科事典の閲覧者も減っていきました。気づけば、ソーシャル機能だけが残り、オンライン上でのセッションが非常に活発になっていきました。
1982年の初めには、ビジネス機能を搭載したのですが、百科事典の機能よりもソーシャル機能の方がビジネス的には上手く活躍することになりました。
当時はソーシャルネットワークやソーシャルメディアという言葉すら誕生していませんでした。ただ、私たちが偶然提供していた機能が、今のソーシャルメディアの持っている価値と合致していたのです。そういった背景から、ソーシャルメディアがビジネス化していくことになります。
雑誌を中心にしたオンライン上のファンコミュニティ
私たちのビジネスが大きく拡大していった理由に、雑誌社とのパートナーシップ連携があります。特にコンピューターに特化した趣味の雑誌が人気でした。Tandy利用者向けの雑誌やAtari利用者向けの雑誌が我々に協力してくれていました。
私たちは両雑誌を好む人たちのグループを特別に作成して、デルファイ上で小さなコミュニティを作っていました。雑誌を出版する企業からすると、自分たちの雑誌の読者と広告主が同じグループで活動しているのを一度に見ることになったんだと思います。
ただ、Atari利用者も日常の全ての時間をAtariに使うわけでなかったので、多くの利用者は Atariを出版する会社のスタッフが占めていました。
他にもデルファイ内で特定の興味に限定したグループを広く作成していました。グループが沢山できてくると、利用者も新しい発見があったのではないかと思います。
その中でも雑誌に関するグループは非常に多くの方が参加していました。このようにコミュニティが拡大しつつも、どのようにビジネスを構築していけば良いかをなかなか掴めていませんでした。
私たちのグループが徐々に大きくなっていく実感はあったものの、ビジネス上上手く回っているかどうかはわかりませんでした。
そこでGroup Linkという雑誌社が独自のプライベートネットワークを作成できるような機能を準備したのです。雑誌社は独自のサーバーを私たちのテクノロジーとソフトウェアを利用して作ることができるようになりました。
そして、1987年に私たちがグローバルビレッジと呼ばれる企業として独立した際に、Group Linkのサービスはビジネスとして組み込まれるようになりました。
Kohei: とても面白いお話ですね。ありがとうございます。デルファイに関わった後に、ヴェスさんは国際電気通信連合(ITU)で国際的なプロジェクトに関わるようになったと伺っています。ITUでは “World e-trust initiative” に関わっていたと聞いていますが、こちらのプロジェクトについてお伺いしてもよろしいでしょうか?
国際標準を目指す上で乗り越える必要がある大きな問題
Wes: わかりました。プロジェクトに関わるまでに、私はスイスのジュネーブに行ったことはありませんでした。プロジェクトに関わり始めてからも、自宅から参加していましたね。私はここでの経験を書籍にも書いているのですが、プロジェクトでの経験を通してオンライン空間でプライバシーと匿名性を保証したPKIアイデンティティ認証を導入することの重要性を理解しました。
ITUでは “E-trust for commerce” と呼ばれるプロジェクトには、世界中で開発途上の商取引を発展させるために関わっていました。私は利用者サイドの視点からプロジェクトに関わり、当時の同僚であるハマドゥン・トゥーレ氏(後のITU事務総局長)とアレクサンダー・ニトコ氏(後のITU企画部運営長)がビジネスサイドから関わっていました。2004年後半から、2005年初頭にかけて “World e-trust initiative” が発表されることになりました。
ただ、ITUに参画する多くの国からは “World e-trust initiative” へ非協力的な意見が多く寄せられました。多くの国は自国の証明書認証機関を使っていたことが理由でしょうね。彼らからすれば自国のPKIこそが、自らのPKIであるということです。
さらに “World e-trust initiative” では、各国の証明書認証機関が “World e-trust initiative” の下で機能する仕組みになります。これでは、各国の主権が上手く働かないという意図があったのだと思います。

もう一つお伝えしたいことがあります。私が数年前の国連情報社会世界サミットで話をする機会があったのですが、そのサミットには “World e-trust initiative” を廃止するように働きかけた方も参加されていたみたいです。
トゥーレ氏とニトコ氏はどうにか続けたいと思っていたみたいですが、残念ながらこのプロジェクトは廃止されることを余儀なくされました。現在はオスミオシティという名前に変わり、私がプロジェクトを担当しています。
ここからは余談です。先程プロジェクト廃止を働きかけた方がいると話をしたと思いますが、私が国連でお話しした後に直接コンタクトをとる機会がありまして、「インターネットが初めて誕生した際に、私たちの主権が奪われる恐れがあることに気が付いたんだ」と教えてくれました。実際には、そうではないのですが。
私たちはこれまでに主権が奪われることについて公表することはありませんでした。ITUの“World e-trust initiative” に対しては皆がそう思っていたのかもしれません。他の同僚とも話をする機会がありましたが、何か折り合いをつける必要があったのかもしれませんね。
別の言葉で表現すると、ITUの取り組みが主権を脅かすものになる可能性があったのです。各国の主権というのは、インターネット上のコミュニケーションによって大きく左右されることになるのです。ITUがどういった背景で設立されたかはご存知ですか?
実は最も古い国際的なガバナンスを定義する組織で、1865年に設立されています。
(動画:ITU The first 150 years)
なぜITUが設立されたのかを紐解いて考えると、いくつかの国が暗号化通信に脅威を感じたことが発端になっています。特定の国が、自分たちの領域の外で暗号化通信を行うことへの懸念があったのです。暗号化通信が当たり前になれば、対象国以外が通信内容を解読することができなくなります。
1865年から積み重ねられてきた議論は、各国が簡易に通信できる環境を恐れていたことに関連しています。ITUではインターネットの標準に準拠したIRC(International Record Carrier)と呼ばれる法があることをご存知ですか?ライセンスを発行された各国の参加者が国を越えてテキスト通信を行うためのルールとして定められたものです。
この通信を行うためにはPRCライセンスを取得しなければなりません。現在このライセンスが廃止されたのかはわかりませんが、私がデルファイを開発した当初は取得する必要がありました。当時は私たち以外にはあまりこのライセンスについて詳しい人がいませんでした。
インターネット誕生初期は、簡単に通信ができるような設計が準備されていたのです。ただ各国は通信や暗号化、情報検索を容易に実現できる環境が自国の主権を脅かすことを恐れていました。私から明確な解はないのですが、各国が懸念を示していたのはそうだと思います。
Kohei: ヴェスさんのご経験を教えてくださりありがとうございます。これまでITUの歴史や考え方については聞いたことがなかったので、非常に興味深く面白いお話しですね。ヴェスさんのご経験を通して、非常に現実的な立ち位置が理解できました。
ここからは次の質問に移りたいと思います。ヴェスさんが別の方とのインタビューで「インターネットが壊れてしまった」とお話しされていたのがとても印象的でした。
1980年代からインターネットを見られてきたヴェスさんに、当日のお話も伺ってみたいと思います。インターネット初期から今までに、インターネットはどのように変化してきたのでしょうか?
ヴェスさんがインターネットに関わり始めた1980年代のお話しについてもお伺いさせてください。
〈最後までご覧いただき、ありがとうございました。続きの後編は、次回お届けします。〉
データプライバシーに関するトレンドや今後の動きが気になる方は、Facebookで気軽にメッセージ頂ければお答えさせて頂きます!
プライバシーについて語るコミュニティを運営しています。
ご興味ある方はぜひご参加ください。
Interviewer, Translation and Edit 栗原宏平
Headline Image template author 山下夏姫
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
