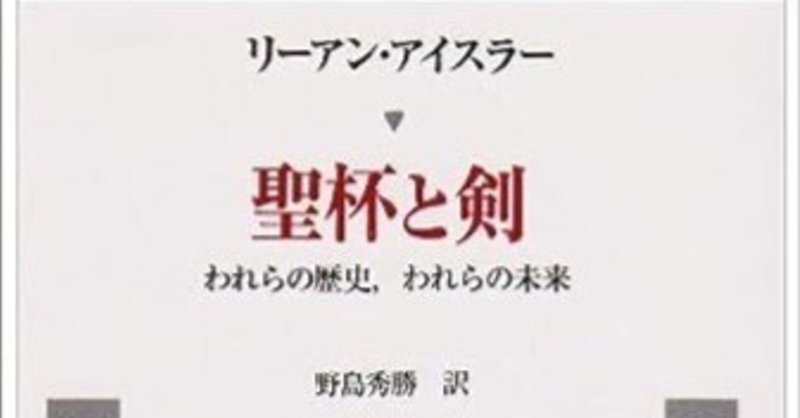
阿波と東国❸ 杯から剣へ
さて、今回は千葉を代表する神社、香取神宮の核心に迫ってみたいと思います。
前回の記事で香取神宮で祀られている経津主とは、
忌部系図にある由布津主と飯長媛夫妻だと考察しました。
忌部系図はこちらです。

経津主の別名はイワイヌシ(斎主)です。そして忌部系図では飯長媛に斎主が付いています。
斎主とは神を斎い祭る人で、祭祀を主宰する人のことです。
なので経津主=イワイヌシ(斎主)であるならば、
経津主=イワイヌシ(斎主)が祭祀をする別の神が香取神宮にいたことになります。つまり現在の主祭神より以前に存在した香取の神です。
それは誰なのか?
僕はそのヒントが阿波にあると思っています。
香取神宮の第一摂社に側高神社という社があります。
ここは非常にマイナーな神社ですが、よく手入れされ、境内にも荘厳な雰囲気の漂う、僕の大好きな神社です。
神社の伝承に干珠・満珠のような話があったり、髭撫祭という奇祭があったり、興味深い点はいくつかありますが、なかでも注目なのは、その御祭神です。
こちらに祀られる神は「言わず語らずの神」として、口外を戒められています。
しかしながら秘されると人は探りたくなるものというのが世の常で、その結果、いくつかの説が流れるようになりました。
まず大正10年発行の香取郡誌によると、
主祭神=高皇産霊尊・神皇産霊尊
相殿神=天日鷲命・経津主命・天児屋根命・武甕槌命・姫御神
阿波忌部の祖、天日鷲が入っています。
そして明治25年に香取神宮より発行された香取神宮小史によると、
祭神:側高神(= 経津主神ノ后神)
香取神宮の見解では経津主の妻ということになります。
忌部系図だと飯長媛に該当します。
香取郡誌の相殿神を見るとわかりますが、この並びは天日鷲を除くと
春日四神です。つまり「藤原氏」の氏神ですね。
この側高神社の祭神が秘匿とされた理由には、藤原氏の影響があると僕は見ています。藤原氏にとって都合の悪い神だったから神社側も時の朝廷に忖度して口外を慎んだ。
こういう経緯なのではないでしょうか?
相殿神にある天日鷲と春日四神
本当は阿波忌部系の神を祀っていたのに香取神宮の宮司家に藤原氏が入るようになると、元の神である主祭神は口外を憚られるようになり、春日四神が相殿神につけ加えられた。
僕はそう考察しています。
一般的な歴史認識では香取の神、経津主は物部氏の神とされています。
この物部氏も祖である伊香色雄を通じて阿波忌部と非常に繋がりの深い氏族なのですが、香取宮司家を代々世襲している香取氏はもともとこの物部の系統でした。
そして物部系香取氏直系で続いてきたこの系譜にある時、中臣氏から養子が入ります。下記に系図を記載します。

香取宮司家として代々続いてきた香取氏は五百島(いおしま)の代で中臣氏から養子を迎え入れます。以降、性を香取から中臣朝臣に改めます。
※この流れは鹿島神宮でも同様に起こり、鹿島香取の藤原氏による支配権が確立していきます。
僕はこの香取宮司家の変化が側高神社の祭神を秘匿にさせたのだろうと考えています。
側高神社は相殿神に春日四神と天日鷲を祀っています。であるなら本来の祭神は阿波忌部系の神のはずです。そして香取神宮小史による香取神宮の見解は経津主の妻、つまり女神だと言っています。
僕は経津主の妻であるとは思っていませんが、女神だということには賛同します。
つまり側高神社の本当の祭神は古来より阿波忌部が崇めた女神だと。
そしてその神は香取神宮で古来より斎主が崇めた神と同一なのではないかと考察します。
僕は生まれが東国三社のお膝元であり、鹿島香取、両神宮とも幼い頃から非常に馴染み深い神社でした。
でもなぜか両神宮とも武神であるという伝承に、とてつもない違和感を覚えたのです。その頃は古代史の知識もなく、ただ感覚として感じただけです。僕が古代史を調べるきっかけになったのは、その違和感を払拭するためです。
両神宮の歴史に途中から中臣氏が入り込み、時の朝廷に合わせてその性格を変化させていった痕跡を見つけるたびに僕は喜びました。
封印されてしまった神々の手がかりを探ることが僕の古代史研究の目的です。
封印はいつか解かれるからです。
歴史は勝者が創るものという万国共通の格言があります。通常、世界の権力者たちは過去の信仰を跡形もなく消し去ります。自分たちの王政にとって邪魔でしかないからです。過去を消し、自分たちの歴史を新たに構築していくのです。これは世界中、共通してみられる歴史の流れといえます。
しかしそれが当てはまらない国があります。それがこの島です。この島で実権を握った歴代の覇者たちは、過去の歴史を封印さえすれど、決して抹消はしない。僕はそう思えてなりません。必ずどこかにヒントを残す。そんな気がしてなりません。
僕は神社を記憶の保存庫と呼んでいます。しめ縄が示す遺伝子の形はその最たるもので、記憶を繋げるために存在してると思います。神社の座す場所、そしてその祭神は王族の移り変わりを現代に伝えます。
世界史を見ても過去の王宮は必ずといっていいほど破壊されます。しかしこの島では残すんです。祭神や伝承は変えたとしても、その場所だけは残すんです。
まるでいつか封印がとかれる日がくることを予期しているかのように。
僕はその場所に残ったわずかな痕跡を頼りに本当の歴史を探ります。
封印が解かれる日がもう間近に迫っているということを、遺伝子が感じるからです。
幼い頃に感じた鹿島香取、両神宮が武神であるという伝承に対する違和感。
それはある書物を読んだ時、確信に変わりました。
鹿島神宮元宮司 東実氏著『鹿島神宮』という本です。
その中で東実氏は古来、鹿島神宮の御神体とは鹿島の海底に沈んだ大甕であったと記述しています。そしてその大甕は豊前から来たと。
この内容は以前の記事「秘された歴史 茨城という茨の城❷」でも触れましたが、この甕神信仰は九州から多氏が持ち込んだ信仰で多氏とは古事記を編纂した太安麻呂を輩出した古代史族です。
つまり太古の昔、鹿島は甕神を信仰していたことになります。
祭神名も武甕槌といい、甕神の名残が残っています。
僕はこの甕神でありまた武神でもあるという矛盾に、とてつもない違和感を覚えたのです。
まず甕神の甕とは物を入れる器です。世界各地にある聖杯伝説を見てもわかる通り、器とは女性性をあらわします。一説では女性の子宮を象徴しているともされますね。多産や豊穣を意味する女性原理の神と、武神という破壊や支配を意味する男性原理の神が同居する武甕槌。この同一性を欠いた神格に僕はどうしようもない違和感を覚えたのだろうと思います。
そして通説では聖杯信仰が人類における信仰の起源により近いとされています。
リーアン・アイスラーは、その著書『聖杯と剣』(1987年)のなかで、人類が最初に作った道具は剣ではなくて杯であること、杯が象徴する、命を養い、育てる女性原理が、その後の歴史の中で、支配し、奪取する男性原理に取って代わられたのだと説きます。
この島でもそうですね。神武誕生以前、この島には縄文文明が長い間文化を形成してきました。縄文人はとんでもない数の縄文土器という聖杯を各地で作り続けました。
つまり剣ではなくて杯です。そして同時期に作られた縄文土偶もそのほとんどが女性です。縄文の歴史とは女神を信仰する女性原理の世界でした。つまり支配や略奪ではなく多産と豊穣を崇めたのです。
この話はそのまま鹿島神宮の歴史に当てはめることができます。
つまりリーアン・アイスラーが記したように、太古から信仰されていた女性原理が、その後の歴史の中で、支配し、奪取する男性原理に取って代わられた。
そしてその男性原理を鹿島神宮に持ち込んだのが、中臣鎌足をはじめとするのちの藤原氏だと考察します。
では中臣・藤原の系譜はどの武神の神格を持って鹿島香取の神を武神に変更したのでしょう。僕はその武神のモデルとなった神も阿波に存在すると考察します。
阿波市市場町香美郷に建布都神社という神社があります。ここももちろん式内社です。その主祭神は建布都神とされ、阿波の出雲平定で活躍する武神です。これは鹿島の神、武甕槌の別名とされています。しかしこの建布都神には経津主の名前も入っています。経津主は別表記で布都怒志とも書かれます。
つまり中臣・藤原の系譜はこの阿波のタケフツという武神の神格を2つに分け、
鹿島の「タケ」ミカヅチ、香取の「フツ」ヌシを武神にすり替えたと。
もともと1人だった神を2人に分けているとすれば、古事記に経津主が登場しない理由も納得できます。
つまり実際に出雲の国譲りが阿波で行われた時代には、建布都神しか存在していなく、実際国譲りで活躍したのも建布都1人であったと僕は考察します。そしてそれはあくまで阿波での話であって、鹿島香取から武神が出向いたわけでは決してないということです。当時鹿島香取には建布都という武神とは何ら関わりのない、おそらくは女神が存在していたはずですから。
この歴史の流れは鹿島香取に限ったことではなく、全国に存在する縄文の聖地は、古来から続く女神信仰の女性原理をのちの時代に武神による男性原理で上書きされている。そう解釈していいと思います。
瀬織津姫、菊理媛、磐長姫、もっと言えば卑弥呼がそうです。記紀にはほとんど登場しない、しかし歴史においてとても重要な女神が日本には多く存在します。
この世界史における女性原理から男性原理へと上書きされていく神々の性格をもとに、側高神社の本当の祭神と香取神宮で古来より斎主が崇めた本来の神を考察していきたいと思います。ここまでの話の流れでいけばそれは当然女神となるはずです。
千葉の開拓には阿波忌部が関わっていることをこれまで説明してきました。だから秘匿とされる側高神社の神も斎主が崇めた香取神宮の神も阿波忌部が崇めた女神になるだろうというのが僕の考察です。
香取神宮には境内に奥宮と呼ばれる社があり、ここは経津主の荒御魂が祀られているとされていますが、僕はここに香取の本来の神が鎮座すると考えています。


香取神宮の中でもとびきり荘厳で、空気のピンと張り詰める聖域です。
ではここに祀られる阿波忌部の女神とは?
このまま進みたいところですが、長くなりましたので続きはまた次回に!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
