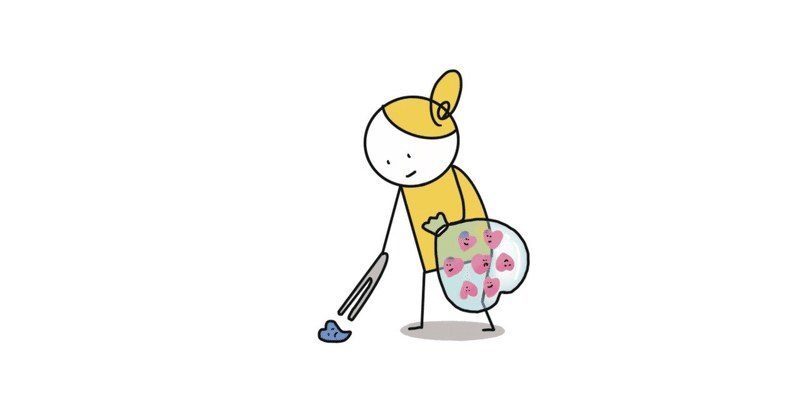
#268 当たり前をどう教えるか
当たり前にやってしまう
・ゴミが落ちていたら拾う
・大人を見かけたら元気にあいさつする
学級において、こんなことができたら素敵だなと思う行動を、当たり前にようにする子っていませんか?
「こんな行動を学級に広がったらいいなあ」と思い、学級で紹介することにします。
言葉で伝える難しさ
「今日ね、○○さんが階段ですっとゴミを拾っていたんだよ。
○○さん、なんでゴミを拾ったの?」
ここで、
「ゴミを拾うと学校がきれいになって気持ちがいいからです。」
と答えてくれるとありがたい。
でも、
「いや~、当たり前だから・・・」「ん~、いつもやってるから・・・」
となると、全体へ広げるのが難しくなってくる。
身体知と言語知
その場でそう行動するのが当たり前になっている状態を「身体知」と呼びます。もう身に付いている状態です。意識しなくてもできる行動ですね。
自転車の乗り方が分かりやすいと思います。一度乗れるようになると、意識しなくても当たり前にように乗れますよね。
一方で、言葉で説明できる知識を「言語知」と呼びます。
「ゴミを拾うと、学校がきれいになる。きれいな方が気持ちよく生活できる。」と言葉で説明することができます。
当たり前をどう教えるか?
さて、学級の場面に戻りましょう。
「いや~、当たり前だから・・・」
と答える子は、ごみを拾うことが、身体知として身に付いています。
身体知は個人のものなので、これを他人に伝えるためには、言語知に変換する必要があります。
T「そうか、当たり前に拾っているんだ。じゃあ、みんなは、ゴミを拾うことをどう思う?」
C「いいこと。」
T「なんで?」
C「学校をきれいにしているから。」「みんなのためになっているから。」
T「なるほどね。では、○○さんはみんなのためにやっているんだ?」
C「いや、みんなのためもあるけど、自分のためにもなっている。」
T「どういうこと?」
C「みんなのためになるとうれしいから。きっと、自分のためにもなっていると思う。」
続く・・・
当たり前を、子どもとのやりとりで言語化していきます。
「ゴミを拾うことは、みんなのためになる。そして、人のためになる行動すると自分もうれしい気持ちになれる。」
○○さんの「身体知」を学級全体で「言語知」にしました。
次は、実際に行動し、「うれしい」という気持ちを感じる必要があります。子どもたちは、頭ではわかっているけど、行動できないものです。(※大人も同じですね。)
そこで、実際に取組を促します。経験を積むことで、徐々に「身体知」になります。うまく「身体知」となった子は、その後は当たり前にように行動を続けることでしょう。
知っていることを経験させる
「言語知」で留まっていることを経験させ、「身体知」にする。
「身体知」で留まっていることを「言語化」し、価値付けする。
当たり前を身に付けさせるには、「言語知」と「身体知」を往還することが大切ですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
