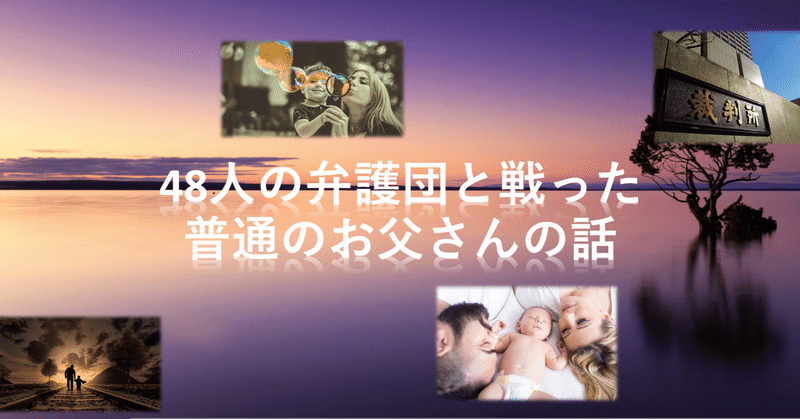
2 高等裁判所での抗告棄却
刑事告訴の再決意
前回までに執筆したとおり明らかに即時抗告の理由がなかったにも関わらず、新たに証拠を作成してまで起こされた即時抗告。もうこれをみて私はこういった考えの相手方弁護士が元妻についている限り、裁判での決着、引き渡しは不可能だろうと思い知りました。家事事件での解決が不可能であれば、刑事事件として告訴するしかありません。この抗告理由をみて私は、過去に散々門前払いにあった警察に刑事告訴をしに行くことを決意しました
詳細は別に執筆します。
※記事の準備中※
控訴理由書に書かれた誹謗中傷、嘘


このように相手方は明らかに事実と異なる印象操作を高等裁判所に対して主張をするようになりました。これには2つの大きな問題があると思っています。
1.同居期間において何の問題がなかったにも関わらず、それをことさらに虚偽主張で否定してみせること
2.子の連れ去り後に別居親との接触を極端に減らし、愛情の供給を妨げ、疎遠にすることで別居親からの愛情を忘れさせてしまうこと
これはどちらも非常に大きな問題であり、前者は不当な手続きであるし、後者は児童虐待であろうと思う。
これらは調査官調査で本人が語っていたころから時間が経過し、別居親との暮らしが疎遠になっていく中でいわゆる「片親疎外」が完成しつつあることも示していると私は考えています。
親子間に問題があったから引き離したのではない。引き離した後に親子間に問題を捏造するのが連れ去り指南弁護士の手法なのです。
だから本来ならすぐにでも子の連れ去りは解決しなければならない。時間をかけて調査、審判、即時抗告をしていれば、子は同居親とだけ過す時間の中で別居親の愛を忘れてしまう。家庭裁判所は保全を認めるべきでした。
しかし、東京高等裁判所は彼女らの訴えを聞き入れなかった。むしろ一蹴に付したのです。
東京高等裁判所による抗告棄却
東京高等裁判所は非常に簡潔に彼女らの主張を否定してみせました。
まるで聞く耳を持たなかったと言っても良いでしょう。それはそのはずです。家裁審判が彼女らの主張を聞き入れてもなおそれは認められないと丁寧に判事していたものに対して真っ向から噛みついてみせたわけですから。
裁判所の判断


このように客観的証拠のない相手方が裁判所の心証操作を図ろうとした主張については、ばっさりと切り捨てられました。
あらゆることが次々と否定されていきます。
もし、相手弁護士らがここまでひどい嘘を重ねなければ、東京高等裁判所もここまで強い文言で彼女らの主張を否定する事はなかったのでしょう。
そして、ここが肝です。

抗告人は、未成年者らの親権者が相手方と指定されているにも関わらず、平成28年1月に相手方に無断で子らの単独監護を始めたことは不当であるというべきであり、これを是認することはできない。
これまで東京家庭裁判所では元妻らの行為について
「配慮を欠いた」
「不相当である」
程度の表現に抑えていました。強く元妻側を非難することはなかったのです。元妻が子らを連れ去った事は問題であるけれど、その一方で彼女にも配慮を見せ、強く非難する事はありませんでした。
しかし、とうとう、彼女らに対して裁判所の強い憤り、怒りが文面に表れるようになってきます。
「不当というべきであり、是認することはできない」
とまで言われるようになってしまいました。
とどめはこちら。

そのほか縷々主張するが、~いずれも採用することができない。
これはまあ、高等裁判所が控訴理由等を棄却する時に用いる常套句のようなものらしいのですが、もうね、これを見たときは、本当にそのとおり!と思いましたよ。
「なんだかごちゃごちゃ言っているけど、全部採用できないよ!」
なんて痛快な事を言うんだ…。
これって、抗告の理由書をかいた弁護士にしてみたら屈辱以外の何物でもないですよね。
こうして子の引き渡し審判は高裁でも維持される事になりました。元妻らには最高裁に上告する権利が生じる事になります。しかし、家裁、高裁にここまで丁寧に丹念に自分らの主張を拾ってもらいながらも全否定された彼女らに上告という選択肢はもはやなかったのでしょう。このまま審判は確定することになります。
「やった~。酷い目にあったけど、なんとか認めて貰えた…。これで子どもたちが返して貰える。」
そう思いますよね?私も当時の代理人弁護士もそう思ました。
子らがいつ戻っても支障がないよう色々進学準備等を進めます。
しかし、ここまでで、連れ去りから約1年がもう経過しています。子らは新しい学校に馴染み、新しい友達もできている一方、かつての友達とは1年以上断絶が続いている状態です。
子の連れ去りが平成28年1月。子の引き渡し審判の確定が平成29年1月。
そして、なんと恐るべきことに、実は令和5年3月現在、今でも次男は引渡しがなされる事がなく、とうとう彼は成人してしまいました。
三男は自ら父親に助けを求め、警察に保護されながらなんとか私の下に帰還しています。しかし、それも子の連れ去りから3年と8か月が経過してからでした。
そう、ここまでの1年の戦いはこれから待ち受けるエンドレスな戦いに比べたらまだエピローグに過ぎなかったのです。
子の連れ去りに遭った父親が子の引き渡し判決を得る事は非常に稀でめったにない、ほぼない
と言われています。ですから私はここまでがハードルかと思っていましたが、本当のハードル、困難は実はここからだったのです。なんと恐ろしい事でしょう。
費用だってここまでに要したものとこの後に要したものでは倍以上の差があります。この後の方がめっちゃ大変なのです。
「判決はチリ紙以下である。」
相手方弁護士の橋本がその著作で自分らの意向に沿わない判決に対して、強制力が乏しいものであれば、それはチリ紙以下だと表現していますが、それがどういう意味であるのか、私は今後、身をもって思い知らされる事になります。
これからも記事を追加していきます。感想やリクエストなどありましたらTwitterでお知らせいただけると大変励みになります。
よろしくお願いします。
弁護士が委縮して
— papi-bushi (@bushi_papi) February 23, 2023
「子の連れ去りなど、不当で違法な助言」
ができなくなる未来を目指して戦っています。一審、控訴審は勝訴、次は最高裁です。
プロフィールのnoteを見て貰えたら詳しく執筆してあります(記事はまだ追加予定)。
僕と
「同じ未来を夢見てくれる人々」
に応援して貰えると嬉しいです! pic.twitter.com/pH8xZ9pqrZ
前の記事(1 家庭裁判所「子を引き渡せ」に対する元妻らから即時抗告)へ戻る
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
