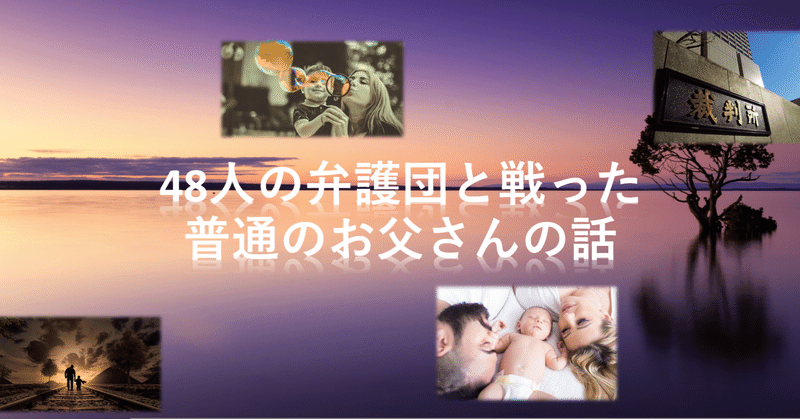
8 審判が出るまでの最後の攻防

概ね調査官の意見のとおりであること
前回の記事で散々虚偽主張していた事が息子たちの証言、調査官の調査により暴露されてしまった相手方弁護士。
しかし、今までの自分たちの主張と真っ向から反する調査報告書を出されたにも関わらず、たとえ違法助言弁護士たちであったとしても、調査官の意見に真っ向から反論するような事はしません。本当は悔しくて悔しくて仕方のない様子がこの後の文書に続くのですが、
「調査官の調査が間違っている!」
などという主張は家庭裁判所ではかなりのタブーなのでしょう。調査官の意見のとおりと言わざるを得ない事情が見え隠れしています。
皆さんも調査官調査があって、仮に自分にとって納得のいかない調査結果が出たとしてもそれをひっくり返すのは困難であるという事を知っておきましょう。後から調査官調査が間違っていたとは言えないですし、言ったところで裁判所に聞き入れて貰えないのです。
私は調査官の調査が相手方弁護士の嘘を論破するようなものになるよう、相手方弁護士の主張が事実と異なる点について、可能な限り自分で調査して証拠を集めていました。調査官調査ではいかに相手の主張が事実と異なるかを証拠を見せて説明し、調査官が特に興味を持ったものは見て貰うだけに留まらず、さらに証拠化しました。
ですから相手方弁護士たちが思っている以上に、そして調査官調査報告書にて報告された以上に私と調査官は事実について共有している事になります。証拠についても私がしっかりしたものを持っている事を裁判所は知っていますが、相手方は知らない。これ、相手方の立場にしてみたら怖いですよ。たくさん嘘をついて相手を陥れてきた人達ですが、どこでどんな嘘をついたら嘘がばれる落とし穴にはまるか分からなくなったわけですから。
このあたりの証拠の調査、精査については正直なところを言うと別居親だからできた事だろうと思います。どうしても子育てをしていればそれに時間が掛かる。裁判に向けた調査や証拠集めなどをする時間はなかなかとれません。ひょっとしたら子の監護をしている親は、弁護士に丸投げしてしまわざるを得ないほど忙しい人もいるのかも知れませんね。ここは明らかに別居親の方が有利な点だと思います。しっかり入念に準備をしましょう。
答弁にて認否を明らかにする
このあたりは弁護士さんに委任していれば弁護士さんが作成する書面になるのでしょうが、答弁書や準備書面できちんと相手の主張については認否を示しておく必要があります。認否を示しておかなければ、思わぬところで裁判所が相手の主張を鵜呑みにしてしまう事があります。

こんな形で良いのです。争いがあるところ、明らかに否認すべきところ、また、争いがないところを交通整理してあげます。これで裁判所からも両者の言い分の相違が浮き彫りになります。この書面を作るのは主に弁護士の先生の役割になろうと思います。なかなか難しいことですから。具体的な反論はさておいても事実と異なる相手の主張に対してはきちんと「否認」、評価を争うところはきちんと「争う」と一言だけでも裁判所に伝えておきましょう。
家庭での出来事、事件について誰よりも詳しいのは自分。弁護士ではない
大切な事を書きます。忙しい監護親は別居親と違ってこのあたりの準備が万端にできず、弁護士に丸投げになってしまうかも知れませんが、
「家庭での出来事について一番詳しいのは弁護士ではなく、自分」
だという事です。弁護士の先生は裁判の実務や法律については詳しいですが、家庭で何があったのかまでは詳細に知らない、分からない。そこはきちんと当事者が責任を持って伝えて直してもらう必要があるのです。全部丸投げではいけません。

細かいところですが、弁護士が作成した認否の書面を事実に即する形で訂正して頂いています。
私は当事者ですから家庭の事を熟知していますし、証拠なんかも読み込んでいますが、弁護士の先生は私の専属ではなく、他の事件も抱えている中で仕事をしてくださっているので、どうしても細かい事情が分からない事がありますからそこは当事者がきちんと正すべきです。
当時の代理人弁護士は私が修正を求めれば、きちんと前向きに検討してくれました。弁護士の先生の中には専門家の自分が作った主張書面を素人の当事者が直すなんて事は気に入らないと考えているような方もいらっしゃいますが、それでは当事者の訴えが正しく裁判所に伝わりません。
誤解のないように申し上げますが、当事者の言い分を100%鵜呑みにして欲しいというわけではなく、当事者の意見に対して、弁護士という専門家の見地からの意見を踏まえてお互い意見交換をしながら答弁書に反映できる先生が優秀な弁護士であると言えます。
事実を淡々と述べる
弁護士の書く準備書面や答弁書等で認否を明らかにしていただくには、ごちゃごちゃ書きませんからすっきりと数ページに抑えてしまうものです。あとは私達当事者の陳述書で事実を補正していきます。特に答弁書で「否認する」「争う」としたところについて、では事実はどうなのかをきちんと説明していくわけです。
ここはひとつの賭けだったのでしょうが、少し長文になる陳述書を書きました。読んで貰えないリスクがあるものでしたが、ここで説明しておかないとタイミングを逸すると思えたからです。私は
1 離婚から再同居までの経緯
(1)監護状況全般について
(2)先方の事実誤認
2 再同居から連れ去り前日までの経緯
(1)監護状況全般について
(2)先方の事実誤認
3 離婚から再度の同居及び元妻による子の連れ去り事件までの時系列
4 連れ去り事件後の面会交流
について40ページほどの陳述書を書きます。可能な限り双方からの主張書面や提出された証拠、調査官調査で触れられた部分については引用し、相手方の主張が間違っている事、調査官の調査やこちらの主張が正しい事の裏付けとして紐づけていきます。

本当はもっと少ないページに抑えたかったのですが、最終的にはこれ以上削れないと言う判断で40頁の陳述書を提出しました。これも弁護士と何往復もメールのやりとりをしながら作成したものです。
時系列については日時を入れ、分かる範囲で夜とか時間も入れました。私の手元には過去の出来事についてその日時を証明できる証拠があったからです。証拠との紐づけについても留意して、自分たちの主張に説得力を持たせるよう工夫しました。

あえて証拠化しない
家じゅうのものというものを全て持ちされてしまうと証拠集めに苦労しますが、日時を特定する証拠というものは案外あるものです。
具体的に何をもって、どんな証拠を用いて日時を特定したかについてもここで触れたいのですが、連れ去り指南弁護士もこのnoteを見ている可能性がある事を思うと、なかなか書きづらいものですね…。
もちろん自分の拙い記憶力を辿って書いたわけではありませんし、事前に裁判に向けて備えていたわけでもありません。
私たちは持ちうる証拠を根拠に主張反論をしましたが、反訳や日時を特定した証拠そのものは提出しませんでした。既にどんな証拠があるかは裁判所に伝えてありましたから、後は知らないのは相手方のみ。わざわざ相手にこちらの手の内、どんな証拠を持っているかを教える必要はありません。
相手の無茶な主張のうち、裁判所にとって取るに足らないであろうものは、相手にしません。争点がぼやけてしまうからです。裁判所が気にするであろうもののうち、確実に証拠をもって反論できるものは証拠を根拠に反論し、証拠がないが相手の主張が間違っているものについては「否認」したり「争う」として裁判所に判断を委ねるほかありませんでした。それでもこの段階では証拠化せずに済むものは証拠化しません。
相手方弁護士らからは私から反論があったもののうち、どれに証拠があって、どれに証拠がないか分からず、反論しようにも反論しづらく、やりづらかっただろうと思います。
「むやみやたらと証拠化しない」
これも大事な作戦だろうと思います。
この頃になってくるともう相手方の主張書面は支離滅裂になってきます。
電話での会話を録音したものを証拠として提出されましたが、電話の内容から先方の言う電話のあった日が虚偽である事が判明。
また、離婚後同居の再開までの間において「一切の面会交流が実現せず、また相手方はことさらにそれを妨げた」という主張を相手方はしたにも関わらず、
「(当時、)面会交流中に子らから「~したい」という発言があった。」
などと、実はしっかり面会交流が行われていた事を示唆する矛盾した主張を始めるようになります。
また、私たちが申立て名古屋での監護養育状況の調査を前提とした名古屋家裁での子の引き渡し審判申立。これを東京に移送するよう相手方橋本弁護士は意見していたにも関わらず、名古屋での監護養育環境について適切な調査がされていない事が問題だと騒ぎ出すようになりました。
こうやって必死になって相手はこちらを攻撃し、酷い誹謗中傷を繰り返しますが、相手にしてはいけません。これは相手方との言い合いやケンカではないのです。相手がつく嘘や私への誹謗中傷は、私を侮辱するもので腹立たしいものですが、裁判所を欺くためにされたものだと理解します。ですから相手からの嘘や誹謗中傷に対して怒りをあらわにするのではなく、
「事実は~であって、相手方主張は事実と異なる。相手方はこのようにして裁判所を欺こうとするもので不当であるといえる」
と返してあげれば良いのです。判断するのはあくまで裁判所なので裁判所がどう判断すれば良いかを導くような主張をしましょう。
さあ、家裁での手続きもそろそろ大詰め。次回以降、家庭裁判所の裁判官が心証開示をしてこの手続きを決着に図ります。

これからも記事を追加していきます。感想やリクエストなどありましたらTwitterでお知らせいただけると大変励みになります。
よろしくお願いします。
弁護士が委縮して
— papi-bushi (@bushi_papi) February 23, 2023
「子の連れ去りなど、不当で違法な助言」
ができなくなる未来を目指して戦っています。一審、控訴審は勝訴、次は最高裁です。
プロフィールのnoteを見て貰えたら詳しく執筆してあります(記事はまだ追加予定)。
僕と
「同じ未来を夢見てくれる人々」
に応援して貰えると嬉しいです! pic.twitter.com/pH8xZ9pqrZ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
