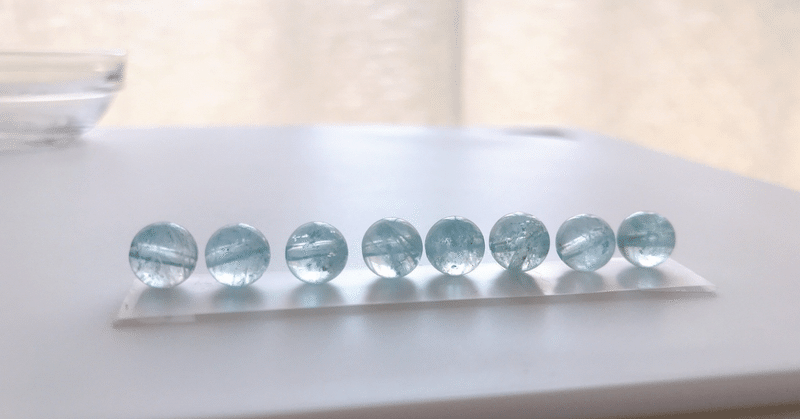
スプリントを「番号」ではなく「名前」で見分ける
ドン・ノーマンの「より良い世界のためのデザイン」を仕事の合間に読み通した。
忙しい日々の中ゆるんだ視座、視野をしゃんと元通りにしてくれる一服の清涼剤。ノーマン先生に外れなし。特に、パートⅣ「人間性中心」に心地よさを感じる。これまでも何度となく出会ってきた、デザインとアジャイルの再邂逅。いや、本当この道を信じてやってきて良かったよ。先生。
モジュラーの概念を引っ張り出して、アジャイルの解説を入れてくる。モジュラーか、そうだね。スプリントの概念はモジュラーに通じるんだよね。モジュラーをソフトウェアに適用するとオブジェクト指向の話になり、プロセスに適用するとアジャイルになる。
少し前に、「スプリント強度」という語彙を見出したんですよ。「正しいものを正しくつくる」という本の中で。
「スプリント強度」とノーマン先生があげてくれた「モジュラー」のイメージは合致しますよ。結合度合いが低く、凝集度が高いからこそ、一つ一つのスプリントの意味が増すし、スプリント間での方向性を変えやすくなる。
さっきのスプリントと次にやるスプリントで、何が違うのか。それを言語化したものが「スプリントゴール」だ。スプリントを番号で呼ぶのは無粋だね(スプリント1、スプリント2、スプリント3…)。名前で呼んでやろう。そのスプリントの存在意義を言葉にしたのがスプリントゴールだ。さっきのスプリントと、次にやるスプリントは、別モノなんだ。
スプリント強度とは、自分たちがスプリントをどれだけコントロールできているかを示す尺度のことだ。プランニングでスプリントに名前をつけて(スプリントゴール)、何をするか決める(スプリントバックログ)。1から2週間のタイムボックスを終えるときにレビューで確かめる。名前に偽りがなかったか、つまり、何ができて、何ができなかったのか。踏まえて、何がわかったのか、だ。
このとき、全然思うようにできなかった…というのは寂しいね。ただ、それ自体も発見だったかもしれない、何か発見があったことによるのかもしれない。自分たちで解決できる範疇のことについては、次に向けて備えいきたいね。ふりかえりをやろう。少しずつスプリントのコントロールを取れるようになっていけば良い。そのためのタイムボックスでもある。
いくつかのスプリントを経て、スプリントという運動を想定通りにこなせるようにする。名前に叶う結果が出せる。プランニングで思い描いた動きができるようになる。そこからだよ。自分たちの仕事の中に、「想定外の発見」を見出し始めるのは。自分たちの体のコントロールができるからこそ、寄り道したり、脇道にそれてみたり、走って取り戻したり、少し立ち止まって休んでみたりもできる。
スプリント強度を高めるための工夫を取っていこう(書籍内 "スプリント強度を高める戦術" 参照)。自分たちで自分たちの動きを思うようにできるためにね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
