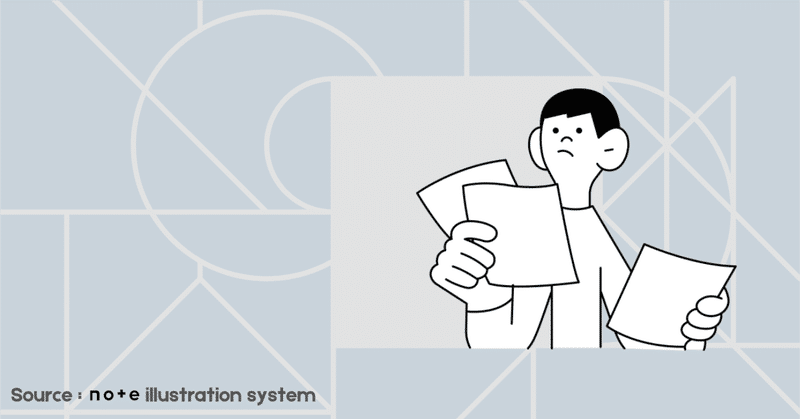
適応障害による退職後の手続きと選択肢
前の記事にも書いたように、今の会社を退職することにしました。
退職にあたって、必要な手続きがいくつかあるので、本記事でまとめます。
必要な理由と手順を記載し、感情に左右されず、淡々とこなすためです。
1.退職の手続き
①退職届の提出
②誓約書の記載・提出
・ 情報漏洩防止等を目的とした会社指定の誓約書。
③貸与物の返却
・ PCやスマホなど、会社からの貸与物を返却。
④雇用保険被保険者証離職票の発行依頼
・ 人事部に申請。
・ 離職後の失業手当の申請に必要。
2.年金
①退職前は厚生年金
・ 国民年金の金額に上乗せした金額の合計を会社が半分負担してくれていた。
※国民年金よりもらえる金額が多い。
・ 支払い方法は、給与天引き。
②退職後の離職期間は国民年金
・ 国民年金の種類は、1号/2号/3号が存在
■第1号被保険者
・ 第2号、3号に該当しない場合はこれ。
<支払い方法>
・第1号被保険者に該当する場合は、納付書が送られてくるため、納付書/口座振替/クレジットカード/アプリ決済(Paypayなど)で支払い
・納付期日は翌月末日
<国民年金への加入手続き>
・市役所/町村役場へ出向き、基礎年金番号が記載されている書類(基礎年金番号通知書または年金手帳など)を持参して手続き。
・退職日の翌日から14日以内に行く必要がある。
■第2号被保険者
・厚生年金加入者であることが第2号の条件
※厚生年金の加入者と同時に国民年金加入者にもなっているということ
>私は、厚生年金から外れるため、これには該当しない。
■第3号被保険者
・第2号被保険者に扶養されている配偶者であることが条件
・第2被保険者全体で負担するため、個別に納付する必要がない。
※第2号被保険者の厚生年金で実質納付を負担することになるが、厚生年金は扶養者の給与で決まるため、被扶養者になったからといって、扶養者の負担額が増えることはない。
・扶養者の勤務先を通じて加入手続きを行う。
※具体的には、扶養者の事業者を経由して被扶養者(異動)届を提出する。(勤務先手順に従う)
>扶養に入るか否かで変わる。
結果、後述するが、扶養に入れそうなので、これに該当するかも。
扶養に入る場合は、第3号被保険者に該当する。
<被扶養となる条件>
①退職後の1年間の見込み収入が、年収130万円未満であること
- 既に今年収入があっても計算に含めなくてよい。
- 退職金は計算に含めなくてよい。
- 失業手当は見込みに入れる必要がある。
②扶養する人の年収の半分未満であること
③扶養する人の配偶者、子、孫、兄弟姉妹であること(これら以外の親族は同一世帯での同居が必要)
>ポイントは①退職後の1年間の見込み収入であり、見込むことが出来るのは失業手当分、では、いくら見込めるか。
<失業手当の見込み>
■給付される日額の計算
・過去6か月の賞与を除く給与 ÷ 180日が基本手当日額となる。
基本手当日額の年齢区分ごとの上限値に対して、日額ごとに割り振られた給付率を乗算したものが実際に受け取れる手当となる。
私の場合は、30-44歳の年齢区分の基本手当日額の上限値15,430円 × 給付率50%の、7,715円/日 である。
■給付日数
自己都合退職の場合、雇用保険被保険者だった期間により異なる。
私は10年未満のため、90日
※会社都合の退職の場合は、期間や離職時の年齢により基準が異なる
■合計
7,715円 × 90日 = 694,350円
>130万円未満であるので、扶養には入れそうだ。
■現在は働くことが出来ない疾病を患っている場合
失業手当は、現在働くことが出来る方を対象にした手当のため、医師から安静にすべきといわれている期間は、申請が出来ない。
しかし、その期間は、受給の延長手続きができる。
通常は、退職した日から1年経つとその会社でかけていた失業保険は受け取れなくなるが、病気などで現在働くのが難しい人は最大で4年まで失業保険を受け取るのを延長できる。
<見込み収入の足しとなりそうな他の手当>
社会保険給付金制度というものがあるらしいが、在籍中に申請しなければならないらしく、時間がないため、難しい。
3.保険
離職期間の選択肢は3つ
①扶養者の健康保険に加入
>出来ればこれがよい。扶養に入る場合はこれ。
②任意継続制度へ加入
・前職の保険へお金を払って継続加入
③国民健康保険へ加入
・保険証を会社へ返却し、社会保険資格喪失証明書を受領する。
・退職した日の翌日より14日以内に市区町村の役所で加入手続きを行う。
4.保育園の継続
これが一番の問題である。
扶養に入り、働いていない場合、保育園継続が出来なくなる可能性がある。
居住している市の役所のホームページで保育可能となる条件を調べてみた。
※市区町村により条件が異なる。
条件は、「教育・保育給付認定を受けることが出来るか」とのこと。
子供の年齢の条件はさておき、重要なのは「保育の必要性の有無」で条件は以下。
■保育の必要性が認められる条件
1.月64時間以上就労をしている場合
2.病気や怪我があったり、精神や身体に障害がある場合
3.親族の介護や看護をしている場合
4.震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
5.求職活動(起業準備を含む)を継続して行っている場合
(保育所等の利用承諾日から起算して90日目が属する月の末日までに月64時間以上の内容の就労証明書と変更届の提出が必要)
6.就学をしている(職業訓練を含む)場合
7.出産の前後である場合
8.出産の前2か月から(多胎妊娠の場合は出産月の前4か月から)出産後56日目が属する月の末日まで
9.きょうだいの育児休業中や育児休暇中(就労先が認めた法令に基づかない育児のための休暇)である場合
10.その他、法令等に定めのある場合
この中では、2か5が該当しそうである。
5の求職活動は、体調がうまく回復してくれれば、問題なさそうである。
求職の証明は、保育所等利用申込書の表面の職業欄に「求職活動中」と記入すれば、求職活動であることの確認書類は不要とのこと。ただし、3か月以内に就労証明書が必要となる。
2については、主治医の意見書というの市指定の様式に、「疾病により保育が困難である」と記載して頂いたものを提出すればよさそうだ。
診断書については、主治医に必要であれば記載可能と言っていただいたため、問題ないだろう。
これで少し安心した。
長くなってしまったが、結論としては、2パターンである。
1.離職後に安静にしてしばらく働かずに休む場合
- 年金は、国民年金だが、扶養に入ることで納付は不要。
- 保険は扶養者の勤務先の健康保険へ加入。
- 失業保険は、求職活動が出来るようになるまで延長申請。
- 保育園は、「疾病により保育困難」な旨の意見書を提出
2.離職後に働ける状態であり、すぐに求職活動を行う場合
- 年金は、国民年金だが、一旦扶養に入り、納付は不要。転職後は転職先の厚生年金へ加入。
- 保険は扶養者の勤務先の健康保険へ一旦加入し、転職後は転職先の健康保険へ。
- 失業保険はすぐに申請。
- 保育園は、求職中であることを指定書類に記載して提出し、3か月以内に仕事を決め、就労証明書を提出する。
あとは、自分の体調と相談。
最近あまり体調も良くないので、一旦安静にして休息を取ろうかとも思っている。経歴書に空白期間があると、再就職の面接の際に色々言われてしまうのだが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
