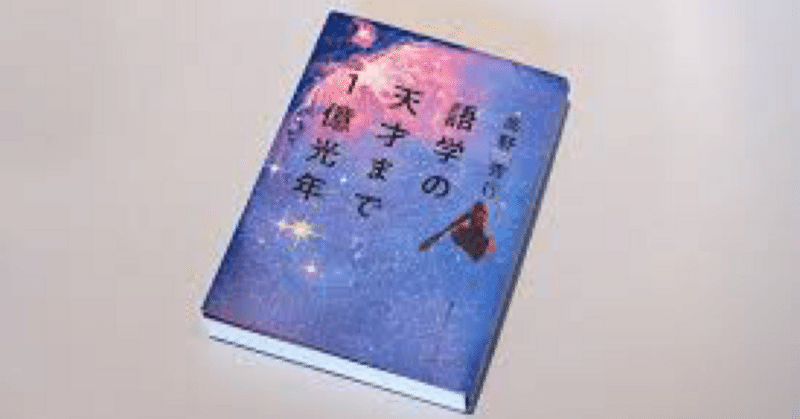
19作品目 読書「語学の天才まで1億光年」(高野秀行)
どうも自家焙煎珈琲パイデイアです。
「淹れながら思い出したエンタメ」18作品目です。
毎週、何かについて書くというのは、簡単なようで難しい。
本一冊読めばいい、映画を一本観ればいい、ということでも無いのです。
もし、それが、私の中で、ここに書こうと思うほど面白くなければ、もう一冊、もう一本、読んだり観たりする必要があるわけです。
これは批評ではないので、面白かったものだけ書きたいし、ましてや、これはイマイチだったなんてことを書く気はさらさらないわけです。
そういうわけで、ここに書きたいと思う面白いものを見つけるまでに、これがなかなか時間がかかるわけです。
ま、これはたまに書かない週がある言い訳みたいなことです。
今回はいつだったか、前に読んだ本です。
ノンフィクション作家の高野秀行さんの「語学の天才まで1億光年」です。
ノンフィクション作家として、インド、アフリカ、南米、東南アジア、と世界各国を飛び回り、行く先々でその国の言葉を取得していった著者の、言語取得までの方法論というよりも、スマホで翻訳が出来る時代において、言葉が持つ力について考えました。
まず、この本と読み進めると、どれだけ、著者の高野さんがぶっ飛んでいるか、これに衝撃を受けます。だってね、よく分からない怪獣を見つけに、テレビディレクターに半ば、騙くらかされた形で、アフリカのコンゴ、ザイールへと向かう。
この導入だけで、あ、これは常人の物語ではないな、と読む側に諦めと覚悟を決め覚ます。
ある種の覚悟を決めると、この本はかなり興奮する本です。
何をするにも、なんかしらの障碍にぶつかり、それをなんかしらの方法で強行突破していく、どこの国に行ってもこんな感じ。これはジャンルの分からない面白さです。
一人の人間の途方もない旅の途中に生まれる数々のコミュニケーションを通して、言語の可能性、面白さ、そして、潜在的な世界の現実が垣間見られます。
印象的だったのは、著者がフランス人コンゴ研究者に会った時のエピソードです。
コンゴを研究するのに、現地の言葉を話さない仏人研究者は、日本人研究者のフランス語が弱いことを指摘します。
どれだけ現地の言葉が話せても、フランス語に精通していなければ、フランスの研究には敵わないと言うのです。
コンゴはフランスの植民地という過去があり、現在でも経済的にはフランスから自立しているとは言えません。
そんなフランスとコンゴの関係性を言語の視点から垣間見るのです。
我々の意識しないところで、言語がいかに世界を支配しているか、そんなことを考えます。
最近、ラテン語の勉強を始めたのですが、やはり我々の意識は歴史、宗教、そして、言語を屋台骨に現在の社会環境に肉付けされていることを改めて実感します。
そんなことを、私なんかは机の上でなんとなく感じていますが、著者の高野さんはそれを異国の空気の中、骨身に染みているわけです。
その熱量が感じられる文章も読み応えがありました。
<information>
自家焙煎珈琲パイデイアは「深煎りの甘味」をテーマに日々、珈琲の焙煎をしております。よろしければ、ぜひお試しください。詳しくはこちらを。
パイデイアのHPでも毎週金曜日、「焙きながらするほどでもない話」というたわいもないエッセイを更新しております。よければ覗いてみてください。
それから、さらにSpotifyで「飲みながらするほどでもない話」という自主配信ラジオを毎月偶数土曜日に配信しております。
よろしければ、こちらもぜひお聞きください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
