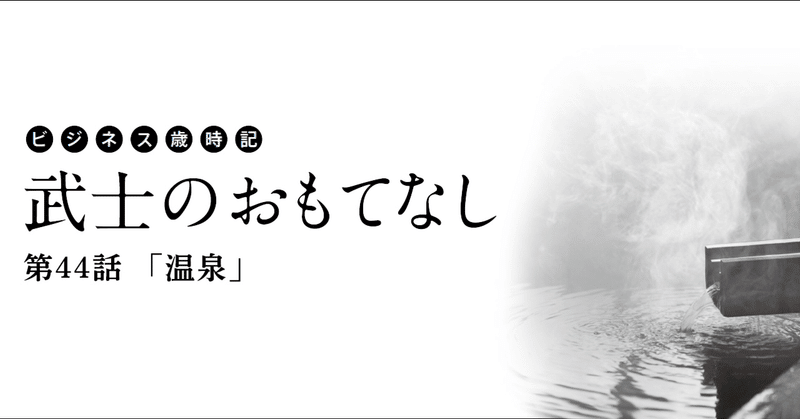
ビジネス歳時記 武士のおもてなし 第44話「温泉」
将軍の実力を示した、温泉の力
10月は、温泉旅行なども楽しい行楽の秋。その昔、江戸時代の将軍や大名たちも同じでした。中でも熱海温泉の湯に惚れこみ、子供たちを連れて長逗留し、それができない時は「熱海よいとこ日の丸たてて、御本丸へとお湯が行く」と地元に残る唄にもあるように、熱海の湯を江戸城まで“お取り寄せ”して楽しんでいたのが徳川家康です。
今でも、熱海の湯前神社※では10月初旬に湯汲み神事が行われ、湯桶で温泉を運んだ当時の様子を再現するイベントなどが行われています。今回は、この温泉を、武士たちがどのように利用し、そして庶民たちへと広まっていったのかについてご紹介しましょう。
火山帯が国土の中央を走る日本は、世界でも有数の温泉国。古くは、すでに平安時代には風邪を予防するなど治療のための入浴が行われており、室町時代には仏教を広めるために温泉※が利用されていたと言われています。
戦国時代、武将たちは温泉療法を積極的に取り入れ、戦で傷ついた兵士たちの野戦病院として温泉を使うようになりました。国内には“隠し湯”と呼ばれる秘湯が数多く点在しますが、「温泉を制する者は権力を手にする」ともされ、領土内に効能のある名湯をどれだけ掌握しているかということが、勝利の鍵を握るための武将の実力とさえ言われました。
そんな武将の一人に、“信玄の隠し湯” ※で知られる武田信玄がいますが、温泉好きの将軍としては家康の右に出る者はいないでしょう。自分で漢方薬を調合するなど元来の健康オタクだった家康は、静岡の駿府城からの地の利が良いこともあったのでしょう、記録に残るだけでも慶長2年(1597)から数年置きに熱海温泉を足しげく訪れています。
慶長5年(1600)、関ヶ原の戦いに向かう途中にも、数泊したと言われています。慶長9年(1604)には、息子の義直と頼宣(よりのぶ)を連れて逗留。お忍びでの湯治であったため、宿帳には家康の名前を記帳することができず、宿の亭主がその日付の箇所に白紙を挟んで代々の申し送りがされてきたという話も伝わっています。
この時、家康は関ヶ原で活躍した大名の吉川広家(きっかわひろいえ)※の体調が良くないことを思い出し、5桶の熱海の湯を陸路で京都の伏見へ輸送しましたが、療養先が大坂と知ると、今度は伏見から船を使って運ばせています。これが「献上湯」「お汲み湯」の走りとされ、以後は江戸城の歴代の将軍に定期的に運ばれるようになりました。
そして、家康が温泉に連れていった徳川頼宣は、まさに温泉の申し子ともいうべき大名。慶長7年(1602)、子宝を願って温泉で湯治をしていた「お万の方」と家康の間に誕生し、駿府城主を経て後に紀伊藩主となりましたが、父の血を引く温泉好き。元和5年(1619)に紀州に藩主として赴任してから、弘法大師ゆかりと伝わる龍神温泉を発見します。この温泉がもたらす恵みを領民と平等に分かち合うため、村の年貢を免除、12年ごとに温泉場を藩費で修理改築していたことが知られています。
8代将軍徳川吉宗の時代になると、享保11年(1726)10月から献上湯の定期便が本格的に始まり、それまで4人がかりで陸路により運ばせていた温泉を、船による海上輸送で4日置きにするなどして、他藩主たちの憧れの的になりました。これを真似て、わざわざ幕府に許可を申請して、江戸の藩邸に温泉を運ぶことが流行しました。
この人気を江戸の商人たちがだまって見ているわけはありません。将軍様御用達の名湯として、市中の湯屋にも運ばれるようになりました。江戸時代後期になると、すでに庶民たちも「お伊勢参り」や「善光寺詣で」などの旅行で温泉の良さを知っていますから、それが江戸で手軽に楽しめることをウリにした商売だったのでしょうが、江戸の水で数倍に薄めた温泉だったそうで、その効能がどうだったかまではわかりません。
【監修】
企画・構成 和文化ラボ
東京のグラフィックデザインオフィス 株式会社オーバル
※湯前神社
「病を除く効果がある」と神様のお告げで祠を立てた、熱海の湯を守る神を祀った神社。神社前には熱海温泉の源泉とされる大湯が湧き、秋には湯汲み神事などの例大祭が開催される。
https://www.ataminews.gr.jp/spot/313/
※仏教を広めるために温泉
施浴や薬湯といい、寺院などが建物内に入浴できる浴堂という設備を作って無料で開放し、施しのひとつとして庶民や病人を入浴させた。
※信玄の隠し湯
山梨県の積翠寺温泉や下部温泉などのほか、長野県の渋温泉や岐阜県の平湯温泉など10数件を超える温泉が知られている。
※吉川広家 [1561 - 1625]
江戸前期の武将。天正11年(1583)に上京するが、兄の死により家を継ぎ、出雲の富田城に居城。文禄・慶長の役に両役とも従軍。関ヶ原の戦いでは西軍だったが、ひそかに徳川氏に通じて不戦の姿勢を示し、自らの主君である毛利輝元氏と領国民のために奔走したとされる。
参考資料
『江戸の温泉学』(松田忠徳著 新潮選書)
『温泉と日本人 増補版』(八岩まどか著 青弓社)
『日本風俗史事典』(日本風俗史学会編 弘文堂)
『江戸大名の好奇心』(中江克己著 第三文明社)
『甦る江戸文化- 人びとの暮らしの中で-』
(西山松之助著 日本放送出版協会)
『江戸の旅』(今野信雄著 岩波新書)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
