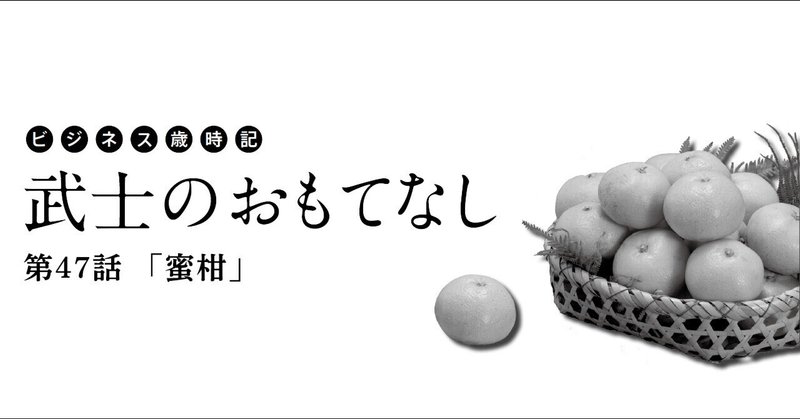
ビジネス歳時記 武士のおもてなし 第47話「蜜柑」
武将も待ち望んだ、暮れの贈答品
「下積みの蜜柑ちいさき年の暮れ」(浪化)── “こたつ蜜柑”などというように、蜜柑(みかん)は手軽に食べられる冬の果物ですが、物流が発達していなかった昔は現在のように豊富に手に入るものではなく、子どもたちはお歳暮で届く木箱などに入った贈答用蜜柑を楽しみにしていたものでした。
贈答品としての蜜柑の歴史は古く、すでに江戸時代にもありましたが、当時は武家や裕福な商家など限られた人たちの間での高級品でした。あの食通の徳川家康も蜜柑を好み、親しい大名などには頻繁に贈っていました。よほど気に入ったのでしょうか。
晩年を過ごした静岡県の駿府(すんぷ)城には、紀州(和歌山県)の初代藩主から贈られた蜜柑の苗木が、「家康お手植えの蜜柑」※として残り、現在も400年の時を超えて収穫されているそうです。
そして、紀州の2代藩主となった家康の10男の徳川頼宣(よりのぶ)※は、父の好物でもあった蜜柑を藩の特産品としました。今回は、頼宣の時代から本格的にはじまった、蜜柑栽培と贈答の歴史を辿ります。
蜜柑は、最初は漢方薬の「陳皮(ちんぴ)」として、中国から遣唐使がもたらした柑橘類のひとつとされています。甘い柑橘類で蜜柑という名前がつきましたが、このころの蜜柑は、現在私たちが食べている種子がなく果汁が多い「温州蜜柑」とは違う、やや小ぶりなことから「小蜜柑」とも呼ばれた「紀州蜜柑」です。
その特徴は、甘味だけではなく酸味も強く、皮が少し厚くて小ぶりなこと。そして、温州蜜柑と大きく違うのは、1個の果実に5~6個の種子があるということです。験(げん)をかつぐ武士にとって、これは大事なポイント。
「梨」を「ナシ(無し)」ではなく「有の実」と呼んだように、種子がない温州蜜柑を「種なしでは、後継ぎが途絶えてしまう」と忌み嫌い、紀州蜜柑を珍重するというこだわりがありました。
藩の財政を建て直すために、ここに目をつけたのが徳川頼宣です。2代目藩主として元和5年(1619)に紀州に入国したときに、この紀州蜜柑が気に入り、平地が少なく8割が山地という領地で働く農民たちに収入をもたらす農作物として植栽を促進しました。それだけではなく、生産者である農民たちの中から生まれた出荷組合的な組織を認め、関西だけではなく、江戸へ出荷する輸送の保護政策もとったとされています。
その施策で恩恵を受けた農民の出荷した紀州蜜柑が、廻船で最初に江戸に送られたのは寛永11年(1634)。荷揚げされた400籠は、ひと籠1両という価格がついたそうです。当時の1両は現在のだいたい4万円にあたり、蜜柑景気に沸いた紀州藩でした。
「沖の暗いのに 白帆が見える あれは紀伊国屋の蜜柑船」。江戸へは海上輸送で運ばれましたが、海が荒れると輸送がストップしてしまうことも多く、そこで紀伊国屋文左衛門※の「蜜柑船」の逸話で知られるようになりました。江戸では鍛冶屋たちの商売道具の鞴(ふいご)に感謝する行事に、火や太陽をイメージする橙色の蜜柑は欠かせないものでした。
行事の最後には、蜜柑を豆まきのように豪勢にばらまき、めったに蜜柑などを口にすることのできない庶民はそれを楽しみにしていました。しかし職人たちにとっては、その値段の高騰や品薄が悩みの種でした。
そこで、文左衛門が暴風雨をものともせず、故郷の和歌山から江戸に、蜜柑船を走らせて届けたことから一躍有名となりました。その時の売上げを元手に、材木商として莫大な資産を得ることになったという話は、柴田錬三郎など数多くの作家によって小説になっています。
こうして江戸の武士たちを中心にはじまった蜜柑の贈答の習慣は、種子のない温州蜜柑が主流になり、形や規模を変えて現在も続いています。今でも生産者から直接取り寄せると、箱の中に葉付の小蜜柑などが一緒に入っていることもあります。
これは、正月を迎えるお飾り用としての葉付蜜柑。本来は同じ柑橘類の橙(だいだい)ですが、小ぶりな紀州蜜柑が使われることも多かったそうです。江戸の年の暮れを想像しながら、どうぞ良いお年をお迎えください。
【監修】
企画・構成 和文化ラボ
東京のグラフィックデザインオフィス 株式会社オーバル
※家康お手植えの蜜柑
徳川家康が400年以上前に、静岡県の駿府城の天守台辺りに自ら植えたとされる紀州蜜柑。昭和25年に県の天然記念物に指定された。現在の駿府城公園内にあり、12月には蜜柑の収穫行事なども行われている。
※徳川頼宣[1602~1671]
江戸初期の大名で、徳川家康の第10子。幼名は長福丸。大坂冬と夏の陣に参加し、元和2年(1616)家康の死後、静岡の駿府城を与えられ、翌年加藤清正の娘と結婚。元和5年(1619)和歌山55万石余の城主となる。善政を指揮し、蜜柑の普及にも貢献したと言われている。
※紀伊国屋文左衛門[?~1734]
江戸時代の元禄期(1688~1704)の豪商。蜜柑船を走らせて巨利を得たこと、江戸で寛永寺の造営の資材調達を請け負って財をなしたなど、さまざまな経歴が伝説化され伝わっているが史料が乏しく、詳細はまだよくわかっていない。
参考資料
『紀伊国屋文左衛門の生涯』(山木育著 マネジメント社)
『江戸の食生活』(原田信男著 岩波書店)
『たべもの日本史総覧』(歴史読本特別増刊事典シリーズ17)
『江戸の食文化』(原田信男著 小学館)
『図説江戸時代食生活事典』(日本風俗史学会 雄山閣出版)
『飲食事典』(本山荻舟著 平凡社)
『たべもの語源辞典』(清水桂一著 東京堂出版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
