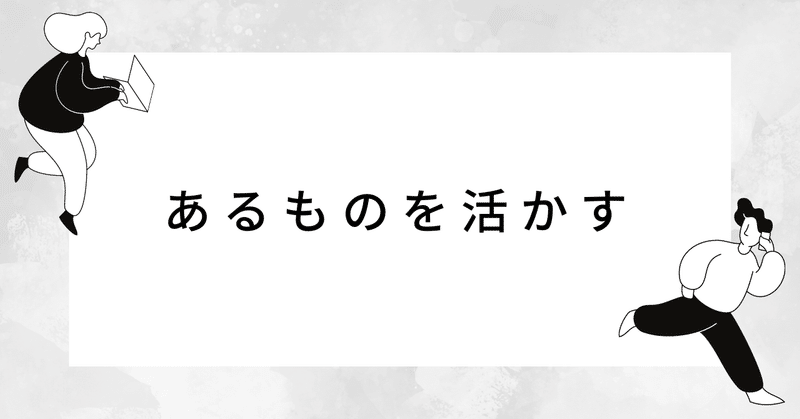
あるものを活かす
わたしたちが運営しているファブラボやまぐちという施設では、3Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を、市民の皆さまに開放しています。
2015年から8年間運営していますので、それはもうたくさんの方々にご利用いただいています。ありがたい。
近年、事業で活用してくださるユーザーさんが増えてきたこともあり、どのように活用されているかをインタビュー記事として掲載し始めました。
なぜユーザーインタビューを始めたのか?
端的に言うと、事業で活用してくださる方々をもっと増やしたいからです。そのために、どのような使い方が出来るのか?を、他のユーザーさんの事例を知ることによって想像しやすくしたいという意図があります。

このタイミングで始めた理由としては、身も蓋もない話ですが、ようやく出来る体制が整ったからです。これまでもやりたいなという気持ちはありましたが、単純に余裕がなかっただけです。
今、私たちのチームにはWeb制作、インタビュー、写真撮影、動画撮影ができるスタッフさんが在籍しています。すべて内製できるようになったので、やってみようということで動き始めました。
これから、半月に一本のペースで記事を公開していき、いずれは独立したWebサイトとしてまとめていく予定です。
と、ここまではポジティブな理由で、もうひとつ大きな声では言えない別の理由があります。
ここだけの話、もうひとつの裏事情
私たちの会社は、クリエイティブ・カンパニーを名乗っており、つくる仕事に軸足を置いています。細かく言うと他にも色々やっているのですが、現状最も売上比率が大きいのはWebサイトの制作と運用です。
2023年7月に9期目の決算を終え、品目別売上比率を計算したところ、運用の売上が制作を初めて上回りました。
いよいよ来たか、と思いました。
Web制作会社がなくなるという話は、結構前から言われていました。ノーコード・ローコードでWebサイトが制作できるツールの老舗であるJimdoの日本語版がリリースされたのが2009年。専門家でなくてもWebサイトが作れるようになる未来は、14年前に既に見えていました。
会社を設立する前から、Web制作という仕事は近いうちに衰退するだろうと予感していました。制作環境は進化して、どんどん作りやすくなる。そうすると、プレイヤーが増えて単価は下がる。究極は、ユーザー自身が制作するようになり、外注に出す案件がなくなる、という展開を考えていました。
ただ、意外と世界は急に変化しないもので、当時は5年も続けばいいほうだと思っていたWeb制作の仕事を、なんだかんだ10年続けてこれました。しかし、近年はWebマーケティングの会社やコンサルティングファームなどがWebの運用を提案するようになり、市場は運用メインにシフトしています。
作って、納品して、終わり…だけの企業が生き残るのは、いよいよ難しい時代になってきたのは間違いありません。
チームとして運用に舵を切る
2019年頃から運用の知見を増やすため、個人的にコンテンツマーケティングのカンファレンスに参加したり、リブランディングのチームで勉強会を開催したり、Web広告運用の仕事を増やしたり、少しずつ運用に軸足をずらしてきました。その結果が、売上比率に現れたという見方もあります。
10期目となる今年度は、いよいよチームとして運用に舵を切るタイミングだと考えています。その取っ掛かりとして、手元にあるリソースを活用してできること、それがファブラボのユーザーインタビューというコンテンツを発信することというわけです。
まずはファブラボの事例紹介を軸にしたオウンドメディアを作る、それを自分たちで運用して得たノウハウをお客様に還元する。それが、ユーザーインタビューの裏の目的です。
それ以外にも水面下で進行していることは幾つかありますが、いずれにしても今期は大きな変化を伴う年になるでしょう。
生成AIの飛躍的な進化も相まって、これからデジタル・クリエイティブに携わるすべての事業者が変化を強いられるはずです。変化する時代に取り残されないように、自らも変わり続けなければなりません。
あるものに目を向けて新しい価値を生む
経営相談に乗っていて面白いのは、資金や経験が十分でない事業者ほど、リスクを軽視して未経験の事業に投資をしたがる傾向にあるということです。
一般的に、新しい事業やスタートアップの失敗率は高いとされています。ハーバード大学ビジネススクール上級講師のシカール・ゴーシュ教授によると、ベンチャーキャピタルから資金調達を行ったスタートアップの約75%が、投資を回収できる段階に至らないそうです。
かくいう私も恥ずかしながら、リスクを軽視して未経験の分野に投資して、痛い目にあったことが何度かあります。幸い致命傷にはならず、色々な方の助けを借りることで、どうにかここまで生き延びてこれました。
ユーザーインタビューに関しては、これまで積み上げてきた手元にあるものを活かした取り組みなので、リスクはほとんどありません。コンテンツは既にある、メンバーは揃っている、あとはひたすら愚直にやるだけです。
9年間のストックを活かして、10年目以降を生き残るための、新たな価値を生み出してきましょう。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
