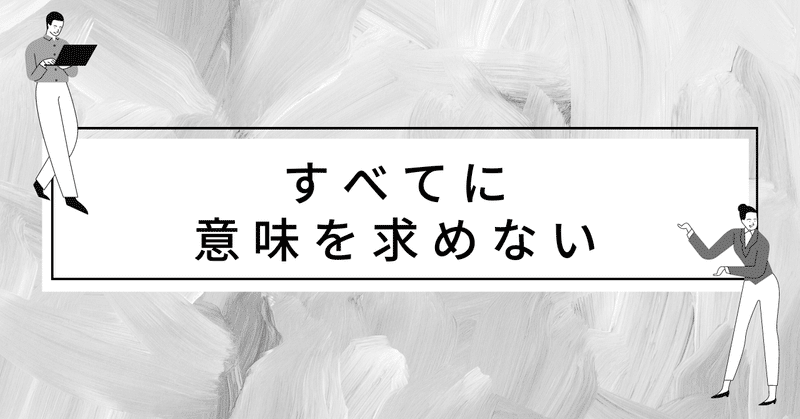
すべてに意味を求めない
前回の投稿の最後に、知らないことを深掘りすることはできないと書きましたが、知らないことを知ろうとすることは誰にでもできます。
誰にでもできるのに、意外と多くの人がやっていないのが、知らないことを知ろうとする努力ではないでしょうか?ここで言う「知らないこと」とは、これまで自分が興味関心を持ったことがない、専門外や守備範囲外のジャンルのことです。
この知らないことを知ろうとする努力こそが「知の探索」だと、私はそう解釈しています。
興味がないことに興味を持つ余裕がない
現代社会は情報が溢れかえり、スマートフォンひとつで多様な価値観や文化に容易に触れることができます。このような環境で、私たちの興味関心もまた多様に細分化されています。
私たちの脳には見たいものを見ようとする性質があり、普段は興味があるジャンルや、自分ごととして捉えている分野に関する情報を、優先的に収集しています。
情報過多の社会において、私たちは常に莫大な量の情報にさらされており、脳はそれらすべてを同時に処理することができません。そのため、無意識のうちに必要な情報のみをピックアップし認識しています。
「推し」の情報は自然と視覚や聴覚に飛び込んできますが、どこの誰かもわからない人の情報は、関係ないと割り切って脳が無視しているのです。
知らないことを学ぶためには、それなりの時間と労力を要します。しかし、興味関心があるジャンルの情報すら溢れかえっているのに、興味がないことを知るために割けるリソースなんかないよ…と思われる方も多いでしょう。
おのずと興味を持つように仕向ける
興味がないことに興味を持つためには、こちらから能動的に接触をする必要があります。興味があるなしに関わらず、とにかく接点をもつのです。
分かりやすい例を挙げると、図書館に行って、普段行ったことがないジャンルのコーナーに足を運び、まったく興味がない本に目を通してみる。それだけで、新しいジャンルとの接点を作ることができます。
また、他者に薦められた本を読む、音楽を聴く、映画を見る、といった方法もあります。かつて香川県の大学の教授とオンラインで繋がり、お互いが推薦した書籍を読んで感想を語り合うという遊びをしていたときは、およそ自分では選択しないであろう分野の知見をたくさん得ることができました。
自分ではない誰かがセレクトした情報を、片っ端から摂取するといった方法は、興味がない情報にふれる機会として有効です。例えば、YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」で紹介された本を全部読む、といった方法はいかがでしょうか。
SNSなどのレコメンド機能を利用するのも有効です。ただし、Webサービスのアルゴリズムは、あなたに有益な情報を提供するためのものではなく、利用時間を増やして広告収入を上げることが目的だったりするので、気を抜くとすぐにあなたが欲しがりそうな情報ばかりを提供するようになります。
他者との対話から学ぶ
他者との対話からも、新しい知見を得ることができます。特に私がお薦めするのは、初対面の人の話を聴くことです。同業種の勉強会なども貴重な学びの機会ではありますが、異なる属性の方が集まるイベントやワークショップのほうが、興味がないことに興味を持つきっかけとしては有効です。
対話といえど、あくまで目的は他者の話を聴くことです。自分の話はそこそこにして、相手の話を引き出すような質問を投げかけてみましょう。能動的な姿勢で話を聴いていくと、次第に相手のことに興味が沸いてくることを実感できるはずです。
他者との対話から学ぶことは、身近なところでも実践できます。例えば、私たちが所属する組織には、多様な文化やバックグラウンドを持つスタッフが働いています。それぞれの専門分野や趣味の領域の話を聴いてみることで、新たなジャンルの知見を広げることができます。
動画配信サービスやPodcastなどで、一方的に話を聴くのも良いと思います。その際も、できるだけ自分が知らないテーマを選ぶことがポイントです。多様な人が登場するソースとして、例えば「日本財団」のYouTubeチャンネルはいかがでしょうか。
役に立つかどうかは後回し
小説「宮本武蔵」で有名な歴史小説家の吉川英治は、「我以外皆我師(自分以外のものはすべて私の師である)」という言葉を残しています。自ら興味を持ちさえすれば、他者から学べることは無限にあります。
知らないことを知ろうとする際のポイントは2つあります。
ひとつめは、インプットの量を増やすことではなく、ジャンルの幅を広げることです。情報収集の偏食をなくすことを意識すると、自分のなかに多様性を構築することができます。
多様性(たようせい、英: diversity)とは、幅広く性質の異なる群が存在すること。性質に類似性のある群が形成される点が特徴で、単純に「いろいろある」こととは異なる。
その多様性のなかから「一見、関係なさそうな事柄を結びつける」ことで、個人レベルのイノベーションが生まれます。多様性の幅が広ければ広いほど、ユニークなアイデアを生みだせる可能性が高まります。
もうひとつのポイントは、すべてを意味のある学びにしようと思わないことです。多様な視点の組み合わせがイノベーションを生むのであれば、今日得た知識がすぐに役に立つとは限りません。
数年後に他のなにかと組み合わさって画期的なアイデアに昇華するかもしれませんし、何の役にも立たず忘れられていく可能性も大いにあるでしょう。ただ、知っていると知らないの差は、人生を左右するぐらい大きい。
最近はタイムパフォーマンス(時間対効果)という考え方が流行していますが、知見を広げるためには、一見役に立たなそうなことにも臆せず時間を割いてみることです。その学びに意味があるのかなんて、役に立つ日が来るまで分からないのですから。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
