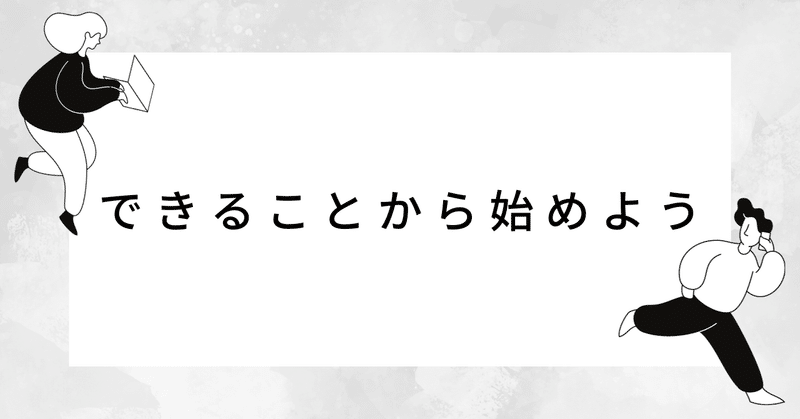
できることから始めよう
これまで我流の仕事観をつらつらと綴ってきましたが、最近になってそれにエフェクチュエーション(実効理論)という名前が付いているということを知りました。
エフェクチュエーションとは?
エフェクチュエーションは、不確実性の高い状況における意思決定の一般理論として、近年注目されているそうです。
エフェクチュエーションの大きな特徴は、従来の経営学が重視してきた「予測」ではなく「コントロール」によって、不確実性に対処する思考様式であることです。
アメリカのヴァージニア大学ダーデンスクールで、アントレプレナーシップの経営学者であるサラス・サラスバシー教授は、熟達した起業家と呼びうる人々の意思決定に共通する明確なパターンを発見しました。
それは次の5つの特徴的な経験則(ヒューリスティクス)であり、それらを総体としてエフェクチュエーションと名付けました。
エフェクチュエーションの5つの原則
手中の鳥(Bird in Hand)
許容可能な損失(Affordable Loss)
クレイジーキルト(Crazy Quilt)
レモネード(Lemonade)
飛行機のパイロット(Pilot in the Plane)
エフェクチュエーションとコーゼーション
一般的な経営では、最初に具体的な目標を立てて、それを達成するために逆算してなにをすべきか?を考えます。このような思考様式をコーゼーション(因果論)と呼びます。
コーゼーションのプロセスでは、顧客のニーズや競合の製品・サービスについて分析をするために市場をリサーチし、それをもとにリターンを予測して、できるだけ正しい事業計画を立案することが重視されます。

(エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」より引用)
目的が明確であり、環境が分析に基づいて予測可能な場合においては、コーゼーションの考え方は有効です。一方で、環境の不確実性が高い場合や資源に制約がある場合には、すぐに行き詰ってしまいます。
コーゼーションでは対処できない高い不確実性に対して、目的ではなく手段を拠り所として、それを活用して生み出すことのできる効果(effect)を重視するという思考がエフェクチュエーションです。

(エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」より引用)
エフェクチュエーションの5つの原則
エフェクチュエーションの5つの原則を読み進めていくなかで、私の仕事観と様々な共通点があることが分かりりました。
手中の鳥(Bird in Hand)
熟達した起業家には、最初から市場機会や明確な目的が見えなくても、すでに持っている「手持ちの手段(資源)」で何ができるか?を考えるという意思決定のパターンが見られました。
このように「目的主導」ではなく「手段主導」で新しいアイディアを発想する思考様式が「手中の鳥」です。
これは「手持ちのカードで勝負する」という発想と一致しています。
許容可能な損失(Affordable Loss)
アイディアを実行に移す段階では、期待できるリターンの大きさではなく、うまくいかなかった場合のリスクを考慮して、その際の損失が許容できるかという基準で判断します。
許容できる範囲でリスクテイクするというという考え方は、「できるだけ小さく始める」の中で語っていることと共通しています。
クレイジーキルト(Crazy Quilt)
エフェクチュエーションの発想で行動する起業家は、アイディアの実現に協力してくれそうな、あらゆるステークホルダーとパートナーシップの構築を模索します。
パートナーの協力を得ることによって、「手持ちの手段(資源)」が拡張され、改めて「何ができるか」を問うことができます。
キッズデザイン賞&グッドデザイン賞をW受賞した「未来の山口の授業 at School」などは、新しい「あり方をデザインする」ことができた、パートナーシップなくしては成立しないプロジェクトのひとつです。
レモネード(Lemonade)
パートナーが提供してくれるのは「手段」だけではなく、新たな「目的」ももたらされることが考えられます。パートナー自身の目的もまた「何ができるか」の方向性に影響を与えます。
予期せずしてパートナーからもたらされた手段や目的を受け入れ、偶然をテコとして活用しようとする発想が「レモネード」です。
意図しない偶然を許容し、「計算のないものへの愛情」をもってポジティブに昇華させるという考え方です。
飛行機のパイロット(Pilot in the Plane)
ここまでのプロセスでは、未来の結果に関する「予測」をしていません。
結果が予測できない高い不確実性のなかでも、自らがコントロール可能な活動に集中することで、最初には思いもしなかったような新しい製品・事業・市場の可能性に到達することができるのです。
予測ではなくコントロールによって望ましい結果を生み出そうとするという考え方は、「雷に打たれる日は来ない」で触れた創発的戦略にも通ずるところがあります。
「何ができるか」を見つめ直してみよう
私は熟達した起業家とは程遠い存在ではありますが、意思決定の根底にエフェクチュエーションの要素が多く含まれていることが分かりました。
一方で、「ありたい未来の姿」から逆算するバックキャスト思考も持ち合わせており、コーゼーションのプロセスを選択する側面もあるようです。
コーゼーションとエフェクチュエーションのどちらが優れているという話ではなく、状況によってうまく使い分けられると良いでしょう。
特に、状況が目まぐるしく変化する不確実性(VUCA)の時代においては、手元の「何ができるか」にフォーカスしつつ、パートナーを集めてできることを拡張していくエフェクチュエーションのプロセスが相性良さそうです。
バラバラに考えていた思考を、ひとつのフレームワークとして整理してもらってとてもすっきりしました。改めてエフェクチュエーションの思考をもって、「何ができるか」を見つめ直してみようと思います。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
