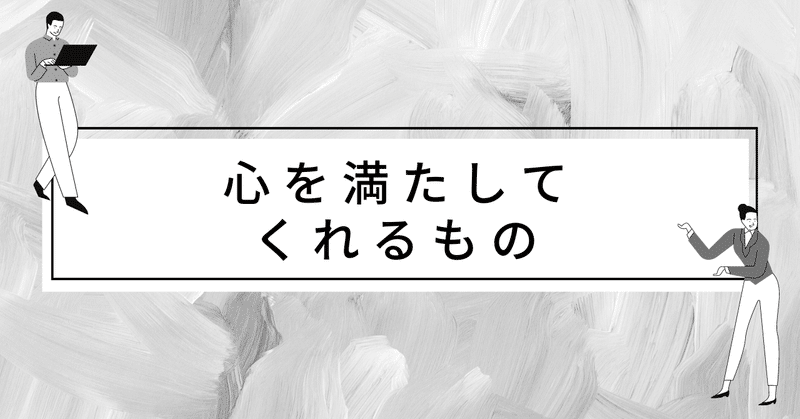
心を満たしてくれるもの
ファブラボやまぐちのWebサイトを、8年ぶりにリニューアルしました。
今回も田中チズコ先生にイラストを描いてもらいました。

書籍の表紙や挿絵・雑誌の連載などを担当されるようになり、昨年はオリジナルの絵本を出版されるなど、あれよあれよと人気作家になられたチズコ先生。8年経った今でも、私たちのオーダーを快く受けてくださって、本当にありがとうございます。
たまたま立ち寄ったイベントでの出会い
チズコ先生のかわいいイラストは、ファブラボやまぐちの印象を決める大切な「顔」です。
ですが、最初からイラストを描いてもらおうと決めていたわけではなく、先生との出会いは本当にたまたまでした。
2015年7月、とある展示会へ行くために、ファブラボ立ち上げスタッフと一緒に東京ビッグサイトを訪れました。その際に、同会場で行われていた「第4回 クリエイターEXPO」というイベントが面白そうだったので、ついでに見ていこうという話になりました。
クリエイターEXPOは、イラストレーター、漫画家、写真家、ライターなど、総勢700名を超えるクリエイターがブースを構えて出展し、来場者と直接商談ができるというイベントです。せっかくの機会なので、全ブースをざっと見て歩くことにしました。
数百あるブースを順番に訪ねていく中で、半分ぐらいきたところで先生のブースが気になり、立ち寄ってお話をさせていただきました。

肩肘張らない少し間のぬけたタッチで
ちょっぴり野暮ったくて親しみやすいイラストを描きます。
と、ご本人がプロフィールで仰っているとおり、まるで子供の頃によく目にしていた、旅先のお土産に描かれているような、かわいくも野暮ったいイラストが妙に新鮮で、とても印象に残りました。
また、会話のなかで感じたご本人の印象が、イラストの雰囲気と完全に一致していたので、「面白い人だな、またお話ししてみたいな」と思いながらブースを後にしたのを憶えています。
ビジュアル先行で決まったコンセプト
クリエイターEXPOのブースを巡っているときの私たちは、具体的に何かを探していたわけではなく、どんな人が出展されているのかなという興味本位の状態でした。
これから手掛けるファブラボのWebサイトを、どんなデザインにしようかなという、ざっくりとした課題は頭の中にありました。ただ、いつまでにどうしたいといった、具体的なプランは持ちあわせていませんでした。
ただ漠然と「初心者でも親しみやすく、敷居が低い印象にしたい」という希望があり、そこにちょっと野暮ったくて親しみやすいイラストが、パズルのピースのようにバチッとはまったのです。
その日の夜、渋谷のスペインバルで食事をしながら感想を共有した際に、あの人にお願いしたら楽しいWebサイトが作れそうだねと、全員の意見が一致して、その場でイラストを依頼することに決めました。
そこからオンライン上のやり取りでコンセプトを決めて、イラスト15点とロゴマークを描きおろしていただき、めでたく初代のWebサイトを公開することができました。

その後のファブラボやまぐちは、イラストの雰囲気に牽引されるかたちで、野暮ったくて親しみやすいイベントやワークショップを開催してきました。ビジュアルがコンセプトを作ってくれたといっても過言ではありません。
「カワイイ」の現代的意義
思い返してみると、私が自分の仕事にかわいいイラストを起用したのは、このときが初めてでした。当時アラフォーのおじさんだった自分と、かわいいものは無縁であるとさえ考えていたかもしれません。
でもこのときは、チズコ先生のイラストを見たときに、自分の口角が5度ぐらいあがった感覚を、Webサイトを通してユーザーさんたちと共有したいと思ったのです。
一般社団法人 情報処理学会が発行している「情報処理」という冊子のなかに、「かわいい」という感性価値についての特集記事を見つけました。

「カワイイ」の現代的意義という章に、以下のような記述があります。
18世紀ころから急進展した西欧近代は、唯一絶対の真理を追求し、最適化、最大化をどこまでも実現しようとしてきた。強い者、優れた者だけが評価され、弱い者、劣った者は排除されて当然という意識が、現代ではグローバルな規模で拡がっている。
だが、多くの人間は、心の中に弱さを隠し持っている。誰もが強く、同じ正義に立つわけでもない。人は不完全で多義的である。その弱さや矛盾を、ありのままに共感し、愛しみ合う関係を、現代人は切実に求めているのではないか。(中略)
「カワイイ」への人々の熱狂は、現代に存在するそのような社会関係への希求を露わにしている。ならば、「カワイイ文化」は、今後、一方で多様な異文化との交配を進めると同時に、他方で、「不完全性」「弱さ」「哀しみ」「悪」をも内部に包含する「可愛い」の哲学を貫くことによって、さらにその魅力と社会的価値を高めるに違いない。
※本特集タイトルの表記は「かわいい」であるが、本稿ではより現代性を強調する意味で「カワイイ」を用いる
これ、分かるような気がします。世の中には力強く洗練されたデザインが溢れていて、ときにマッチョであることを強いられている気がして、疲れてしまうことがよくあります。
そんなとき、人はかわいいものや野暮ったいものに救いを求めたくなるのかもしれません。決して洗練されたものを否定するつもりはありませんが、私自身は専らそうではないもののほうに惹かれるのです。
奇しくも、この特集が執筆されたのも2015年です。もしかしたら私たちがかわいいイラストを描いてくれる方を選んだのは、時代に影響された必然だったのかもしれません。
口角があがる感覚を共有したい
前回の投稿の最後に「今よりも生活に寄り添う仕事を増やし、もっと地域と仲良くなっていきたい」と書きました。私が捉えている生活に寄り添う仕事とは、精神的充足の提供に近いと考えています。
特に、かわいいものやユニークなもの、ときに野暮ったいものに触れたときの、口角があがるあの感じ。あの瞬間、確かに自分の中の何かが満たされている感じがするのです。
そのあたりの感覚に、新しい仕事の種が隠れているような気がします。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
