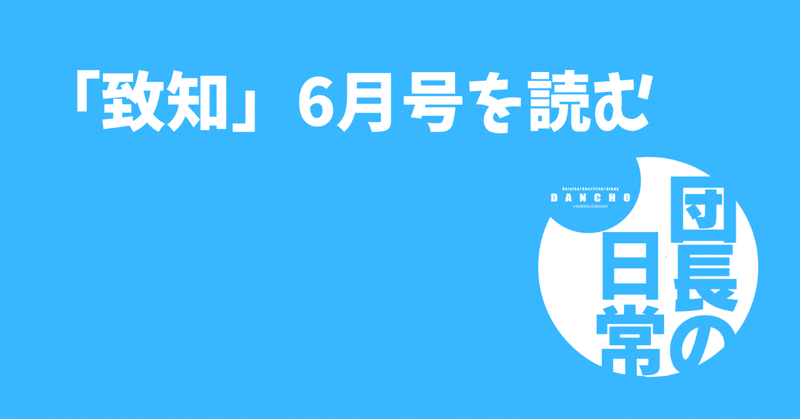
「致知」6月号を読む
毎月初に「致知」が事務所に届く。
「致知」は、"人間学を学ぶ月刊誌"と銘打っている。
昭和51年8月に第三種郵便物に認可されたから、この8月で48周年になる。
ネット時代で紙媒体がどんどん消えていく時代に、「致知」だけはますます読者を増やしているのだ。
日本人は捨てたものではない。
5月初めに届いた「致知 2024年6月号」を読んでいる。
今まで届いた「致知」も捨てることなく、ふと悩んだり、迷ったりした時に取り出して、過去の記事にアットランダムに目を通すことをしているが、何気なく目に留まった記事で、悩んだり迷ったりしていることの解決の処方箋を見つけることがたびたびある。
「致知」は私にとって、そんな"人間学を学ぶ月刊誌"である。
6月号の[特集]「希望は失望に終わらず」の一つに、理学博士の佐治晴夫さんと文学博士の鈴木秀子さんの対談が掲載されていた。
佐治先生は、長年宇宙の摂理を探究する中で、宇宙生成の法則が人間の生き方の法則と不思議なほど一致しているのだと仰る。人生で直面する様々な困難や試練も、その法則を知ることで解決の糸口が見えてくるのだと。
シスターとして信仰の一道を歩み、多くの人たちを幸せに導いてこられた鈴木先生と共に、「失望を希望に変えていく道」を語り合われた対談は、「人間とは何か」「人間にとって幸せとは何か」を教えてくれるものだった。
人生で起こるすべての出来事をよきものとして受け入れる。これは現代宇宙論の考え方にも通じるものだ。
年を取ると、病気はするし運動能力は落ちる。いろいろなネガティブな面が出てくるのですが、逆に年を取ってからでないと分からないこともたくさんあるんですね。また、年を取ったからこその出会いもある。人間、年を取ると面白くなるというのは本当ですね。
人間の寿命について、
私たちは身近な人や友人など「他人の死」に遭遇します。これは現実として受け止めることができる。しかし、自分が死ぬ「一人称の死」は意識することができません。
自分にとって時間とは一体何なのだろうかと、カトリック教会の司教で哲学者だったアウグスティヌスは「現在イコール永遠」と定義しました。
私たちは過去を過ぎ去ったものと考えますが、そう考える自分は現在にいる。先のことを考える自分も現在にいる。つまり、過去も未来も現在に含まれ、それが永遠に続くというんです。
私たちの人生は、「いま、ここに」しかないんです。人生は突き詰めると、「いま、この時を生きていくことだ」というのが私の人生観です。
偶然という幸運の女神は、準備された心にのみ降り立つ。
出会いに偶然はなく、必ず何らかの意味があります。
人生における一つの出会いが如何に小さなものであっても意味がある。
自然界のすべてを含めて互いが独立した存在ではなく、それぞれが相互依存である。「あなたがいて、私がいる」という関係にある。
すべてが相互関係にあるのであれば、お互いに気づかないところでお世話になっているだろうし、逆に気づかないところで相手を傷つけてしまっているかもしれない。
そこに思いを馳せる時、湧き上がってくるのが感謝と悔い改めの心です。「ありがとう」「おかげさま」「お互い様」「ごめんなさい」。この4つの言葉が、混乱する現在の社会を救うキーワードになると思っています。
この世には独立したものは存在せず、すべてが他との依存関係による。
慈悲の慈とは、「人に安らぎをあげられたらいいな、と心から願うこと」、悲とは「人の苦しみや悲しみを、和らげてあげられたらいいな、と心から願うこと」です。
「あの辛かった体験のおかげでいまがある」と感謝する。
あなたのこれからがあなたのこれまでを決める。
「いまさら」の"さ"を"か"に替えて、「いまから」ですね。
人間が最も成長できるのは試練の時、苦しい時なんですね。
苦しい出来事を神様の助けをいただきながら、一段一段乗り越えるところに人間の成長があり、それが大きな恵みにもつながっていく。
「この試練にも必ず意味があるし、試練に向き合う自分のことをすべて分かって支えてくれる神様が共にいてくださる」と思えば力が生まれて、やがて希望も生まれるのではないでしょうか。
患難も忍耐も一見辛いことのように思えますが、それがないと私たちはわがままな人間になってしまいます。
忍耐することで人間が練り上げられ、後に自分が思いがけないほどの力がついてきていることに気づく日がやってくるんです。
紛争のきっかけは自他の区別にあります。そこに相互依存という認識が芽生えれば、少なくとも紛争は減っていくはずです。
一人ひとりの小さな思いと行動、小さなゆらぎによって、信じられないようなことが実際に起こるんですね。
実に心が洗われる対談だった。
不動院重陽博愛居士
(俗名 小林 博重)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
