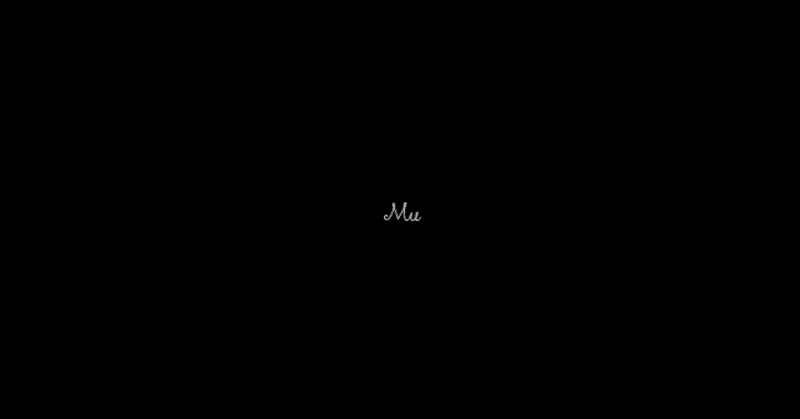
インターフェースは無を指向する
スマートフォンの普及をきっかけに、ユーザーインターフェース(UI)の出来の良さがサービスやプロダクトの重要なポイントとして語られ、議論されるようになりました。
もちろん、それ以前にもUIの重要性については議論されていましたが、例えばアプリのレビューで一般的なユーザーが「UIがいけてない」とか書くようになったことはUIという言葉が一般的になり、かつタッチデバイスでのユーザー体験(UX)におけるUIの重要性が上がったことの証左なのかなと思います。
デバイス・プラットフォームによる依存
では、UIデザイナーは革新的なかつ独特な使いやすいUIを作りあげれば、プロダクトのUXをより良くできるのかというと、そうでは無いと思っています。
アプリやWebの開発に関わったことのある方には馴染み深いと思いますが、AppleのApple Human Interface GuidelinesやGoogleのMaterial Design、MicrosoftのMicrosoft Designなど、各プラットフォームごとにUIのお作法というものがあります。
多様なプロバイダーが提供するプロダクトでも、同じプラットフォームで使い慣れたUIを踏襲することで、学習コストが少なく、使いやすく、より良いUXを提供できます。
なので、各プラットフォームのお作法を守りつつ、プロダクトの特徴やコンセプトを取り入れて形にするのが、UIデザイナーの腕の見せ所だったのですが、今後はそれも変わっていくのかなあ、と思っています。
UIの個性化、もしくは無
まさに消えるUIの流れ https://t.co/ccRl47UQYP
— ottiee (@ottiee) February 5, 2020
引用した2020年のUIトレンドで、特に「4.コンテンツがブランドになる」で触れられているように、プロダクトのUIは今後、無個性化する流れになると思っています。
UI自体がブランドになっている、例えばPinterestやTinderなどがそうですが、そういうものも標準的なUIとして取り込まれ、さらにプロダクトごとの差異は無くなっていくと思います。
これはUIの無個性化の流れですが、その先にはおそらく「インターフェースの無」が来ると思っていて、UIをユーザーが全く意識せず自由にコントロールできるような時代になってくるのかなあ、と。
改めて、デザイナー(特にUIデザイナー、僕自身もそうですが)はどうやってコンテンツを引き立て、UIを「透明」、僕の言葉で言うと「無」にしていくかを考える時期に来ているのだと思います。
終わりに
いつもTwitterで無を観測してはつぶやいているのはこう言う思考があるからです。勤勉でよいですね。嘘です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
