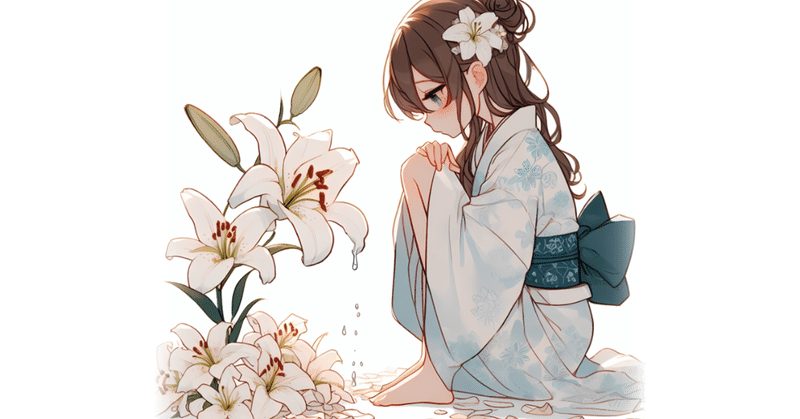
斜線堂有紀氏の「徒花は今、新たに芽吹く」を考える
【特報!!】
— 実業之日本社 文芸出版部 (@JITSU_NICHI) April 25, 2024
『貴女。 百合小説アンソロジー』
2024年6月27日発売決定!!
豪華執筆陣は、
青崎有吾、織守きょうや、木爾チレン、斜線堂有紀、武田綾乃、円居挽 (敬称略)
新時代のトップランナーが贈る
全編新作アンソロジー、待望の第2弾!
予約は4月26日午前0時より順次開始予定です。 pic.twitter.com/zOiEcL2aA8
2024年4月、百合小説アンソロジーの発売日が告知されました。謳い文句には「新時代のトップランナー」と表現されています。
7月6日発売 吉屋信子「返らぬ日」の解説を担当しました。一冊通して少女同士の愛を描いた傑作百合小説であり至高の少女小説の復刊です。時代を切り裂き今に届く少女達の愛を刮目してください。徒花は今、新たに芽吹く。 pic.twitter.com/R5I10TGhWa
— 斜線堂有紀 (@syasendou) July 5, 2023
そのなかに斜線堂有紀氏の名前があります。この方といえば、上記の「徒花は今、新たに芽吹く」が批判されたことで記憶に新しいです。
実際にされた「徒花は今、新たに芽吹く」への批判理由
過去の女性同性愛差別を肯定しているのではないか
現代日本でも当時と同様に養子縁組する他に法的な関係を結べない現状を認識していないのではないか
こういった批判に対して氏は以下のように返答されています。
こんにちは、この度は言及して頂きましてありがとうございます。解説中でも、今でもまだ同性婚ができないことに触れた上で、けれど愛を愛として尊び、センチメントで終わらせない精神が今も篝火となっていることを「日曜病」を引きつつ書かせて頂いておりますので是非お手に取ってみてください。
— 斜線堂有紀 (@syasendou) July 6, 2023
今は徒花ではないというのか? という点において、私はこうして沢山の方が差別に反対し声を上げたり、龍陽さんのような方がこうして疑問を提示してくださることで、徒花の時代は終わり実を結ぶ段階に来ているのではないかと考えております。
— 斜線堂有紀 (@syasendou) July 6, 2023
丁寧な返信本当に痛み入ります。そう仰っていただけること、心より嬉しいです。徒花という表現は吉屋先生ご本人も用いていたものですが、今こうして龍陽さんのような方がいらっしゃってくださることを見れば、吉屋先生であればもはや徒花ではないと言ってくださるのではないか、とも思っております。
— 斜線堂有紀 (@syasendou) July 6, 2023
私はこの返答で認識が誤っていないことを証明できたようには感じません。解説した作品の著者が「徒花」という表現を使っていたからというのは何の反論にもなっていませんし、ましてや社会に深い理解をしている人がたくさんいるので良いというのも現状を無視した典型的な無関心層の発想です。(そもそも「こうして疑問を提示してくださる~」は自身に対する批判の矛先を無理やり明後日の方向へ持っていこうとしているようにしか見えませんが。)
レズビアン・ムーブメントは、私の目には、まだ始まったばかりのように見えます。最近やっと、本格的な活動をする人が出てきた、という感じです。私もレズビアン活動に二年間かかわってきましたが、今、個人個人が二重の戦略を取るべきだと感じています。
一つには、現在、一般の社会においてレズビアンが見えていないので、そこで、「私はレズビアン、この人もレズビアン」とあえてラベルを引き受ける必要があるのではないかということです。二つ目には、個人的にはセクシュアリティを自己アイデンティティの一側面にすぎないのだと捉えるということです。確かにセクシュアリティは重要ですが、「どういうふうに生きていくか」という面をトータルにみてゆく必要があります。
「レズビアンは特別なものではなく、自分にはそういう側面もあるだけなんだ」と本当は言いたいのですが、ゲイやレズビアンが見えていないそんな今の時点で、そう言ってしまうと、「日本史上、一人もレズビアンがいませんでした」ということになってしまうのではないでしょうか。それで私はあえて先ほどの第一の、「レズビアン」というラベルを引き受けるつもりです。具体的な運動の方向性としては、あくまで文化的・芸術的なものでいきたいと思っています。
(1999年4月10日第1版第1刷)
第二章 「アート」の力を信じて――荒瀬直子さんの場合
63ページより引用
[インタビュー]1994年9月11日
上記の当事者インタビューは本記事公開日から30年ほど前のものですが、果たして現在の日本はここから進歩しているでしょうか。今の時代の日本は、誰かが積極的に「レズビアン」のラベルを背負って社会に訴えなければならないところを脱している段階に来ているでしょうか。
そう考えると、やはり「徒花」というのは軽率が過ぎるように思います。
さて。読んでみたら誤解だとわかるそうなので、実際に読んでみました。以下、表記を一部略しますが、河出書房新社の吉屋信子『返らぬ日』からの引用となります。奥付によると、2023年7月10日初版印刷、2023年7月20日初版発行となっております。

これは、百合がまだ徒花であった頃の、傑作少女小説である。あるいは、正統派百合小説である。
ここに収録された作品は全て、一九二三年から一九二八年までに発表されている。二〇二三年現在から見てなんと約百年も前に綴られた物語だ。それでいて、描かれた少女達の心の揺らめきは、今もなお多くの読者を引き込むだろう。その筆の瑞々しさ、繊細な心の交流は、現代の百合好きにも響くだろうからだ。そして何より、彼女達の愛に対するひたむきさ、自らの愛を全く疑わぬ強さこそが読者のことを引きつけるだろう。この一冊は、徹頭徹尾愛というものを賛美している。
冒頭に「ドン!」と突きつけられる「これは、百合がまだ徒花であった頃の、傑作少女小説である」です。私は本の帯に掲載されたこの一文が文章全体のどこかの一部なのかと思っておりましたが、どしょっぱつにインパクト重視で埋もれにくいように置いてあったのです。これではもうこの時点で読みたくなくなる人も出てきてしまうでしょう。
では、本人が主張するように、この解説に対する差別批判がどれだけ的外れなものなのか、最後まで読んで改めて確認してみましょう。
現在では、徒花と散らず想いを実らせる百合小説も多い。現実の同性愛に関しても亀の歩みではあるが、法整備が進んでいる。愛する二人が結ばれることは、前ほどは夢物語ではなくなった。足りないところは多々あるけれど、愛をふみにじることに対しての抵抗は生まれてきているのだと思う。
これは驚きました。「法整備が進んでいる」とは、具体的にどの件のことを書いているのでしょうか? 例えば「LGBT理解増進法」なんて、政権政党が「国民の理解が追いついていない」と無理な言い訳をして、性的マイノリティ保護のやってる感を出すためだけの法律です。しかも、そんな理解増進の法でさえ、ごく一部の特定支持団体にご配慮し、ムダに揉めていたという有り様です。
それとも各自治体のパートナーシップ条例あたりのことを指しているのでしょうか? 条例は「法」ではありませんが、「法も条例も、どうせ似たようなものなんだから、細かいことは気にするな」ということなのでしょうか。
そもそもこの「解説」からは実際に活動されている方々への敬意がまるでなく、「なんとなく改善するムードになってきているから気楽な気分でやっていこうぜ」という、努力している先人を足蹴にする態度で呆れる他ありません。「敬意」は大げさだと言うのであれば、せめてそれなりに尊重の姿勢ぐらいは示すのがマナーではないでしょうか。
「選挙に絶対行きたくない家のソファーで食べて寝て映画観たい」の期間限定全文公開が終了しました! 皆さん沢山読んでくださってありがとうございました! https://t.co/6jCuhRPNfm
— 斜線堂有紀 (@syasendou) May 8, 2023
これだけ同性愛者差別に対する関心の無さで改めて感じましたが、同氏の『選挙に絶対行きたくない家のソファーで食べて寝て映画観たい』(『百合小説コレクション wiz 』収録)は令和の今ノンポリの傲慢さが最大限に発揮された小説です。人間ひとりひとりに行動の許容量があるので、すべての当事者が活動に参加しなくてもいいわけですが、「社会が悪い」だの言い訳をして活動参加している人を蹴り飛ばすような話を正当化するのはあまりに醜悪ではないでしょうか。
結局「徒花」にしろ「選挙」にしろ、同氏にとっては初めから真剣に考える対象ではないのかもしれません。しかしそれは、ただの思考停止にすぎないということを、読者は理解する必要があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
