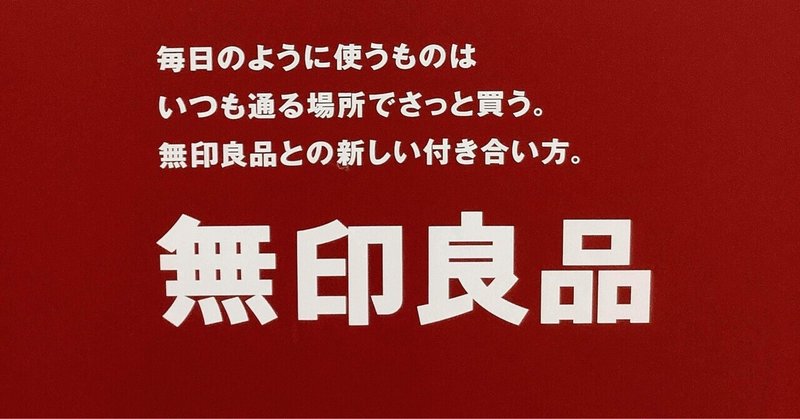
『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』
おはようございます🌞おたけです。
こちらの記事では、最近読んだ本を紹介します。
『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』松井忠三、角川書店、2013
株式会社良品計画会長であった松井忠三さんが書かれた『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』を読みました。
印象に残った部分を書き留めます。
「それぐらい、口でいえばわかるのでは?」と思われるようなことまで明文化する。これは“仕事の細部”こそ、マニュアル化すべきだという考えがあるからです。
細かすぎることまでマニュアル化されていると、新人教育がしやすいと思いました。
例えばベテランが新人に教えるときに、
ベテランが当たり前だと思って使ってる専門用語を乱立されるとその時点で嫌になってしまうからです。
そうではなくて、明文化して誰が見てもわかるようにすることで、
マニュアルを見れば仕事内容が頭に入ってくる、何をやればいいかがわかるようにする、
というのは結果的に効率的になると思いました。
そして、毎月マニュアルが更新されるようです。
これについても非常にいいなと思いました。
マニュアルと聞くと、形骸化してあってないようなものというイメージがあったのですが、良品計画では違うようです。
社員の息がかかったマニュアルは、業務効率をアップさせます。
優秀な人を採用するためにコストをかけるのではなく、優秀な人材を育てるべく社内に人材育成の仕組みを作るほうが、時間はかかっても組織の骨格を丈夫にします。
優秀な人材は集まらないので、育てる仕組みを作ろうという考え方です。
具体的にいうと、中途採用などで高年収を提示して、優秀かつ異色の経歴を持つような人材を雇うのではなく、
新卒採用でポテンシャルがありそうな人材を育てていくということでしょうか。
これによって、企業側も人件費が抑えられるし、将来の幹部候補をいち早く育てられそうで良いと思いました。
無印良品では、全員を「さん付け」で呼ぶように徹底しています。
部下に対しては、男性も女性も「さん」、上司に対しても「さん」です。
このような話をよく聞きますが、
実際に組織内でどれだけ定着しているかは謎です。
アルバイト同士だとあだ名で呼んだり、下の名前+ちゃん付けで呼んだり
ということはザラにあるのではないでしょうか。
「徹底しています」ということですから、かなり浸透していると考えていいのでしょうか。
ともかく、この「さん付け」には「風通しをよくする」という効果があるようです。
確かに、言霊というものがあって、日頃から上司を「〇〇部長」と呼んでいると
「あ、この人は部長だから私よりくらいが上だ、何も意見できない」という思考になってしまうかもしれません。
「さん付け」にはこれを防ぐ効果がありそうです。
日本のビジネスマンの生活を見てみると、対照的です。
早朝から夜遅くまで働きづめで、週末は仕事の疲れから出かける気力も起こらない。そんな会社人生を何十年も送り、定年を迎えた頃、自分には何が残っているのでしょうか。
無印良品の社員もみな仕事に熱心で、残業するのは当たり前という風潮がありました。特に商品部の社員は毎日終電まで仕事をし、週休二日のうち、一日は洗濯や掃除で追われ、もう1日でなんとか休めるという状況でした。こういう生活を送っていては、生産性は上がらないし、仕事のアイデアもなかなか生まれません。
そこで、私は社員の残業を無くそうと決意しました。
日本人は本当に働き者ですよね。
残業を無くそうとしましたが、急には無理だったようです。
最初は週に一日から「ノー残業デー」を作ることにし、段階的に全員定時退社を目指していったのです。
段階的にやるのはとてもいい発想だと思いました。
時間があると、ある分だけ仕事をしてしまうのが日本人の悪いところかもしれません。
やらなくてもいいことはやらない、
明日でもいいことは明日やる!
こんなことを肝に銘じたいと、読んでみて思いました。
以上、『無印良品は、仕組みが9割 仕事はシンプルにやりなさい』を読んでみての感想でした。
最後までお読みいただき、
ありがとうございました✏️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
