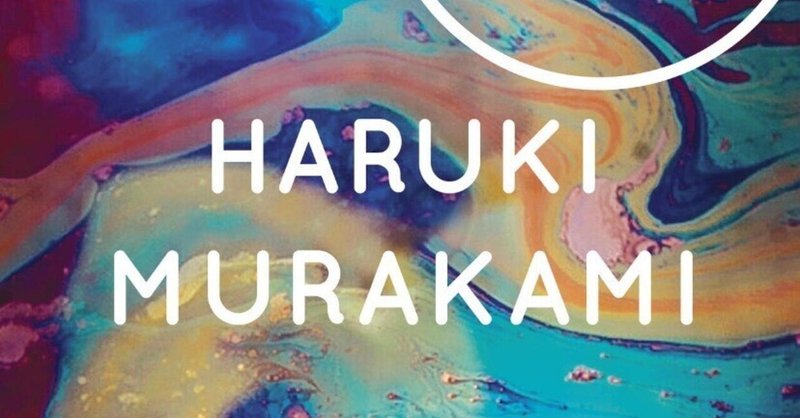
【洋書多読】After the Quake (251冊目)
After the Quake by Haruki Murakami
総語数: 34,839 Words
開始日:2024年4月23日
読了日:2024年4月29日
多読総語数: 10,400,348 + ? words
村上春樹の短編集『After the Quake』を読了しました。
こちらは「神の子どもたちはみな踊る』というタイトルで、同じ短編が収録された文庫本が新潮社から発売されています。
今回本書を手に取った理由は、先日ご縁があってスポットで授業をさせていただいた福岡市内にある某日本語学校で教材として使用したかったため、です。
そのクラスは、何でも日本語を学びに来ている外国人に「翻訳」を教えるクラスだそうなんで、担当の先生が急にレッスンができなくなってしまい、かと言って代役がそう簡単に見つかるわけもなく…という状況で困りはてた校長先生が、手当たりしだいに知人に「英語ができて日本の文学にもそれなりに通じてて、英語の先生なんかをしている、日中それなりに暇な、そんな(レアな)日本人が福岡にいないか?」と聞いて回っていた中でご縁がつながったものです(見つかるんですね)。
外国人が日本語で読んだ小説を英語に翻訳するクラス。その講師として急遽白羽の矢を立てていただいた僕がすぐに思いついたのが、村上春樹の翻訳でした。
世界中で読まれている村上春樹には、非常優れた英訳版がたくさんあります。僕自身も英語版・日本語版もそれなりに読み慣れているし、前に「村上春樹を英語で読んで日本語を考える」クラスをセブ島の語学学校で複数回やったことだってあります。
要はそれの逆をやればいいんだろう?と。
その時は『4月の晴れた日に100%の女の子に会うことについて」という短編を使いましたが、今回は「海外で一番読まれている村上春樹の短編」と言われている『かえるくん、東京を救う』を題材に選ぶことにしました。
その短編が収録されているのが『After the Quake(邦題:『神の子どもたちはみな踊る』)』だったというわけです。
とても楽しくて、ハッピーな読書体験でした
本書を英語で読むのは初めてでしたが、『神の子どもたちはみな踊る』なら、複数回読んだ記憶がありますし、『かえるくん、東京を救う』だってよく知っています。
そんなわけなので「一度日本語で読んだことのある英文」という、英語力アップと英文読解に大変有効な条件を兼ね備えた一冊を手に取るきっかけを与えられることになりました。
読みはじめてすぐに「楽しい」と思いました。
今日も筑前前原駅(福岡県糸島市)に向かう電車の中で、かつてツイッター(現エックス)で頂戴した「英語学習に楽しいものなんかあるか、おまえそれでも英語講師か?このクソが」的な趣旨のたくさんのクソリプのことを思い出していました。
僕にとっては英語力とは楽しんだものが伸ばすことのできるチカラだと思っているので、糞だなんて以ての外です。
というか、苦しまないと英語が伸びないと思っている人って本当に気の毒だと思います。だって人生の大半の時間をそんな「苦しいこと」に費やして、そのあと訪れるつかの間の「達成の瞬間」の、ほんの一瞬の喜びを求めているんだから。
そんなコスパの悪いこと、僕は絶対やりたくないです。
そんなわけで、現代日本最高峰の文学を当代一流の日→英翻訳者が訳した一流の英文で読めるという僥倖を心ゆくまで堪能した上に「翻訳の授業の先生という経験(時給5,000円×2時間)」というおまけまで頂戴してしまって、英語学習において苦しむことこそを至上としている人ほんとごめん…みたいな素敵な時間を過ごすことができたのでした。
英語はまあそれなりに難しいです。文学だし。
ま、でも万人におすすめできる一冊か?と言われればやっぱりそうは問屋が卸さないです。
語彙や熟語の難しさはもとより「ザ・ハルキワールド」とでもいうべき文学的、哲学的な表現も満載です。たとえTOEIC900オーバーの方でも、英検一級ホルダーでも、村上春樹に興味がない人は読みすすめるのは辛いでしょう。
でも、この村上春樹的哲学表現の部分はネイティブのアメリカ人も英訳された『かえるくん…』を読んで「Oh my…」と言っていたので、ネイティブ日本人の僕が読んでもちょっと苦しいハルキワールドの部分はこれはもう語彙力や読解力を超えたメタフィジカルな難しさなのでしょう。そのニュアンスまでをも見事に英語にトランスレートしているジェイ・ルービン氏、本当に職人です。
そんなわけで、『After the Quake』と過ごした一週間は、僕には本当に幸せな時間でした。大好きな村上春樹の英語を読めて、しかもネイティブのアメリカ人と、翻訳の授業で、そのニュアンスの違いや言葉遣いの細やかさ、繊細さについて思う存分語ることができたわけですから。
ずっと「多読なんか意味ない」「クソ」などの罵声に耐え続けてそれでも多読を続けてきた僕に神様がくださった最高のご褒美の時間だった、本書の読書体験にはそんな感じさえしています。
それでも英語が好きだ!
柴田元幸先生の『翻訳教室』という本が朝日文庫から出ていて、その本でもこの『かえるくん〜』は取り上げられていたと思います。そちらも随分ワクワクしながら読んだ記憶があります。
もちろん僕の授業はそんな柴田先生のそれには遠く足元にすら及ばないのはわかっています。僕のレベルで柴田元幸先生を語るな、と。
でも『翻訳教室』の行間から伝わってくる、「英語が好きで好きでたまらん!」という英語に対する想いだけは、自分だって決して柴田先生に劣っていない、そんなことを思ったりしたのでした。
ちなみに授業は大成功で、生徒さんたちからの評判も良かったらしく、そのことを校長先生が評価してくださって、スポット授業が終わった今も、光栄かことにささやかな友託を賜っています。
『After the Quake』は、僕の英語との向き合い方やお付き合いの仕方が、たとえ人とはかなり異なっていたとしても、決して間違ってなんかいなかったっていうことを思い出させてくれる一冊でもありました。
決して易しくはないですが、この記事をお読みくださった方が一人でもたくさん『After the Quake』を手にとってくださり、至福の時間を過ごしてくださることができたなら、タドキストとしてはこれ以上、多とすることはありません。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
