
◆読書日記.《エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』》
<2023年11月15日>
<本書の概要>
ドイツ生まれのユダヤ人、社会学者・精神分析学者E・フロムが亡命地アメリカで書いた代表作。1941年刊。ナチズム台頭の因を社会、経済的側面からだけではなく社会心理学的側面から分析する必要を論じて注目された。人間やある社会階層が政治、経済的危機状況に置かれたときにおこる「権威主義的性格」をマゾ・サド的側面から解明。ファシズム運動を、一方ではヒトラーの権威に従いその犠牲になることに喜びを感じ、他方では自分より劣った者たとえばユダヤ人を蔑視(べっし)・虐待し、欲求不満や劣等感を解消しようとした心理や行動の現れとして描いている。個性の喪失と画一化が進行している現代社会に対しても示唆に富む。
<著者略歴>
1900年、ドイツのフランクフルトに生まれる。ハイデルベルク、フランクフルトの大学で社会学、心理学を専攻し、1925年以後は精神分析学にも携わり、精神分析的方法を社会現象に適用する新フロイト主義の立場に立ち、社会心理学界に重要な位置を占めた。ナチに追われてアメリカに帰化し、メキシコ大学などの教授を歴任。1980年没。
<本書の概要と著者エーリッヒ・フロムについて>
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』読了。
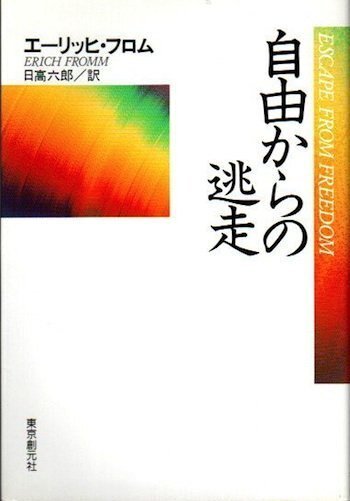
フロムはフロイト左派として、フロイト理論を受け継ぎながらもフロイトは人間心理の社会的影響を視野に入れなかった事を批判する立場を採る。
本書はその社会心理学の立場からファシズムを支持する群集心理を批判的に分析する。
ぼくは『正気の社会』を読んでからのフロムのファンである。
フロムはユダヤ教正統派の両親の元でドイツに生まれ、そのためにドイツ国内で反ユダヤ主義が優勢になりナチスが政権を掌握すると、国外へ移住する事となった。
本書はそんなフロムの移住先アメリカが二次大戦に参戦した1941年という、大戦真っただ中の時期に書かれた。
西洋的な精神とは、中世の民衆に代表される封建社会の「支配‐服従」的心理構造から脱して、民主主義という自らの自由意思で自分らの事を決める「自立した個人」と「自由」とを手に入れる精神史を歩んできた(という認識があった)。
西洋人にとって、自らの手で「自由」を獲得した歴史があるからこそ、「自由」という言葉には大きな意味がある。
ジョン・スチュアート・ミルが『自由論』を書き、ハロルド・ジョセフ・ラスキが『近代国家における自由』を書いて、近代人にとって「自由」という考え方がいかに重要かを確認して来たように、西洋人は文字通り血のにじむような努力をもってして近代的な「自由」を手にし、それを維持してきたのである。
フロムも本書の冒頭で「近代のヨーロッパおよびアメリカの歴史は、ひとびとをしばりつけていた政治的・経済的・精神的な枷から、自由を獲得しようとする努力に集中されている(P.10)」と指摘している。
それはヘーゲル的に言えば人が(とりわけ西洋人が)「絶対精神」「理性」を獲得する歴史でもあった。
だから、もう寡占的な封建国家のような、民衆が不自由を強いられる支配体制を近代人が望むはずがない、「理性」を手にした近代人が、そんな愚かな事を二度とするはずがない――という確信を粉々に崩したのが二度にわたる世界大戦という経験だった。
そしてそれは、まさにヘーゲル的な「絶対精神」を手に入れ歴史の頂点にあると確信されていた「西洋世界」を中心として巻き起こった事件でもあったのだ。
二次大戦の特徴として、封建社会に退行するかのような全体主義を、デモクラシーを手にしたはずの「自立した民衆」が支持してしまった。
文明の頂点にあるはずの理性的な近代人が、自ら「自由」を放棄し、嬉々として「支配‐服従」関係を受け入れたのである。
なぜなのか?
――という問題から、そういう「ファシズムを支持してしまう民衆の心理」の謎を追求するのが本書の目的となる。
だから、本書のテーマは非常にシンプルである。
しばしば名著と呼ばれる本はそのメインテーゼが非常にシンプルだったりするものだが、フロムの本もそれに当てはまるだろう。
冒頭にも述べたように、フロムはフロイト左派と呼ばれフロイト理論を踏まえながらも、それを社会心理、群集心理に適用した。
そしてそのスタンスは、フロムの学説の中軸となり、彼によるフロイト批判の中軸にもなった部分でもあった。
フロイトは人の精神分析を自己充足的なものとして追求した部分が大きい(人間精神を自然の本能に根差した完結体として構想した)とし、フロイトは人間が社会的存在であるという事実を見落とし、社会と人間心理との相互関係について考察を行わなかったというのが、フロムのフロイト批判である。
フロムの心理学の特徴は、人の性格というものは社会と個人とのダイナミックな相互影響関係によって成り立つものだとしている所であろう。
「社会」が細胞分裂して「個人」になるわけではない。「社会」とはそもそも「個人」が集まってできたものである。
だから、その「社会心理」や「群集心理」というものは、必ず「個人の心理」から始まっているものだ。それゆえ、まず個人の心理分析がなければならない――というのがこの社会心理学の前提としてある。
そして、フロムがフロイトを批判したように、個人というものはそれ自身や家族など近しい関係によってのみ性格特性が決まるのではなく、少なからず「社会」からの影響も個人的な性格形成には関わっている。個人の生活習慣や育成環境や家族の発言内容など、それら全て社会的な構造が反映されたもので、それらが個人に影響を与えないなどと言う事はありえないというわけである。
だから、人の性格というものは社会的な影響を受け、社会的な影響を受けた個人が集まって社会になっているという、ダイナミックな相互影響関係によって成り立っているのだ。
社会的性格は、社会構造にたいして人間性がダイナミックに適応していく結果生まれる。社会的条件が変化すると社会的性格が変化し、新しい欲求と願望が生まれる。これらの新しい欲求が新しい思想を生み、ひとびとにそれらの思想をうけいれやすいようにする。これらの新しい思想が、こんどは新しい社会的性格を固定化し強化し、人間の行動を決定する。いいかえれば、社会的条件は性格という媒体を通して、イデオロギー的現象に影響を与える。他方、性格とは社会的条件にたいする消極的な適応の結果ではなく、人間性に生得的な生物学的要素にもとづく。あるいは歴史的進化の結果内在的となった要素にもとづく、ダイナミックな適応の結果なのである。
フロム学説の特徴がここに良く現れている。
フロムにとって人間とは、あくまで「社会的存在」である事が大前提なのである。
すなわち、フロムは個々人の性格分析を行うのではなく、その社会に住む人々に共通するある心理的構造を引き出し、それが社会的構造とどういう影響関係を形作ってきたのかという事を分析する事で「社会心理」を炙り出そうとするのである。
<本書の構成について>
ここで念のため、本書の全体構成を把握しておこう。
・序文
・第一章 自由―心理学的問題か?
・第二章 個人の解放と自由の多義性
・第三章 宗敎改革時代の自由
1 中世的背景とルネッサンス
2 宗敎改革の時代
・第四章 近代人における自由の二面性
・第五章 逃避のメカニズム
1 権威主義
2 破壊性
3 機械的画一性
・第六章 ナチズムの心理
・第七章 自由とデモクラシー
1 個性の幻影
2 自由と自発性
・付録 性格と社会過程
本書ではまず、近代に至るまでに西洋が獲得した「自由」とはどういうものだったのかを、歴史的精神史として振り返って確認する所から始まっている。
上の目次を見てもお分かりの通り、西洋世界においては「宗敎改革時代」と「近代」とでは、「自由」というものの意味している所は違っているのだ、というわけである。
これをぼくなりに両者の違いを簡潔にまとめさせてもらうならば、「自立した個人なき自由」と「自立した個人の自由」という事になろうか。
西洋中世社会においては「個人」の自由というものは著しく制限されていた。
明確に階級が分かれており、その階級は絶対的なものがあった。個人は生まれた環境によってその人生はほぼ半ば以上決定しており、決まった階級社会の中で決められた職業につき、周囲の期待する役割を務める事が個人の人生であった。
例えば中世ヨーロッパの全人口のほぼ9割を占めたと言われる農村の人々が、将来は貴族になるんだ!という夢を持ってもそれが叶えられる道があるわけではないし、同じように大道芸人になりたいとか画家になりたいとかという選択肢があるわけではなかった。
彼らの人生は子供の頃から両親の望む職業に就くと決められており、その環境の同僚ら――農業であったら周辺農家であったり、職人だったらギルドであったり――の期待する役割を粛々と務めあげる事が当然だったのである。
かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割(それは当時においては自然的役割でもあった)という点でのみ、自分の存在を意識していた。また他人も「個人」としては考えなかった。町へやってきた百姓は異国人であり、同じ町のなかでさえ、階級のちがう人間はたがいに異国人と考えられていた。自分自身は他人や世界について、それを分離した存在として考えるような意識は、まだ十分に発達していなかった。
(※余談だが、こういった感覚は近代まで日本の農村では根強く残っていたものと思われる。更に言えば、そういった封建主義的な感覚は、日本の農村だけでなく、まだ日本の様々な組織文化の中からは完全に拭いきれていないものとも思われる。その点については過去、宮本常一『庶民の発見』のレビューにて軽く触れているので参照されたし)
そんな彼らにも「自由」はあった。
が、それは自分の役割の小さな枠組みの中での小さな自己決定の事でしかなく、家に帰ったら何をやるだとか、そういった個人的な生活の枠内の事であって、それが「自由」だと思っていたわけである。
フロムも本書にて「しかしこのような社会的地位の限界を破らないかぎり、自由に独創的な仕事をすることも、感情的に自由な生活をすることも許された。(P.53)」と指摘している通りである。
これがぼくが上に、中世ヨーロッパにおける「自由」を「個人なき自由」と書いた理由である。
それに対して、近代人の「自由」とは自分の将来は自分で決めて、自分が何者であるのか、どういう人生を歩みたいのかという事は自分の自由意志で決定してやっていく、自分の人生を他人に決定されるのではなく、自分で自由に決める事ができる――それが近代的な「自由」の概念になったし、その自由を行使できる人間が近代的な意味での「個人」となったのである。
そもそも民主主義というのはそういう「自由」を行使していくという事で、国の事は他人(支配者)任せではなく、国の構成員である個人個人がそれぞれ「自分が国を動かしていかねばならない」という意識を持っており、だからこそ自分たちの住む国や地域の事について関心を持って政治に対して口を出して行く――それが民主主義というものだった。
その自由な民主主義の最先端にあると思われたはずのドイツが――ナチス政権が国を掌握してからは、時代に逆行するような事をし始めたのである。
何故か? この本書最大の謎を社会心理学として解明するのが第五章の「逃避のメカニズム」であり第六章の「ナチズムの心理」であった。
そして、そのナチズムの心理に対抗するため、健全な近代人のための本来の「自由」とはどういった心理なのか、そしてそういった健全なデモクラシーを確立するための社会とはいかなるものなのか、という事を提示する「第七章 自由とデモクラシー」で本書は締めくくられる事となる。
このようにざっと本書の全体構造を見渡してみても、西洋人にとって近代に至ってやっと獲得する事の出来た「個人による自立した自由」というものが、如何に重要な考え方だったのかが分かる。
だからこその、近代に起こった全体主義による「民衆の自由の放棄」という現象のインパクトが如何に大きかったのかというその理由も想像に難くないだろう。
<『自由からの逃走』は過去の問題ではない>
本書はこのように、基本的には第二次大戦中にナチスを支持する民衆の心理を分析した、西洋人による西洋的精神分析であったと言えるだろう。
それゆえ、本書のテーマは時代的にも地理的にも、二重の意味でわれわれ日本人には「遠い」という風に思えてしまうかもしれない。
だが、ぼくが以前から言っているように、こういうわれわれの地点から隔たった「外部の視点」というものは逆に重要で、自分たちが常識だと思っている考え方を相対化してくれる力があると考えている。
それに、この問題の焦点にあるのは「こういうファシズムが過去にあった」という歴史的事実を振り返って反省する事にあるわけではなく、また「近隣のファシズム国家を警戒する事」が眼目にある訳でもない(それも確かに重要な点ではあるが)。
それよりさらに重要なのは、こうしたファシズム的な心理はわれわれ現代人の心理や制度の中にも、未だにその種を孕んでおり、それを克服しきれていないという点にある。
われわれのデモクラシーにたいする容易ならぬ脅威は、外国に全体主義国家が存在するということではない。外的な権威や規律や統一、また外国の指導者への依存などが勝ちをしめた諸条件が、まさにわれわれ自身の態度のなかにも、われわれ自身の制度の中にも存在するということである。したがって戦場はここに――われわれ自身とわれわれの制度のなかに存在している。
これは過去の問題ではない。われわれも現在進行形で最大限に注意しなければならない――まさに「戦場はいま、ここ」にあるのである。
何より、本書を読んでいささかウンザリとさせられたのは、本書で提示されるナチズムを支持する民衆の心理が、日本の身近に見かける人物や、いわゆる保守層と呼ばれる人物などに、しばしば見られる部分が多々あった事である。
西洋が中世から近現代にかけて「自由」を獲得して来たプロセスを見て、その上で日本の歴史を改めて振り返ってみると、日本はまだ西洋的な「個人の自立した自由」のパーソナリティを獲得していないんじゃないのか?と思わざるを得ない。
例えば日本人がよく「一人勝ち」した人間をねたみ、「一人負け」した人間をバカにしがちだと思われるのは、そのパーソナリティが典型的な「集団主義」的なものだからだ、とそう思う。
要するに、日本人は「孤立」がイヤなのだ。
「自分一人だけ負けてしまう」という孤立を恐れるし、勝つ時も「皆と一緒に勝った」という感覚を分かち合いたいと思うのだろう。
西洋が獲得して来た個人主義的な自立心が日本人には薄い、という事の証左が、こういった所に端的に現れているのではないかと思うのである。
「集団主義的パーソナリティ」というのは、何かしらの組織に所属していないと安心できないパーソナリティだし、それは同時に、よく言われるように「よそ者を排除する心理」にも通じているのである。つまり、ナチズムの反ユダヤ主義もそういう「集団主義」の排他的心理なのだ。
こういった性格傾向は、本書で説明されているナチスを支持した民衆の「逃避のメカニズム」を思わせるものなのである。
サルトルは『実存主義とは何か』の中で「人は自由の刑に処されている」と言っていたが、これはエ-リッヒ・フロムの『自由からの逃走』のテーゼにも共通する事である。
「自由」とは、多すぎる選択肢の中から自分の判断で選んで、それによって起こる全ての責任を自分で負わねばならないという事だ。
つまり「孤立」が前提なのだ。それは「一人勝ち/一人負け」になりやすい。
そういう「孤立」がイヤだから、「多くの人が〇〇を選んでるから自分もそれを選ぶ」という「多勢」の方を選んでしまう……というのは、わりと日本人に典型的な「権威主義的パーソナリティ」の型ではなかったか。
近代的に「自由」になった個人というのは、中世の時代の様な周囲の人たちとの連帯感に包まれて安寧を得る事もできず、自分で自分の将来と人生を決めてその選択に責任を持たねばならない不安と戦わねばならない。
こういう点からも「個人が自立した自由」が何故孤独なのかが分かるだろう。
資本主義社会は個人に比べて圧倒的に巨大な組織が世間にごろごろと存在している。
そういった組織に対して自分は何とちっぽけなのか……という「無力感」と、現代民主主義的な「自分の人生は自分で決める事ができる」という自由にまつわる「孤独感」が、近代人の心に「権威主義的パーソナリティ」を育てる。
本書では「権威主義的パーソナリティ」の特徴として、サディズム及びマゾヒズム的性格傾向というものが説明されている。
サドとマゾという性格傾向は両極端なものではなく、実は背中合わせ的な性格であり、両方の性格傾向が一人の人間に備わっているという事もある。
それが「支配‐服従」的心理傾向を生み出すのであり、例えば目上に対しては喜んで服従するマゾヒズム的な態度を見せ、目下に対しては精神的物理的に支配したいという支配欲求を出すサディズム的な性格を見せる、と言った形で現れるわけである。
本書によれば、サディズム及びマゾヒズム的性格傾向の心理的共通点は、いずれも「孤独感と無力感の恐怖にみちている(P.169)」のだという。
そういった孤独感や無力感からの心理的逃避メカニズムとして、上には喜んで服従し、下には抑圧的な支配的態度を示す「権威主義的パーソナリティ」が現れるのである。
(中根千枝『タテ社会の人間関係』 にて日本社会は序列意識が強いといった事が書かれていたが、こういう権威主義的なパーソナリティとは、特に序列社会で良く見られる傾向なのではないかとも思われる)
こう書いていくと、徐々に「権威主義的パーソナリティ」の性格傾向が、日本人の中にもけっこう見られるというのが分かって来るのではなかろうか。
「組織」という権威に寄り添い、政府や国家や企業という「大きなもの」の中に自分も含まれているのだと思い込む事によって自我を拡大し「無力感」や「孤独感」から逃れる。
これが「自由」を放棄し、組織や国家の理不尽な命令であっても無批判に肯定してしまう「権威主義的パーソナリティ」成立のプロセスなのであり、それが「支配‐服従」関係という封建社会の心理的構造に逆戻りする心理なのである。
彼らは大きなものとの一体感を得て孤独を癒し、虎の威を借りて立場の弱い者や社会的マイノリティを攻撃する事で自身の無力感を解消する。
――ぼくが本書を読んで「いささかウンザリさせられた」と書いた理由がお分かりになっただろうか?「彼ら」が為政者を何が何でも擁護したがり、逆にしつこく在日韓国人や性的マイノリティを差別したり中国を批判したりするのは、彼らがまさに「権威主義的パーソナリティ」を体現しているからではないのか。
こういう性格の人たちは、弱者に対して苛立ちを覚えるのだそうだ。彼らが好きなのは、自分がその権威に抱かれて安心できる絶対的な権力なのである。
だから、彼らが信奉している権威が失墜してしまった時、彼らは手のひらを返して怒り狂って攻撃する側にまわるようになる……というのも本書に書かれていた事だが、これはまさに日本が二次大戦時の敗戦を迎えてから起こった日本人の反応そのものではないか。

ぼくはこういう態度を端的に「卑怯」と感じてしまう性格なので、この手の「権威主義的パーソナリティ」は心の底から嫌いなのである。
二次大戦の敗戦によってあれほど民主主義の大切さを教育されながらも、日本は今の今まで実質的に民主主義精神は根付かなかった。
それは思うに、日本的な「長いものには積極的に巻かれに行く事で心の安寧を得る」という古くからの日本的な「阿闍世コンプレックス」的精神を克服できなかったためでもあるのではないかと思うのだ。
<無意識に権威と同一化してしまう「にせの思考」とは>
精神分析学の理論というのは、ぼくにとっては非常に興味深いと思えるものが多いのでフロイトもフロムも個人的に大好きである。
例えば本書で説明されている「にせの思考」というのも、ぼくにとってはなかなか興味深い考え方だったので、ぼくなりにかみ砕いて説明しよう。
人間は自分の選択や考え方というものは大抵は自分の頭で考えて出した結論だと思っているものである。
が、「にせの思考」というものは、例えば人間はしばしば自分のものでない他人の考え方を無批判に自分の中に受け入れてしまい、それを「自分の頭で考えた事だ」と思い込んでしまう事である。
本書では都会から来た客と漁師のたとえ話が面白かったので、そちらをアレンジしてご紹介しよう。
自分は今から海に出ようと思っているのだが、参考までこれから天気がどうなるのか両者の意見を聞いてみる事にする。
すると漁師は自分の今までの経験から、空模様や湿度や風の具合、波の様子などを見て「これから天候は荒れるよ」と答える。
それに対して都会から来た客は「いえ、天気予報では今日は完全に晴れだと言っています。雨は0%ですよ?」と言う。
漁師は「いや、自分の経験ではこれから海は荒れてくる。海に出るべきではない」と主張する。
そんな漁師に対して客は少々小ばかにしたように「それはあくまであなたの主観にすぎないでしょう?そんなもの、まったく科学的な考え方じゃないですよ」と嘲笑った。
――さて、この場合に注目して頂きたいのは、この結果、果たして天候はどうなったのかという「結果」ではない。
彼らの「思考プロセス」がどのようなものだったのか、という事だ。
漁師が出した結論というのは、自分の経験から様々な状況を踏まえて、自分で決めた事である。
それに対して都会から来た客のほうは「科学的」とは言っているものの、たいていは天気予報のメカニズムやその的中率といった「結論に至るまでの理屈の中身」については無知であったりするものだ。
都会から来た客が漁師を「科学的な考え方じゃない」と言っているものの、その「科学的な考え方」の中身を、彼が一から検討したわけではない。
彼の発言をよく見てみれば、彼は「天気予報の科学」の中身については何一つ言及せず、ただたんに「天気予報では今日は完全に晴れだと言っていた」という「伝聞」を自分の正統な意見として主張しているだけなのである。
要するに彼は「天気予報」という、一般庶民が広く見て参考にしている「権威」的な意見をそのまま自分の中に受け入れて、それを「自分の意見」だと思い込んで主張しているのである。
ただたんに「権威」の意見を繰り返しているだけなのに、彼は漁師を「科学的な考え方じゃない」と言い、遠回しに自分は科学的な思考を持っているものだと思ってしまっている。
本人は「自分の頭で考えて得た結論だ」というスタンスでいるのだが、その内実は単に「権威」の意見をそのまま「自分の思考」と思い込んでいるだけ――これが「にせの思考」の典型的な一例である。
これは以前もご紹介した『シニア右翼 日本の中高年はなぜ右傾化するのか』の中で古谷経衡が、シニア右翼が人気の保守系言論人たちの発言する内容をそのままうのみにして受容・拡散しているという事を批判的に書いていたが、まさにこの例に見るシニア右翼の行動も「にせの思想」の一例だと言えるのかもしれない。
彼らはただたんに人気の保守系言論人の言っている事を無批判にネット上にコピペし、それを自分の意見だと思い込み、自らを「保守」だと主張しているというわけである。
但し、これは恐らく権威主義的パーソナリティを持つ人々だけではなく、多かれ少なかれ、それ以外の多くの人たちも無意識に陥っている心理的傾向なのではないだろうか。
同じような現象は、ある主題についてのひとびとの意見、たとえば政治についての意見などを研究しても観察できる。一般の新聞読者に、ある政治的問題についてのかれの考えを尋ねてみよ。かれは新聞で読んだ多かれ少なかれ正確な記事を「かれ」の意見として答えるであろう。しかも――そしてこれが本質的な点であるが――かれは自分のしゃべっていることが、自分自身の結果であると思い込んでいる。
彼らは無意識に「権威の言葉を繰り返すスピーカー」と化すわけだが、それを当人たちはまるで意識していないわけである。
ファシストが権威と化した場合、しばしばその言葉が熱狂的に社会に拡大していくのは、こういうメカニズムも働いているのだろうと思わせられる。
<では、この逃避のメカニズムを克服するには?>
本書では封建主義から近代国家における資本主義社会へと変化した事によって獲得した「自由」が、逆にかつてあった人と人との連帯感を引きはがし「孤独感」や「無力感」を生み出してしまうその背景を詳細に説明している(その詳細が気になる方は是非本書を読もう)。
彼らの無力感、寄る辺の無さの原因の一つには、封建社会から近代へ変化する事によって起こった「あらゆる古い権威の失墜」にもある。
このテーマについて語らせるには、フリードリヒ・ニーチェをおいて他にいないであろう。
かつてニーチェは、近代人は伝統的な権威の失墜によって、西洋の持っていた価値観が崩壊し、かつての目的を喪失してしまった――自分も含めて全てが無価値だと否定するその考え方を称してニヒリズム――「消極的ニヒリズム」と批判的に呼んだ。
このニーチェによる近代人の捉え方は、半ば本書のフロムの考え方と一致している。――それが本書を読んでいて、ぼくが最も興味深いと思った所であった。
ニーチェが、近代人が陥った「消極的ニヒリズム」を克服する手段として提示したのは、「神(絶対的な権威)なき世界の新たなる価値観」となるべき人物像――「超人」になる事であった。これはある種、目的を失った近代人が目指すべき具体的なロール・モデルを示したものでもあった。
絶対的支配者などいない。王様などいない。自分たちの道を示してくれる神は死んだ。死後の安寧を約束してくれる観念も死んだ。教会の権威も失墜した。
何もかも失ってしまった荒野のようなこの世界で、これからは全て自分たちが行き先を決めなければならない。
――ニーチェはこの状況を「消極的」に捉えるのではなく、「積極的」にとらえる「積極的ニヒリズム」によって近代的な虚無感の克服を考えた。
同じようにフロムも本書で、ナチを支持する民衆らを「ニヒリズムに囚われた人たち」と指摘している。
面白いのは、こうした「ニヒリズムに囚われた人たち」にならぬよう、それを克服するある種の近代人の理想像としてフロムが提示したのも「積極的な自由」を体現する人、であった。
つまりは、権威に寄り添う事によって自らの寄る辺なさを癒そうとする「消極的な自由」を体現する人を克服するパーソナリティとしての「積極的な自由」を体現する人、であり、そういった健全な人間を作る社会を目指すべきだと言っているのがフロムの立場なのである。
近代人にとって自由は二重の意味をもっているということ、これが本書の主題であった。すなわち、近代人は伝統的権威から解放されて「個人」となったが、しかし同時に、かれは孤独な無力なものになり、自分自身や他人から引きはなされた、外在的な目的の道具になったということ、さらにこの状態は、かれらの自我を根底から危うくし、かれを弱め、おびやかし、かれに新しい束縛へすすんで服従するようにするということである。それにたいし積極的な自由は、能動的自発的に生きる能力をふくめて、個人の諸能力の十分な実現と一致する。自由はそれ自身のダイナミックな運動法則にしたがい、自由の反対物に転換しようとする一つの危機に到達した。デモクラシーの未来は、ルネッサンスこのかた近代思想のイデオロギー的目標であった個人主義の実現にかかっている。今日の文化的政治的危機は、個人主義が多すぎるということにではなく、個人主義が空虚な殻になってしまったということに原因がある。自由の勝利は、個人の成長と幸福が文化の目標であり目的であるような社会、また成功やその他どんなことにおいても、なにも弁解する必要のない生活が行われるような社会、また個人が国家にしろ経済機構にしろ、自己の外部にあるどのような力にも従属せず、またそれらに操られないような社会、最後に個人の良心や理想が、外部的要求の内在化ではなく真にかれらのものであって、かれの自我の特殊性から生まれてくる目標を表現しているというような社会にまで、デモクラシーが発展するときにのみ可能である。
ニーチェのニヒリズムには「消極的‐積極的」という二重の意味があったのと同じように、フロムの提示する「近代人における自由」にも「消極的‐積極的」という二重の意味があった。
「孤独な無力なもの」となった人々の心理を克服するものとしてフロムが本書で提示した「積極的な自由」を体現した人物のパーソナリティが、ニーチェが「消極的ニヒリズム」に対抗するものとして提示した「超人」の造形に似ていたのは、当然の事だったのかもしれない。
虚無的な心境に陥った人間が、自らの不安定さを癒すために「権威」というものに進んで従ってしまう。――だからこそそういった心理を克服する「積極的な自由」を体現した人物は、自分以上のいかなる者にも従属しないのである。
積極的な自由はまたつぎのような原理を含んでいる。すなわちこの独自な個人的自我に優越した力は存在せず、人間はその生活の中心であり、目的であるということ、また人間の個性の成長と実現とは目的それ自体で、たとえより大きな尊厳をもつように思われる目標にも、けっして従属しないということである。
「おのれ以外の何者にも従属しない」という、この自立した人物像というのは、いかにもニーチェのアフォリズムに出てきそうな考え方ではないだろうか。
自分以外のいかなる権威にも従属しない――思えば、これはある意味デモクラシーの基本的な考え方ではないだろうかとも思うのである。
ここで田中芳樹『銀河英雄伝説』でのぼくの好きなワンシーンを引用させていただこう。
「皇帝(カイザー)ラインハルト陛下、わしはあなたの才能と器量を高く評価しているつもりだ。孫を持つなら、あなたのような人物を持ちたいものだ。だが、あなたの臣下にはなれん」
ビュコックは視線を横に動かした。頭部に血のにじんだ包帯を端整とはいえぬ形に巻きつけて、彼の参謀長が一本のウイスキー瓶と二個の紙コップをかかげてみせた。老元帥は微笑してスクリーンに視線をもどした。
「ヤン・ウェンリーも、あなたの友人にはなれるが、やはり臣下にはなれん。他人ごとだが保証してもよいくらいさ」
ビュコックの伸ばした手に紙コップがにぎられるのを、ラインハルトは一言も発せず見守っている。
「なぜなら、えらそうに言わせてもらえば、民主主義とは対等の友人をつくる思想であって、主従をつくる思想ではないからだ」
乾杯の動作を老元帥はしてみせた。
近代的に自立した人間というものは、尊敬すべき人間を見たら「あの人を師匠として崇めて彼の弟子になりたい」と思うのではなく、自分より弱い者を見たら、かれらを従えて権力を振るいたいと思うのでもなく、尊敬すべき人間とも、弱者やマイノリティと呼ばれる人たちとも、対等な立場で友人になりたい、と思う事なのではないのだろうか。
それが相互に自立した人間たちの連帯であって、それは自由ではあっても、決して孤独ではないはずなのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
