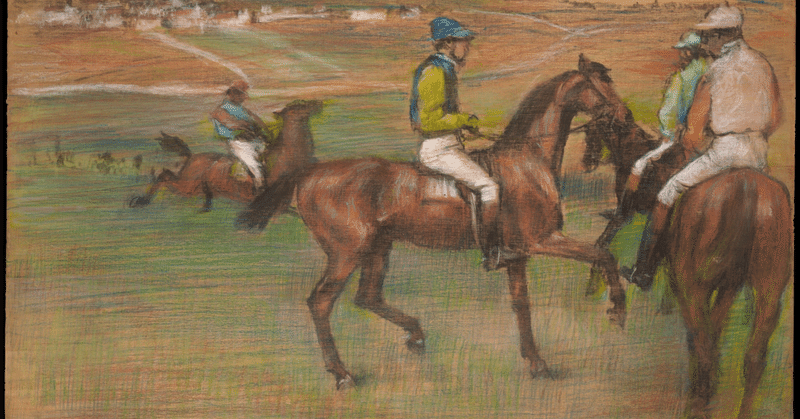
ミュージアムの中の人が、なぜかいろいろあって「スポーツ(「との比較を行う上で」というテイで美術館・博物館も対象とした「文化観光」も無理やり含めた)ツーリズム」の非常勤講師をしている話 #02
自己紹介はあらためて行いますが、いろいろな業界を見聞きした経験をもとに、現在関わっているミュージアム業界(そんな言葉ないw)についての(あまり知られていない)ことを中心にご紹介できればと思い、noteをスタートすることにしました。今回のネタは前回に引き続き、ミュージアムの中の人がいろいろあって「スポーツ(芸術文化も無理やり含めた)ツーリズム」の非常勤講師をしている話。
前回はこちら
さて実質的2回目の今回は、ようやく本題の(さわりとなる)「スポーツツーリズム」の3つの種類について。この内容はスポーツツーリズムやスポーツビジネスのどの本にも書かれているベーシックな話なのであっさり行きます。
そもそも「スポーツツーリズム」という言葉をイメージしたときに、たいていの方が2つまでは簡単にイメージできるはずなのです。
1つめは「見る」。
最近でいえば2019年に日本で行われた「ラグビーワールドカップ」や残念ながら無観客開催となりましたが、2021年に行われた「2020東京オリンピック・パラリンピック」。かなり前の話ですが2002年の「FIFAサッカーワールドカップ 日韓大会」は日本のスポーツツーリズムを語るうえで大きなきっかけになったイベントだったといわれています。そして日本各地で行われているプロ野球(主にNPB)、Jリーグ、Bリーグに大相撲といったプロスポーツに、高校野球(春の甲子園、夏の甲子園)などなどが含まれます。今年(2023年)でいえば、沖縄などで開催されるバスケのワールドカップを見に行く、あるいは女子サッカーワールドカップやラグビーワールドカップを見に海外まで行く、というケースもこのタイプに含まれるわけです。
つぎは「する」。
東京マラソンなど各地のマラソン大会に参加する、あるいは、同様に各地で行われているトライアスロン、しまなみ海道ツーリングやビワイチ、アワイチなどに代表されるサイクリングなどがその代表例と言えるでしょう。また近年のアウトドアブームを背景にしたSUP(スタンドアップパドル)やキャニオニングなどのアウトドアアクティビティに参加するなどのケースも増えつつあります。ちなみにキャンプそのものは以前からあるコンテンツなので、ここでは扱いません。グランピングは新しいコンテンツですが、正直スポーツ要素薄まるし。
で、問題の3つめ。
3つめがスッと出た方はもうこのnoteを見る必要はありません。はい。で、肝心の3つめですが、「ささえる」になります。あまりピンと来ないかもしれませんが「ささえる」という観点でのスポーツツーリズムが存在します。とはいえピンとこないのもそのとおりで、全体的な割合は高くありません。高くはないもののスポーツならではの行動としてピックアップされています。
さきほどもご紹介しましたが2021年に延期の上、無観客開催となった「2020東京オリンピック・パラリンピック」。この大会ではオリンピック全体として8万人、東京都としても数万人のボランティアの方々が裏方として参加されていました。当然、ボランティアとして参加するために各地から東京に滞在したという方もいらっしゃいます。同様に、ラグビーワールドカップでも各開催地で多くのボランティアの方々が集まりました。このように大規模なスポーツイベントの裏方として参加するために開催地で滞在することを積極的に実践する方々も(数は多くはありませんが)いらっしゃいます。
ご紹介した3つの種類に関しては一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構のウェブサイトにまとめられていますのでご参考に。
このようにスポーツツーリズムは「する【Do】」「見る【Watch】」「ささえる【Support】」の3つの種類に分類されるのです。とはいえ、3つの種類それぞれの市場としての大きさや動く人数イメージはバラッバラな状況だったりします。それぞれの特長に関しては次回以降でご紹介していきます。
はい、あっさり終わりました。前回がコテコテすぎたな。
#03へつづく…
