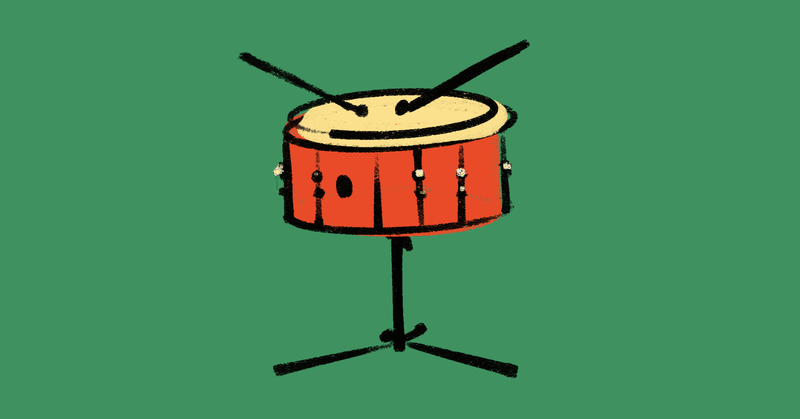
『センスの哲学』(千葉雅也著、文藝春秋)を読んでみて、昨日のスピーチを振り返る
今回は、「センスの哲学」(千葉雅也著)を読みました。
単純に面白くて、一気に読めました。
これは「センスが良くなる本」です。
という表題はキャッチーですが、ちょっとドキッとしますよね。
昨日、人前でスピーチをした
唐突に個人的な話で恐縮ですが、昨日は、人前でスピーチをする機会がありました。
思ったより緊張はしなかったのですが、うまく言いたいことが言えたのかというとどうだったかな。昨日、意識しようと思ったことは、意識してやってみたつもりです。
終わった後、何人かに「話どうだった?」と感想を聞いてみました。
「いや、いいこと言ってたと思うよ」というありがたい感想をいただけたのですが、、、
ただ別の人に「うん、中身はいいこと言ってた。でもちょっと眠くなりかけたかな笑」と言われてしまいました。
そんなに長いスピーチではなかったと思いますが・・・笑
ということで、中身はまあ及第点だけど、聞いている人が眠くならないようにというのが、昨日の課題でした。
「センス」とは、ものごとをリズムでとらえること
話を戻して、本書の言いたいことは、割とわかりやすく書いてあると思います。
(ただ、じゃあこの本の内容が深くないかというと決してそうではなく、本当に難しいことは本書の言いたいことのその先、あるいは、その手前にあるんじゃないかとは思います)。
一言でいえば、
・ものごとをリズムとして捉えること、それがセンスである。
なんらかのモデルを目指すというのは、それが持つ意味を求めること。
しかしこの本では、「意味よりも手前で、ものごとがそれ自体として面白いのか」を重視します。
このリズムというのは何なのか。
それは、「うねり」と「ビート」という概念に分解されて説明されていたり、「差異」と「反復」という概念を用いて説明されていたりしますが、その辺がどういうことなのかは、本書をお読みいただければと思います。
(なお、合っているのか自信がないのだけれど、たぶん単純な「うねり」=「差異」、「ビート」=「反復」というわけではないのだと思う。この本書の概念の配置の仕方も、センスなんだろうなという気がする)
とにかく、この本は、意味や目的から離れてただ形を見るというのが基本スタンスです(フォーマリズム)。
昨日のnoteはセンスに無自覚だった。
さて、これを踏まえると昨日のスピーチの反省点が見えてきます。
昨日は、話す内容、中身にしか着目していませんでした。
つまり、意味や目的だけに着目していて、センス=リズムでとらえることに無自覚だった。
センス = リズムでとらえること = ビートとうねりでとらえること
だとすれば、話す内容、中身だけにとらわれずに形を意識する必要もあったわけです。
だから眠くなる人が出てしまったんだと思います。
自分センスねえなぁ(笑)
つまり、中身とか目的よりも「話し方が9割」で大事(!?)
ということで、まとめて終わらせてもよかったのですが、本書では、そのちょい先でいろいろ面白いことを言っている気がするので、ちょっとだけ触れて終わりにします。
意味のリズム
中身とか意味よりも形とかリズムに着目するのがセンスだよ
というのが、メインで本書から受け取ったことですが、本書では、「意味だと思っているもの」をリズムにしてしまう「意味の脱意味化」なることを言います。
われわれが「意味だと思っているもの」は「大意味」であり、一方で、大意味ではない「小さな意味」=「小意味」に着目する面白さがあると言います。
もっとも、本書は、フォーマリズムを極端化するのではなく、意味がわかることもまた重要、つまり、両方大事といっています。
この点に関連して、本書は、感動には、大まかな感動と構造的感動があると言った部分が印象的でした。
ひとつは、大まかな感動です。いい話だとか、悲惨な話だとかいう感動で、それが作品の大意味に属することは、もうおわかりと思います。それに対して、もうひとつの感動がある。あちこちに展開する小意味の絡み合い、そこにおける意味のリズム、つまり、いろんな事柄の近さと遠さのリズミカルな展開を面白く思うこと。これも一種の「感動」だと思うんですね。これは、ディテールがどう組み合わさって作品になっているかを見ることで、すなわち「構造」を見ることです。これを「構造的感動」と呼びましょう。
略
・センスとは、喜怒哀楽を中心とする大まかな感動を半分に抑え、いろいろな部分の面白さに注目する構造的感動ができることである。
そういえば、前に「勉強の哲学」を読んだ時の沼感も今思えば構造的感動だったんだろうなあ。
また、唐突な思いつきですが、最近だと、構造的感動が一番典型的に見られるのは、「M-1グランプリ」じゃないかなと思います。
4分間の序盤で、ちょっとおもしろい小ボケを入れて、忘れたくらいの後半で回収する、この構造的感動が爆笑につながっているネタが、高得点につながっている印象があります。
確か錦鯉が優勝した時のネタで、「おじいさんは優しく寝かせる」というひとボケをいれて、最後に、渡辺さんがマサノリさんを優しく寝かせるというオチで回収するというのがあり、これも構造的感動なのかなと思います。
いやーでもこれをスピーチに入れるのは難易度が高いなあ笑
そうはいってもまずは、センスに無自覚よりも自覚することが大事、中身にこだわるだけじゃなくて、次のスピーチがあったらリズムを意識してやってみると、もっと面白くなるかも、そんな感じです。
ということで、「今日一日を最高の一日に」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
