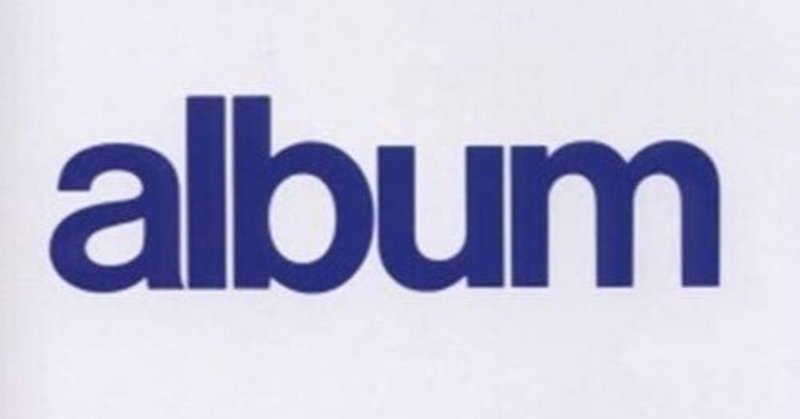
[過去原稿アーカイヴ]Vol.19 Public Image Limited『Album』ライナーノーツ(2011)
ジョン・ライドンのPILが1986年に発表した5枚目のアルバム『Album』2011年にリマスター再発された時に書いたライナーノーツ。
https://note.com/onojima/n/n08a20155f0fe?magazine_key=m7b47445efa2f
https://note.com/onojima/n/n1a7039d4fb76?magazine_key=m7b47445efa2f
本作は1986年2月に発表されたパブリック・イメージ・リミテッド(PiL)の5枚目(ライヴ盤を入れると7枚目)のアルバムである(原盤番号:VIRGIN V2366)。全英アルバム・チャート14位まで上昇し、3作目の『フラワーズ・オブ・ロマンス』(11位)以来のチャート上の成功をおさめた。なお本作はレコード(ヴァイナル)は『アルバム』、CDは『コンパクト・ディスク』、カセットテープは『カセット』と、それぞれタイトルがつけられている。収録曲・曲順等、内容はすべて同じである。プロデュースはビル・ラズウェル。PiLが起用した初めての外部プロデューサーだった。
本作からは「Rise (7" Edit) / Rise (Instrumental)」(Virgin VS841「Home (7" Edit) / Round」(Virgin VS855)「Seattle (7" Edit) / Selfish Rubbish」(Virgin VS988)と3枚のシングルがカットされ、それぞれ全英シングル・チャートで11位、75位、47位まで上昇している。
前作『ジス・イズ・ホワット・ユー・ウォント、ジス・イズ・ホワット・ユー・ゲット』の制作途中で、結成以来の盟友であり欠かせぬ音楽的パートナーだったキース・レヴィンを失ったことは、ジョン・ライドンにとって、大きな痛手だったに違いない。後にビル・ラズウェルが認めたように、ライドンの発想や音楽的アイディアには天才的なものがある。だが彼は楽器ができず譜面が書けるわけでもない。アイディアをを形にして音楽として完成させていく技術がない。ヴォーカリストとしての卓抜、閃きの鋭さ、時代の動向を鋭敏に捉えるセンス、皮肉と諧謔に満ちたパフォーマンスや歌詞といったライドンの類い希な資質を受け止め、具現化し、さらに膨らませていくパートナーが、ライドンには必要なのだ。しかしウォブル、レヴィンという優秀なパートナーをライドンは次々と失ってしまうのである。
さらにライドンは、妥協のない実験的・挑戦的なアルバムを続け、ヒット・レコードにも恵まれず、ツアーはやらない、意味のないライヴをやらないという方針もまた、かたくななまでに貫いていたから、当然のように経済的に困窮し始めていた。『ジス・イズ・ホワット・ユー・ウォント〜』で聴けた、かってないほどのコマーシャルなポップネス(『ジス・イズ・ホワット・ユー・ウォント〜』の元のタイトルは『コマーシャル・ゾーン』だった。脱退したキース・レヴィン・ヴァージョンの『ジス・イズ・ホワット・ユー・ウォント〜』が『コマーシャル・ゾーン』としてリリースされている)は、その苦境の打開の手立てだった。さらに絶対にやらないと言っていたツアーをおこない(だから初の日本公演は実現した)、ロックは死んだと言いながら、その日本公演で即席のトラのバンドをバックに、愛想を振りまきながら「アナーキー・イン・ザ・UK」を歌うしかなかったのである。そこであらわになっていたのは、反逆のパンク・ロッカーでもなく、シリアスな前衛ロックの作り手でもなく、英国伝来のシニカルで悪意に満ちたパフォーマーとしてのライドンだった。ちなみに東京公演のライヴ盤『ライヴ・イン・トーキョー』とヴィデオ『PiL日本'83』は、ライドンの困窮を見かねた当時の日本盤発売元、コロムビア・レコードの担当者Hディレクターの申し出で実現した。これに感謝したライドンは、H氏への恩義として、PiL及びセックス・ピストルズの日本盤発売権を長い間コロムビアに与えていた、とされる。
[2022年注:2016年に日本語版が上梓されたライドンの自伝『怒りはエナジー』によれば、初期のPiLがライヴやツアーをほとんどやらなかったのは彼らの意思ではなく、やりたくてもやれなかった、とのことである]
あれほどまでにかたくなに自らのポリシーを崩さなかった誇り高き男ライドンのこうした変化に、眉をひそめる向きもあった。だがそうはいっても、世間のライドンに対する期待感がいささかも衰えたわけではなかった。初の日本公演は中野サンプラザ6回公演をすべてソールドアウトにするという人気ぶりだったのである。ピストルズ解散時のようにひとりに戻ったライドンは、ニューヨークを拠点としてさまざまな交流を始める(ライドンがNYに居を移したのは81年初頭のこと)。当時のニューヨークはヒップホップの興隆期であり、ライドンはヒップホップのゴッドファーザー、アフリカ・バンバータと出会い、共演シングル「Time Zone」を発表する(84年12月)。御大バンバータと互角に渡り合い、実に楽しげに奔放なヴォーカルを披露するライドンは久々に精気にあふれている。今でも時々フロアで鳴るクラブ・クラシックスであり、たぶんライドンは本場のヒップホップに積極的にアプローチして、目に見える成果を得た、おそらくほとんど初めての白人ロッカーだったのではないか。
そして、ここで出会ったのがプロデューサーのビル・ラズウェルであった。ライドンは新たな音楽的パートナーにラズウェルを指名。ようやくライドンの感性や意志を、音として具現化してくれる人材を、ライドンは獲得したのである。そして作られたのが本作なのだ。1985年8月から9月にかけてNYのパワーステイション・スタジオで録音。
マテリアルやゴールデン・パロミノスのメンバーとしてNYの先鋭的なジャズ/ロック・シーンの最前線に関わる一方、ミック・ジャガーのソロやハービー・ハンコック「ロッキット」、さらにはヨーコ・オノやフェラ・クティ、マヌ・ディバンゴあたりまでプロデュースを手がけ、ニューヨークのアンダーグラウンド・シーンとも積極的な交流を持っていたラズウェルとライドンの出会い。当代屈指の売れっ子プロデューサーにとって、パンク・ロックの象徴的存在であるジョン・ライドンは、プロデュースの対象としてきわめて魅力的に映ったはずだ。素材は抜群。楽器や曲作りはおぼつかないが、どんなバック演奏だろうが負けないだけの個性と力量、そして厚かましいほどの存在感を持っている。しかもお抱えのミュージシャンや曲作りのパートナーがいるわけでもない。プロデューサーの腕次第でどうとでも料理できてしまう。そしてキース・レヴィンを失って以来、これといった方向を見いだせずにいたライドンにとっても、このやり手プロデューサーの登場は頼もしく映ったのだろう。おそらくは音作りの権限のほとんどを与える(もちろん、気の向くままに口は出す。ライドンの突飛なアイディアの数々に、ラズウェルは驚きっぱなしだったという)。かくしてできあがったのが本作というわけだ。はせ参じたのは、ラズウェル人脈の強者ミュージシャンたち。驚くほど多彩かつ豪華なメンバーが揃っている。
まずは1曲目の「F.F.F.」。元フランク・ザッパ・バンド/アルカトラズで弾きまくっていた変態超絶テク・ギタリストのスティーヴ・ヴァイ。Pファンクの業者キーボード奏者バーニー・ウォーレル。なんと元マイルス・デイヴィス・バンド/ライフタイムで叩きまくっていたジャズ・ロック・ドラマーの超大御所トニー・ウイリアムス、今やローリング・ストーンズのツアーに欠かせぬバーナード・フォウラー。これだけのメンツが勢揃いして、演奏されるのは、まったく小細工なしの、「ど」がつくほどのストレイト・アヘッドなハード・ロック・ナンバー。それをバックにライドンは、実に気持ちよさそうに、ライドン節全開で歌いまくる。これは虚を突かれた。ハード・ロックとパンクが敵同士のようにいがみ合っていた時代だったから、これはパンク/ニュー・ウエイヴにずっかりはまっていたぼくのような聞き手にとっては青天の霹靂だったし、痛快でもあった。
アイリッシュ・トラッドをニュー・ウエイヴ風に歪めたような「Rise」は、やる人がやればずいぶん牧歌的な曲になりそうだが、そこはライドン。アイルランド出身の彼らしいケルト魂が炸裂だ。この曲ではなんと坂本龍一教授まで参加。さらに驚きは「Fishing」で、なんと元クリームのジンジャー・ベイカーが、ドシンバタンと彼らしい豪快なドラムを披露する。これまたドスコイなハード・ロックで、バックの演奏だけ聴いていると時代がパンク以前に遡ったかのようだが、ヴォーカルが入ればやはりライドンの世界。ヴァイのエキセントリックなギターと意外に調和している。この曲にはアート・アンサンブル・オブ・シカゴのマラカイ・フェイヴァースまで参加。ラズウェルの人脈の幅広さには驚かされるが、フリー・ジャズの大御所にこんなハード・ロックを弾かせるのが面白い。
そしてアナログA面最後は、ガムランを思わせるエスニックなオープニングからスロウなロック・ナンバー「Round」。このあたりのエキゾティックでハイブリッドな演出は坂本のアイディアもあるのかもしれない。こうした趣向は「Ease」でも同様である。坂本はこの3年後にヴァージンと契約、傑作『ビューティ』を発表して本格的な世界デビューを飾るわけだが、本作での活躍ぶりも関係しているのかもしれない。
さてこうやって順を追って聞いていくと、実にさまざまな要素が入り込んだ、きわめてエクレクティックでヴァーサタイルなアルバムであることがわかる。決してハード・ロック一辺倒というわけではないし、そんな単純な作品でもない。でもそういうシンプルな印象を受けてしまうのは、全編で弾きまくるヴァイのギターもあろうし、ラズウェルの戦略のうまさもあろう。これまでのPiLにつきまとっていた一種の重苦しさ、自分で自分を律してしまい自縄自縛に陥ってしまったような息苦しさ、自分で作った迷路に迷い込んでしまったような苦悩が、ない。一人になって身軽になり、迷路を抜け、一気に視界の開けた広場に出てきたら、ライドンが本来持っていたであろう皮肉と諧謔に満ちたパフォーマー/エンタテイナーとしての資質が出現したのである。ハード・ロックという飛び道具的なキーワードを用意、物量作戦的な豪華ゲストの参加で、コロンブスの卵的にそれを実現してしまったラズウエルの力量は、さすがと言うしかない。
もっとも、ハード・ロックとして聞くなら、プロデューサーのクールな視線が勝ちすぎていることも確か。おそらくはライドンなど関係なく、ラズウェルの指示に従って各ミュージシャンが淡々とこなした演奏をラズウェルが冷静に組み立てて、カラオケよろしくライドンに歌わせたのだろう。ヴォーカルとバックが呼応しあって熱く盛り上がっていく、というロックらしい場面がまったく浮かんでこない。どこまでもクールで乾いているのだ。いわばゲーム感覚、「ごっこ」としてのハード・ロック。これがラズウェルの、そしてライドンの資質であり、このアルバムの面白いところだ。どこまでもライドンは「脱ロック」であり「反ロック」の人なのだった。
このままライドンとラズウェルのコラボレーションが続けばさらに面白いことになったかもしれないが、残念ながら両者の関係が悪化し、共演はこれきりとなってしまった。だが一期一会の出会いだったからこそ、こんな面白いアルバムができた。そう言えるかもしれない。
2011年5月24日 小野島 大 Dai Onojima
よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。
