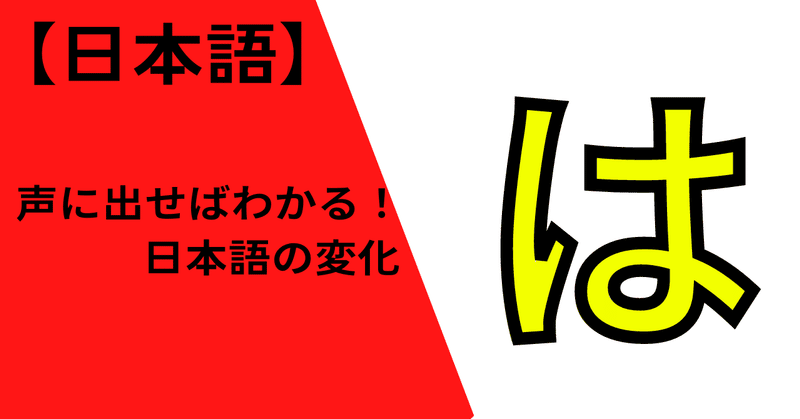
子ども「『私は』の『は』は、なぜ『ワ』なの?」←説明できる?
4歳の娘に、絵本の読み聞かせをしていた時のこと。
「『は』って、どうして『わ』って読むの?」
と聞かれた私は、答えることができなかった。
国語教師なのに。
「パパ、だめじゃん」

という娘の言葉に999のダメージを受けた。
専門書を読み、調べに調べた。
そこで得た”誰かに話したくなる日本語の面白い話”をみなさんとシェアしたい。
⬇️今回のお題⬇️

❶「は」の不思議
「たー」
と
「だー」
を発声し、口の動きを比べてほしい。
(実際に発声してみてください!!)
口の動きは同じであることがわかるはずだ。
「た」も「だ」も、上の歯茎の裏周辺に舌をくっつけて、弾くような動きをする。
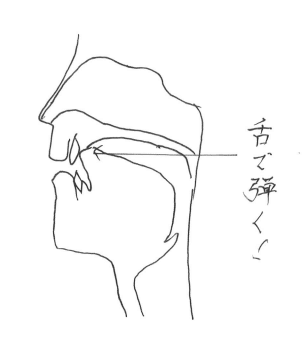
(鼻、口、喉、舌の位置がわかるもの)
同様に、
「か」と「が」
「さ」と「ざ」
「た」と「だ」
も口の動きは同じである。
つまり、「口の動きは清音・濁音のぺア(清濁のペア)で同じ」ということが言える。

では、
「はー」
と
「ばー」
は、どうだろうか。
(記事の終盤で大切になるので、ぜひやってください😮)
「はー」
は、口を閉じる動きはないが、
「ばー」
は、上唇と下唇が一度くっつく。
つまり、「口の動きは清音・濁音のぺア(清濁のペア)で違う」という性質があるのだ。

なぜ、『は』だけ仲間外れになるのだろうか・・・・・・。
やっぱり『は』は変なヤツなのだ。

❷古文に注目
『は』を『ワ』と読むケースで真っ先に思い浮かぶのは、中学・高校で学ぶ古文だ。
「語頭(単語の一文字目)以外の『は・ひ・ふ・へ・ほ』は、『わ・い・う・え・お』に直す。
(例)
◆いふ→いう
◆つはもの→つわもの
ということで、注目すべきは古文――昔の日本語である。

(photoAC)
昔において『は』はどのように発音されていたのだろうか?
「そんなものわかるワケねーじゃん。録音機器がないんだから」
↑この意見は的を射ている。
私もそう思う。
だが、学者たちの執念は、すさまじかった。

彼らは『昔の人がどのように発音していたのかがわかる資料』を見つけ出したのだ。
その資料とは、『キリシタン資料』と呼ばれるものである。
ヨーロッパから来日した宣教師たちが、日本語を学ぶために使った辞書や読み物などだ。

キリシタン資料には、当時の日本語がローマ字表記されている。
《例》
cotoba(言葉)
narau(習う)
キリシタン資料のひとつである『天草版 伊曾保物語』では、
fasi(橋)
fito(人)
fodo(ほど)
などと記されている。
(『ファシ』などのルビは私が振りました。原文には書かれていません)
昔、
「は・ひ・ふ・へ・ほ」
は、
「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」
と発音されていたのである。
【注意】
「ふ」だけ特殊です。
「フ」は「フゥ」となりません。
これを裏付ける「なぞなぞ」もある。
1516年の『後奈良院御撰何曽』という書物には、
「母には二たび会ひたれども、父には一たびも会はず」
訳:母には二回会うけれど、父には一回も会わない(ものって、なーんだ?)
というなぞなぞが載っている。
そして、答えは「くちびる」と書いてあるのだ。

「母」を「ハハ」と発音すれば、上唇と下唇がくっつくことはない。
しかし「ファファ」と発音すれば、上唇と下唇は、二回くっつく。
(実際に発声してみてください!!)
母には二回会うけれど、父には一回も会わない(ものって、なーんだ?)
というなぞなぞが成立しているということから、「母」は「ファファ」と発音されていたことがわかるのだ。


❸「ファ」からの変化
「ハ行」が「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」と発音されていたことがわかった。
この「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」が「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」になった、というわけではない。
まず、
「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」
と発音していただきたい。
(実際に声に出すのがポイント★)
わぉ、めっちゃ言いづらい(゚o゚;
唇を活発に動かさなければ、「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」と発音できない。
だから、
「ファ・フィ・フ・フェ・フォ」
は、唇の動きが少なめである、
「ワ・イ・ウ・エ・オ」
というワ行の音に変わった。
川:「かは」→「かは」
※表記は変わっていないが、発音は変わった。以下、同じ。
恋:「こひ」→「こひ」
声:「こへ」→「こへ」
顔:「かほ」→「かほ」
ファ行では発音しづらいから、ワ行に変わった。
昔の人だって、ラクできるならラクしたいのだ。


※正確には、「ワ・イ・ウ・エ・オ」は「ワ・ウィ・ウ・ウェ・ウォ」と発音されていた。
のちに、「ウィ」→「イ」、「ウェ」→「エ」、「ヲ」→「オ」に変わった。
❹発音と表記のズレ
つまり、ある時代では「かは」と書いて「カワ」と読む、という状況だった。(発音と表記のズレ)
「わ」という平仮名も存在していたため、
「かは」と書いて「カワ」と読む
「かわ」と書いて「カワ」と読む
というややこしいことが起きていたのである。
そこで1946年に国が「現代かなづかい」を定め、発音と表記のズレを調整しようとした。
そこでは、
と示されている。
例として、
【庭】
には(不適切)
にわ(適切)
【歌わない】
うたはない(不適切)
うたわない(適切)
などが挙げられている。

※現在は「現代かなづかい」ではなく「現代仮名遣い」(1986年告示)が基準とされています。
❺現代かなづかいの例外
しかし、「現代かなづかい」には、
とも書かれている。
助詞の『は』とは、『私は』の『は』のことだ。
(「現代かなづかい」には明記されていないが)助詞の『は』は極めて使用頻度が高かったので、
「私は」
を
「私わ」
と書くようにするのは、当時の人も抵抗があったのだ。
あなたも、

と言われたら、読むときも書くときも困惑するだろう。
したがって、発音と表記のズレが残るのは承知で、
と定めたのである。
(他の助詞『へ』『を』も極めて使用頻度が高かったので、同じ)
というわけで、答え。

娘には、なんとか説明できそうである。(ニッコリ)
しかし、まだ疑問が・・・・・・

❻「ハ」はどこに行った?
鋭い方は、
「ファフィフフェフォ」が「ハヒフヘホ」とは変化せず、「ワイウエオ」と変化したことは理解できた。
しかし、それなら「ハヒフヘホ」は存在しないことになる。
現在は「はた(旗)」など、「は」を「ハ」と発音する言葉はきちんと存在する。
これ、なんなの?
と疑問に思ったかもしれない。
さきほど、「ファ」は「ワ」に変わった、と書いた。

が、実はこれは語頭以外(言葉の先頭以外)に限った変化だったのだ。
以下の例をもう一度見ていただきた。
すべて、語頭以外の変化である。
川:「かは」→「かは」
恋:「こひ」→「こひ」
声:「こへ」→「こへ」
顔:「かほ」→「かほ」
語頭の「はひふへほ」は、「はひふへほ」に変化できなかった。
なぜか?
言葉が変わってしまうからである。
語頭で「はひふへほ」への変化を起こすと、次のような混同が発生する。
旗:
「はた→「はた」
(「綿」と混同)
舟:
「ふね→「ふね」
(「畝」と混同)
縁:
「ふち→「ふち」
(「内」と混同)
したがって、語頭の「はひふへほ」は、「はひふへほ」は変化しなかった。
しかし、やはり「はひふへほ」は発音しづらい。
だから、やはり唇の動きが少ない「はひふへほ」に変化した。
【補足】
「はひふへほ」は、「唇をくっつけて弾くように離す」という動作が必要。
「はひふへほ」にはその動作は不要。=負担が少ない。
まとめると、以下のようになる。

❼ハ行の変遷
「は」は、もともと「は」と発音されていた・・・・・・。
この事実を知った人は、びっくり仰天するかもしれない。

そんな人に、もう一つのびっくり事実を。
「は」は、もともと「は」と発音されていた。
「は」と「は」を実際に発音し、唇の動きを比べてほしい。
「は」の方が、しっかりと唇を弾かねばならない。
つまり唇を動かす負担が大きい。

したがって、はは、唇の動きが少ないはに変わったのだ。
つまり、さきほどの説明(下の図)は不十分であり、

正しくは、

である。
「は」が「ぱ」なワケねーだろ
という人には、下記のことを思い出してほしい。

「は」と「ば」だけ、「清濁の口の動き」が違う、という話である。
さぁ、
「ぱー」
と
「ばー」
を発音してごらんなさい。
口の動きは同じになったよね?
つまり、「ば」と正式に対応するのは「ぱ」なのである。

このことからも、「は」は、もともと「は」と発音されていたことがわかる。
歴史の教科書で学ぶ、卑弥呼は、
ぴみこ
と呼ばれていたということになる。なんか威厳が無いよね😅

出版を目指しています! 夢の実現のために、いただいたお金は、良記事を書くための書籍の購入に充てます😆😆
