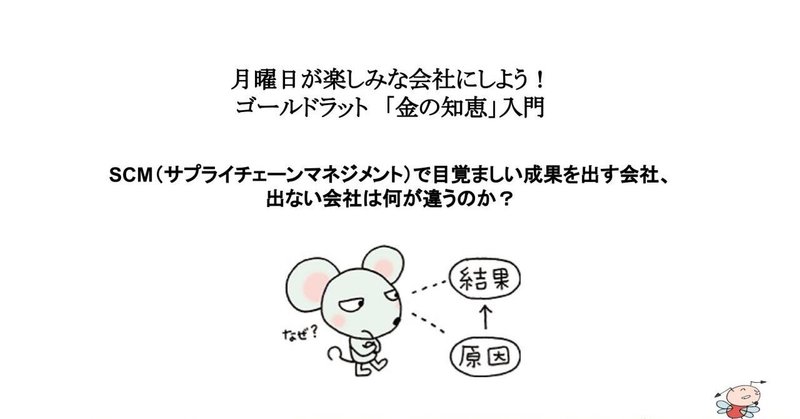
サプライチェーンマネジメント(SCM)で目覚ましい成果を出す会社、出さない会社は何が違うのか?
サプライチェーンマネジメント(SCM)で目覚ましい成果が出る会社と出ない会社では何が違うのでしょうか?
以前、ITサプライヤーの方から
「同じソフトウェアをサプライチェーンまで入れてるのに
なぜ目覚ましい成果が出ないのか?」
という相談を受けたことがあります。
サプライチェーン改革の難しさはどこにあるのか
サプライチェーンのことについて考えてみると、実は自分の会社で閉じてないのがサプライチェーンです。
通常は社内の改善活動をしますが、
社内の改善活動ではなく社内に閉じてない。これが一番難しいところです。
実際にはお客様がいて、そのあと小売業がいて、そして物流がある。
営業があって、生産があって、調達がある。
B to Bと言われる会社であっても、どこまで関わってくるかは変わります。
メーカーと言われるB to Cの商品を作ってる場合でも
営業から物流とか小売とか、または卸を介しているということもあって、実態はB to Bという場合もあります。
このような場合、生産、SCM、営業、調達、物流、IT、財務、経営企画の幹部と、会社のすべての部署が関わっているのがサプライチェーンの現実です。
まさに会社を儲けさせるエンジンとも言えます。
すべてのステークホルダーをwin-winで繋げてあげないといけないという大きな特徴があります。

皆さんの会社のオペレーションはどうでしょう?
全体最適でやってますか?部分最適でやっていますか?
「全体最適にしよう!」というスローガンを言っている会社は、
実は全体最適ができないのが現状です。
なぜかというと、全体最適ができていれば、そんなことスローガンさえ言わないからです。
例えば小売だと、もっと安くしたいと思っています。安く仕入れて行きたい。そのために、まとめ発注します。
物流はもっと効率に物流効率を上げたいとなると、まとめて発送した方が効率が良くなると考えます。
営業は、もっと売上を上げたいと言います。
そこで、まとめた方が安くなりますよっと言って、まとめて発注してもらって押込み受注をします。
生産現場は、まとめ生産をします。そして、もっと安く調達したいのでまとめて発注する。どうでしょう?
それぞれのチェーン内で一生懸命頑張っていますが、これはすぐ隣のサプライチェーンでさえも迷惑かけていませんか?
この中で一つでも部分最適あったら全体に成果をもたらしません。
なぜかと言うと、このサプライチェーンの一番弱いところが律速、つまり制約になるわけです。
質問です。
みなさんの会社に部分最適の行動ありますか?
もしかしたら「ある」と思うかもしれない。
そういう人たちは、部分最適の行動を喜んでやっていますか?
自分さえ良ければいいと本当にそう思っていますか?
本当は皆さん、全体最適にしたいと思ってんじゃないでしょうか。
自分の属する組織の目標達成のために一生懸命働いていると思います。
それが部分最適になっていまうのです。
実はゴールドラット博士はこう言っています。
「どのような尺度で私を評価するか教えてくれれば、どのように私が行動するか教えてあげましょう。もし不合理な尺度で私を評価するなら、私が不合理な行動をとったとしても、文句を言わないでください。」
部分最適で評価されながら全体最適な行動しようとすることは
ものすごく難易度が高いです。もし、部分最適のあるルールが会社の中であれば、IT化するとどうなりますか?
それをITのルールに取り込むと、どうなりますか?
部分最適のルールをこれから何年も使うんですよ。
部分最適の行動の温床なりませんか?
それぞれの組織でどういうことが起きているかというと
本当は全体最適を目指したいが、なんか部分最適になってしまうジレンマとはどんなことがあるのでしょうか?
各部門の抱えるジレンマ
物流現場のジレンマです。
業績を上げたいというのは部分最適です。そのために効率を上げるし、そのためには、まとめて運ぶ必要がある。
さらに市場の変化に迅速に対応する必要がある。そのためには今、必要なものしか運ばない。どうしようか?これは対立しています。
まとめて運ぶと市場の変化に迅速に対応することが出来ないし、今、必要な物しか運ばないと効率を上げることに妥協を強いてしまう。
どうですか?これはIT技術で解決する問題でしょうか?

さらに営業現場はどうでしょうか?
業績あげたいという気持ちがあります。そのためには売上を上げる必要がある。そのためには安くしてもたくさんの人に売る。売り上げは大事です。
一方で業績を上げるためには利益を確保する必要がある。そのためには、今必要なものしか売らない。これも実は対立してる。
しかし、たくさん安くしてもたくさん売ると、利益を獲得できなくなるし、今、必要な物しか売らないと売上確保することに対して妥協してしまいます。これはどうでしょうか?このジレンマIT技術で解決しますか?

生産現場はどうでしょうか?
業績を上げ続けるためには、効率上げる必要がある。効率を上げるためには、稼働率上げて、まとめて作る必要がある。
このようにやることは、ごく普通の考え方だと思っていませんか?
一方で業績を上げるためには、市場の変化に迅速に対応する必要がある。市場の変化に迅速に対応するためには、今必要なものしか作らない。それも対立してしまいます。
まとめて作ると、市場の変化迅速に対応することできないし、今必要なものしか使わないと効率を上げることに対して妥協してしまうことになる。
これITで解決しますか?

更に調達現場です。
業績を上げるためにはコストを下げる必要がある。そのためにはまとめて買う必要があります。まとめて買ってくれたら、ルートが増えたら安くしますっと言われます。
一方で業績を上げるためには、市場の変化に迅速に対応しなければならない。そのためには今必要なものしか買わない。これもジレンマですね。
まとめて買うと、市場の変化に迅速に対応出来ないし、今必要なものしか買わないとコストを下げることに妥協してしまうことになります。
これはIT技術で解決できますか?
デジタルトランスフォーメーションで全てが解決する。
どうやらここにはちょっと落とし穴がありそうだと思いませんか?

ゴールドラット博士はチェンジ・ザ。ルールの本で、「Necessary But Not Sufficient」と副題を付けています。
実は、彼はIT技術を否定はしていません。
むしろ、もともとIT技術者です。彼が言ったのは「ITが必要だが充分じゃない。チェンジザルールが重要である」ということです。
彼のこの本で言いたいことは、IT投資のテクノロジー装備だけでは利益向上に繋がらない。なぜならば、何もルールが変わっていないからだと言い切ってますね。「サプライチェーン難しさは一つの組織になっていないからだ」と言いました。
win-winでつなぐ必要がある。どこが一番大事なチェーンなんでしょう?
この中でどれでしょうか?どう考えても多分お客様のところです。
ここが良くならないと、ここで売り上げ上がらないと全部のサプライチェーンが潤うことはないです?
いくら自社を良くしたとしても、お客様の売り上げが上がらなければ結果として悪くなります。

売上はどのように立つのでしょうか?
これは最終ユーザーが購入するまで売れたとは言えません。次のチェーンに渡しても、実は自分たちの仕事が終わったと言えません。
社内と社外どちらのマイナスを消すのが大事でしょうか?
言い換えると、お客様のマイナス消すのと社内マイナスを消すのと、どちらが良いでしょうか?
そう考えると、お客様のマイナスを消さないとお金入って来ないのではないでしょうか?社内のマイナスを消すことが目的になったらどうでしょうか?
社内プロジェクトが欠品と過剰在庫の同時解消と言っていますが、現実でまとめに発注してたらどうなりますか?
ボコっと発注されてしまったら、ボコっとまとめて配送されてしまう。
ボコボコっと発注が来てしまうので、やっぱりうまくいかないよねって外のせいにする。それで問題解決しますか?問題は解決しないですね。
実は社内のマイナスを消すことを目的にすると、最大の障害は、社外によってやっぱり社外の問題では無理だよね、と言い訳になってしまいます。
本当の制約に取り込むなくていいのでしょうか?
相手の立場に立って考えるということはどういうことか?
これが一番大事な制約であるとすると、制約以外の改善をしても全て無駄になってしまいます。制約に全力を傾けるにはどうしたらいいかと考えなければならない。
ゴールドラット博士は小売業と卸売業の方々が、実は売りを立てることが大事で、そのためにもっとも重要なものって何だろうっていうのを語っている動画があります。この動画は、観ていただきたいです。
動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=YHCjfSf1pEg(9:02~ SCM改革の本質)
「相手の立場になって考えなさい。」
と親から言われたことないでしょうか?
10回ぐらい言われたらできるようになるのでしょうか?
お客さんの立場になって考えるということは何度もやってみても
お客さんを安くしろって言ってるからと言って、それがお客さんの望みであるかどうか分からないです。
お客さんが安くして欲しいと言ってくるのは、実はもっと儲けたいからだ。であれば、お客さんにより儲けをもたらすために何をしたらいいか?
安くする代わりに少ない在庫で、もっと速く商品が回転して儲けるようにするとどうでしょうか?
少ない資金で儲かります。というと嬉しいですよね?
相手の言われたことを鵜呑みにするのか?相手を考えて、相手に「こんなことをしたいんじゃないですか?」と言われるのでは、どちらが頼もしいでしょうか?
自分たちのwinを先に考えると思いつきません。相手のwinをまず考え、全てのオペレーションを再構築して考える。
ゴールドラット博士はこう言っています。
「win-winを本当に望むなら、まず相手のwinを大きくし、その中で自分のwinを得ることを考えるべきだ。」
彼はユダヤ人です。だからまず相手のwinを考えて、その中で自分のwinをいくばくか貰うという、そういう考え方が大事だと。
まず相手です。親に言われたことと変わってないです。
多分、上司から言われたことと変わってないはずです。
でも、具体的に相手の言ったことを鵜呑みにするか。実はそのいったことから本当の要望を導きだして、それを相手にもたらしてあげるよ、この差があるということです。
オムロンの事例は非常に高く評価されてます。
オムロンのサプライチェーン革新の本質は営業革新であるとも言える。
なぜか?
最終ユーザーが購入するまで売れたとは言えないとしました。
小売業と卸売業に、商品を収めたらお金をもらえるということになりますが、それで売れたと言わない。最後の最終ユーザーがPOSレジスターを鳴らした、POSをチンと鳴らした瞬間まで売れたと言わないで決めました。
たくさん押し込んだらどうなりますか?
結局、滞留するか、または安売りされるかです。
取引先だって本当はできれば高く売りたいと思っています。
定価で売った方が利幅が大きいです。彼らのサプライチェーンは自分たちの欠品とか過剰在庫を無くのではなく、お客さんの在庫欠品をゼロにしようという取り組みです。
例えば、収めた商品が1週間で売れたとするとします。
収めた1週間後にキャッシュレジスタがパチンと鳴ります。
しかし、それを収めた商品の支払いはだいたいが翌月か翌月払いです。
その間にお客さんのところにもうお金が入ってくるとしたら、資金が切れません。
だから一般的に実は在庫実際のゼロだといいます。
小売業は60日ぐらい在庫があるのが、毎日納品することで棚に入れるのを3日に1回だとしても、3日分の在庫を持てば足ります。
60日分を入れてしまうのと、3日周期でチャリンチャリンチャリンと回すのとどちらが良いでしょうか?
お客さんのマイナスを消すことに努力をするのはどうでしょうか。
売るものが変わります。
今までは新しい血圧計が出来ましたと営業していたのが、「我々とやると御社の在庫を半減できますよ。30日でも多い、1週間で充分ですよ。60日分買わなければならないのと1週間でいいです。」と言われるのと、どちらが良いでしょうか?
それも欠品しません。そうすると、余剰キャッシュが生まれます。回転率は2倍の3倍と劇的に上がります。60日だったものが10日だったら6倍になる。どうでしょうか?悪い話ではないです。商品を売るのではなく、我々とお付き合いすると財務的に有利ですよ。と売り込むことができます。
売り込む先はCFO/CEOが相手です。
なぜならば、劇的な経営改善をもたらすどうですか?
営業担当は、これを買ってくださいというのと、我々とやると財務効果が非常に良くなります。と売り込む。在庫を押し込む業者と、経営改善に貢献する会社どっちの商品を優先したくなりますか?
店頭に行った時にあれを買おうと思ったけど
店員さんに、「これ売れてますよってこれだったら絶対間違いない」と言われてつい買ってしまったということはないですか?
逆に、安物買いして銭失いすることもあります。
そう考えると、実は小売業の方々で店頭の人たちって我々に対してものすごく影響力があります。棚の一番いいところで「売れてます。」と言われればそれだけで「これなのかな、間違いないかな。」と思います。
だから売り上げが上がります。
月を追うごとに在庫が減っていきます。
なぜならルールを変えたから結果が早く出るんです。優れたルールをシステム化すると、より速く、より広く展開でき、効果も大きくなります。
オムロンは、スタートはお客さんのマイナスを解消する目的でスタートしました。いろいろな生産革新はしましたが、生産革新という言葉を止めました。生産革新といったら生産革新になってしまうからです。
全体最適のマネジメント革新とか、お客様の分です。社内ではありません。お客様も増えてサプライチェーンなんだから全体最適にしましょうとしました。
実際に改革しようとすると起きること
言うは易しで実際には、いろいろな障害があります。
実行しようとすると、
お客様の在庫を減らすと売上が下がります。予算達成ができなくなります。60日間押し込んでいたのを、例えば押し込まなくなったら、少なくとも1ヶ月分は無くなります。1週間分にしてしまえば、どうでしょうか?
1、2日ぐらいになってしまったらどうでしょうか?
売上がなくなってしまいます。
また、他社に棚を取られてしまうと言われます。
さらにお客様が販売データもらえませんと言われます。店頭には週に一回も売れない在庫はザラにあるので定数管理も出来ませんとか言われることがあります。
さらに、お客様はやっぱり安いものを求めているんですという人もいます。
更に、相手が言うこと聞いてくれるはずありません。物流コストが大幅に上がりますと。十倍上がります。エアで飛ばす必要がある。そんなことで利益が十倍も下がります。すごい利益がふっとんでしまいますと。
生産技術がまだなくて、柔軟に対応できませんとか。
さらに、生産キャパシティが足りませんと言われる。
でも、ちょっと待ってください。60日分のキャパを先取りして生産していたんです。今、工場で作ったものが60日後に売れています。
60日分のキャパが生まれるんだけど大丈夫と言っても、
いや、それでも今、生産現場が足らないと言われます。
さらに、工場の稼働率が下がりコストが上がりますと言われます。
稼働率を上げて、いま売れていないものを作るのはどうしてでしょうか?
さらに、部品リートタイムが長すぎて対応できません。生産技術の問題で小ロット対応難しいです。部品不足で生産さえままならない中で、もうこれは無理ですよと言われます。
しかし、なけなしの部品で今いらないもの作ってるというのはどうでしょうか?60日分の部品を作るのはもったいないです。
生産はすべて外部委託なので無理です。本当でしょうか?
これで無理だと思いますか?外部委託だから言うこと聞くということはないのでしょうか?
生産があるメーカーならまだしも、そもそも生産のない小売店・流通では無理ですと言われますが、ちょっと考えて下さい。
小売業はお客さんです。メーカーから小売業に売ってる、サプライヤーからお客さんに提案しているのを、今度はお客さんからこういうことやって欲しいと要望を出す。お客さんとサプライヤーのどちらが力がありますか?
さらにDXプロジェクトでERP刷新して、まずはデータを見える化しないと無理です。本当でしょうか?エクセルがありますよね。
昔のやり方をそのままやったらどうなりますか?その分だけ、1億、10億ではないすごい金額が無駄になります。こちらの方がリスクが高いです。
さらに社長の号令を聞いてチャレンジしたけど、それさえうまくいかなかった。社長の号令でさえうまくいかなかったと言われますけど、win-winを現場でやったのでしょうか?
これ、全部過去問です。
すべて、部分最適な問題が出されています。全体最適にしたらすぐ解決できる。そうすると圧倒的な競争力が得られる。
オムロンさんのようになりたいと思いますよね?
でも簡単ではありません。
なぜでしょうか?
すべての組織の中にはびこっている長年の規制概念を変えなくてはならない。これがなかなかできません。
1社ができても自分たちはできないと言われます。
なぜかと聞くと、あの会社だから出来るからと言われます。
組織の中で染み付いた既成概念を変えるって難しいです。
TOCは皆が相手のwinを先に考えて、サプライチェーンを作ることができます。TOCを学んでみてはいかがでしょうか?

金の知恵はありましたでしょうか?
月曜日が楽しみな会社にしましょう。
動画視聴はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=YHCjfSf1pEg
◆Onebeatを導入した事例を知りたい方はこちら↓https://www.1beatjapan.com/casestudy
◆過剰在庫と欠品を防ぐためのお役立ち動画を視聴したい方はこちら↓https://www.1beatjapan.com/video
◆Onebeatのカタログ請求をしたい方はこちら↓https://form.k3r.jp/goldrattjapan/brochure
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
