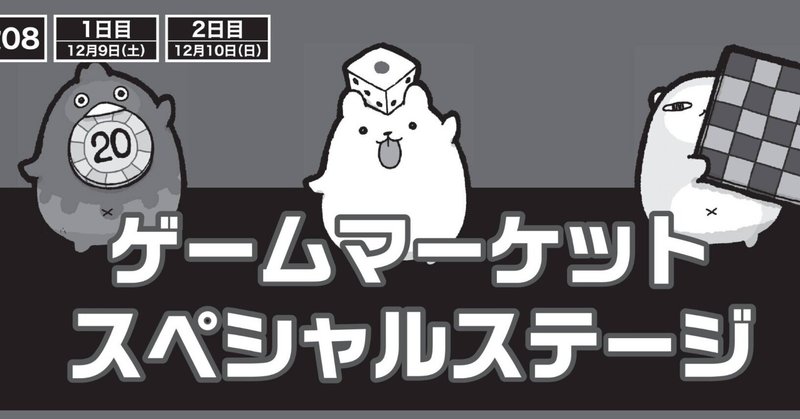
マーダーミステリーの口コミに関する変化はあるのか、否か
ゲームマーケット2024春の1日目「マーダーミステリースペシャルトークショウ」にて、登壇させて頂きました。
https://x.com/Kancho1003/status/1780920713014280661
司会は、かわぐちまさしさん、ずっちーさん。
二部構成で私は二部の出番です。とりあえず豪華な登壇者に混ぜてもらえるだけで、大変恐縮でした。二部で、一緒登壇したのは、堀江貴文さん、白雪りらさんです。
かわぐちさんこと、かんちょーさん、ずっちーさん、りらさんとは、もちろん面識もあり、マダミスの同卓歴もあるので安心ですが、問題はホリエモンこと堀江貴文さんです。初対面であり、何を話せばいいか……とトークイベント前にはとても緊張していたのですが、そこまでクロストークはなく、それぞれが質問に対してコメントをするという形式だったため心配は杞憂となりました。
ホリエモンの提案
さて、いくつかの質問に対して返事をしたり、ホリエモンさんが自身が登場人物として参加する『堀江貴文殺人事件』について熱く語り、『ヒカル殺人事件』についても熱弁し(色々な意味で)、大いに会場を盛り上げてくれました。そんな中「マーダーミステリーが流行るために」といったテーマで堀江さんがとても興味深いことを話していたので、その話について考えてみたいと思います。
彼曰く、SNSで呟きたくなるような、ネタバレに抵触しないけど、それは言ってもいい、そして興味をひくような内容で拡散させていくようなもの、という内容でした。マーダーミステリーにおいてネタバレを避けた感想は難しいことで、たとえば犯人役だった場合、「つかまりませんでした!」や「つかまりました!」はネタバレに当たります。そのキャラクターが犯人だということが未プレイの人にわかってしまう(また、この作品にはプレイアブルキャラクターに犯人役があるのだ、ということもわかる)ためです。
ゲームの本質に触れるのも難しいです。たとえば「二部構成で二部は協力ゲームだった」「実は現実世界ではなくVRの世界だった」「登場人物は実は多重人格で一人の人間だった」なども遊ぶ前に知ってしまうと、作者の想定している体験度を損なう要素のため、ネタバレになることが多いです(作品ごとに公開設定は決められているため、必ずの限りではありません)。そういった様々な制約のもと感想を呟くことになるため、「楽しかったー」を軸とした、曖昧な感想が多くなりがちです。
余談ですが、私は主観として楽しくなかった、出来が著しくよくないものに関してはSNSでの感想は書かないようにしています。なので、書いた時点で、個人的には伝えたいことがある、と思ってください(大体、感想を出すのは遊んだ3~4割の作品ですかね;;)。
話を戻しまして、このホリエモンさん話を聞いて、私が頭に浮かんだのは『アニクシィ』『カノケリ』『シノポロ』『キモナス』という四季のマーダーミステリーです。
https://ibarayugi.wixsite.com/iraba/seasons
この一連のシリーズはマーダーミステリーとしての犯人捜しの他に、キャラクターたちが住む国が「滅亡」するか「存続」するか、どちらかの結末が存在します。また、この滅亡or存続に関しては、SNSでの感想はOKとされています。つまり、感想を明確に伝えることができ、それを見たフォロワーには「存続」したいという気持ちを掻き立てるアピール力を持っています。個人的にはこのシリーズの滅亡・存続はかなりエポックメイキングなことだと思っていて、効果的なSNS用のマーダーミステリーが流行るようになる、というホリエモンさんの見解には、さすがの目の付け所と感じました。
具体的に確認していませんが、あくまで想像の範囲ですが、脱出ゲームの「成功」「失敗」にも通じる部分があると感じました。あちらも文化として謎のネタバレはNGですが、ゲームの結果を伝えることができる、というのは大事だと思います。
また、補足する形で白雪りささんの意見では「犯人可変型」のマダミスが流行るのでは? という意見もありました。これは「捕まった」「逃げ切れた」「捕まえた」「逃げられた」などに対する解決策への提案でした。つまり、遊ぶたびに犯人が変更になる以上、犯人に関する結果もその卓ごとに異なるということになり、それを発信しても、自分たちが遊ぶ際には影響がない、ということです。良い意見だとは思いますが、それで面白い作品を作るのはかなりハードルが高そう……とは思いました(実際そういった作品もあるにはありますが、そもそも可変型ということが秘匿されたサプライズなシナリオのことが多いです)。
この方向性を模索する場合、何度も遊ぶことができる可変型の推理ボードゲーム(古くはクルードなど)や、毎回役職が変更になる人狼ゲームに寄って行くのかな、とも感じました。
木皿儀の見解
これらの意見に関しては、私もとても感銘を受けて、筆を執った次第です。
マーダーミステリーの問題点のひとつにブラックボックス。ということがあります。公開されている内容以外のことがネタバレに当たり、伝えたいけれどネタバレに抵触するため発信できない、という構造です。
この構造のメリットは「プレイ時の新鮮味の担保」できることで、デメリットは「拡散力の欠如」「プレイ時のミスマッチ」などが挙げられます。
・プレイ時の新鮮味の担保
事前情報を知らなければ想像もしていない展開に直面した際に、より感動を得られます。新鮮さをどこまで感じさせるか、どこで予想を裏切るか、これがシナリオを制作している作者の腕の見せ所です。
・拡散力の欠如
SNSにおいてネタバレに注意しながら曖昧な感想しか伝えられず、面白さを伝えるのが難しいです。結果、画一的な感想が並んでしまい、どの作品が秀でているかということが分かりにくくなるというのも付随したデメリットです。
・プレイ時のミスマッチ
ブラックボックスの場合、実際に蓋を開けた趣味にそぐわない(先日、SNS上で話題になった、センシティブマダミスなど)ことが起きやすくなります。ここは作者が適正な判断で設定し、面白さをどこまで店舗出来るかを考えていってほしいです。
ある意味相反するメリットとデメリットですが、ここに風穴を開けられるような作品が生まれることで「ゲーム的満足度」以外のプロモーションとして有機的に機能する作品が生まれてくるのでは、という期待を感じられるトークイベントでした。
自分でもいくつかは試みている部分があります。たとえば『あなたの原罪』という探偵キャンプさんにて遊べる公演型のマーダーミステリー作品は、フォトスポットを用意しキービジュアルと同じような構図で撮影ができるというようにしました(探偵キャンプさんの発案で、謎解きの文化に近いアプローチです)。このフォトスポットという方向性は、『七色の結婚式』や『黄色い勿忘草』、『オーギュリー』『サイバーファミリ―』、劇的シリーズなど、公演型であり部屋を作品用にカスタマイズしている作品に顕著に見られる要素ですね。
オンラインマダミスではエンドカードの文化が育ち、そこにどんな情報を載せるかという部分が模索されています。ビジュアル的に見栄えを良くする、印象的な文字を並べる、動く、結果により内容が変化する、というようなものがあります。今後もここは掘り下げられていくと思います。
結論
諸々、ゲームの本編とは関係ないように見えますが、作品を世に出す以上、「面白い作品を作る」「多くの人に遊んでもらう」はどちらも重要なことになります。ボードゲーム業界でよく議論されていた『制作』と『宣伝』の問題と通じる点があります。宣伝が上手いが中身が伴わない作品が、内容が良くても宣伝が不十分な作品よりも売れてしまうことがある、という構造です。
マーダーミステリーにおいてはブラックボックス問題がある以上、宣伝(プロモーション)はとても重要です。現状は市場のパイがまだまだ小さいため宣伝よりも口コミの方がかなり影響力があります。もしかしたらそれは逆転していくかもしれません。
昨今では、まさにホリエモンさんやヒカルさんといった影響力のある人が制作に参加してきたり、アニメ作品などとのコラボも充実していく可能性があります。それらはそういった作品が作られるという時点で話題としてのバリューが見込めます。あとは面白ければ口コミなどの評判で広がっていくことでしょう。
とはいえ、そういった外側の情報が乗せられない作品が基本にはなると思います。そうなると、クオリティが高く作品、要素に特化した作品、特定の人に刺さる作品といったものが注目されていくことになると思いますが、基本は面白い作品を作っていけばいいというわけです。そして、ネタバレに対する革新的なアイデアが浮かべば、それが今後のマーダーミステリーを広めるきっかけになると期待しています(長々と書きましたが、つまりホリエモンさんの言うことは、かなり的を得ているということです)。
個人的には四季のマーダーミステリーシリーズをベンチマークに、模索していこうと思います。製作者の皆さんもぜひ、何か良いアイデアがあれば実践してください。まる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
