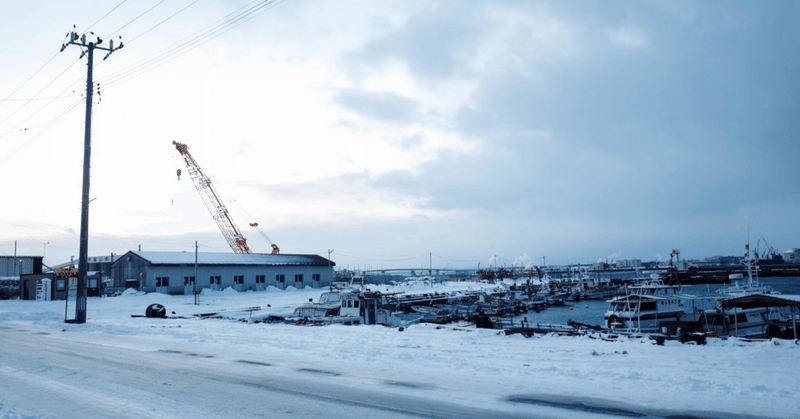
最愛は海色 第12章
こんなに近くにいるのに孤独になることもあるのだと、優多さんと出会ってからはじめて知った。
十六年生きていても、はじめて知ることがたくさんあるから驚く。
優多さんが教えてくれたことが、抱えきれないほど胸の内にある。
「窓見て!」
珍しくアラームよりも先に起き、しゃんと目が覚めた。
窓から差しこむ光を眺めていると、携帯が鳴った。画面を見ると、久々に優多さんから連絡がきていた。
「雪だ」
「初雪だね」
見慣れた景色が白く薄化粧をしている。
雪が降ってはしゃぐのも、雪が降った喜びを真っ先に私に教えてくれるのも愛しい。優多さんの心の中に、私の影をはっきりと見つけられたような気がした。
「歩く?」
「歩く」
まだ人が眠っている時間。一番乗りにおそろいの足跡をつけた。本降りではないから、この足跡はすぐ消えてしまうけれど。初雪が降るたびに、私はこの冬を思い出すのだろう。
優多さんは、自分自身と向き合う時間が増えた。
きっとそれは、私に話しても解決しないことで。今までぴったりと心が重なっていたことのほうが奇跡だった。
「富田さんがね、一度この街を出たからこそ、この街の良さにもっと気づけたと言ってたんだよね」
「うん」
その先を言わないのが、優多さんだ。彼が遠いところに行こうとしていることは、ずっと前から気づいていた。
孤独なまま、冬は過ぎた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
