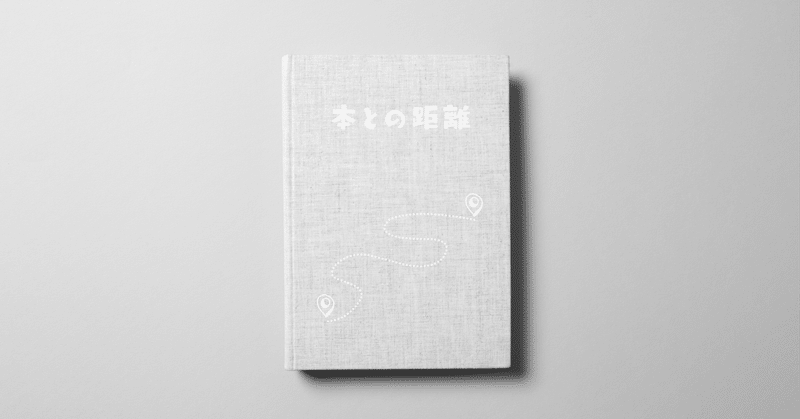
本との距離④(800字)
壮絶10代を過ごしてきた母が選んだ本に囲まれて、牛歩以下、かたつむりのようなブックライフがはじまった4~5才。まずは絵本から。
『じごくのそうべえ』以外にも記憶に残っている絵本はいくつかある。『どろぼうがっこう』に『グリーンマントのピーマンマン』は、共働きのなか、母が読み聞かせしてくれたのを覚えている。
泥棒だって勉強するんだなぁとなんとなく思ってたし、(クレヨン)しんちゃんに共感できるほどにピーマン嫌いだったのもあり、食べると嫌いなのに読むと好きになっちゃう絵本のキャラに惹き込まれていた。
そう、文字は読めるようにはなってたけど、読み聞かせられないかぎりは、やっぱり”絵”で魅せられる時期だった。自分で文字も含めて、読むようになったのはキャラありきの『バーバパパ』シリーズだったような。
幼いながらにも『どうぞのいす』は道徳的なもので印象深かった。4人兄弟の3番目、間に挟まれた次男で、かなり自己中だった。弟に物を貸したりするのすら頑固になっていた頃で、母に叱られたりし、どうぞと「次にゆずる」というメッセージが響いたんじゃないだろうか。
さて、本へ接近するきっかけはビデオからもつくられていた。小学校に上がる前は、微妙なタイミングで引っ越しが重なり、弟と二人で家で過ごすことが多く、ビデオを観て過ごすことも多かった。カンフー以外にも影響は受けていて、それこそが『ゲゲゲの鬼太郎(3期)』だった。恐ろしいような、かわいいような、異形の妖怪たちにビビビときた。
カンフー関連で、動きを真似したくなるジャッキー・チェーン出演作品も関心を持った。そこになんかやたら出てくるなと思っていたサモ・ハン・キンポー製作のキョンシー映画『霊幻道士』に衝撃を受けたときと同時期に、水木しげるに出会ったのだ。
『ねないこだれだ』を皮切りに、"こわいけど気になる"キャラが出る絵本にやたら気をとられていた。そして、小学生になる。
もしも投げ銭もらったら、もっとnoteをつくったり、他の人のnoteを購入するために使わせてもらいます。
