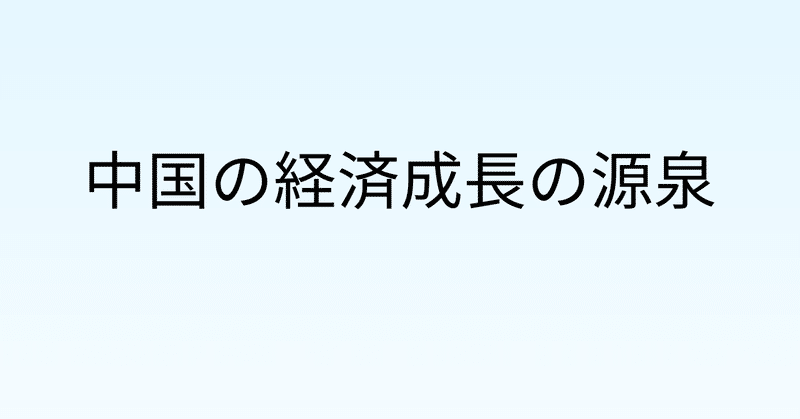
人口ボーナス論(2)ー中国の経済成長の源泉
はじめに
中国の労働力人口が減少しているにも関わらず,中国の経済成長は続いている。「中国に人口ボーナスはあったのか?」で述べたように,人口構造の変化が中国の経済成長を小さいながらも押し上げたことは確かである。しかし2010年代から第1の人口ボーナスはなくなっており,今後の高い経済成長は期待するのが難しい。
一方で,第2の人口ボーナスの存在がこれまでの研究で指摘されている。労働力人口が減少し,その後高齢者が増加することが見込まれると,人々は貯蓄を増やし,その貯蓄が投資を増加させ,持続的かつ永続的な経済成長が続くとされるものである。
まずは,中国の経済成長について,一般的な生産関数から事実を整理していきたい。本稿の結論を先取りすると,中国の経済成長が旺盛な投資によってもたらされているということ,その投資も徐々に生産を促す力がなくなってきているということである。
経済成長モデル
長期的な経済成長は,労働,資本,でもたらされる。生産関数の一般形は以下のように示される。
$$
Y = F(K, L)
$$
資本と労働が投入されて,生産(所得)が生み出される関係を示している。両辺を労働で割ると
$$
\frac{Y}{L} = F\left(\frac{K}{L}, 1\right)
$$
となる。労働で割る意味は,①1人あたりの生産(所得),1人あたりの資本ストックが計算でき,人口規模に対して中立的になること,②経済厚生という点からは,生産規模の大きさではなく,生産水準の方が重要だからだ。
中国のデータ
モデルから中国の長期的経済成長を見ていくが,まず上記モデルのためのデータを整理する。データの出所は中国国家統計局の統計年鑑やHPで公開されている「国家数据」である。簡単なものから説明していこう。
Lの推計
Lは労働力人口(人数)である。これはそのまま労働力として利用する。
Yの推計
Yは価格変化を除いた実質GDPを採用する。統計年鑑では1978年の値を100とした実質GDPの指数が公開されているので,これを2010年基準(=1)と設定し,2010年の名目GDPを基準にして各年の実質GDPを推計した。
Kの推計
Kは資本ストックである。中国では1980年以降の全社会固定資本投資(フロー)が公表されているのでこれを利用する。投資財の価格に関する適切なデータがなかったので,GDPデフレーター(名目GDP÷実質GDP)を利用して,2010年基準で投資額を実質化した。
資本ストックは対象年に社会にどれくらいの生産手段(資本)が存在するかを示すものであり,毎年の投資を積み上げていくとともに,減価償却分を考慮する必要がある。1980年時点の資本ストック額が推計できないため,スタート時点の1980年はそのまま投資額を資本ストックとして,毎年の投資額を足していく。ただし,毎年減価償却(資本がすり減っていく)が行われるので,1990年から2020年までの10時点の産業連関表(注1)の付加価値に占める固定資本減耗の平均比率14%を用いた。具体的には以下の計算式で資本ストックを計算した。(Kは資本ストック,δは減価償却率,Iは投資,tは時点を示す。)
$$
K_t = (1-\delta) K_{t-1} + I_t
$$
あとでも述べるが,1980年のスタート時点がフローデータであるため,最初の10年間ほどは資本の積み上げが過大になってしまう問題点がある。
(注1)産業連関表は0と5の年に基本表,2と7の年に延長表が公表されているため,10時点の産業連関表が利用可能である。
中国の経済成長
データが用意できたので,中国の経済成長を見てみよう。
生産,資本,労働

ここからわかることは,労働力数の上昇が緩やかなのに比べて,資本ストックの上昇が急激である。とくに2000年以降,資本ストックは急速に拡大した。これは都市部の住宅建設が進み,高速道路や高速鉄道などの社会インフラ建設が進んだことを示している。資本ストックほどの上昇率ではないが,中国の生産は順調に成長している。ここからも中国の経済成長において資本ストックの拡大が重要であることを示している。
労働1人あたりの実質GDP(労働生産性)
労働1人あたりの生産(労働生産性)の増加を見てみよう。

値で見れば,中国の労働1人あたりの生産(労働生産性)は着実に上昇している。1990年は1989年の天安門事件の影響による国内生産の縮小,諸外国からの経済制裁などが影響し,この年のみ減少した。
労働1人あたり生産(労働生産性)の伸びは比較的安定しており,1990年の経済不況,1990年の労働統計の断絶,を考慮して,1991年から2022年までの労働1人あたり生産(労働生産性)の成長率を計算すると,期間の平均成長率は8.2%である。
「中国に人口ボーナスはあったのか?」で述べたように,人口1人あたりの所得は以下のように分解することができる。
$$
\frac{\Delta y^n}{y^n} = \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta y}{y}
$$
人口1人あたりの所得は,労働生産性が一定であれば,総人口の成長率に対する労働力人口の成長率の大きさで決定する。図2から明らかなように,比較的労働生産性は安定している(長期的には微妙に下降傾向にはあるが)。すなわち,労働人口が総人口より早く上昇すれば,人口1人あたりの所得は,8.2%を上回り,労働人口が総人口より早く減少することになれば,人口1人あたりの所得は8.2%よりさらに下回ることとなる。2010年代の第1の人口ボーナスは-0.36%,2020年代は-0.94%なので,今後は7%前後にまで下がることが予想される。
労働1人あたり実質実物資産額(資本装備率)
労働1人あたり資本ストックの動向を見てみよう。

労働1人あたりの資本ストック額は,労働1人あたりにどれだけ工場や機械や社会資本に恵まれているかを示している指標であるので,資本装備率とも呼ばれる。上記でも述べたように中国の社会資本の拡大,工場の拡大により,労働1人あたりの資本ストックは大きく上昇し,1991年から2022年までに26倍になった。この間労働力人口は1.16倍にしかなっていない。たとえて言えば,労働者1人あたり利用できる機械が1台であったのが,26台にまで増えたということである。あるいは,労働者1人あたりが利用できる高速道路が1㎞だったのが,26㎞にまで延長したことを示している。
資本ストック推計において,1980年のスタート時点がフローの値を利用しており,そのまま毎年の投資額を足していくので,どうしても1980年代の1人あたり資本ストック成長率は大きくなる。その推計問題を避けるために,労働生産性と同じく,1991年から2022年までの労働1人あたり資本ストックの成長率を計算してみると,労働生産性と同じく比較的安定している。この期間の平均成長率は,10.8%である。
1単位あたり資本が生み出す実質GDP(資本生産性)
生産関数が示すように,労働者1人あたりの実質GDPは,労働者1人あたりの資本ストックが生み出す。労働生産性と資本装備率をみると長期的には比較的安定しており,資本装備率が10.8%毎年増加し,労働生産性は毎年8.2%増加している。つまり労働1人あたり資本ストックが上昇しても,それがまるまる労働1人あたりの生産(所得)につながっているわけではない。資本装備率と労働生産性の間にある2.6%の差をどう説明するかという問題が残っている。

1元の資本ストックが増加すると,1元以下の生産に変換されており,長期的にはゆるやかに減少傾向がある。
1単位の資本ストックあたりの生産(所得)の成長率をみてみると,これも比較的安定している(1980年代は上記で述べたように資本ストックの推計問題がある)。1991年から2022年までの年平均成長率は-2.3%である。
つまり,資本ストックの限界生産性が毎年2.3%減少していることを示している。限界生産性とは,資本ストックが1単位増加したときに生まれる生産(所得)が徐々に減少していくことである。労働者1人が1台の機械を使っているとして,もう1台機械が手に入れば,生産は倍近く増えるだろう。しかし,20台の機械がもう1台増えて21台になったからといって,生産効率が倍近く伸びるわけではない。このように資本ストックが限界的に1単位増加した労働の生産性が減っていくことを限界生産性が逓減するという。
つまり,
労働生産性8.2%≒資本装備率10.8%ー資本生産性2.3%
という関係が示唆される(注)。
おわりに
以上の簡単な経済成長の分析からわかることは以下の通りである。
労働ではなく,資本拡大が中国経済成長の源泉である。
第1の人口ボーナスを加味すると,労働力比率はマイナスの効果になるので,2020年代後半は7%前後に下がる可能性がある。
労働生産性成長率,資本装備率の成長率,資本生産性の成長率には比較的安定した関係がみられる。
中国の持続的な経済成長において,労働増加が期待できない以上,資本の増加はもっとも重要な役割を果たしている。しかし,資本投下を増やしていったとしても,資本生産性は安定的に低下しているので,今後は低成長の時代がくることは避けられない。
注
1人あたりの生産(労働生産性)は,資本生産性と資本装備率の掛け算で示される。
$$
\frac{Y}{L} = \frac{Y}{K} \cdot \frac{K}{L}
$$
ここから,成長率の関係を導けば以下のとおりになる。
$$
\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta k}{k}
$$
ここで,$${y = \frac{Y}{L}}$$, $${\quad h = \frac{Y}{K}}$$, $${\quad k = \frac{K}{L}}$$である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
