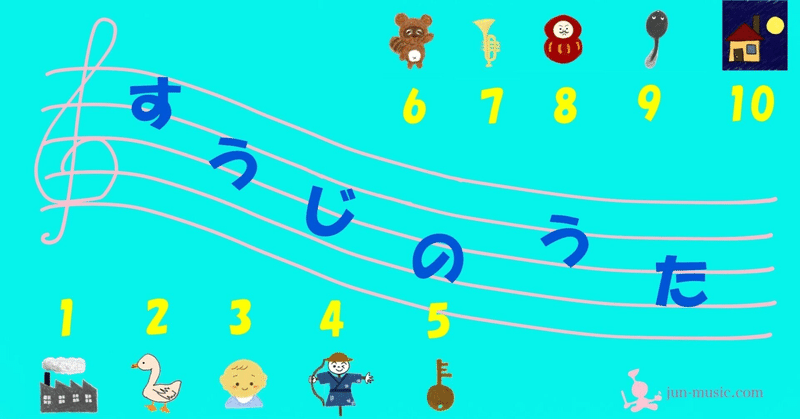
No.754 「あっちゃー、そん通りだわ!」
何年経っても変わっていない自分に苦笑してしまいたくなるのです。
もう四半世紀も前の話になりますが、その日は、近づいた体育大会の最後の演目・フォークダンス(当時、定番の「オクラホマ・ミキサー」)の練習もしました。全校生徒を数パートに振り分け、グラウンド狭しと、踊りの輪を作ることから始まります。
私の担当パートにも4クラスの男女が参集していたのですが、私から見て左側に男子、右側に女子が並んで座っていました。ご存知のように「オクラホマ・ミキサー」は、輪の内側の男子が右手を差し出し、輪の外側に並んだ女子の左手を優しく握って歩きながら適当な輪の大きさに広げてゆくことから始まります。
私は手前から男女を導いて輪を作ろうと思っていたので、輪の外側となる左側に女生徒が並んでいてほしかった訳です。
「ありゃ、男女が左右逆に並んじゃったんだねー。」
と言ったら、高3の女生徒が、すかさず、
「先生、後ろから左回りに輪を作ったらいいんじゃありませんか?」
と言いました。へっ?一瞬、息するのも忘れました。
「あっちゃー、そん通りだわ!」
と「オジサン一本取られた」体でした。私の頭に全くない発想が、彼女にはあったのです。柔らかい発想というか、常識にとらわれない発想というか、私の苦手とするところです。いまだに忘れられないシーンです。
昨日、今年最初の「古典教室」を開催しました。老若善男善女がうちそろい、正月恒例となった参加者全員で落語(今回は「厩火事」)を順番に読んで味わった後、去年、5回シリーズで鑑賞した『建礼門院右京大夫集』のまとめを少し行いました。
90分の講座が終わり、次回からのお話を「百人一首」にしたいと提案したところ、喜んで賛成してくださった方が多く、撰者の中世歌人・藤原定家は、あの世でうれし泣きしておられることだろうと思った次第です。
実は、数年前に「古典教室」で「百人一首」の鑑賞を最初から行ったことがありますが、半分いったところで中座し、別の作品に切り替えていました。そのこともずっと気がかりだったので提案したのでした。
しかし、前からの生徒さんだけでなく、新たな参加者も何人かいます。そのこともあったので、体裁を少し変えて、もう一度初めから「百人一首」に挑もうかなと思っていましたら、
「先生、最後(100番)から順番に前にやっていったらいいんじゃありませんか?」
とM子さんに言われました。
「あっちゃー、そん通りだわ!」(PART2!)
と思いました。そうすれば、最初からの方も、途中からの方も気持ち新たに打ち込めます。どうして、私は、あんなに柔らかく、美しい発想が出来ないのでしょう?25年前の私は、依然として同じまま(健在?)だったのです。もう「苦笑」以外にありません。
ふと、脳裡を駆け巡るものがありました。私が、まだ30代の、髪の毛がクログロ、フサフサとして「見てくれ!」と言わんばかりだったころに、クラスの生徒と一緒に「内田クレペリン検査」を受検したことがあります。
「クレペリン検査」とは心理検査で、1桁の足し算による作業曲線が個人の精神や心理的な特徴と関係するという事を発見した20世紀初頭のドイツ人精神医学者エミール・クレペリンの名前をいただいています。その後、日本の心理学者、内田勇三郎が「内田クレペリン精神検査」(クレペリンテスト)として完成させたと言われています。
その結果、私の個人診断所見には、赤鉛筆で次のように書かれていました。
「仕事は真面目で繊細だが、もの堅きにつき、窮屈すぎるきらいはある」
要するに「石頭」という事でしょう。私の頭の堅さはお墨付きのようです。
「あっちゃー、そん通りだわ!」(PART3!)
※画像は、クリエイター・JUN音楽教室@趣味だけど本気でピアノ🌈夢をかなえよう🌈さんの、タイトル「子ども遊ぶのは得意だけど・・」をかたじけなくしました。お礼申します。
