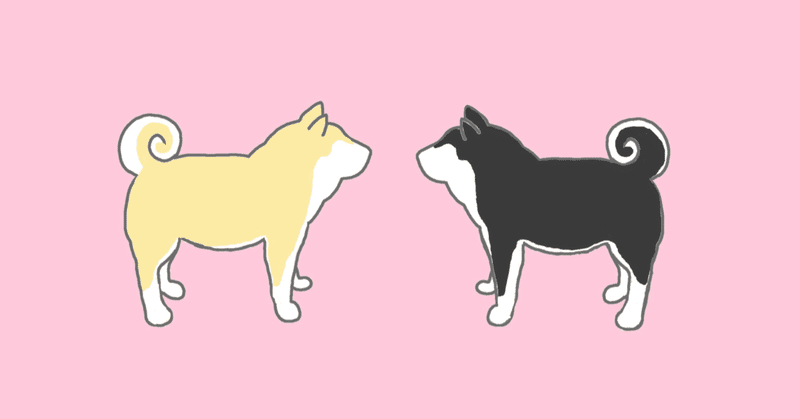
「カウンセラーは話を聞いていて自分が病んだりしないんですか?」:コメントシート雑記①
学生さんからのコメントシート
秋になった。
毎年、筆者はPT・OTの養成の専門学校や大学で心理学や臨床心理学の授業を担当している。いずれの学校でも好き勝手やらしてもらっているのだが、毎回授業後にコメントシートを書いてもらって、それについて10〜30分しゃべるということをやっている。
これがすごく楽しい。学生からの評判も悪くないようである。20〜40人の専門学校であれば全員分読み上げることができるのだけど、大学だと10人分くらいしか取り上げれなくて、ちょっと残念ですらある。
さて、コメントシートにはカウンセラー/臨床心理士・公認心理師である筆者に対していろいろな質問が寄せられていたりする。これは我々に向けられているまなざしであると思うので、「個人の意見だけど」と断った上で、なるべく答えるようにはしている。
いくつかの質問は、毎回同じなのできっと皆が疑問に思うことなのだろう。それに対する筆者なりの解答についてちょっとまとめようと思う。回答を決めておいて、ラクしたいからね。
「カウンセラーは話を聞いていて自分が病んだりしないんですか?」
絶対にくる質問
絶対にくるのが「カウンセラーは話を聞いていて自分が病んだりしないんですか?」という質問である。
これに対する答えは、「僕はめったに病まない」である。
なぜ病まないのか。その理由は「(臨床心理学を基盤とする)カウンセラーはクライアントの話を、自分の体験と切り離して聞くことができる」からである。誤解を招きかねない表現でいうのであれば、「他人事」として話を聞くから、と言える。
話を聞いていて辛くなる時:「自分事」として話を理解する
では、話を聞いていて自分が辛くなる時というのは、どんな状況なのか。それは二つのケースが想定できると思う。
一つ目は「相手のことを自分の一部のように感じており、そのために自分も傷ついてしまう」という場合である。自分の子どもが悲しい・苦しい体験をしたという話を聞くときに、ついつい親も涙を流してしまう、というのがこれである。
二つ目は「相手の話から、自分の過去の経験を思い出してしまい、そのせいで辛くなってしまう」という場合である。友人の失恋話を聞いている時、過去の自分の失恋体験を思い出して悲しくなる、というのがこれである。
いずれにしても、相手の話を聞いていて辛くなるのは、あくまで「自分」が傷ついたり、あるいは過去に傷ついたりしたから、であると言える。すなわち、相手の話を「自分事(じぶんごと)」としてしまうから、辛くなるのである。
相手の話を「自分事」としてしまうことは、誰しも日常的に経験している。だからこそ、ハードな話を仕事として聞いているカウンセラーに対して「病まないの?」という疑問が寄せられるのであろう。
カウンセラーの傾聴:「他人事」として話を理解する
しかし臨床心理学を基盤とするカウンセラーが、仕事としてクライアントの話を聞く時には、「自分事」として話を聞くことは、少なくとも理想的ではない。カウンセラーが話を聞くのは、あくまでクライアントの話であり、「他人事」としてそれを捉えるのである。
ここでいう「他人事」とは「親身になって話を聞かない」ということではない。セラピストはクライアントの話を聞きながら、そこを追体験していく。しかしそれは、あくまで自分ではない相手の話として行われるものなのである。この二重の性格ーつまり相手の話に入りこみつつ、自分を見失わないことーの必要性は、カール・ロジャーズによる「共感」の概念によって、古典的には表現されている。
クライアントの私的世界をそれが自分自身の世界であるかのように感じとり、しかも「あたかも、のごとく」という性質を決して失わないーこれは共感なのであって、これこそセラピーの本質的なものであると思われる。
クライアントの話を聞くとき、セラピストは「あたかも、のごとく」という性質を失うことはない。それが相手の話であること、すなわち自分とは異なる他者の話であるということを十分に理解しながら、傾聴していく。このように話を聞くことによって、セラピストの共感はあくまで技術としてクライアントに提供されるのである。セラピストはそこに自分の体験を混ぜて、クライアントの体験を簒奪することはない。だからこそ、セラピストの共感がクライアントの自身の体験に作用することができるのである。
そうやって追体験していくところには、クライアントのものである苦しいもの・辛いものが存在することは確かにある。それに触れる時、苦しさ・辛さというものはセラピストにも体験される。しかしそれは「あたかも、のごとく」体験されるものであり、セラピスト自身の経験に基づく苦しさ・辛さではない。
そのため、面接が終わるのであれば、苦しさ・辛さはセラピストの手から離れ、その中に存在するものではなくなる。だからこそ、臨床心理学に基づくカウンセラーはクライアントの話を聞いて、辛くなって病んだりすることはないのである。
クライアントの話を聞いて病まないために
とは言いつつも、これは一つの理想的状態である。否応なしにクライアントの体験が自分の体験と近い場合は混じってしまうことはある。ただそれでも、この混在はある程度これは技術的に予防できるものである。
まず、クライアントの話を具体的に聞いていくことが必要である。日時、場所、他の登場人物の具体的情報、その他諸々のコンテキスト、そういったディティールに関する情報はなるべく集めておくに越したことない。話の腰を折らず、相手に失礼にならず、相手の世界を追体験できる程度の情報をどう集めていくかというのは、その必要性の説明や関係性の構築も含めて、面接技術の中で大切な要素である。
何よりクライアントが話す中でわからないことがあった時、それをきちんと尋ねることが大切である。クライアントの経験や状況を十分に把握できていないのであれば、そこを埋めるために自分自身の経験を使わざるを得ない。そうなると、もはやその話は「自分事」になってしまう。面接が終わった後でも、自分の傷つきとしてそれが持ち越されてしまうことで、結果的に「病む」ことが生じてしまうかもしれない。
もう一つ、しつこく前段にて「臨床心理学を基盤とするカウンセラー」と言ったのは、そうでないカウンセラーがいるからである。それが、自分自身の病と回復の経験を基盤としたカウンセラーである。こうしたカウンセラーは、自分自身の経験を基盤としてアセスメント、共感、介入といったものを行うために、必然的に「自分事」としてクライアントの話を聞くことになる。そのため、クライアントの話を聞いて「病む」こともあるだろう。あるいは、「自分事」に沿わないクライアントの体験に対して、自分を守るために攻撃的にそれを排除しようとしまうかもしれない。
臨床心理学を基盤にしていても、未消化の傷つきを抱えたカウンセラーは同様の間違いを犯してしまうことがある。もちろん、筆者もその中に含まれているだろう。人間である以上、傷つく経験を避けることはできない。しかしそうであっても、きちんとクライアントの話をクライアントの話として聞いていこうという営みが、臨床心理学を基盤としたカウンセラーには求められていると思う。
おまけ・それでも傷ついてしまう時
ただし、壮絶なトラウマ体験を聞く時は別である。トラウマ体験は、技術を「貫通」してセラピストを揺さぶる。面接が終わっても、その痛みは残り続けてしまう。トラウマ臨床において、セラピスト自身のケアが重要であると言われるのは、このためである。
なぜだろうか。
まず考えられるのは、クライアントの傷つきが大きすぎるからである。これはあるだろう。その次に考えられるのは、外傷性逆転移と呼ばれる特殊な逆転移が生じている、という説明である。これも妥当であろう。
もう一つの説明は、トラウマによって生じる外傷は、全ての存在の本質的要素への脅かしであるから、それを「他人事」として処理することができないから、というものである。トラウマは、どうしても「自分事」となってしまうのである。この辺りの考え方については、この記事の最後にちょっと書いたものになっている。
最後の説明を僕自身としては気に入っているけども。
参考文献
カール・ロジャーズ(2001)「セラピーみよるパーソナリティ変化の必要にして十分な条件」伊藤博・村山正治訳『ロジャーズ選集(上)』誠信書房
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
