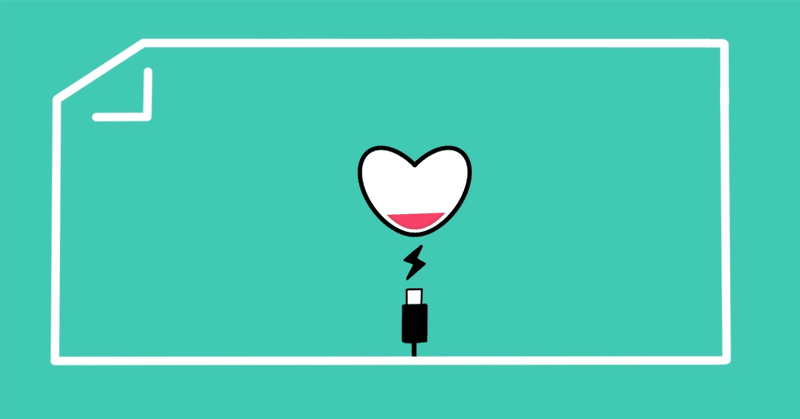
トラウマにおける「逆転」の扱い:心理的逆転の概念を手がかりに
※金額は投げ銭の設定です。全文無料で読めます。
はじめに
心理的援助の中でも、トラウマが背景にある人、とりわけ複雑性PTSDと呼ばれる人たちへの支援は困難を極める。その中の理由の一つとして挙げられるのが、トラウマ治療の中で生じる独特の治療抵抗的な振る舞いである。この振る舞いに対して、TFT(思考場療法)の創始者であるロジャー・キャラハンが論じた心理的逆転(Psychological Reversal)と呼ばれる概念を結びつけることで、それを解消しようという試みがしばしばなされている。
こうしたセラピストは、従来であれば非常に対応が難しいような困難事例に対しての治療例を報告しており、心理的逆転という見方とその解消のプロセスは臨床的に非常に有用な要素を含むものであると思われる。しかしながら、そうしたセラピストの述べる心理的逆転の修正法は、通常の心理学とは異なった体系への志向性が強いものとなっている。そのため、その技能の取得は一般的な心理学教育の中でトレーニングを受けてきた心理職にはややハードルが高いものと感じられるかもしれない。
そこでこの記事では、まずこうした心理的逆転の概念に対して、さまざまな角度から再検討をすることとする。そのためここで扱う心理的逆転とはカッコ付きの「心理的逆転」となのる。その結果、より広い立場の支援者がこの概念を安全に建設的に取り扱うことが可能となれば幸いである。
心理的逆転
心理的逆転とは
それでは、心理的逆転とは何なのであろうか。先に述べたように、これはTFTの創始者であるキャラハンによって「発見」された概念である(Callahan, 1991)。これは人間の動機づけが自己利益に向かうという本来の働きとは正反対の方向に働く状態を作り出すものとされ、努力を妨害し、良いことをしようとすることでストレスを感じさせることになるものであるという。キャラハンはフロイトの「死の欲動」やエリスの「自己敗北(self-defeat)」に言及し、心理的逆転はこれを説明するものであると述べている。
このように、心理的逆転とは、体内の自然治癒力 (エネルギー) をブロックされるために生じる、効果的な治療介入を妨げる身体と心の状態である。嶺(2019)はキャラハンに言及して「治療効果が現れない、治療してもすぐに悪い状態に戻ってくる、あるいは治療直後にネガティブな反応が現れるなど、治療者を悩ませる事象が起こっている時には、この現象がクライエントに潜んでいる可能性がある」と述べている。それが起きたクライアントについては、このように描写されている。
(こちらはクライエントの味方であり、協力者であるにもかかわらず)クライエントから攻撃的な言葉や態度をぶつけられる、クライエントにとって有効な治療を提案したり実際にそのセラピーを提供している間に「それはできない」「それはいやだ」「これは○○」などとさまざまな抵抗をされる、治療者から見て「今日はなかなかうまくいったな」と思える治療の直後に「全然よくなかった」とか「まったく変わっていない」というような非常にネガティブな感想を言われる、次の予約までの間に「こういうことをしてください」とお願いしたことをまったくしてもらえず「こういうことはしないでください」と注意を促していたことを行って悪化させて戻って来られてしまう、前回の治療で扱ったはずのテーマがまた同じような形で課題にあがってくる、あるいは何度も何度も同じ地点をグルグルと歩き回るようなルーピングが起こる…
この心理的逆転は、通常の意識のレベルにおいては気づくことができない。そのため実践者は心理的逆転のチェックとして、アプライド・キネシオロジーの手法である筋肉反射などを用いてその身体に働きかけ、その有無の確認を行う。その後に、主に身体に働きかけるアプローチでそれを解消しようというのである。
重要なポイントとしては、この心理的逆転について、キャラハンは純粋にエネルギー心理学の観点から見ていることである。フロイトやエリスについて言及はしているものの、背後にある心理的プロセスについては、そもそも想定がされていない。やや逆説的ではあるが、心理的逆転の発生は、少なくともオリジナルのキャラハンにおいてはであるが、心理的に説明されるものではないのである。そのため、心理的に説明される治療抵抗と、心理的逆転は決してイコールなものではないのである。
※この点についてはTwitterユーザーのコッテル(https://twitter.com/kottur_lover22?s=20)先生にご教授いただいた。この場を借りて感謝を示したいと思う。
トラウマと心理的逆転
しかし、心理的逆転の特定とその解消について見ると、少なくともその実践面においては身体への働きかけを強調した概念であるということは出来るだろう。そうした側面から、近年トラウマに対するアプローチとして注目されつつあるソマティック心理学と親和性が高いものとなる。そうした手法に熟達した治療者が、トラウマの影響によって生じた自己イメージや身体への否定的影響に働きかける際に、この心理的逆転の概念と修正を取り入れている。その結果、TFTに限らず、トラウマ・ケアを学ぶ際にこれに出会う機会は増えているのであろう。実際、とりわけ複雑性PTSDの人に心理的逆転のチェックを行うと、それが生じていることが非常に多いと述べられている(嶺, 2019)。
ただし、こうした心理的逆転の概念をトラウマ臨床の場面で使用しているのが、いずれも熟達した治療者であるということに留意する必要がある。筆者が最初にトラウマケアについて学んだ治療者に、心理的逆転の概念についてやや批判的な立場から質問したことがある。すると彼は「それはわかるが、そうとでも言わないと説明できないような現象があるのだ」と答えた。心理的逆転などを臨床的な工夫として取り入れているのは、十分にトレーニングと経験を積んだ治療者でさえ「これまでの治療経験はあっさりと吹き飛ばされてしまった」と語るような重症例における、”全き悪意”ともいうべき虐待者との格闘の上でたどり着いたものである、ということは留意しなくてはならないだろう。
それを端的に示すのが、「自己敗北性(self-defeat)パーソナリティ障害」概念についてである。これはDSM-3-TRの付録に収録された概念であるが「心理的逆転と密接に関連しているように見える」とキャラハンによって言及されたと嶺(2019)が述べている。確かに心理的逆転はこの自己敗北性パーソナリティ障害と似通ったようなものに見える。しかしこれは、一度は検討されたものの、診断基準への採用が見送られることになった概念である。その理由としては、この障害はマゾヒズムを念頭に置きながら作成されたものであるが(Millon, 2004)、その典型例がDV被害を受けながらもそこから逃れられない女性の姿であったからである。
これが診断名として収録されることは、こうした暴力被害から生じた問題を本人の問題とされる可能性があったし、あまつさえ被害者本人が望んでいると捉えられることがあり得たのである。こうした「政治的」理由から、正しくも単純な病理として虐待後の症状が捉えられることは避けられたのである。ハーマンは、『心的外傷と回復』の中で、このように述べている。
これまでのあまりに長い間、精神科医の意見は無情な世間の判断を反映したものでしかなかった。すなわち、被害者は虐待を「求めていた」というのである。かつてのマゾヒズム概念も最近の外傷嗜癖という定式も、要するに被害者は虐待の反復を求め、それによって満足を得ているといわんとするものである。そんなバカなことがあろうか。
一見自己破壊的に見える行動について、それを心理的逆転と呼び、あまつさえ本人が望んで行っているのだと解釈することは、二重の誤りである。しかしそれが「無情な世間の判断」であるという指摘も、きちんと臨床家は踏まえなくてはいけないし、自身の中にもそうした判断がないか自己批判しなくてはならない。
もう一つ重要な点は、この記事において指摘されているように、現実にも「心理的逆転」とされた事例の多くは単にセラピストがラポールが構築、問題の十分な理解、有意義に関わり、安全の提供といったものができていないのではないか、ということである。
※なお、この視点はTwitterユーザーの@jonnynovemberさんの一連のツイートで気づかせていただいたことであり、この場を借りて感謝を示したいと思う。
逆転とトラウマをめぐる諸概念①:ピエール・ジャネ
さて、述べてきたようにキャラハンは心理的逆転を単にエネルギーの流れというもので説明しており、それを心理学的に説明することをしていない。しかしそれがトラウマが背景にある人において頻出するというのは、どういうことであろうか。それはエネルギー心理学の観点から説明することが可能なものであるかもしれないが、その仕事は筆者の手にあまるものであるし、別の立場からもこれを検討しようという本記事の趣旨からも逸れてしまう。そこで、次にトラウマ臨床の中で心理的逆転と類似する概念を見ていくことを行いたい。
まず心理的逆転の概念に極めて近いものとして挙げられるのは、ピエール・ジャネによる「心理的貧困」という概念である。これはジャネにより1889年に出版された『心理学的自動症』の中で登場したものであり、心の統合力が低下していることを示す用語である(ジャネ, 2013)。ジャネは患者がこうした心理的貧困の状態にあることで、たやすく解離症状を呈すると説明したのである。この心理的貧困の状態を作り出すものとして、ジャネは現代でいえばトラウマ記憶にあたる固着観念というものを想定する。それ自体が生み出す精神的動揺と、そこに新たなトラウマ体験が加わることで、固着観念は精神にウィルスのように撒き散らされ、あらゆる形で反復して生じるようになるというのである。モロー・ド・トゥールの言葉を引用しながら、ジャネはこのように述べる。
固着観念は、あらゆる形で反復しながら根拠もなしに出現してくる。それは知性全体の深い根本的な変容の結果である。それを誤った考えと混同しているのは、心理学の大きな間違いであろう…(患者は)間違いを犯しているのではない。われわれとは違った知的領域で動いているのである。
後にジャネはこの理解を進めて、それを「経済論的心理学」としてまとめている(ジャネ, 1981)。ジャネは心や精神にある種の量的なエネルギーがあることを想定して、それを「心理的力」と呼んでいた。この心理的力は「心理的緊張」と呼ばれるもう一つの心の基本的機能の働きによって、統合された心の働きを生み出すものとした。ジャネは精神疾患を、この心理的力か心理的緊張か、そのいずれかの働きが低下して生じるものとして描いた。
先にあげた心理的貧困の概念は、心理的力というエネルギーが枯渇した状態として受け継がれている。エネルギーが貧窮した状態となると、活動性が低下し、社会的な活動をしなくなるという。そして最終的には「人間的破産」に至ると述べているのである。『心理学的自動症』では、心理的貧困の反対にジャネは強力な統合力を持つ天才を置き、通常の人間はこれと心理学的貧困であるヒステリーの状態とを揺れ動くような存在であると述べている。後に絶大な心理的力と高度な心理的緊張を併せ持つ人物を、経済論的メタファーを用いてジャネは「心理的億万長者」と呼んでいる。破産に向かう人を成功に向かわせるようエネルギーを高めて、また効率的に使用する方法を考えるというのがジャネの心理療法である(エレンベルガー, 1980)。
もう一つ大事なのは、ジャネはこの心理的力は、ある程度生理的な力、いわば体力と同一であるとみなしていたことである。そのためエネルギーの減少に対する治療的アプローチとして、まずエネルギーを増大させるために睡眠や栄養を取ることを勧め、そしてその節約として身体的異常がないかを精査する必要があると述べている。そこから対人関係の中にエネルギーを吸い取るような人物がいないか、また会社など職業生活でエネルギーが効率的に使えているのかを検討し、そこに対して治療者は教育的・指導的に関わるのである。
こうしてある程度患者がエネルギーを取り戻したところで、「精算」としてトラウマ記憶に取り組むことになる。後にジャネが重要視したのは、ある行為を最後までやり切ることによって生じる、精神的なエネルギーの増大の現象である。トラウマとなるような出来事においては、主体が望んだ行為が中断してそのまま取り残されているとジャネは考える。これが慢性的なエネルギーの消耗の原因となってしまっているのである。そのためそれを最後までやり切ることによって、心理的な負債の精算を成し遂げようというのである。
まずジャネの心理的貧困の概念とその発展としてある経済論的心理学における貧窮は、多くの点で心理的逆転と共通している。まずこれらは共に身体と繋がったエネルギーの存在を想定していることである。そして両者は共に建設的な極と破壊的な極を想定し、通常においては建設的なベクトルに向かうはずが破壊的なベクトルに向かうものとなっていることを問題としている。キャラハンは単にエネルギーの逆転と見たのであるが、ジャネはその大きな要因として下意識にある固着観念、すなわちトラウマ記憶とそれが繰り返されることによるエネルギーの持続的な消耗と捉えていた点で、よりトラウマの観点と近づく。ただその一方で、ジャネがその後に発展させた経済論的心理学においては、そうした固着観念よりも、むしろ日常的な生活習慣や対人関係の影響を重視していたことは注目に値する。これは心理的逆転が必ずしもトラウマに由来する概念とは限らない、という説明と関わるかもしれない。
また、ジャネは心理的貧困によって引き起こされる解離症やエネルギーの不足による精神衰弱の症状を、決して本人が意図や意思といった能動的なものが介在するものではないこと強調していたことに留意しなくてはならない。先に引用した箇所にもあるように、ジャネは患者が「誤った考え」を抱いているというような説明を拒否している。それらは「違った知的領域で」の活動の結果なのであり、それはまさに「自動症」として、本人にとっては受動的な経験として生じるものである。ジャネの解離の概念からは、マゾヒズムという解釈は生じ得ない。これはこの後述べる、フロイトの抑圧のシステムとは対照的である。
こうしたジャネのアイデアは、パット・オグデンやヴァン・デア・コークなど、現在のソマティック心理学に親和性のあるトラウマ治療者の源流となっている。また、先にも言及している嶺(2019)が用いているホログラフィートークの技法は、先に述べたジャネの方法論と多くの共通点を持つ。これらの治療者が心理的逆転の概念と親和性があることを考えれば、ジャネの中に心理的逆転の概念と近しいものを発見できるのは必然であると言える。
しかしながら、不幸なことにジャネの功績はこの後述べるフロイトの影に長い間埋もれ続けてしまっていたものである。それゆえに、ジャネから見る心理的逆転の視点は依然として馴染みがないものに留まるかもしれない。これをさらに馴染みのあるものとするためには、心理学と心理療法のスタンダード、フロイトから始まる道を辿る必要があるだろう。
逆転とトラウマをめぐる諸概念②:反復強迫と再演
フロイトの著作の中には、心理的逆転と近似の概念を多く発見することができる。とりわけトラウマ臨床と関わりがあるのは、「反復強迫」と「死の欲動」の概念である。既に述べたように、キャラハンは死の欲動は心理的逆転で説明できる、と述べている。
フロイトはその初期においてはヒステリーの病因としてはっきりと「早過ぎる性的体験」というものを据えたが、後にそれが現実のものか空想のものかの区別が困難であること、そして当時の男性社会の中で成功するために、これを撤回することになる(森, 2005:ハーマン, 1999)。そして結果として、フロイトは背後にトラウマ体験を想定しなくても性的発達の歪みを説明できる理論として、精神の内部における欲動−防衛の関係を中心に据えた精神分析の基礎理論を作り上げたのである。これはトラウマという概念が生まれて以来、一貫してそれが現実の外傷から心理的影響の重視へと進んでいった最終的な帰結である。しかしこのフロイトの転向は、現実に生じた被害の否認という過ちを長い間生じさせることとなり、それは批判される通りである。
しかし、第一次世界大戦という出来事が、フロイトを再びトラウマの問題に向き合わせることになる。戦争神経症の患者が襲われる外傷性悪夢やフラッシュバックを、従来の願望充足の視点では説明できなかったからである。フロイトは、外傷体験がこのように何度も立ち戻って侵入することを「反復強迫」と名付けた。これは快感を求める欲求という従来のフロイトの理論を逸脱したものであった。そしてフロイトはこれを推し進めて「死の本能」という概念に辿り着くのである。
(反復強迫に対して)フロイトは当初これを外傷体験を消化し乗り越えようとする方策と考えた。しかしこの説明では彼も満足しなかった。それでは再演の持つ、彼のいうところの「デーモン的」な質をどこか捉えそこなっている。というのは、反復強迫は意識の意向を無視し嘲笑し、実に頑強に抵抗するので、フロイトはこれが適応的な、生命肯定的なものであると説明するのをあきらめ、「死の本能」という概念をつくらざるを得なくなった。
死の本能の概念は精神分析の枠組みを超えて広がりを見せることはなかったが、一方で強迫反復の概念は「再演」としてトラウマ臨床の中で重要な視点として取り上げられることになる。これはまず、外傷経験が繰り返されることが統計的に明らかにされたということが大きい。重度のトラウマを被ることによって、他者に被害を与えること、再びトラウマ被害にあうこと、そして境界性パーソナリティ障害と診断される可能性が飛躍的に増加することが明らかにされたのである(コークら, 2001)。こうしたデータは、再演や強迫反復はトラウマ後に普遍的に生じるものであり、それは被害者が「誤った考え」を抱いているためなどではなく、それを症状として治療上で扱うことが必要であることを示している。
そして同時に重要なことは、強迫反復は「外傷性転移」として治療関係の中にも持ち込まれるということである(ハーマン,1999)。治療関係自体が、転移と逆転移という現象を通じて、トラウマ的出来事の再演の舞台となってしまうのである。この視点がトラウマ臨床の中に根づいたことは、フロイトの存在の一つの功績であると言えるだろう。
フロイトは反復強迫はトラウマを克服せんとするために生じるものではないかと考えた。フロイトは、ジャネとは対照的に自我の能動的な関わりを前提としていたために死の本能というアイデアを導入したが、ジャネに習ってそれが受動的に引き起こされるものと考えることも十分にできるだろう。近年の理論家たちが述べることをまとめると(ハーマン, 1999:コークら, 2001:白川, 2016:ウォーカー, 2023)、再演や反復は元はその行動はそのトラウマ場面を生存するために最も適したものであったが、そこで人間関係のパターンと否定的自己イメージが固定化されてしまったがために、それが自己利益にならない場面でも繰り返されてしまうことで生じると考えられている。
ウォーカー(2023)は、とりわけ幼年期の虐待によって作り上げる超自我を「内なる批判家」と呼ぶが、嶺(2019)はこれがまさに心理的逆転を生むものであると説明する。
時間の経過とともに、この恐れと悲しみと恥は、親による放棄のすべての責任が、その子ども自身、そして大人へと成長した本人自身にあるのだとする有毒な内的批判家を生み出し、いずれはその内的批判家がクライエント自身の最悪の敵となって、複雑性PTSDの奥深くに沈潜することになる。この有毒な恥辱感と内的批判家は成長したクライエントのなかに常に存在し、それによってクライエントは自分自身に「私は助けられない」「私を助ける者などいない」という絶望感を教育し続けるかもしれないし、親から受けたあらゆる罵倒の言葉を自分に言い続けるかもしれない。また、親の放棄や恥辱感から、「私は打ち捨てられるのが相応しい」「私は惨めでどうしようもない奴だ」「こんな私には惨めな人生が相応しい」「私は幸せになんかなれない」「私には不幸がお似合い」と教育し続け、誤解し、その間違った論理を深く納得してしまうのかもしれない。さらに、日常のちょっとした刺激が引き起こす「感情的フラッシュバック」によって再び過去の惨めな状況に退行させられるようなことがあると、その誤解はさらに上書きされたり、維持されたり、強化されていくようになる。つまりこれが「心理的逆転」である。
こうして見ると、心理的逆転は認知のレベルにおいては再演や強迫反復と極めて近いものとして捉えることができることがわかるだろう。これらフロイトまで遡ることができる概念と近しい一方で、先に見たように行動や身体に注目するとジャネのアプローチに接近するというのは、心理的逆転という概念の興味深いところであるように思う。トラウマ臨床の中にはさまざまな「逆転」の観点があり、そのためにそれは心理的逆転という概念と結びつけられると考えられる。
バウンダリーの問題としての逆転
最後に対人関係におけるバウンダリー(自我境界)の問題も逆転としても捉えることができるので、それについて述べたい。
バウンダリーとは精神的な領域において、自分がどこから始まってそして終わるのか、そして他者はどこから始まるのかを明確にするような心の働きである。健全なバウンダリーによって、私たちは社会の中で安全に他者と互恵的な関係を築くことができる。その結果、私たちは自分にとって良いものを内部に取り入れ、そして悪いものを外部に取り入れることができるのである(参考:人間関係における「境界線(バウンダリー)」の大切さ)。
その一方で「人が成長の過程で虐待を受けると、境界線の役割を逆転させ、悪いものを内側にとどめ、善いものを外側に閉め出してしまうことが」あるというのである(クラウド・タウンゼント, 2004)。われわれの文脈においては、ここで虐待というトラウマ的視点と、逆転という表現が注目に値するだろう。バウンダリーの問題は、トラウマ環境下においては逆転としても生じるのである。
それではこのようなバウンダリーの逆転はどのように生じるのか。『その後の不自由』を参照しながら述べてみたい(上岡・大嶋, 2010)。正常のバウンダリーが育つような家庭においては、子どもが真ん中に置かれ、その周囲を何重にもクッションで包むように、「父、母、きょうだい」→「祖父、祖母、イトコ」→「友達、近所の人、学校」といったように、それぞれの間に境界線があって配置されているという。これは「応援団を持つ」と表現されている。
しかしながら、逆転したバウンダリーが成立するような家庭においては、父のアルコール依存症や暴力、両親の不和などの緊張感があり、子どもは真ん中に位置することができず、結果として応援団を持つことができない。そこでは子どもは家族の緊張の緩和の役割を果たす存在となってしまう。本来は子どもとして自分の問題を誰かに助けてもらうべき時期に「私ががんばらなきゃ家族が壊れてしまう」「自分のせいだ」と家族の他のメンバーが背負うべき問題を担うことになってしまうのである。本来であれば、家族の不和は取り入れたくないものである。例えそれがあったとしても、健全なバウンダリーであればそれを自己の内部に取り込まなくて済む。しかしバウンダリーがないとそれを弾き返せずに侵入を許してしまう。そればかりか、そうした環境を生き残るために、自分自身を後回しにして積極的にそうした緊張感を自分の中に取り込もうとしてしまうのである。
こうして、バウンダリーの逆転が生じるのである。バウンダリーが逆転した状態では、自分の痛みや問題よりも、他人の痛みや問題を優先する。他の人のためであれば動けるのであるが、自分のためには動けない。自分の問題には責任をもたないけども、他人の問題には責任をとろうとする。そのため他人のSOSには敏感になって助けようとするのであるが、一方で自分からは決してSOSを出せない。重要なのは、このSOSが出せないということがその生存のために必要であった、ということである。
そうした孤立した状況において生じるのが、自傷やアルコール、あるいは対人関係におけるアディクションの問題である。バウンダリーの逆転は、アディクションに帰結すると捉えることができる。しかしこれは、大嶋(2019)が表したように、医学モデルで捉えることができないような「生き延びるためのアディクション」である。そうすることでしか生きられなかったものであり、本質的にそれは過酷な環境における生命維持的な側面を持つ。しかしそうした環境が終わると、それは「その後の不自由」として本人を苦しめることになる。それは対人関係の中で、良いものを排除し、悪いものを取り入れるというバウンダリー機能の逆転という形で現れる。こうなると回復が妨げられてしまうのである。
回復は、必ずしもアディクションを辞めたり、トラブルが起こらなくなったり、経済的自立をするようなものではない。それは「どこかで、誰かと、緩やかにつながる」ことにある(上岡・大嶋, 2010)。バウンダリーの感覚を取り戻すことによって、対人関係の中で良いものを取り入れ、悪いものを排出することで、その人の持っている自然な回復の力があらわれていくのである。
トラウマ臨床と逆転の概念
以上、心理的逆転を手がかりとして、トラウマ臨床を中心に様々な概念を追ってきた。心理的逆転は、もとはクライアントが自己利益に反する行動を行う説明として、エネルギーのレベルにおける二つの極を想定し、それが逆転した状態であると説明する概念であり、それ以上でもそれ以下でもないものであった。これが近年注目を浴びるソマティック心理学と身体への注目という点で親和性が高いため、トラウマ臨床をめぐる難しさを表現することに用いられるようになったのである。
しかしながら、これはトラウマ臨床の中に「逆転」ということが本質的に含まれていることに他ならないからであろう。それはフロイト、そしてジャネという、今日の精神医学・臨床心理学の始まりを作った人たちの中に類似の概念を辿ることが出来ることが、それを示していると思われる。その逆転はトラウマ的出来事を契機として、そうした環境に適応するために強化されることで成立し、将来の被害が繰り返されることにもつながる。そしてその逆転は、対人関係の中での自然回復が妨げ、使えるコーピングのパターンが限定するという、治療上の困難へと帰結してしまうものである。
このように、トラウマを抱える人たちに、それがオリジナルのキャラハンが述べる心理的逆転と同一であるかはともかく、ある種の「逆転」と表現できるものが存在し、そしてそれが治療上の課題として存在しているということは言えるだろう。ではこれにどう対処すればいいのか?
嶺(2019)は、心理的逆転を解消することは複雑性PTSDの治療において非常に重要であると述べ、その方法としては認知に働きかけるトップダウンのやり方と、身体的なアプローチを含むボトムアップのやり方があると述べている。キャラハンの述べる心理的逆転はおそらくは認知的アプローチでの解消は志向されないため、ここではより広範囲の逆転を指すものであると思われる。しかしながら、前者のトップダウンの方法はまさに逆転によってそれが阻まれるのではないだろうか。もしそれだけで上手くいくのであれば、それはクライアント側の要因が大きいだろう。
その一方で、後者のボトムアップの方法は、経験が十分でないセラピストには困難であり、セラピスト側の要因に大きく左右されてしまう。もちろんセラピストには、自らの技能を伸ばす責務がある。しかしそうはいっても、いきなり熟達する技法を用いることは難しいし、かえってクライアントを危険に晒す可能性もあるだろう。
逆転に対して、既存の心理療法の枠組みを踏襲しながら取り入れることが出来るアプローチは存在しないのだろうか?この問題については、いつか別の機会に触れることができれば幸いである。
参考文献
ウォーカー, P. 牧野有可理・池野良子(訳)(2023)複雑性PTSD 西和書店
大嶋栄子(2019)生き延びるためのアディクション 金剛出版
上岡陽江・大嶋栄子(2010)その後の不自由:「嵐」のあとを生きる人たち 医学書院
クラウド, H. & タウンゼント, J. (2004)境界線 地引網出版
コーク, B. A., マクファーレン, A. C., & ウェイゼス, L. 西澤哲(監訳)(2001)トラウマティック・ストレス:PTSD及びトラウマ反応の臨床と研究のすべて
白川美也子(2016)赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア ヒューマン・アスク・ケア
ジャネ, P. 松本雅彦(2013)心理学的自動症 みすず書房
ジャネ, P. 松本雅彦(1981)心理学的医学 みすず書房
ハーマン, J. L. 中井久夫(訳)(1995)心的外傷と回復<増補版> みすず書房
Callahan, R. J. (1991) Why do I eat when I’m not hungry? Doubleday
嶺輝子(2019)「楽になってはならない」という呪い:トラウマと心理的逆転 松本俊彦 「助けて」が言えない:SOSを出さない人に支援者は何ができるか 日本評論社
Millon, T., Grossman, S., Millon, C., Meagher, S., & Ramnath, R. (2004) Theodore, Personality Disorders in Modern Life. Wiley
森茂起(2005)トラウマの発見 講談社
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
