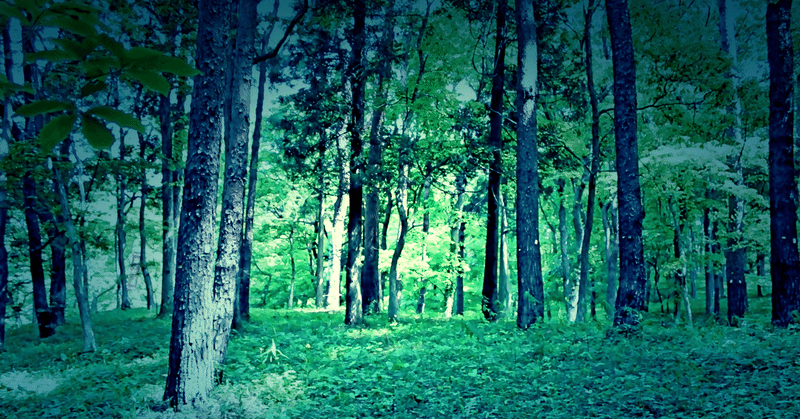
「なんで死んではいけないのか」と問われたとき①
はじめに
「なんで死んじゃダメなんですか?」
臨床場面で、こうした問いがセラピストに向けられたとき、どうしたらいいのか。教科書的には、なぜそうした問いが発せられたのか、その意図をクライアントに聞いていくことになる。こうした問いが発せられる背景を見ていく作業そのものに、治療的意味がある。
その一方で、生きる意味や、死んではいけない理由について説明し、説得させるということが目的になることはない。それは臨床心理学の領域を超えるからである。ひたすら傾聴に徹するのもいいだろう。それはそれなりの意味があると思う。
しかし、時としてその問いに向き合う必要があるのも、また臨床であると思う。リストカットやODを繰り返してフラフラで面接室に入ってきたり、身体治療を受けた後のベットサイドで話を聞いたり、そんな時にそれが訪れることがある。
説得するのが良い、というエビデンスはない。しかし、死生観を話すことで自殺のリスクが増えるというエビデンスもまた、ない。津川(2009)が述べるように、自殺を防ぐ一番の方法は、そのことについてセラピストとクライアントがオープンなコミュニケーションを継続していくことにある。
結局はケース・バイ・ケースではあるが、コミュニケーションの引き出しはなるべく多い方が良いと思う。そんなことを思いながらいろいろ機会あるごとに調べてきたし、また実際に臨床の中で話し合ってきた。それをここらで一回、忘備録としてまとめておきたい。
ちなみに僕は自殺予防の専門家でもなんでもない。ただのペーペーの臨床家として、短い経験から思うことを思うがままに書いているだけであるので、その点ご容赦してほしい。
内容的には前回の記事と同じく、ジェシー・べリング著、鈴木幸太郎訳『ヒトはなぜ自殺するのか:死に向かう心の科学』(化学同人、2021年)が元ネタの一つである。他にも、ジェニファー・マイケル・ヘクト著、月沢李歌子訳『自殺の思想史:抗って生きるために』(みすず書房、2022年)を参照しながら哲学者の議論を拾っているので、興味があればぜひこちらを読んで欲しい。
自殺の積極的意味はあるのか?
自殺は決してよいものではない。そんなことは皆わかっている。にもかかわらず、死に向かおうとするのである。
そのため、死に向かう人はちゃんと理由を持っている。いうならば、自分で自殺することを合理化しているのである。
この合理化には、うっすらと他者に対する優位性が含まれるときもある(もちろんなのだが、ないときもある)。つまり「誰も知らない、死んだ方がいいのだという事実」に気づいたということである。
しかし実は、さまざまな仕方で自殺を正当化する議論は存在しているのである。臨床場面でそれを紹介すると、クライアントは非常に真剣に聞いてくれる。
もちろん、これを以て自殺をすることを推奨する必要はないし、してはいけない。しかしこうした議論を知り、そしてそれに言及していくことで、治療者はフェアな議論の相手となることができる。クライアントの対価は、オープンなコミュニケーションの継続という、自殺予防のプロジェクトへの参加である。
という訳で、自殺にある積極的意味についてまずは扱う。
自分の人生を自分で選ぶこと
古代から、神話や伝承の中で英雄的な死というものは美化されてきた。ギリシャ神話では多くの神や英雄が激しい感情と共に死を選んできた。このテーマは、現代まで繰り返し語られている。しかしそれに危険性があることは、例えば特攻隊にまつわる神話と現実のギャップを見れば明らかである。
思想的な意味で、自殺に対する積極的意味を最初に力強く与えたのはソクラテスの死である。ソクラテスは若者を堕落した罪に問われて死刑を宣告された。牢番を買収して脱獄するように勧める弟子たちに対して「単に生きるのではなく、よく生きる」と言い自死を選んだソクラテスは、死をも選びうる人間理性の偉大さを示す永遠のシンボルとなったのである。
これは、自ら死を選ぶという作用の中に、一種の積極的要素が含まれていることを示すものである。それは自分の人生を自分で選ぶという、能動性である。私たちは普段、こうした能動性が脅かされる経験をすることは少ないだろうし、それがあったとしても別の方法(例えば仕事を変えるとか転居をするとか)で回復しようとする。
しかしどうしようもない不幸な状況やうつ症状の中では、自死だけがそうした能動性を取り戻す方法になり得る。とりわけ、焦燥感が重なる抑うつにおいて自殺リスクが高まるのは、そうした理由からである。
ストア派は、直接的にそうしたソクラテスの思想を受け継いだ。ストア派の「自殺のすすめ」は、生を肯定するために死をも肯定することを要請するものである。
現実のストアの実践者は簡単に死を選ぶことは少なかったようだが、ストア派の人間理性への(過大)評価からそうした結論が導かれたということは、その系譜にある認知行動療法の治療家は心に留めておくと良いかもしれない。抑うつ状態においては、理性を自殺によって生じる負の側面を理解するのではなく、正の側面を肯定する方向へと使用してしまうかもしれないからである。
その後西洋では、主に自殺をキリスト教が禁じた反動として、例えばディビット・ヒュームなど、宗教的権威に対する人間の自由意志の重要性を説く哲学者によってたびたび自殺が肯定的に語られることがあった。
そして、こうした伝統は西洋だけではない。日本の武士による切腹も、死のタイミングすら自己決定するという、自律性の究極の表現であったという。その背景には名誉を重んずる個人主義という、武士の特殊なメンタリティが存在したと指摘されているが、現代社会でも承認欲求という言葉で同質的なものを見出すことができるかもしれない。
現実の臨床場面でも、自殺に向かう行動の中に「自ら選んだ」というポジティブな要素を見出したという語りはよく聞かれる。抑うつ状態における学習性無力感と視野狭窄の中で、それが魅力的に映ることはなんら不思議なことではないと思う。他にも、いつでも死ねるという選択があるということで、能動的な感覚を持つことができるという話もよく聞く。現実のリスクの評価とこうした積極的側面のバランスを見極めることが、臨床場面ではときに必要になる。
自殺が適応的になる時
自殺は生存本能に反する行為である。動物は自傷行為はするが、デュルケーム的な「自殺」の定義に当てはまるような行為はすることはない。よく知られているレミングの集団自殺のエピソードは、神話と映画プロデューサーの演出によって作られたものである。フロイトが反復強迫を説明するために持ち出した「死の本能」の概念も、面白いアイデアではあるが現代的なトラウマ臨床ではあまり採用はされないだろう(※)。
しかし、生物の本能は自らの個体の生命維持だけでなく、遺伝子を残すという点においても働く。この後者の機能が働く時、すなわち自らの生命を超えたものに利するように動く時、前者の機能である生命維持が損なわれることはあり得るのである。
わずかな例外を除き、ほとんど全ての文化において自殺は観察されるが、その中で重要な位置を占めるタイプの自殺は、それが名誉や恥に関わるものである。ある人物が重要な文化的タブーを犯した時、その人はスティグマ(汚名)を持つことになる。そしてスティグマは、不治の感染症のように、周囲にいる人物を汚染することになる。そうした時、べリングが述べるように、自殺は自分の血縁集団から「自分を駆除」することによって、自分の近似の遺伝子を残すためのベストの行動となりかねないのである。日本における切腹はさらにこうした面が強調されており、若年で見事に切腹した親族が取り立てられるということすらあった。
もっとも、べリングが続けるように、こうした行動は現代の社会においては十分にそれに見合う成果をもたらすものではないと思われる。しかしながら、我々の心にはモジュールとして「こんな状況であれば、私が死んだ方が、みんな幸せになる」というものが存在している可能性は十分にある。そしてそのスイッチは、名誉や恥といったものに関連して、容易に押されてしまうのである。
中立的視点から自殺を見る:症状と手段
次に積極的とは言えないまでも、中立的な視点から自殺という行為を見ていこう。これは医療者や対人支援職としては取り扱いやすい視点である。中立的視点から「死にたい」という気持ちを見るのであれば、それを否定することなく扱うことができるからである。
まずは症状としての自殺を取り上げ、そして次に手段としての自殺を取り上げる。
症状としての自殺
前の記事の冒頭で述べたような「あなたは死にたいと思っているのですね。それはうつ病の症状からきているものであって、本来のあなたはまた別の考え方をしているはずです。今はお薬をのんで、しっかりと休んでください。どうしても我慢できないときは、入院も検討しましょう。さて、次の通院まで死なない約束はできますか?」というような対応は、希死念慮を症状として扱うものである。ここではもう少しだけ、この視点について述べる。
一つの有力なアイデアとして、自殺で死ぬだれもが精神疾患だということである。これに近しい考えは、いわゆる電通事件以降に裁判所が「相当因果関係」として採用している。つまり、自殺という結果が生じたということは、生前うつ病があったということが認定される、ということである。
いわば「結果論的診断」ともいうべき、自殺という結果から全てをうつ病を診断するということの精神医学的な妥当性については、村松(2014)が詳細に検討している通り、やや粗雑にすぎるだろう。
しかしそれがうつ病でないとしたとしても、前の記事で述べたように、自殺の既遂は一種の特殊な精神状態によってなされるということは確かであるように思われる。ストア的な理性に基づく自殺というものは、ほとんど生じ得ない。これはストア派の哲学者たちでさえも、セネカのように自死を強要された場合がほとんである、ということによって示されている。
このことは、自死によって残された家族にとって重要なことである。決してあなたをないがしろにしたから、大切でなかったから、その人は死を選んだのではないのである。むしろ先に述べたように、自分が居なくなることが良いことだ、と思ってすらいたかもしれない。本人にも、残された家族にも、責任がないということを説明するのは大切である。
手段としての自殺
忘れてはいけないポイントは、自殺は手段であるということである。死ぬことそのものを目的に行われる自殺は(滅多に)ない。それは手段として行われるのである。では自殺の目的とは何か?これには明示的なものと、隠されたものがある。
まず明示的なものである。それが自殺が、苦痛を回避するという目的の元で行われる、ということである。この説明については、ほとんど本人も納得してくれるものである。しかし自殺は、この目的に対して、あまりいい手段とは言うことができないものである。
まずあげられるのは、せっかくそれによって平穏を得たとしても、死んでしまってはその利益を得ることはできないことである。ヘクト(2022)はモンテーニュの著書を引用して「死という代償を支払って、安心や、苦痛や苦しみの不在、現世における不幸からの脱去を買い取っても、われわれになんの幸福ももたらしはしない。戦争を避けても、平和を享受できなれば詮なきこと…というしかない」と、このことを説明している。
次にあげられるのは、取り返しがつかないことである。人生というのはあまりにも不確定なものである。誰がこの3.11を、このコロナ禍を想定できただろうか?12年前にアメリカの砂漠の真ん中の街で薄いビールと水タバコに溺れながら「人生もう終わった」と感じていた僕に、12年後は心理職として働いているよ、と言っても信じなかっただろう。自殺という取り返しのつかない手段で断ち切ってしまうには、あまりにも人生は予測ができない。同じくヘクトが述べるように、『ロミオとジュリエット』や『ウェストサイドストーリー』といった悲劇は、自殺の手段としてのそうした弱点が出てしまったものである。
そして自殺には、もう一つ隠された目的がある。それは自分が死ぬほど困っているということを、周囲に伝えるということであり、そして自分の命を賭け金として状況を変えようとすることである。
この手段としての自殺(あるいは自殺企図、ほのめかし)というのは、効果的すぎるという点が弱点である。今まで困った、辛いと言っても「もっと頑張れ」「我慢しなさい」としか言われてこなかったのに、死にたいといった途端に周囲が大騒ぎするのである。そうであるなら、どんどんとそちらに吸い寄せられていっても不思議はないだろう。
べリング(2021)もまた、進化論に基づきこうした戦略が有効であることを説明している。ただ同時に強調するのは、その人が変化を起こすために「操作的」戦術を用いるとしても、自分の思い通りにするために意識的に戦略を立てているのではない、ということである。「彼らの苦痛は本物である…死にたいけど救われたいというこの両面性こそが、自殺する人の絶望を強めている」のである。
そのため、周囲が隠されたこの目的だけ取り上げることは、悪手であると言える。そこで筆者は自殺企図をした人には、ベットサイドでは次のような声かけをする。
「今まで誰にも言えない苦しい思いを抱えて頑張ってきて、それでこれしかないと思って、今回こうしたこと(自殺企図)をされたのですよね。だけども、自殺というのはあまりいい手段とは言えないと僕は思うのです(理由を説明する)。でも、一つだけよかったことがあります。それはこうして、あなたが本当に苦しくて、困っていて、なんとかしたいと思っていることが皆に伝わったということです・・・せっかくの機会ですから、別の手段がないか、もう一度検討しませんか?今度はわれわれも一緒に、考えますから」
ここまで、自殺の積極的側面からはじめ、そして中立的視点からそれについて扱う方法について見てきた。次の記事では、もうちょっと積極的な立場から自殺に対する反対を述べていきたい。それは「生きる意味」についての問いに答える、ということでもある。これもまた、自殺の誘惑があるクライアントを説得しようというものよりも、オープンなコミュニケーションを継続するための材料として考えていただければ幸いである。
※フロイトの死の本能については、現在(23年7月27日)では少し見方が変わっている(参考記事)。人格の全体性を保った人間が、単なる物体としてのヒトへと還元されていく時、そこに強力な死へのドライブが働くことを臨床の中で気づいたのである。強迫反復やシビアな環境の中で生きるために、人格の全体性を放棄し、解離した単なる物体であることを選択せざるを得ない人はいるが、そこで働くものは確かに「タナトス」と言い得るかもしれない。
続き:次の記事
参考文献
ジェシー・べリング、鈴木幸太郎訳(2021)ヒトはなぜ自殺するのか:死に向かう心の科学 化学同人
ジェニファー・マイケル・ヘクト、月沢李歌子(2022)自殺の思想史:抗って生きるために みすず書房
村松太郎(2014)「うつ」は病気か甘えか。:今どきの「うつ」を読み解くミステリ 幻冬舎
津川律子(2009)精神科臨床における心理アセスメント入門 金剛出版
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
