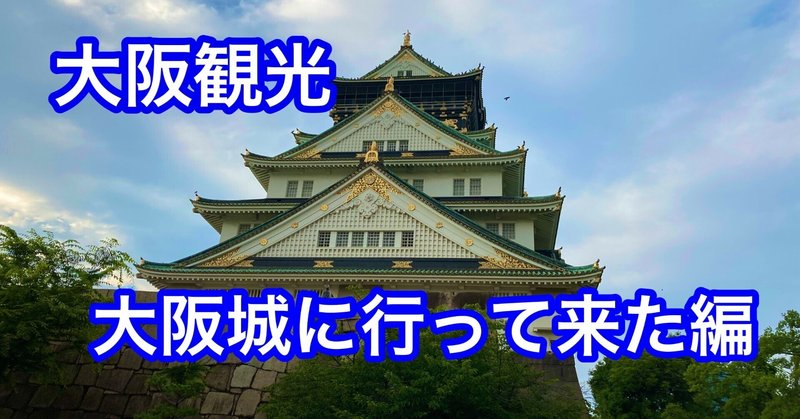
【大阪観光】 #1 〜 大阪城に行ってきた編(2023年6月)
こんにちは♪
北海道民のオジロワシ🦅です。
家族旅行で久しぶりに大阪に行きましたが、
今まで行ったことのない「大阪城」は、ぜひ一度は見てみたい🏯。
北海道にはお城は松前城しかないですからね。
江戸城も今は石垣だけなので、本格的なお城を見るのは初めてです😸
以下、訪問ログです💁🏻

大坂の中心地に再現された歴史舞台
「大阪状」といえば、豊臣秀吉が築いたお城として有名ですが、
実は様々な歴史を持っている城です。
エピソード.0:石山本願寺の時代
時は戦国、「応仁の乱」から30年後の明応5年(1496年)。
浄土真宗の蓮如上人が、坊舎をこの地に築いたのが大阪城の始まりです。
その後、この坊舎は、浄土真宗の拠点「石山本願寺」となり、たくさんの商人や町人が集まる寺内町として発展しますが、
天下統一を目指す織田信長との抗争の結果、天正8年(1580年)、「石山本願寺」は焼失してしまいます。
エピソード.1:豊臣の時代【初代】
その2年後の天正10年(1582年)に織田信長は「本能寺の変」で討たれますが、翌天正11年(1583年)から、政治の主導権を握った羽柴秀吉が天下統一を目指して、石山本願寺があった地に、安土城を越える壮大な大坂城の築城を開始します。
羽柴秀吉が関白になった天正13年(1585年)、
大坂城の天守閣が完成。
更に秀吉は、天正14年(1586年)に豊臣という新しい姓を天皇から賜り、
天正18年(1590年)、名実ともに天下を統一し、
大坂城が豊臣政権のシンボルとなります。
その12年後、慶長3年(1598年)に秀吉が62歳で亡くなった後、「関ヶ原の戦い」(1600年)、「大坂冬の陣」(1614年)を経て、慶長20年/元和元年(1615年)の「大坂夏の陣」で、豊臣氏は滅亡。大坂城も落城します。
この時、徳川幕府によって、豊臣の大坂城は跡形もなく埋め立てられてしまいます。
※余談ながら、
徳川家康が征夷大将軍に任じられるのは、「関ヶ原の戦い」の2年後。慶長8年(1602年)のことです。
エピソード.2:徳川の時代【2代目】
「大坂夏の陣」から5年後の元和6年(1620年)、2代将軍・徳川秀忠の命により、大坂城の再築工事が始まります。
10年の歳月をかけて2代目の大坂城は完成しますが、それから約40年後、4代将軍・家綱の時代に、天守が落雷によって焼失してしまいます。
以来、天守がないまま、徳川が作った大坂城は、幕府の西日本支配の拠点として続きますが
1868年に起こった明治維新の動乱で、多くの建物が焼失してしまいます。
エピソード.3:昭和の天守閣復興【3代目】
明治以後、大阪城は陸軍用地として使われます。
その後、昭和6年(1931年)、当時の大坂市長であった関一氏の提案で大阪城の天守閣が鉄骨鉄筋コンクリートで復興されます。
寛文5年(1665年)に天守が失われてから266年の時を経て、大阪城の天守閣は再びその姿を現したという訳です。
知っているようで、意外に知らない、大阪城。
まさか、三代目だったとは、驚きですね!😅
▶ アクセス
大阪城の住所は
大阪府大阪市中央区大阪城1-1。
住所そのものが「大阪城」なんですね😅

大阪城は広いので、東西南北の角に駅があります。
南西側が「谷町四丁目駅」、南東が「森ノ宮駅」、北東が「大阪城公園駅」。
「谷町四丁目駅」側の「大手門」を通って「大阪城公園駅」の「青屋門」へ向ける3kmのルートがおすすめだそうです。
なお、営業時間は9時〜17時(天守閣への入館は16時半まで)となっています。
我々一家は、ホテルのある弁天町から真っ直ぐ行ける地下鉄・中央線で向かいます。
15分程で「谷町四丁目駅」に到着。

東改札を出て、9号出口から地上へ。
目の前に、NHK大阪放送局と大阪歴史博物館がドドンと現れます。

この建物の先、駅から徒歩10分弱で、大阪城公園の入口に到着します。

大阪城公園を散策する
ここから大阪城の天守閣まで結構距離があります。
ブラブラと散策しながら、天守閣を目指します。
(案内板の記述を転記しておきます。)
【大手前の馬場】

大阪城の正面を大手口といい、大手前と呼ばれるその手前一帯は江戸時代「馬場」と呼ばれていた。
範囲は上町筋の西、今の大阪府警察本部や大阪府庁の敷地付近にも及んだ。
馬場は小高い丘のある芝生の広場で、大阪城在番の舞台が交替する際の駐留場所として使われたほか、町人に開放され憩いな場所となっていた。
幕末には軍事的緊張が高まり、ここに土塁が築かれたり兵舎が建てられたりしている。
明治維新を経て大正13年(1924)、大阪市は陸軍からこの付近一帯を借り受けて大手前公園を開設した。
これが現在の大阪城公園の出発点である。

【大手門(重要文化財)】

城の正面を大手(追手)といい、その入口を大手口(追手口)、設けられた門を大手門(追手門)とよぶ。
現存する大阪城の大手門は寛永5年(1628)、徳川幕府による大阪城再築工事のさいに創建された。
正面左右の親柱の間に屋根を乗せ、親柱それぞれの背後に立つ控柱との間にも屋根を乗せた高麗門形式である。
屋根は本瓦葺で、扉や親柱を黒塗総鉄板張とする。
開口部の幅は約5.5メートル、高さは約7.1メートル。
親柱・控柱の下部はその後の腐食により根継がほどこされているが、中でも正面右側の控柱の継手は、一見不可能にしか見えない技法が駆使されている。
門の左右に接続する大手門北方塀・大手門南方塀も重要文化財に指定されている。
【多聞櫓(重要文化財)】

大手口枡形の石垣の上に建つ櫓で、大門の上をまたぐ渡櫓と、その右側に直角に折れて接続する続櫓によって構成される。
徳川幕府による大阪城再築工事により寛永5年(1628)に創建されたが、天明3年(1783)の落雷によって全焼し、嘉永元年(1848)に再建された。
土塁や石垣上に築かれた長屋状の建物を一般に多聞(多門)と呼ぶが、その名称は戦国時代の武将松永久秀が大和国(今の奈良県)の多聞城でこうした形式の櫓を初めて築いたことに由来するといわれる。
現存する多聞櫓の中でもこの多聞櫓は最大規模で、高さは約14.7メートル、建築総面積は約710.25平方メートルある。
渡櫓内部には70畳敷を最大とする部屋が4室、続櫓内部には廊下のほか9畳・12畳・15畳の部屋が計6室あって多数の兵や武器をたくわえることができ、枡形の内側に多くの窓があり、また大門をくぐる敵を真上から攻撃する「槍落し」の装置が設けられるなど、高い防御能力を備えている。
大阪城の二の丸には京橋口・玉造口にも多聞櫓があったが、現存するのはここだけである。
【大手口枡形の巨石】

枡形とは城の主要な出入口に設けられた四角い区域にことで、敵の進入を食い止める役割を果たした。築城技術の進歩にともなって強固な石垣造りのものがあらわれ、大阪城の大手口枡形では城の威容を誇示する巨石が数多く使用されている。大手門をくぐって正面に位置する大手見付石は、表面積が約29畳敷(49.98平方メートル)で城内第4位、左の大手二番石は約23畳敷(37.90平方メートル)で第5位、右の大手三番石は約22畳敷(35.82平方メートル)で第8位、いずれも採石地は瀬戸内海産の小豆島と推測されている。
現存する大阪城の遺構は豊臣時代のものではなく、元和6年(1620)から約10年にわたった徳川幕府再築工事によるもので、石垣は将軍の命令を受けた諸大名が分担して築いた。
この個所は当初肥後熊本藩主加藤忠広が築き、のちの築後久留米藩主有馬豊氏が改築した。
【千貫櫓(重要文化財)】

大阪城の大手口を守る重要な隅櫓である。
西側と南側は塀に面し、大手門に向かう敵を側面から攻撃することができた。
創建は徳川幕府による大阪城再築工事が開始された元和6年(1620)で、戦後の解体修理工事の際、墨書で「元和六年九月十三日御柱立つ」と上棟式の日を記した部材が見つかった。
二の丸北西に現存する乾櫓と同様に大阪城最古の建造物で、いずれも工事責任者は、茶人としても有名な小堀遠州である。
具体的な場所や規模は不明ながら、前身となる豊臣秀吉築造の大阪城にも千貫櫓はあり、さらにそれよりも前、織田信長が大阪を領していたころにも千貫櫓はあった。
名称の由来に関しては、織田信長がこの地にあった大坂(石山)本願寺を攻めた際、一つの隅櫓からの横矢に悩まされ、「千貫文の銭を出しても奪い取りたい櫓だ」と兵士たちの間で噂されたという逸話が残っている。
面積は1階が約217.26平方メートル、2階が約162.95平方メートル、高さは約13.5メートルである。






【桜門枡形の巨石】

桜門の内側には、本丸の正面入口を守るため、石垣で四角く囲まれた「枡形」とよばれる区画が設けられ、上部に多聞櫓が建てられた。
この枡形は徳川幕府による大阪城再築工事の第2期工事が始まった寛永元年(1624)、備前岡山藩主池田忠雄の担当によって築かれ、石材は備前(岡山県)産の花崗岩が用いられている。
正面の石は蛸石とよばれる城内第1位の巨石で、表面積がおよそ36畳敷(59.43平方メートル)、重量は約108トンと推定される。
向かって左手の巨石は振袖石(袖石)とよばれ、表面積はおよそ33畳敷(53.85平方メートル)で、城内第3位である。
なお、上部の多聞櫓は慶応4年(=明治元年、1868)、明治維新の大火で消失した。
【旧第四師団司令部庁舎】

現在の大阪城天守閣と同じ昭和6年(1931)、陸軍第四師団司令部の庁舎として建設された。鉄筋コンクリート造で、ヨーロッパの城を参考とし、左右対称の重厚な外観をあらわす。
昭和20年の第二次世界大戦集結時には第十五方面軍司令部および中部軍管区司令部の庁舎だった。連合国軍による接収のあと、昭和23年から警察(大阪市警察局、大阪市警視庁、大阪市警察、大阪府警察)の庁舎として、昭和35年から平成13年(2001)までは大阪市立博物館として使われた。
平成29年に耐震補強ならびに外装・内装の修復や改装工事が完了し、現在は来訪者向けに土産物や飲食、大阪城公園内の史跡に関する情報などを提供する「ミライザ大阪城」として利用されている。
大阪城天守閣へ










大阪城の中には、天守閣を飾る「鯱瓦」と「伏虎」の原寸大のレプリカが展示されています。
豊臣秀吉が築いた大坂城は「三国無双の城」と讃えられるほどの豪壮な城郭だったそう。
秀吉は難攻不落の城を築くと同時に、政治・経済・軍事・文化の中心地となる大阪の町作りも行います。
これこそが、織田信長から受け継いだ天下統一の構想を、豊臣秀吉が実現した証とされます。
大阪城公園公式サイト
↓
まとめ
大阪城公園は、予想以上に広かったですね。
我々家族は、2時間ほどの滞在でしたが、3~4時間かけてゆっくり散策すると良いかもしれません。
大阪城を見に行く際の参考になれば幸いですw
最後までお付き合いいただき
ありがとうございました
m(_ _)m
(2023年6月15日訪問)
(2023年8月18日投稿)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
