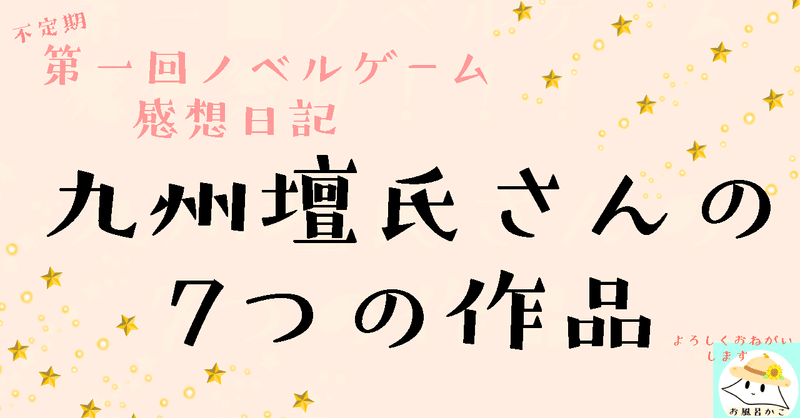
【不定期】第一回ノベルゲーム感想日記 九州壇氏さんの7つの作品
【始めの挨拶】
今回の主役は、九州壇氏さんの7つのノベルゲーム。粒ぞろいのすてきな作品たちです。九州壇氏さん、ありがとうございます!
【感想日記の説明】
私が気に入ったゲームの感想を「勝手に」書くだけ。そのため、問題等があった場合この記事は削除・修正いたします。
紹介とリンクの下に感想があります。感想は全てネタバレを含みますので、読まれる場合はプレイ後を強く推奨します。作品はゲームの公開順に上から並べています。
それでは、始まります。
僕の愛する三匹
【紹介】
短編。ここの紹介文を読むよりも、やったほうがはやい。短いながらも、内容やメッセージ性は十分ある。九州壇氏さんの作品を読んでみたいが、どの作品から読もうかと迷っている人間におすすめ。創作をしている、もしくはしていた人間だとなおよい。
【感想】
私は最近まで、のんびりしたまだら模様のうさぎと、頻繁に口を動かす大きめの黒カラスと一緒に創作をしていました。
みなさんは自作を作っていたとき、どんな仲間たちと一緒に暮らしていましたか?
私が最近公開したのは上記の小さめの動物たちなので、主人公の人間と同じく、そろそろ大きめの動物と出会いたいですね。今後も、愉快な仲間たちと一緒に、いろいろ言い合いながらノベルゲームをつくっていきたいなと思いました。
オリジナリティを出すのは難しいと思います。私の文章も、特徴とかありませんしね。でも、私はまだらうさぎと大黒カラスで物語を描いた。それでいいんですよね。
作中の動物たちでは、きつつき筋トレペンギンがお気に入りです。ワシホウホウフクロウもすました黒猫もにくめない、いい子たちです。
作品が出来上がったときや、物語を描き終わったときって、うれしいし達成感もあるんですけど、やっぱりちょっとさみしいですよね。自分がたくさんの時間をかけて生み出した子たちの物語を閉じるのは、燃え盛っていた火がだんだんと小さくなっていく様を、ただ静かに見届けている気持ちになります。そして最後には「ありがとね」と水をかけて終わらせてあげる。それは「シュウ」という水が蒸発する乾いた音の返事となり、物語は出来上がる。そんな少しのさみしさも私は好きです。
創作への思い、楽しさ、葛藤、喜び、やりがいなど、私の中にあるいろいろな感情を刺激してきた作品です。
私は、文章を書くことが好きです。物語を描くことはもっと好きです!
吟遊詩人
【紹介】
やさしい勤勉な姉貴とやさしいラッパーの兄貴が出る。主人公は小説を書く人間。兄貴のラップ口調がクセになる(かも)。気軽に読めるにも関わらず、読後の爽やかさがたまらない。迷ったことがある人間におすすめ。自分を見つけた人間だとなおよい(と思う)。
【感想】
まずは姉貴について
この姉貴、主人公の執筆に対して、自慰筆なんて呼び方をするのですが、きっちり毎回読んでくれるんですよね。主人公も、姉貴が勉強をがんばっていると知っているのにも関わらず、毎回持っていきます。姉貴は読書家らしいですが、そうだとしても毎回ちゃんと読んでくれるのは、姉貴の家族思いな面がよく出ていると思いました。毒は吐きますが、それは進歩がない主人公へのアドバイスです。自慰筆という言葉は、ただ単にけなしたいのではなく、主人公の小説に対して、真摯に向き合ってくれていることを示しています。また、姉貴の生き方は芯が通っていますね。死にそうな様子で帰ってきても、夢を語るときだけは表情が輝くのは、それだけ本気で取り組んでいるということですよね。
また、勉強勉強と言うのも、やはり主人公を思ってのことですよね。自慰筆をするくらいなら、勉強した方がいいと教えてくれているのだと思います。そこには、自慰筆の無価値さに気付いてもらうという側面も、含まれているのかなと思いました。姉貴は自慰筆のためにがんばっている主人公をみていられないのだと思います。書くのであれば、執筆をしてほしいのだと思います。私はこのやさしい姉貴好きですね。なんとなくですが、すごくモデルになった人がいそうなキャラクターだなと思いました。
次は兄貴について
兄貴のブレなさは目を見張るものがありますね。まさか病院でもあの口調を崩さないとは思いませんでした。しかしそれも理由あってのこと。一度きりの人生を楽しむという兄貴の考えも、姉貴と同じく芯の通ったものです。主人公のことを兄貴なりに考えて心配する様や、姉貴のお見舞いに行こうとさそう描写、帰ってこない主人公に電話をかけまくるところから、楽しんで生きるという考えの中には、家族にも楽しくいてほしいという思いが含まれているのでしょうね。兄貴も兄貴でやさしい人間ですよね。
それでいて、自分はブレない。自分なりのやり方で、主人公を励まそうとする。私はこのラッパー兄貴も好きですね。
ヨウ、ヨウ! でも室内では帽子とサングラスくらいとれよ、ヨウ!
最後に主人公について
優秀な姉貴に認めてもらいたい。そういう動機は、けっこうあるものですよね。厳しいけれど、ほんとうはすごくやさしい、優秀な姉貴に認めてもらえたら、自分にも価値が見出されるのだと思いたいですよね。比較してしまうのもよくあることです。そこにこだわっているのが、弟らしいなと思いました。そして、姉貴にも兄貴にもすごく愛されていますね。やさしい姉貴とやさしい兄貴に甘えている部分もちゃんとがあるのが、よいなと思いました。
そして、ありのままの自分で描いた「そんな、くだらない物語」こそ、自分にとっては自慰筆であり、それを読む人にとっては執筆になるんですよね(と私は思いました)。
「姉貴にも兄貴にもなれない僕には、これが一番だ」
このシーンが特に好きです。共感の嵐によって舞い上がった言の葉ひとつひとつが、私に波状攻撃をしかけてきました。
また、医学書のシーンでだけ「雪ねえ」という呼び方が出てくるところも、よかったです。姉貴、雪ねえとただ単に呼び方が違うだけなのに、主人公がどれだけ姉貴を支えにしていたかが、伝わってきます。この後、自分の書いていた小説のような行動に走ってしまうのも、人間らしいですね。主人公にとっては、荒れるとはこういうことで、それを止めていてくれていた、受け止めてくれていた姉貴がいなくなると、それが現実のものになるという描写も、今作でのお気に入りポイントです。
最後の車内のシーンもよかったです。清々しい終わり方でした! 主人公の精神が表れている。吟遊詩人とはこういうことか、とわかるシーンです。紹介にも書きましたが、ほんとうに読後のさわやかさが心地よかったです。
(余談。どうでもいい、書く価値など塵ほどもない情報を書きますが、私にも一人ですが上がいます。なのでこの作品は、他の作品よりも少しだけ共感できる部分が多かったと思います)
年末年始の恋模様
【紹介】
登場人物はみな受験生。主人公は高野みやび、親友に美香、幼なじみに山本マサル。タイトル通り年末年始の恋を書いた作品。会話のキレがよい。恋煩いをしたことがある人間におすすめ。恋愛の経験はなくても読めるが、あればより心情が読める(と思う)。
【感想】
マサルくん! なにやってるんだ! みやびちゃんがどれだけ泣いたと思ってるんだ! とはいえ、泣いたのはマサルくんも一緒なのでしょうね。似たもの同士ですから。途中までは、うまくいかないよね、などと思って共感していたのですが、見事に裏切られてしまいました。マサルくんの態度がおかしいなとは思っていたのですが、やっぱりそういうことだったんですね。でもやはり、幸せな終わり方をする物語は後味がいいですね。あのままみやびちゃんが強く生きるという話でも、それはそれでよかったとは思いますが、もしこういう結末があるなら、こちらの方が私はうれしいです。それにしてもマサルくんは誰にそそのかされたのですかね。先輩? は多分関係ない人物だと思うので、阿部くんでしょうか。でも阿部くんはそんなことしなさそうなので、別の登場していない誰かでしょうか。あるいは雑誌とかテレビでみたものを友達と話していて、それを素直に信じてしまったとかですかね。何かは分かりませんが、そそのかされてしまうほど素直なのも考えものですね。あと、ともちゃんはすごいですね。この二人ではともちゃんに隠し事など絶対にできませんね。
他には美香ちゃんの存在が大きかったです。美香ちゃんのように、いつも支えてくれる人っていますよね。何かそんな助けられるようなことしたかな、とも思うのですが、こういう人は自分から言おうとしない傾向にあるのでわからない。でもなんとなく、自分にとっては些細なことだったとしても、相手にとってそうしたくなる、大事な何かを気づかずにしているんでしょうね。そういうことを大事にしてくれる人は大切です。素の自分のよさを、大事にしてくれている人ですから。とは言っても、仲良くなることに理由はいりませんし、親友なんてものは、知らないうちになっているものだと思います。でもみやびちゃんに、美香ちゃんという存在がいてくれたことは、やはり大きいと思いました。マサルくんとの恋だけではなく、美香ちゃんとの友情も書かれているのが、いいと思いました。
みやびちゃんとマサルくんには二人ともちゃんと受かって、一緒の大学に行って、たまには喧嘩しながらも、末永く隣を歩く関係でいてほしいですね。嘘ついて泣いて、嘘ついて泣かせた分、一緒に笑って、一緒に笑わせて、仲良くいてください。
(余談。序盤にあったみやびちゃんの「能天気」というセリフに対してマサルくんが言った「ちなみに今日は、いい天気」というのにやられました。笑ってしまった。ジンジャーエールなどもそうですが、このセンスのよさは、私としてはちょっと悔しい……!)
乙女心と夏の空
【紹介】
長編。大学テニスが出てくる。試合の描写はなかなか熱い。そしてなにより、幼馴染の関係性がよい。読み応えもバッチリ。終わりもさわやか。心の機微に敏感であったり、いろいろなことを考える人間におすすめ。人をよく観察する人間だとなおよい。
【感想】
うーん、よかった!! 長編作品ならではの味が満載でした。特に慎ちゃんが眠ったままの日常というものを長く描写することで、四章以降がより際立っていました。いや、ほんとうに良い! たのしかった!
武くんについて
ここまで読んでいただいている方には、なんとなくの傾向でわかると思いますけど、私が好きなのはやっぱり武くんですね。こういうタイプの人間って、いないようでわりといるんですよ。ちゃんと人を見るタイプの人しか気づかないですけど。だからわかってくれる慎一くんが、親友としてあれるんでしょうね。
武くんはほんとうになんといいますか、器用なんだと思います。器用すぎるがゆえに、自分を演じることまでできてしまう人間だと思います。みんなの前では、お調子者の自分がいて、それがみんなに求められているもので、みんながそれを求めるのなら、自分はそれになろうとする。そんなことができる人って実はそんなに多くはないと思います。たいていはどこかでつらくなったりして、演じるのもできなくなっていくものなのではないかと。こういう人にとって、慎一くんのような人はすごく大きい存在なんだと思います。
テニスの試合で慎一くんになろうとする場面では、武くんの思っていたことが顕著に表れていると思いました。部活での慎一くんに、真理ちゃんが求める慎一くんに、そんな慎一くんの代わりにならなければいけない。それはもちろん自分の大事な人である真理ちゃんのために。武くんは器用だから、それもできなくはなかったでしょう。でも、武くんは武くんであり、慎一くんは慎一くんです。それを真理ちゃんに教えられるというのは、ある意味では少し酷なものなのかなと思いました。なぜならその言葉は、「タケちゃんでは慎ちゃんにはなれない」と言っていることと何も変わりませんから。あの場面では、真理ちゃんが思いつめている武くんを救う描写ですが、その後の武くんはいろいろと考えることがあっただろうなと思いました。
その後、武くんが病室で涙を流し、さらに「慎一のところには行くな」と言ったシーンは、真理ちゃんの「タケちゃんは慎ちゃんにならなくていい」という言葉が一番大きな引き金になったのかなと思いました。もちろん仁くんと話したことや、大会の優勝も要因ではあるでしょうが、一番はやはり真理ちゃんの影響かなと思います。日焼け止めを塗るシーンでも、攣薬を持ってきてくれるシーンでも、武くんは弱っていてもつよく振る舞うことができていて、武くんらしいなと思っていました。それが崩れた、というかそれをやめて真理ちゃんにまた思いを伝えたのは、自分は慎一ではないという明確な言葉を向けられたからなのかな、と私は思いました。
ほんとうに武くんはつよい。そして人間としての生き方が下手くそすぎる。慎一くんのことを他人優先などと言っていましたが、武くんも大概だよ! まあそれは真理ちゃんも同じようなものなので、やっぱりこの三人は共通点はないように見えて、どこか似たもの同士なんでしょうね。松本さんに本音を打ち明けて涙を流すシーンも、強がりな武くんがよくわかります。本来なら、泣き虫は真理だけで十分だ、とか自分のキャラに合わない、とか言うんでしょうね。
ただ、武くん、もう強がりはほどほどでいいだろう。まあそれは難しいだろうから慎一くんの前でだけは、思いっきり泣いてやれ。慎一くんと真理ちゃんをくっつけたMVU(Most Valuable 裏方)は武くんなんだから、これからもいっぱい頼っていっぱい頼られる関係でいてね。
あと、私ともアイスジャンケンしましょう!
真理ちゃんについて
おせっかいな人間というのは、どうしてこう魅力的なんですかね。やさしいから? 面倒見がいいから? ただ、そこに押し付けがましさが滲んでいると一気に冷めますが、真理ちゃんはその辺しっかりしていました(まあ私が好きなのはおせっかいな人間ではなく、変に下手に出ることのない人間ですが)。
それはともかく、病院に通い続けるという行為に、このお話を読んでいる最中の私はあまり肯定的ではありませんでした。
〔ここからは少し今作から得たものではない私の考えを入れます〕
そもそも私は、長期にわたって献身的な介護や看病をする人にあまりいいイメージを持っていません。というのはもちろん理由があります。
そういう人たちは、自分のことを二の次にして、自分のことについて考える余裕がないように振る舞うと私は思うのです。献身的な介護や看病といえば聞こえはいいものです。人を思いやる優しい人に思えます。けれどそこには、ある種の逃げの側面も含まれているのではないかと私は思います。献身的な介護・看病は、見つめたくない自分のこれからに蓋をする都合の良い口実になります。看病によって、自分のことからは逃げられる。自分のその先を考えなくて済む。
といったことを思ってしまうので、私はあまり長期にわたる献身的な介護・看病に肯定的ではないのです。
もちろんこれには反対意見もあるでしょうし、この立場は武くんが真理ちゃんへの告白のときに言ったこととほとんど同じです。そして反対意見は真理ちゃんのそれに対する返答です。私はこの返答を読んで、自分の知見が広がったなと思いました。
一緒にいられるだけで幸せという言葉に、逃げを自覚している人もいるのだなと。そしてそれを自覚してもなお、そうやって病院に通い続けることを選んでいるのであれば、それでいいではないかと思いました。それは、自分の選んだ道であり、決して無理をして通っているわけではないのだから。やりたいことをやっている人をとがめる気は、私にはまったくないのでこれも一つの答えか、と思いました。
痴漢のシーンですが、あれはちょっと慎一くんがかっこよすぎではないですかね。あんなことがあったら、誰だって惚れてしまうのでは……? 物語において、人を好きになる理由を明確にしてほしい私から見ても、あれは不満点ゼロでした。いやはやお見事です。さすが慎一くん。
真理ちゃんは真理ちゃんで、なかなかの葛藤をしていると思いました。階段で落ちたときにたかが外れたように泣くシーンは、読むのがつらかったです。思いつめているんだ、それだけ思っているんだということが、形になって表に出てきてしまうと、内部に隠していた感情が見えてしまって、よりつらくなりました。ですが、それを抱えている当人はもっとつらかったですよね。ほんとうによくがんばったと思います。つよい人間だと思いました。
応援を先導したり、スポーツドリンクを持ってきたり、薬を買いに激走したり、病院に通って話しかけたりなどの、自分にできることは何か、についての葛藤は共感できました。真理ちゃんはまじめで口うるさい性格の人だから、自分にも厳しいのだと思います。自分に厳しい人ほど、他人に優しいですよね。そして、勉強面やテニスをやっていた時期のことなどから分かる通り、がんばり屋です。不安な気持ちをたくさん抱えながらも、それでもつよくあるがんばり屋な姿には、自然と惹かれてしまうでしょうね。
二年間よくがんばった! あとは慎ちゃんと仲良く過ごして!! 慎ちゃんとタケちゃんと、なかよくばかやってください!
慎一くんについて
慎一くんには作中何度も起きろ! 起きろ! と思わせられました。回想でしか喋らないのに、なかなかキャラがおもしろかったから余計に。慎一くんはただの『根暗』じゃないんです。体育教師にドロップキックをかますのは、さすがに慎一くんにしかできない。真理ちゃんと武くんのためなら、こういう行動を迷いなくするのがかっこいいです。
三人の出会いはベンチでのよくわからない会話ですが、こういう訳の分からない出会いこそ、長く続きますよね。
他の子と遊ぶ方が楽しいみたいなことを言うシーンはよかったです。三人の関係性があたたかいなと感じました。そうですよね。二人は慎一くんと一緒にいたいからいるだけ。分かりますよ、この三人の会話は読むのですらすごく楽しいんですから、それはそれは当人たちは楽しいでしょう。この三人の会話はなんというか、安心します。お互いに信頼しているのが伝わってくるからですかね。なので回想の場面はたいてい、おーきたきた、と思って楽しく読んでいました。
長距離走の練習の場面も好きです。ジュース買ってくれを真に受けて、自転車で行ってしまう真理ちゃんがおもしろすぎました。まあ一人だけ自転車に乗っているというのが、行ってしまった理由でしょうが、疲れた二人を置いて真理ちゃんが颯爽と川原から離れる姿を想像すると、なかなかおもしろいシーンでした。また、ここの残された二人の会話もいいです。演じている自分ではない自分を見てくれるという人間が、どれだけありがたい存在か。私はこういうの、身に覚えがあるのですごくよく分かります。うれしいんですよ。すごく、ほんとうに。器用に自分を演じて振る舞っているのを見抜いてくれたり、そんなのしなくてもいいとか言ってくれると、もうたまらなくうれしいんですよ。ここの武くんには共感を覚えました。そして思いました。慎一くんがかっこよすぎると。なんだかもういろいろとかっこよすぎですよ。自分を曲げないその精神は、いいものです。
幽霊になったというのは言わんとすることはわかるんですけど、理屈っぽい私からすると、ん? となりました。まあでもはじめの方にあった本屋の前のシーンで、なんとなく超常的要素はあるんだろうなと想像してはいたので、そこまで唐突だとは思いませんでした。ただ、幽霊になった理由とかそんなことは置いておいて、そのときの慎一くんの思いはとてもよい描写だなと思いました。真理ちゃんや武くん、お母さんなど、様々な人が見守ってくれている中、どうしても自分の体に戻れない、目覚めることができない。そうしてみんなを停滞させているのだという思いが芽生え、自分で自分を終わらせたくなるという気持ちは、分かる気がしました。死んだほうがいいんだ、と思ってしまうのも仕方がないと思います。諦めてしまうのも、周りを解放したい思いも、人を優先する慎一くんだからそうなるだろうなと思いました。しかし、待っていてくれる人をずっと待たせてしまう。それを見て、いつ終わるのかわからない不安に打ちのめされてしまう気持ちも、やっぱり少し分かる気がしました。
でも、信じているという真理ちゃんの言葉を聞いて、慎一くんは生きることを諦めないと決めます。やっぱり慎一くんを心から救うのは、神崎くんではなく、真理ちゃんなんですね。ずっと通い続けてくれる大切な人の力は、やはり大きいのだなと思わせられました。
ただ、何があっても生きろという言葉が酷だと言っていた慎一くんには、私は同感です。生きていることでかける迷惑と、死ぬことで救われる人を天秤にかけたとき、どちらが重いかなんてものは明白です。そもそも天秤にかけること自体が間違いな気がしますが、生きろと一口に言うのは簡単です。ですが、それは死んではいけないということで、生きたくもない人生を過ごし続けなければいけない呪いでもあって、精神状態によっては決して耐えられる言葉ではないんですよね。ほんとうにほんとうに追い詰められているときに、何も知らない人にこんなことを言われたら怒りの感情が湧くのは当然なのかなと。まあこの場合は怒りが湧くだけましですね。呆れなどの、もはやほとんどを意に介さない状態まで行ってしまっていれば、もう言葉が意味を持つとも思えません。こんな言い方はおかしいかもしれませんが、その意味ではやはり慎一くんは本心では生きたかったんだと思います。真理ちゃんの信じてるを聞く前から、狼に襲われて死にたくないと思う前から、生きたい気持ちはあったんだと思います。その感情を起こしたのが、真理ちゃんの信じてるだったのかなと私は思います。
とはいえそのあとまた一年間もの間、この周りを停滞させるという苦しみを続けたのだと思うと、慎一くんもがんばったんだなと思いました。それだけに、報われてくれてほんとうによかったと思いました。
やっと起きたね、慎一くん。大好きな恋人と、大好きな親友と、いい人生を。
仁くん、ひとみちゃんについて
仁くんやひとみちゃんも仲のいい友人としてよい人たちだと思いました。武くんのことを気にかけて、飲みに誘う仁くん。いつもと違う真理ちゃんにすぐ気づいて話を聞こうとするひとみちゃん。この二人はとても優しいです。見返りを求める気配など、一切ありません。こういう友人はとても大切だと思います。ただ、こうした友情は片方が優しいだけでは成り立ちません。そこにはやはり、武くんと真理ちゃんの優しさがあると思います。この二人だからこそ、こういった力になろうと思ってくれる友人ができるのだと思います。武くんも真理ちゃんもほんとうにやさしいですからね。いい人間です。こうした持ちつ持たれつの関係は一方的ではないため、側から見ていても気分がよいです。すばらしい関係性であると、私は思います。
慎一くん、武くん、真理ちゃんについて
作中で家族のようなものという描写が出てきます。それは、腐れ縁で、お互いにお互いが大好きで、自分の人生には欠かせない存在だということだと思います。慎一くんと真理ちゃんが付き合うようになってから、武くんはたくさんの思いがあったと思います。そしてそれは、慎一くんも真理ちゃんも同じだと思います。そもそも、抜け駆けして告白、という行為が一見武くんらしくなくて、本当はすごく武くんらしい行為だったと思います。武くんは、おそらく告白する前から気付いてますよね。真理ちゃんの気持ちには。
やはりここにも、お互いの信頼があったのだと思います。たとえどうなろうとも、この三人の関係が終わることはないと、武くんはそう思ったのかなと思います。武くんが行動を起こすことによって、間違いなく関係性に変化があり、慎一くんと真理ちゃんが付き合うことになるだろうという予想は、もう武くんだけではなく、慎一くんや真理ちゃん自身も想像がついていたと思います。それでも、武くんは告白をした。半可な覚悟ではなかったと思います。でもそこには同時に、真理ちゃんも慎一くんもちゃんと正面から受け止めてくれるだろう、という確信もあったと思います。こう思えるのは、それだけこの三人がお互い同士を大切に思って、大事に思って、大好きに思っていたからだと思います。
武くんが真理ちゃんに告白したことを慎一くんに伝えていたシーンは、安心して読んでいました。
ああ、きっと、この三人はいつまで経っても、親友であることはできる。関係性の変化は、強固に繋がれた信頼関係を断ち切るものではない。だから、三人は前に進んだだけだ。停滞をやめただけなんだ、とそう思えました。
はじめは停滞していた慎一くんを、真理ちゃんと武くんが動かした。
次は停滞していた三人組を、武くんが動かした。
最後は停滞していた三人組を、慎一くんが動かした。
そしてそこには必ず、お互いの支えがある。
ほんとうに、やさしい、いい関係です。
この作品はとても良かった。やはり私は長編が好きなのだと思います。心理描写がたくさんあって大満足でした。しかし長編となると、このシーンいるのかな? と感じる場面も少なからず出てくるものです。しかし、日常の積み重ねが物語に影響してくる場合には、やはり長編はとてもいいものになると思います。そしてこの物語は間違いなくいいものでした。
セイシュン真っ盛り!
【紹介】
いろいろなネタが出てくる。どれもセイシュン真っ盛りなネタばかりのため、読むと自分のセイシュン真っ盛りだったときの記憶が蘇る(かも)。立ち絵有り、サウンドノベルが無理という人間におすすめ。劣等感を抱いた経験があるとなおよい(かも)。
【感想】
私はこういう作品も嫌いではないですよ。むしろやりたいことやってるなあ、と思えるので私の方もたのしく読めました。中学の頃はまあ、こんなもんだった気もしますし。ばかなことばっかりで、少しそういうものがあると笑っていたような気もします。
でもなんと言いますか、下ネタってうまくやらないと受けなくないですか? なんかこう生々しいものではだめですし、かといって幼稚すぎるのもなあという思いが交錯して、私はうまく扱える気がしません。でもそんなに気負うこともないのかもしれませんね。受けるよりも不快にさせないことを第一に考えてさえいれば、下ネタも受け入れられるのではないかと思います。
早乙女さんこと委員長が、かわいかったです。風間くんに振り回されて呆れているまじめな人かと思っていたら、まさかお腐りなさっていたとは。攻めの対義語が受けは……一般的ではないですねえ。
でも私は、自分の好きなことに嘘をつかない人は好きです。それをみんなの前で公表するかどうかは関係なく、恥ずかしいことと隠していても、好きなことをやめない方が私は好きです。たまに、これは一般的ではないからとか、受け入れられるのではないからとかいって、自分が好きなことを曲げてやめてしまう人もいますが、そんなことはしなくてもいいんじゃないかなと思います。べつに自分の好きがなんだって構わないでしょう。好きなのだからそれでいいと思います。ただ、それをさも受け入れてもらえるものとして、理解を強要してくるのはだめだと思いますけどね。自分には自分の好きがあるように、人には人の好きがありますから、そこはお互い尊重しあって、もし理解しがたいものだったとしても、非難はせずそういう人もいるんだなあ、という寛大な心でもって接するとよい世界ができると思います。人の好きを否定していては、自分の好きも否定されてしまうでしょうから、仲良くしましょう。
吉野さんのリストカットについてですが、私は今までそういうものをしたこともなければ、見たこともありません。なので、実感としては遠いんですけど、生きた心地を確かめるため、と言われたらなんとなくわからないでもない、のかな……? と思いました。いやでも、やっぱりちゃんとはわからないです。こういう自分でわかっていないものに安易に共感するのは、私の信念に反する。
わからないなりに感想を述べますと、これは依存なのかなと思いました。本編でもやめたいけどやめられないと書かれている通り、これをしないとつらいんですよね。してもつらいでしょうが、しないともっとつらいものなのかなと。中学生ということもあって、家庭と学校という社会にしか属していないと、それが全てのように思えてしまって、依存はこれしかないと思えてしまうんだと、私は思いました。他にも依存できるものはあると思います。依存自体はべつに悪いことではないですし、誰しも少なからず依存はしているとも思います。風間くんとのたのしい会話や学校生活に依存できたら、いいですね。たぶん最後のあの雰囲気ならできるかな、と思います。
さっきも書きましたが、依存はものにもよりますが、悪くないと思います。風間くんの罪も、べつに悪くはないんじゃないのかなあとも思います。だって、風間くんは青春を謳歌しているみんなからの劣等感を紛らわせるためにやっているんですよね? もし忙しくなったり吉野さんとのたのしい日々が出来上がったら、風間くんは今まで通り罪を重ね続けますかね。重ね続けるなら、それは趣味とか好きの部類でしょうからもうやめる理由なんてないでしょうし、それで罪をやめるのであれば凡百の人間が娯楽に依存しているのと同じことで、べつの何かが代替できるということなので、それが罪であると認識する必要はないかなと思います。小難しいことは考えずに、自分のやりたいことに嘘をつかないのがいいのかなと思いました。
タイトル通り、みんなセイシュン真っ盛りでした。
(余談。風間くんも光一くんも、おもしろかった。ネタで笑う、というよりは、なんか自分もこんなんだったかもな、とすこし懐かしい笑いが起きるゲームでした。ほんとうにたのしかったですよ)
君と再会した日
【紹介】
同窓会に行く話。すごく冬の雰囲気がする。私がはじめてプレイした九州壇氏さんの作品。同窓会に行ったことがある人間は、この作品が醸し出す雰囲気だけで、最後まで楽しむことができる(かも)。静かな夜に心を落ち着けて読むのがおすすめ。
【感想】
さっそく私ごとで申し訳ないのですが、私もこの前同窓会に行きました。なので、主人公の日野村さんにはたくさんの共感を覚えました。昔気になっていた人に会えるのは、同窓会の醍醐味であると思います。日野村さんはあろうことか、土井さんのことを宮田さんだと勘違いしてしまいますが、何年も会ってないとこうなりますよね。私も何年も会わなかった人の雰囲気が変わっていたりすると、もう誰かわかりませんでした。たいていは、あれ誰? みたいな会話が起きるので、後になってわかりますが。でも土井さんの場合は宮田と呼ばれているのだから、それは仕方ないです。断言します、日野村さんは悪くありません。きっと、たぶん、悪くないはず……です。
井上さんとの会話で二人は宮田さんの死を、真に受け止め、お互いで共有し、最後には受け入れます。その涙は、間違いなく、悲しさだけではないと思います。ただ、二人にとってはそれだけ宮田さんの存在が、ちゃんとあったのだと思うと同時に読者である私は悲しくなりました。せっかくの同窓会だったのに、日野村さんは宮田さんに会えるかなと思っていたのに、もう会うことはできないのですから。ですが、宮田さんの死をちゃんと受け入れられたのは、救いでした。井上さんがいてくれて、よかった。
死を受け入れた後、宮田さんのことを話す二人は、きっと宮田さんを交えてするはずだった、久しぶりに会って向けるはずだった笑顔で、笑えていたと思います。
私も天体観測は大好きなので、願わくば久しぶりに会う宮田先生の『授業』を聞く日野村さんがみたかった。『授業』は昔の日野村さんにとって、人生の中でどんなことよりも尊く、意味があるものだったと描写されています。そんな二人を見ることは叶わないんですよね。と思っていたら、最後のシーンがまたくるんですよ。あのシーンはきれいでした。星はいつも、瞬いている。届くことのない、行くこともできない場所で。
15年ぶりのあの場所で涙を流す日野村さんは、やっと宮田さんの笑顔を思い出します。他の人に言うとばかにされそうなことを、宮田さんだけが受け入れてくれた。日野村さんはそのことに救われたと思っています。そして宮田さんも、日野村さんに星が好きなことを話します。そんな二人が仲良くなっていくのは自然な流れです。そして日野村さんは、たのしそうに話す宮田さんが、その笑顔が、好きだったんですよね。
宮田さんの代わりに星を見ると誓う日野村さんには、家庭のことなどまだまだたくさんのやるべきことがあります。でも、星を見るという行為は、それをしても大事な、とても大切なものなのだと思います。それが、宮田さんに対する思いの強さなのだと思いました。
(余談。物語があまりにもきれいなので、感想を書くのにもかなり慎重になってしまいました。冬いいですよね。まあ私は移ろいの期間も含め季節はぜんぶ好きなんですけど。冬のよさは、こういうきれいな物語には際立ちますね)
〔ここからは感動作品というものに対する私の個人的な思いがあるので読みたくない方は飛ばしてください〕
あとがきに「『感動系』の作品は、誰かの死を前面に押し出していることが多い」とありましたので、すこし書かせていただきます。
私は人の死を「利用」した感動は好きではありません。そもそも感動を「させよう」という心意気自体があまり好きではなくて、どうして感動するかどうかを読者に委ねないのか、と思ってしまいます。書いた物語が読んだ方を感動させたならなにも思いませんが、はじめから感動「させてやろう」とした作品は、なにか透けて見えます。どこかわざとらしかったり、無意味に引っ張ったり、押し付けがましかったりと、雑念が混じっていてこういうのはあまり好きでないな、と私は感じます。
また、私は制作側の訳の分からない都合で物語の人物を死なせられると、読む気がなくなります。感動やインパクトを与えるためなら、べつのやり方のほうが私は好きです。
そしてなによりも、死が生むのは、怒りや悲しみといったわかりやすいものだけではないと、私は思います。
まあこれらはすべて私の勝手な意見なので、反対派のかたもいらっしゃるでしょう。そもそも舞台設定から命が軽い世界という場合もあるでしょうし、それはそれで全然かまわないと思います。これは単なる私の好みに過ぎませんから。私は自分の好きを押し付ける気はありませんし、人の好きを否定する気もありません。私は死を利用することがだめだとは一度も書いていませんので。これは私がそれを好きかどうか「だけ」の話です。
眠れない夜に
【紹介】
答えのような作品。何度も繰り返し読んでほしい。作品ページの「■このゲームの特徴をリストアップ」という部分によくよく目を通してから読むとよい。九州壇氏さんの他の作品を読んだことがある人間におすすめ。全部読んでからだとなおよい。
【感想】
今までの作品を通して見えてきたものが、この作品には別の形でありました。こんな言葉で締めくくってしまうのは少々雑かもれないのですが、この作品は過去作で感じたことの集大成だなと思いました。私は九州壇氏さんの作品を、『君と再会した日』→『吟遊詩人』→『年末年始の恋模様』→『僕の愛する三匹』→『乙女心と夏の空』→『セイシュン真っ盛り!』→『眠れない夜に』という順番でプレイしました。なので今作は一番最後にプレイしています。だからこそ私は、『眠れない夜に』は九州壇氏さんの7つのノベルゲーム作品における、一つのゴールのような、極めた先の物語なのかな、と思いました。
雰囲気は『君と再会した日』にすこし似ていますし、
姉妹関係は『吟遊詩人』にすこし似ていますし、
両思いなのに思いを伝えられないのは『年末年始の恋模様』にすこし似ていますし、
図書委員や夜を書いているときに出てきた描写は『僕の愛する三匹』にほんのすこし似ていますし、
突然の出来事によって今までの関係性が、という部分は『乙女心と夏の空』にすこし似ていますし、
おでん屋の三人のおじさんたちの中の一人が『セイシュン真っ盛り!』で書かれたあの部分にすこし似ていると私は感じました。
私がこれらすべてを、「すこし似ている」と「ほんのすこし似ている」にしたのは理由があって、それはこれらと同じではなかったからです。同じだったら同じと書いていたのですが、似ているだけでした。
私が読んできた九州壇氏さんの数々の描写の、同じ繰り返しではなかった。そこには新たな視点が含まれていたり、揺るがない視点が含まれていて、物語としての『眠れない夜に』もたいへんよかったのですが、こういった要素があったことを私はすごくよかったと思いました。揺るがない思いはそのままに、やり残していた課題をやったような、そんな印象を受けました。
展開の仕方と、意図的に情報を伏せる部分が自然で、ここもとてもよかったと思います。
茜さんについて
茜さんはやさしいですね。茜さんは自身を臆病者であるといいますが、私もこの辺りには共感できる要素が多かったです。人に嫌われるのって、どこかに支えがないと難しいんですよね。嫌われる場ではないどこかに、自分の居場所や認めてくれる人がいればべつに嫌われるのなんてへっちゃらですが、そうはいかない状況では、どうしてもつらいですよね。特に茜さんの場合は、誰かれ構わずに嫌われるのが怖いという心理のまま接していたので、それはいろいろと無理がたたってくると思います。
でも、そんな内面があっても、やさしい姉であったことは、紛れもない事実で、その面ではやはりいい姉だったのかなと思います。香澄ちゃんに尽くしてあげることに、茜さんなりの理由がしっかりあるのが、私は好きです。やっぱりそんな茜さんの笑顔はすてきなものなのだと思います。笑顔の意味はどうあれ、淳くんや香澄ちゃんにとっては、特にそう感じたことだと思います。
香澄ちゃんについて
依存してしまえる存在を、甘えても許してくれる存在を嫌いだというのは、かなり我がつよいと思いました。茜さんのことを羨ましく思ったり、嫌だと思ったり、そういった思いは何より我がままな自分を認められないことに対する葛藤だと思います。そして同時に、自分の弱さも痛いほど自覚しているなと思いました。弁当のくだりの罪悪感は、私には到底計り知れないものでしょう。ずるいことをした自分も認めてくれる、ほんとうは臆病者で、でもほんとうにあたたかいお姉ちゃんと、真に向き合うことができてよかったと思います。そうしてやっと茜さんと向き合えたのに、不幸なことに茜さんは病院送りに。茜さんを演じてしまうのも、無理はないような気もしました。やっと大好きだと思えたのに、大好きな姉がこうなってしまった、という心の弱りもあったと思います。あのドライブは誰も悪くないと思います。みんなそれだけに茜さんのことが、好きだったということだと思います。
淳くんについて
心理の揺れ方を見ていて、つらくなることが多かったです。わかってはいるのに、受け入れられない。受け入れたら、それは終わりのようで、でも茜さんが病院であの状態になってしまっているのは事実で。それはどうしようもない現実で。
やはりあのドライブについてはだれが悪いとは思えません。あのようにしてしまうのも仕方ないと思います。
けれど、淳くんは夢の茜さんと約束をします。あれをただの夢であったとちゃんとわかって、現実逃避をやめているのがとてもよいと思いました。それでも、その約束を大事に果たしていこうとする淳くんには、もう迷いはないと思います。香澄ちゃんを支えてくれると思います。
こういった作品の後味が悪いのは、あまり好きではないのですが、今作の淳くんも香澄ちゃんも、心理の揺れ動きを通して、前を向いてくれました。
こういう系の作品は変にひねってくるものが多いなと私は勝手に思っているのですが、この物語は静かに、ゆっくり、真っ直ぐ終わってくれます。こういう作風が九州壇氏さんの魅力だと思います。
7つのノベルゲームの最後を締めくくる『眠れない夜に』、とてもたのしかったです。
この答えのような物語。おすすめです。過去作をプレイしてからだと、さらにおすすめ度は増します。読んだことがない方は、ぜひ読んでください!
(余談。おでん屋行ってみたい。あのおじさんが名物化してそうですね。それと、弁当に入っていたたらこが福岡っぽいなあとか思いましたが、偏見……に、なってますかね。大丈夫ですよね)
【書いて思ったこと】
本来私は、おもしろかった作者さんの他の作品だからといって全部を読むなんてことはしないのですが、『君と再会した日』を読んだときに、その考えがすこし揺らぎました。なんというか、突飛なことが起きない作風が、私には合っていたのかなと思います。仕掛けとかはもちろんあるのですが、説得力と、ここまでは行って欲しくないという私の好みを、的確についてきたようでした。
というわけで九州壇氏さんの作品をすべてやってみたのですが、たのしかったです。
うーん、それにしても感想の書き方はこれでよかったんですかね。人物と関係性について、思ったことを垂れ流しただけなのですが、もっと音楽とか画面とかに触れた方がよかったのかな。でも私がなぜお話の、それも人物と関係性についてばかり書いていたのかと言えば、それが好きだからです。理由はそれだけですが、音楽や画面とかに偉そうなことを言うのは、私には荷が重いのでこれでよかったかなと思います。
人の関係性とかが大好きなのは、感想を読んでいただいた方には間違いなくばれているでしょうが、逆に言えば私はそこくらいしかまともに文章におこせないんですね。音楽がいいとか、演出がいいとかを語るのは苦手なので、もし次回があった場合も、このような感じの感想を書くと思います。
【終わりの挨拶】
それでは最後に、九州壇氏さん、すばらしい作品たちをありがとうございました。どの作品も、大いに楽しませてくれました。九州壇氏さんの作品には、かなり昔に公開された作品もあるので、おそらく以前プレイしたという方も多いと思います。私の感想を見て、なつかしいなと思ってくれたらうれしいです。そして、なつかしさついでに、今一度九州壇氏さんのゲームたちを起動してみるのはいかがですか。色あせない名作揃いですし、今と昔とでは受け取り方も変わるかもしれないので。
それでは、今回は九州壇氏さんの
『僕の愛する三匹』
『吟遊詩人』
『年末年始の恋模様』
『乙女心と夏の空』
『セイシュン真っ盛り!』
『君と再会した日』
『眠れない夜に』
を取り上げさせていただきました。九州壇氏さん、ほんとうにありがとうございました!
この挨拶をもちまして、『不定期 第一回ノベルゲーム感想日記』は終了です。
私のノベルゲーム感想日記はタイトル通り、不定期ですので、次回は一週間後かもしれませんし、一ヶ月後かもしれませんし、一年後かもしれません。もっと後かもしれません。気が向いたときにやります。
それでは、失礼します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【この記事を読んだ方へ】
九州壇氏さんの作品は、たのしくありたい気持ちと、それがうまくできないもどかしさを持っている方には、すごくささると思った。
自分の感情を理解していながらも、どうしても素直になりきれない。それに対して、つらく感じることもあると思う。しかし私は、そんな自分も大切にしてほしい。
なぜか?
それは、その不器用さも含めて、自分だから。器用に生きている人の真似は、しなくていい。
自分の感情を捨てない人間は、どうしようもなく不器用だ。だけど、だからこそ誠実だ。
その誠実さは、きっとだれにも劣らない。
それは、誇るものでも、誇れるものでもないけれど、その誠実さを大事にしてくれる人はきっといる。
