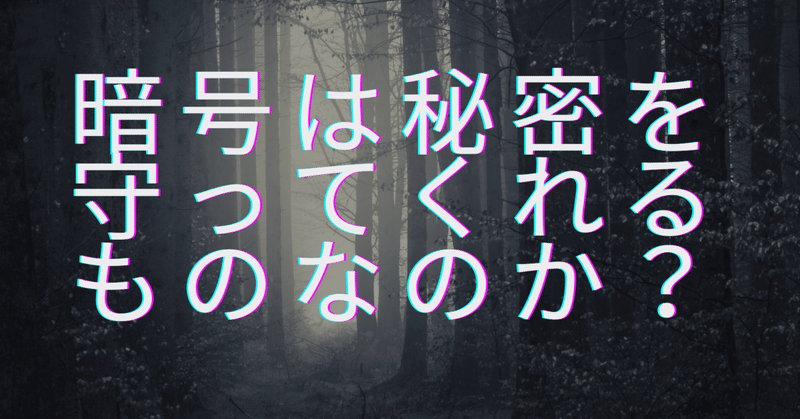
【読書感想】暗号解読
昨今PayPayなどのQRコード決済は広く普及し、マイナンバーカードも所持をしていないと不便な世の中になってきました。
私たちは今、情報化社会の真っ只中にいます。
そんな社会で私たちのプライバシーの保護に一役買っているのが「暗号」ですが、この「暗号」にまつわる歴史ご存知でしょうか?
少し古い本になりますが、今般世界的ベストセラーになった「フェルマーの最終定理」の著者、サイモン・シン氏による「暗号解読」を読んだところ、これまで知らなかった暗号に関する興味深い事実(未読の方は恐らく知らないことばかりだと思います)に驚かされました。
そこで今回は、同著作のごく一部ではありますが、私が特に衝撃を受けた「暗号にまつわる闇」の部分について、みなさんにもご紹介します。
最初の話題は、民間企業が暗号システムを導入する際、「使用する暗号システムは政府が解読できるものじゃなきゃだめ」という制約を課せられたのではないか、という疑惑の案件です▼
民間が使用する「暗号」に政府が介入?!
かつてコンピューターは政府と軍部しか利用できない高価なものでしたが、1950年代にコンピューターの商用化が実現し、さらに1960年代になると機器の価格も下がったことから、民間企業もコンピューターを導入し始めるようになります。
その折、企業は自社の大切な情報を暗号化した上で活用したいと考えますが、他社と通信をするためには、その他社も同じ暗号システムを使っている必要があります。(使っていないと、暗号化したメールを送っても相手に解読してもらえません)
つまり、商業用の標準的な暗号システムの構築が求められました。
そんな中、1970年代にIBM社により強力な暗号システム(「金星暗号」と呼ばれています)がつくられます。使い勝手がよかったことから多くの企業がこれを利用しはじめ、これがアメリカの標準的な商用暗号として採用されるのも当然かと思われていました。
が、ここに待ったを突きつけたのがアメリカ国家安全保障局(NSA)です。
同局は、アメリカ軍と政府の通信の機密保護に責任を持ち、諸外国のメッセージを傍受、解読しようとしている機関です。そんな彼らとしては、自分たちが解読できない暗号が「標準暗号」として頒布されては困ります。
というわけで、サイモン・シン氏の著作によると、NSAの政治的圧力により、IBMが考えた暗号システムを「民間企業では解読がほぼ不可能だと思われるものの、NSAなら解読可能な程度」に制限したものが標準暗号として採用されたと書かれています。(が、いろんな人がいろんなことを言っているようです)
真相は分かりませんが、政府介入はありえそうな話ですよね。
ちなみにこのとき採用された暗号技術は「DES」という名前の規格になっていますが、技術進歩によって現在は脆弱性が指摘され、今は新しい暗号化技術が採用されているようです。(が、これも「政府なら解読できる暗号」かもしれませんね)
次は、暗号には「一般人には知られされない事実」がつきものということを示すエピソードです▼
「最新の暗号研究」は隠されている!?
上段に記載のとおり、1970年代に半ばまでには「強力な暗号化をすること」はできていたものの、「暗号化された文章を元に戻すこと(=復号すること)」に関しては一つ問題がありました。
それは、復号に必要な「鍵」(=暗号解読のためのパスワードのようなもの)を当事者間で安全に受け渡しするためにはどうすればいいか、というものです。
「鍵」がなければ復号できませんが、「鍵」の情報をそのまま通信すると易々と傍聴される可能性があり、そうなると第三者が暗号化された情報を解読できるようになってしまいます。
鍵そのものを暗号化したとしても、それを復号するために別の鍵が必要になるだけなので、問題は解決しません。
詳細は省きますが、この問題の美しい解決策として、1977年に「RSA暗号方式」という安全に暗号を復号できるアルゴリズムがアメリカで発明されました。これは「二千年以上前に暗号が発明されて以来最大の快挙」と言ってもいいくらいの大きな転換点でした。
しかしながら、実はこれと同じような理論が、1969年には英国政府通信本部(暗号解読業務等を行うイギリス政府の機関)の職員が提唱していたのです。その後さらに別の職員のアイディアが加わり、1973年にはRSA暗号方式とほぼ同様の具体的な形になっていました。
このように世界を揺るがせるほどの大発見がアメリカに先駆けてイギリスでされていたのに、イギリス政府はこの事実を対外的に公表しませんでした。
——英国政府通信本部による暗号研究は「極秘研究」だったからです。
この事実はこれ以上秘密にしていても利益がないと明らかになった後、1997年になってようやく公表されました。
(※ちなみに、サイモン・シン氏は、イギリスが情報を公開する前にこの情報を掴んでいたところあったようだと書いています。これが、先に登場したアメリカ国家安全保障局(NSA)です。さすがの情報収集能力ですね…!)
こうした歴史を踏まえると、2023年現在も、世界各国の中枢で知られざる「秘密の暗号研究」が行われているとしても不思議ではありません。
最後に、政府の権力と市民の自由のぶつかりあいに関する話をします▼
「暗号」は誰のためのもの?
上段に記述した「RSA暗号」は政府・軍部・大企業を対象にして開発されました。しかし1980年代後半になると、インターネットはその他一般大衆の手にも届くものとなります。
政府をはじめ、権力のある一部の組織は暗号を使ってプライバシーを保護できるのに、一般大衆の通信は容易に記録・監視できるような状況でよいのでしょうか?
こうした危機感を背景に、「一般大衆向けのRSA暗号」がアメリカで開発・公開されました。(「プリティー・グッド・プライバシー」という名の暗号ソフトウェアです)
ところが、アメリカでは「暗号化ソフト」はミサイルや機関銃と同類の「軍需品」に指定されていたために、この開発者は武器商人として政府に告発されてしまいます。
実のところ、アメリカの他、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドの5カ国は協力して世界規模の秘密情報収集ネットワークを運営しており、「エシュロン」と呼ばれるシステムで世界中の通信情報を監視をしていると言われています。(※諸説あります)
一般大衆が強力な暗号を使えるようになれば、各国はエシュロンで脅威を検出できなくなってしまうかもしれません。アメリカ政府側が開発者を訴える気持ちも分からなくはありません。
その一方で、「プライバシーは基本的人権だ!ほしいままに盗聴・干渉されるべきではない!」と主張する活動家もいますし、こちらにより共感を覚える一般市民も多いでしょう。
様々な意見が飛び交う中、大衆向けRSA暗号の開発者はFBIの捜査を受け、三年に渡る大陪審の審査を受けたものの、最終的には政府側の訴えは取り下げられました。
というわけで、同暗号の開発者にまつわる騒動は落ち着きましたが、当時あった政府側と市民側の意見対立は今も紛糾状態にあるようにみえます。
「暗号」は政府のために使われるべきのか、「一般市民」のために使われるべきなのか、、、難しい問題ですね。(個人的には結局「権力のある人の都合」によって決められてしまいそうだな〜と諦念を抱いていますが)
まとめとおすすめの人
今回は暗号にまつわる「闇」の部分を特にクローズアップしてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
私にとって「情報化社会になればなるほど『闇』が広がっていきそうだな…」という軽い恐怖を覚える、インパクトのある一冊となりました。
とはいえ、この記事で紹介した内容は本の中のごく一部に過ぎず、この他にも古代文明の暗号めいた文字の解読や、第二次世界大戦中に日本軍とアメリカ軍の間で用いられた暗号の話や、近いうちに実用化されるかもしれない「量子コンピューター」の話などもあり、幅広い知識がちりばめられた本となっています。(吸収したい知識が含まれ過ぎてお腹いっぱいになる感じです)
また、暗号作成・解読技術については、複雑な内容もかなり噛み砕いたうえで丁寧に説明されているので、「なるほど、こういう説明だと分かりやすいのね」なんて感心しながら読めると思います。
考古学、歴史、数学、物理学あたりに興味があり、長い文章を読むのが苦にならない人にはおすすめの一冊です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
