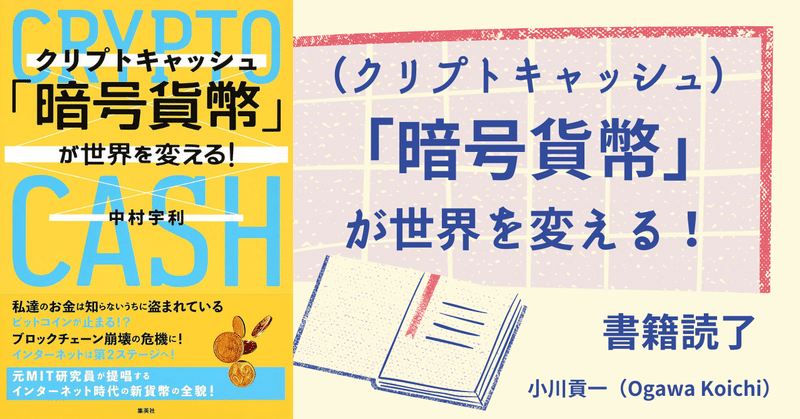
書籍【「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」が世界を変える!】読了

https://booklog.jp/users/ogawakoichi/archives/1/B083LTDZDX
◎タイトル:「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」が世界を変える!
◎著者:中村宇利
◎出版社:集英社
これからは全てのモノがインターネットに繋がる時代。セキュリティ・暗号はその根幹を支える技術のはずだ。
本書を読むと、現時点の暗号技術も脆弱性だらけだという。
クレジットカードが不正利用された被害金額は、年間で世界総額数兆ドルに達しているらしい。
いまだに根本的解決策が見つかっていないようであるが、それではブロックチェーン技術が盤石かというと、そういうことでもないということが、本書の解説で理解できる。
確かに中央集権方式ではなく、分散型にしたことで、新しい概念を取り入れたように感じているが、実際は古くから存在する考え方であって、決して新しい発明とは言い難い。
セキュリティ面についても最初から矛盾を抱えているというのも知らなかった。
同じ台帳を分散化させ、世界中の人がそれらを保有することで、信頼性を担保するということである。
しかし、ネットワークに参加するマイニングノードのうち、51%以上が改竄に協力すればブロックチェーンの取引履歴はそもそも書き換えることが可能だという仕組みらしい。
51%以上をハックすることに対してインセンティブが働かないことや、ブロックチェーンを正しく運用していくための監視が効くから成立しないという指摘は確かにある。
しかしながら、そもそもこういう仕様だということを、正しく知っておく必要があるだろう。
ブロックチェーンの仕組み自体が、盤石ではないということなのだ。
これとは別で、ブロックチェーンの運用面での課題についても本書では取り上げている。
これも私自身勉強不足で理解していなかったことであるが、確かに指摘されていることは今後の継続性(サステナビリティ)で考えてみても合理的とは思えない。
根本的に過去の台帳をすべてブロック化して、分散化により保管されていくので、データの容量は増える一方である。(当たり前だ)
これをPoW(Proof of Work)で力技で作業して取引履歴の正しさを証明する訳であるが、かかる電力は当然増え続ける一方となる。
最初の目論見では、計算にかかるマシンも日々進化する訳だから、データ量が増えたり、電力がよりかかったりするよりも、処理速度が早まって全体で見た効率は悪化しないという前提だったようだ。
しかし実際にはそうなっていないらしい。
もちろん世界の全エネルギーが、再生可能エネルギーだけで賄えるようになったり、量子コンピューターが一般化されたりすれば、大きな変革になるのかもしれない。
(量子コンピューターが実用化されたら、現在の暗号技術が一発で解読されるという別の課題が出てくるらしいのだが・・・)
ビットコインは2024年の今でも値上がりはしているようであるが、この不安定な運用状況でいつまで狂騒が続くのか。
ビットコイン以外のブロックチェーン技術を使った暗号資産(仮想通貨)は、そんなに広がっていないし、消滅したものも多いと聞く。
現実的にビットコインを利用して、街中で買い物ができる訳ではないし、投機以上の利用目的があると思えない中で、今後も発展していくのだろうか。
イーサリアムはNFTの利用などで進化しているように見えるが、それもブロックチェーンの根本的な課題である「取引量増える」→「データ量増える」→「PoW大変」を解決していない以上、どこまで一般化するかは未知数だ。
コロナ禍のお陰で実社会に浸透したPayPayなどの電子マネーについても、私自身も便利に使っているが、そもそもインターネットに繋がっていなかったり、スマホの充電が切れてしまえば利用できないなどの課題は抱えたままだ。
当然インターネットに繋がっている前提で利用する電子マネーは、セキュリティ面で脅威にさらされ続けている。
日本では2024年7月に新札が発行される訳であるが、このニュースを聞いた時に「この現代においてまだ紙幣をリニューアルするのか?」と思ってしまった。
偽造防止の強化ということであるが、今流通している壱万円札がそんな簡単に偽造されているとは思えない。
紙幣を発行し、流通させ、古くなったら取り換えてなどのあらゆるコストを考えると、すべてデジタル化した方がよさそうな気がするが、なぜ紙幣はリニューアルされて残り続けるのか。
そもそも「お金」の成立要件がいくつかあるらしいが、その前提は「信用されているか」ということだという。
日本国が発行したお札が「信用」されているから、日々の買い物など生活に使えるということである。
これは今のお札が十分に信用されている訳で、新札も同様に信用され続けることになるだろうが、果たしてそれでよいのだろうか。
「信用」ということだけで考えると、紙の実体がなくても成立しそうな感じがするが、いまだに「デジタル通貨」については、世界で見ても広がっていない。
各国とも、導入には慎重な姿勢だからだ。
単純に考えて「紙より便利では?」と考えてしまうのだが、そう単純な話ではないらしい。
紙では運用が確かに大変だし、サステナブルな文脈で考えても、地球に優しいとは到底思えない。
それではデジタル通貨が優れているかというと、そういうことでもないらしい。
中国ではデジタル人民元の導入を進めようとしているようだが、その動きに反対するように資産家は現金を集めているのだという。
確かにデジタル通貨は全ての取引履歴が残ってしまう。
監視社会の中国であるからこそ、国家として非常に都合が良いということなのである。
もし紙幣であれば、お財布の中の1枚がどこでどう経由して自分の所にやってきたのかは分からない。
お金持ちの全員が不正をしている訳ではないだろうから、取引履歴を見られてもよさそうなものであるが、やはり気持ちのよいものではないということか。
よくよく考えてみれば、銀行口座に預けているお金だってすでにデータ化されている訳で、資産額については記録として残ってしまっていると言える。
ビットコインだって、取引の台帳を全て残すことが前提であるから、同じことだと思う。
今更履歴を隠すために資産を現金で持つことに意味があるのか不明であるが、今後の流れがどうなっていくのかは予想がしづらい。
著者が推し進めている「暗号貨幣(クリプトキャッシュ)」は、デジタルマネーではあるが、理論上解読されない暗号技術を使うというものらしい。
分散化ではなく、中央集権方式ではあるが、許可された取引所には機能を一部分散化させていくらしいので、そういう意味ではハイブリッド版ということか。
取引履歴は当然残るのだが、そこは今の銀行のようなところがきちんと管理するということらしい。
技術的な部分は、アナログの紙幣や、ビットコインなどの課題を一部解決しているのかもしれないが、果たして普及するのかどうか。
石川県七尾市の地域通貨として実証実験をしたらしいが、技術的な部分よりも、その思想の方に非常に共感をしてしまった。
著者は「お金って、もっと自由に発行してもよいのではないか」と語っていた。
この発想は面白い。今までは信用が前提であったから、国家の後ろ盾が必要だと思い込んでいた。
もちろんビットコインも発行主体がないのだから、信用さえされていれば、国家の存在は不要となっている。
しかし、石川県七尾市のように「地域の価値を再定義してみる」という発想で、貨幣を発行してみるのは、非常に興味深い。
日本・石川県・七尾市と考えてみた時に、そこには今のお金だけでは換算できない価値があるはずだという。
日本というだけで安全であるし、七尾市は食も豊かだ。
カーボンオフセットの考え方で言っても、日本自体が海に囲まれていて、炭素を大きく吸収しているという。
世界規模で考えてみれば「こんな素敵な七尾の住民になりたい」と思ってくれる人は多いかもしれない。
エストニア共和国の「電子国民(e-Residency)」と考え方は近いかもしれないが、データ上で七尾市の市民になったり、そこでだけ利用できる地域通貨を発行したりするのは、まさに「地域の価値を再定義」とも言えると思う。
資本主義の限界が色々と見えてきたために、世界は大きく変わりつつある。
単なる金儲けではなく、別の「豊かさ」を計る指標が必要になってきているのだ。
そこにはデジタルの急激な進化も関係している。
だから「お金」も当然進化していく。
そして、その根底を支えるのが「セキュリティ」だ。
すべてがデジタル化され、ネットワークでつながることで、実現される世界がある。
「便利になる」というだけではない。
今まで小さく閉じられた地域でしか認識されていなかった美しさが、世界的に価値を持ち得るのだということ。
その価値も、独自の地域内だけで流通できる貨幣を使うことによって、人々と社会の関係性がより滑らかになっていくかもしれない。
これだけ考えても、世界が大きく変わろうとしているのを感じてしまう。
そんな素敵な社会が訪れるのを、心待ちしている自分がいる。
世界が良い方向に向かっていければと願う。
(2024/4/13土)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
