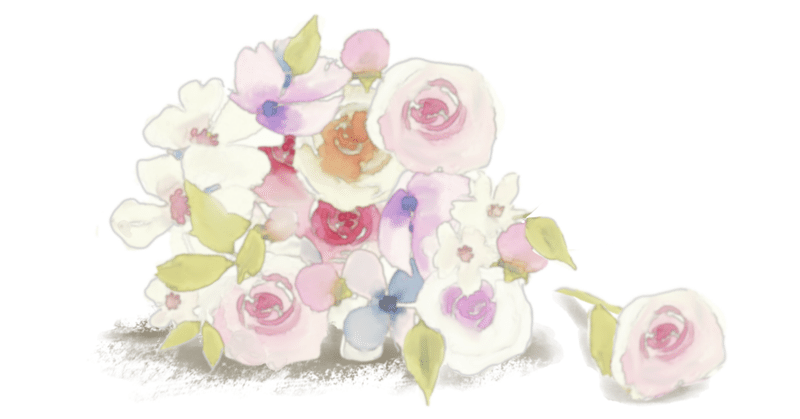
こころの余裕について
エイミー・ベンダーというアメリカの作家がいる。
現代的なおとぎ話、寓話的な短編が特徴的な作家さん。さいしょの短編集「燃えるスカートの少女」、つづいて「わがままなやつら」はいずれも傑作と思う。現代に生きるひとびとの孤独、さびしさ、不条理……と、ひとくちには言いあらわせない感情を、ユーモラスな語り口とストーリーによって、読む人のこころに忍び込ませる。
「無くした人」という短編がとくに好きだ。あらすじはつぎのような感じ。
ある孤児の男の子がいた。男の子は8才のときに両親を水難事故で亡くした。男の子は町のひとびとに共同で育てられる。男の子は両親が死んで2、3年すると、人が無くした物の在りかがわかるようになる。「ひっぱられるような感覚」がして、それで紛失した物の場所がわかる、という。
あるとき、町で誘拐事件が起きる。大きなエメラルドの宝石を持っていることで有名なアレン夫人の小さな子ども、8歳のレナードがさらわれた。アレン夫人に乞われ、男の子はレナードを探す。レナードは遠くにいて、男の子は苦心するが神経を集中させ、ついに探しあてる。レナードは若者4人にいたずらで連れ去られていただけで、レナードは無事アレン夫人の元に帰り、アレン夫人は何度も男の子にお礼を言う。
その晩、男の子は独りベッドの中で自分の両肩を抱き、集中して、こうつぶやく。「どこにいったの? ぼくを見つけにきて。ここにいるよ。見つけにきて」。耳をすませば、波の音が聞こえるかもしれない、と男の子は思う。
この短編を読んで、川端康成の生い立ちみたいだな、と思った。Wikipediaに詳しく書かれているけれど、幼くして両親と死別した川端康成には「一種の予知能力のようなものがあり、探し物の在り処や明日の来客を言い当てたり、天気予報ができたりと小さな予言」をしたりした、とある。
ここで言いたいのは、幼いころに肉親を亡くした人には超能力を芽ばえる、とかではない。エイミー・ベンダーの男の子も川端康成も、身近な肉親の存在が失われたことで感じた孤独や空虚感を、何かを探したり察知したりすることで充たそうとした。心理には、そういう作用があるらしい。
須賀敦子さんのエッセイ「本に読まれて」に、ノーベル賞の授賞式を終えた川端康成とイタリアで食事をともにすることになった折、須賀さんの死去した夫の話におよび、そのさいの川端康成の反応とことばが書かれている。
食事がすんでも、まわりの自然がうつくしくてすぐに立つ気もせず、スウェーデンの気候のこと、あるいはイタリアでどのように日本文学が読まれているかなど話しているうちに、話題が一年まえに死んだ私の夫のことにおよんだ。あまり急なことだったものですから、私はいった。あのことも聞いておいてほしかった、このこともいっておきたかったと、そういうふうにばかりいまも思って。
すると川端さんは、あの大きな目で一瞬、私をにらむように見つめたかと思うと、ふいに、視線をそらせ、まるで周囲の森にむかっていいきかせるように、こういわれた。それが小説なんだ。そこから小説がはじまるんです。
須賀さんは、後年じぶんもものを書くようになって、川端のそのときのことばに、現実と死という二つの世界をつなげる川端文学の秘密が隠されていたのだ、と気づいたという。
つまり、孤独やさみしさ、空虚感が、川端康成の美しい小説や須賀敦子さんの滋味深いエッセイのように、芸術的な感性やクリエイティブを生むのだ、と言いたいのかというと、そうでもない(なんやねん)。
いや、だって「そこから」何を始めるかどうかは、その人が大切にしているものによるし、一方で、人によってはポジティブな方面に向かわないことも往々にしてある。
そのあたりを、自分を見つめつづけて、純粋なことばに残した人がフランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユだと思う。ヴェイユの思索ノート(カイエ)を編纂した『重力と恩寵』に、そのような記述がある。
恩寵が入ってこられそうな全部の割れ目をふさごうと、想像力はたえず働きかけている。
*
あらゆる真空は、(受け入れられないかぎり)憎しみ、ふてぶてしさ、苦悩、恨みなどを生じさせている。自分の憎むものに対して、わざわいがふりかかればよいと思い、そのさまを想像してみると、ふたたび均衡はとり戻される。
*
真空を充たすものとしての想像力が働きだすのを、自分の内部でいつも一時中断すること。
「真空」という単語は、孤独やさみしさ、空虚感と読みかえてもらえばいい。ヴェイユは、ここで「想像力」を必ずしも善いものとして語用しない。恩寵が入りこむのを先に埋める働きとして、一時中断するように戒めている。
同じような内容として、これまたヴェイユと同様に自省のことばを、本人の死後に編纂して出版されたダグ・ハマーショルド(元国連事務総長)の『道しるべ』にも見られる。
空虚への嘔吐感のほかには、おまえが空虚のなかに詰めこむための生命あるものはないのか。
断捨離をしたあとに物を増やさないための秘結は、収納スペースを確保しないことだ、という。人は物理的スペースがあると、そこを埋めたがる。心理も同じで、多くの人はこころにスペースが生まれると欲望という想像力で埋めようと試みる。埋める手段がある大人にとっては容易なことだ。ただ、その手段を取れない子どもは、真空や空虚を感じざるを得ないけれど。
エイミー・ベンダーの「無くした人」の男の子、孤児であると意識しながら育った川端康成、若くして夫を亡くした須賀敦子さん、「真空」を受け入れることが恩寵が生むといったヴェイユ、空虚への嘔吐感を認めつつ世界秩序に生命を捧げたハマーショルドーーこれらの人々のことばを、関連づけて並べてみた。
しかし、こうした高名な小説家、文筆家、哲学者、国連事務総長のことばを前にすると、平身低頭し、高尚に捉えてしまいがちである。
ただ、ここから導き出されるのは、生活感情のある単語で言うならば「ひとは暇を持て余すとロクなことしない」ということだ。気取って言うなら「小人閑居して不善をなす」とも言える。「小人」は、徳のない者を意味する。
要は、孤独やさみしさ、空虚感は不快だけれど、そう感じる自分を直視して、放置してみることが大事なのだと。物理的なイメージにリフレーミングすれば、ワンプレートの皿にスペースが空いていて、そこに肉という欲望を盛るのか、花という芸術を飾るのか。
人は生命維持の本能で、すぐに肉を盛りたがる。しかし、できることなら、花を飾るこころの余裕を持っていたいと思う。
さいきん、アルコールを摂取せずに過ごすことが増えた。体調をととのえて、静かに夜を過ごすのが心地よい。そのせいか、ふいに考えついたことをまとめてみた。
最後まで読んでいただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。 いただきましたサポートは、書籍や芸術などのインプットと自己研鑽に充てて、脳内でより善い創発が生み出されるために大切に使わせていただきます。
