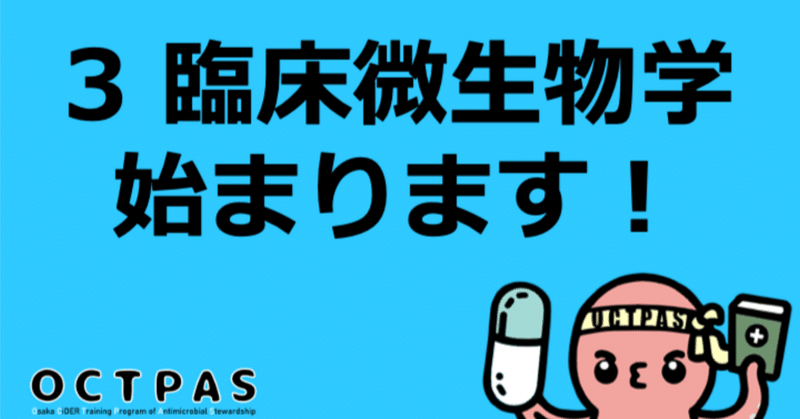
OCTPAS 「3 臨床微生物学」が始まります!
2024年5月8日(水)からOCTPAS(Osaka CiDER Training Program of Antimicrobial Stewardship)で、3 臨床微生物学 が始まります。
薬剤師のみなさんの中には、臨床微生物学を苦手に感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、適切な抗菌薬を選択するには微生物の知識は欠かせません。OCTPASでは、抗菌薬選択や投与中の抗菌薬の妥当性を評価するために必要な知識に焦点を当てることとしました。この機会に微生物に関する知識(病原性や薬剤耐性など)や細かい微生物検査の内容についての知識を習得しましょう。何度も視聴できるのがOCTPASの強みです!ぜひ、納得が行くまでご視聴ください。
3 臨床微生物学 プログラム一覧
「微生物検査室でどのようなことが行われており、菌種の同定や薬剤感受性検査の結果が私たちの手元に現れるまでの行程」が学べます。
第6回(5月8日) 検体提出後から感受性検査までの一般的な流れ
住友病院診療技術部臨床検査技術科 幸福知己
第7回(5月15日)感受性検査の方法と結果の読み方
天理大学医療学部臨床検査学科 中村彰宏
「グラム染色で分類した菌体ごとの微生物学的目線での薬剤耐性機序と、それがどのように微生物検査室で暴かれているのか」が学べます。
第8回(5月22日)細菌の構造と薬理作用
京都橘大学健康学部臨床検査学科 中村竜也
第9回(5月29日)グラム陽性球菌の抗菌薬耐性メカニズムと確認試験
大阪公立大学医学部附属病院検査部 仁木 誠
第10回(6月5日)グラム陰性菌の抗菌薬耐性メカニズムと確認試験①腸内細菌目細菌
公立那賀病院臨床検査科 口広智一
第11回(6月12日)グラム陰性菌の抗菌薬耐性メカニズムと確認試験②ブドウ糖非発酵菌
前 琉球大学病院検査・輸血部 上地幸平
「どのような検体が”適切な検体”なのか、信頼に足る(抗菌薬選択の根拠としていいのか)のか」が学べます。
第12回(6月19日)検体の採取と評価① 血液培養
那覇市立病院医療技術部検査室 大城健哉
第13回(6月26日)検体の採取と評価② 痰培養
大阪大学感染症総合教育研究拠点 山本 剛
第14回(7月3日)検体の採取と評価③ 尿培養
神戸大学医学部附属病院検査部 大沼健一郎
第15回(7月10日)検体の採取と評価④ 膿汁培養
順天堂大学医療学部 三澤成毅
「POCTの特徴と注意点」が学べます。
第16回(7月17日)POCT(point of care testing)
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院微生物遺伝子検査課 原祐樹
OCTPASの受講登録方法
いつでも登録可能です。これまでに配信した動画も全て視聴可能です。
無料で何度でも視聴できますので、この機会にぜひ抗菌薬適正使用支援に必要な知識の習得や再確認にご活用ください。
登録方法は以下のリンクをご参照ください。
お問い合わせ
大阪大学感染症総合教育研究拠点(CiDER)人材育成部門 Mail:foster@cider.osaka-u.ac.jp
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
