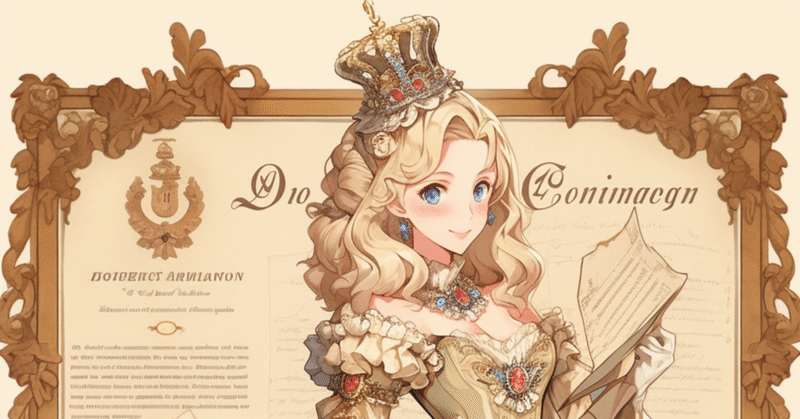
#AIと著作権 - 歴史に学ぶ
「窓の杜」での新しい連載が始まりました。
その名も「生成AIストリーム」。
しかも初回は「画像生成AIが焦がす『善悪の彼岸』」です。
新連載です
— Dr.(Shirai)Hakase #AI神絵師本 #技術書典14 (@o_ob) June 15, 2023
数万字ある初回原稿を担当ハセガワ氏と丹念に(人力で)仕上げました。
素敵なAI画像生成を楽しむための6箇条も役に立つはず…。
最新の著作権まわりの法律を知らない人も多いので、よかったら拡散よろしくお願いします🙇♀️ https://t.co/dIotUJY1WV
まずはぜひ本編を読んでいただいて、こぼれた原稿を供養していきたいと思います。
「知的財産権」と「著作権」について今一度、歴史に学ぼう
生成AIを語る上で、我々日本人は日本の著作権の歴史や特性について今一度学ぶ必要があるかもしれません。文化庁「著作権テキスト」(令和2年度)によると、日本の法律における知的財産権は著作権、産業財産権、その他の3種類があり、著作権は実演等を保護する「著作隣接権」と「著作者の権利」として、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」があります。この「著作者人格権」は、財産権とは異なり、公表権、氏名表示権、同一兼保持という著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできない権利になっています。
文化庁「著作権テキスト」(令和2年度)より
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/92466701_01.pdf
著作権とコピーライト
そもそも著作人格権は他国の法律や文化圏では理解が異なります。なぜなら、日本語の著作権は直訳すれば「Authors' rights(著作者の権利)」であって、「Copyright(複製権)」ではないからです。契約によって移管・移譲が可能な財産権は英語では「Copyright」と定義され、似て異なるものなのです。
印刷の歴史と著作権・著作隣接権
写真の登場よりさらに昔、1450年頃グーテンベルクの活版印刷の発明により、聖書などの書物が大量に印刷できるようになったころ、活版印刷技術の普及により、当初はニセ本が出回ったり、王室などの権力者に不都合な内容の書物が出版されたそうです。そして検閲を目的として、特定の出版業者にのみ出版権を許可する制度が生まれました。この制度のもとで著作者の同意を得ない出版が横行したため、著作者の間に不満がひろがりました。そこでイギリスのアン女王は、著作者の権利を認めた条例を1710年に制定、この条例はアン条例とも呼ばれ近代著作権法の基となりました。著作者の権利を保証したこの制度のもとでイギリスは優れた文学を生み出す社会環境が整い、イギリス文学の黄金期と言われる時代をむかえました。その後、各国が著作隣接権に準ずる権利を認めるには時間がかかっており、1886年以降のベルヌ条約にて、①内国民待遇の原則(同盟国の著作物の権利を、自分の国と同じように認める)、②無法式主義(著作物を作成した時点で自動的に著作権が発生し、登録等は不要)、③死後50年の保護期間、④著作者人格権の保護として著作人格権が定められています。この世界の著作権法の基本合意とも呼べるベルヌ条約は現在、世界の163カ国が加盟しており(資料)、日本は1899年、アメリカは1989年に加盟しています。つまりアメリカで著作者人格権が認められたのは1990年の改正時であり、けっこう最近のことなんですね。
写真登場から観測する生成AIの現在
写真やCGの出身である筆者にとって、現在の生成AIに関連する混乱の様子は、写真技術登場の瞬間に似ているのではないかと感じています。ちょうど1830年ごろ、今から190年ぐらい前のフランスです。それまで画家の大きな収入源は肖像画でした。光と化学を研究していたニエプスはアスファルトを光に当てると硬くなって油に溶けなくなる性質を利用して像を作る印刷技術を生み出します。その技術を学んだ「だまし絵作家」であったダゲールは「本物そっくりの像をつくりたい」と思いダゲレオタイプを開発します。これが初期の写真技術であり、大きなインパクトを与えましたが、この状態の写真はモノクローム(白黒)でしたし、銀板写真は複製したり引き伸ばしたりすることもできませんでした。その後登場したネガポジ方式や引き伸ばし機といった技術は複数の人々の様々な想いによって競争しながら生まれたものです。タルボットはダゲレオタイプを見て、ネガポジ反転した像を使って感光紙に複製する技術「カロタイプ」を生み出し世界初の写真集「自然の鉛筆」を出版しています。タルボットよりも先にネガポジ方式を完成させていたバヤールは運悪く科学アカデミーの支援を得られず、その恨みを込めたセルフポートレート写真を科学アカデミーに送り付けたりしています。その後のカメラの進化、カラー化、ポラロイドなどの革新が続き、20世紀の末1994年ごろにSONY、カシオ、Appleがデジタルカメラを作るころまで銀塩写真の進化は続きます。当時の画家もただ写真に「金持ちの肖像画を描く仕事」を奪われていただけではありません。18世紀末には、売れない画家や実力不足で画家組合に加入できなかった者たちが集まり絵具製造を専業とする「絵具屋」が誕生したそうです。絵具の開発者はより新しい色や商品としてのパッケージ方式を開発していきます。1841年には錫製の「押し出しチューブ」が発明されました。これにより画家は新開発された新しい色やチューブ絵の具という新技術を使って、窓の閉じたアトリエから、より印象的な心情風景を求めて外の風景を描くというモビリティを得ます。写真家も最初は(お金になるので)肖像画のような写真を撮っていましたが、何気ない日常風景や、より写真ならではの表現を求めて多様化し、そして報道写真の時代がやってきます。そうやって写真と絵画、そしてそれにかかわる人々は、お互いに競い合いながら、表現を向上させてきました。
現在の画像生成AIの健康な使い手も、まさにそうやって、新しい技術や表現を日々探求しています。もちろん当時の画材や写真機材と違って、現在はGPU搭載PCと少しの知識があれば、かつてのようにお金持ちのパトロンや、現像暗室がなくても探求できる手軽さはあります。そして大事なことなのですが、画像メディアは個人で作って楽しむだけでなく、「人に見せてこそ価値」という要素もあるのが難しいところなのです。
Wikipedia「写真史」写真技術の発明と研究の歴史
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%99%E7%9C%9F%E5%8F%B2
株式会社サクラクレパス「コラム・絵具チューブの歴史」
https://www.craypas.co.jp/press/feature/009/sa_pre_0016.html
著作権法はアップデートされている、社会の認識も更新せねば。
日本の著作権はアップデートされています。最新の総務省の資料にもある通り、2018年に成立した改正著作権法は、30条の4でAIが文章や画像を学習する際、営利・非営利を問わず著作物を使用できると定めています。
この手の話をすると「日本では学習するのは違法じゃない」とか「著作権は親告罪だろ?つまりバレなければ、訴えられなければいいんだよ」といった甘く見た議論をしている方々がいらっしゃいますが、この認識にも注意が必要です。最新の総務省資料にある通り、刑事罰になる可能性もあります。
たしかに著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害等については過去は親告罪とされていましたが、文化審議会でのディスカッションを経て、2018年以降現在では「著作人格権は非親告罪」となりました。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられます(著作権法119条2項1号)。
つまり自己の著作者人格権を侵害された者は、警察等に刑事告訴(刑事訴訟法230条)や被害相談等をすることができる、ということです。また被害者の告訴がなくても検察が自由に訴追できます。最近では漫画村事件が記憶に新しく、賠償額も大変大きいものとなっております。
▼「漫画村はすべての発端」、KADOKAWA・集英社・小学館が19.2億円賠償求め共同提訴――その狙いと今も続く被害とは - ケータイ Watch (2022/7/29) https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1428483.html
漫画村のその後と具体的な反社会的行為の例についても書きたかったが…。
それに「法律がアップデートされているけど、感情では理解できない人々」についてもちゃんと腰を据えて書きたかった。
いちおう商業出版なので、そこはいい感じにカットされながらも、このチェックリストを作ったという経緯になります。
生成AI時代の『善悪の彼岸』チェックリスト6か条
生成AI時代の『善悪』について、その境界があいまいなままで生成物をつくり公開する行為は無免許運転のようなものです。以下に「生成AI時代の『善悪の彼岸』チェックリスト6か条」を作ってみました。もしあなたが、Stable DiffusionやChatGPTを使って何か生成したときに、眺めてみてください。ChatGPTや生成AIを利用した企業活動であったとしても役に立つと思います。
・どんなプロンプトで生成したか?
・そのプロンプトに他者のIPは含まれていないか?
・どんな感想を抱くために作られたか?
・それは誰かの依頼で作られたものか?
・それを公開することで困る人はいないか?
・それを公開して配布する理由はあるか?
そんなことを考えながらこの原稿を書いていたら数万字になってしまいました。
編集のハセガワ氏にざくざく削られた後ですが、どうぞ比べて読んでみていただけると幸いです。
ところで『善悪の彼岸』って……?
ちなみに記念すべき第1回の原稿タイトルになった「善悪の彼岸」といえばドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの著書「Jenseits von Gut und Böse」(Beyond good and evil)ですね。
善悪の彼岸(beyond)とは、善と悪を超越したところのもの、つまり、既存の道徳的価値観を超えたもの、従来の道徳からの解放を意味しているそうです。Jenseitsは「あちらがわで」という意味なので、イメージとしては「DEATH STRANDING」のような波打ち際をイメージしています。
本当は『神は死んだ!』から始めたかったところですが、さすがにこんなヤバ目の内容でズバズバ削りながら作っている中でそこを残すのが難しかった…。ここは僕のブログなので許してください。
自分は浪人生時代に「倫理政経」という教科をセンター試験で選択していて、この手の哲学書は(めちゃ忙しいはずなのに)眠い目をこすりながら読んでいたことを思い出します。今までの倫理観を引きずっている仲間たちをズバズバ斬っていくような、そういう話をするときに非常に深みがあるタイトル。そもそも「AIと倫理における善悪の彼岸」は1回で終わらせるような内容ではないはず。
また思うところがあったら書いていきたいと思います。
おまけ・カバーイラストメイキング



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
