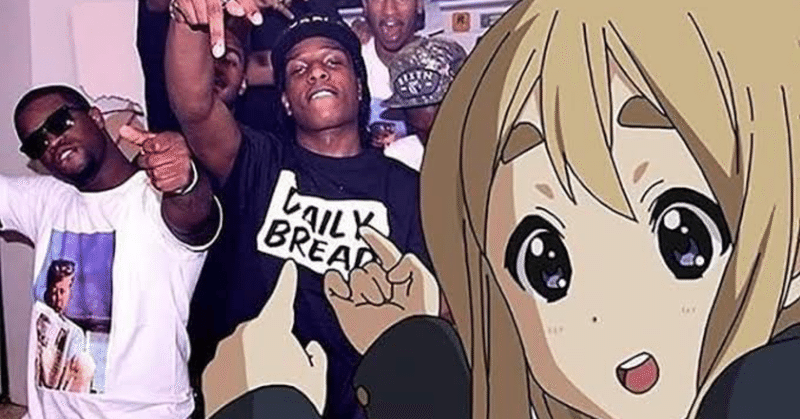
ヒップホップ何も分からないが、入門してみた
はじめに
ヒップホップが何も分かりません。なんか流行ってるなあとは思いつつ、どこから聴いたらいいのかも分からないし、楽しみ方も分からない……と距離を置いていたら、それなりの年月が経ってしまいました。
別にそのまま他所の畑の人間として生きていっても良かったんですが、ここ最近話題にのぼる音楽は多少なりヒップホップへの理解や知識が要求されるものが多く、さすがに話についていけない場面が増えてきました。このままだと音楽を楽しめなくなっていきそうだなということで、今のうちに一念発起してヒップホップに入門してみることにしました。
筆者の現状
まず、「こういう人間が話をしている」という参考情報として、私の現状について簡単に記載します(興味なければ読み飛ばしてもらって大丈夫です)。
これまでの音楽嗜好
おおむね「ロキノン系→UKロック→いろいろ」みたいな流れをたどってきた、典型的な "バンド畑出身" の人間です。途中でハマったポストパンク(特にTalking Heads)からの派生でファンク的なリズム感やグルーヴにも興味を持ち、R&Bやソウルのような黒人ルーツの音楽も聴くようになりましたが、ヒップホップにはハマらず。
何がダメだったのか?
根本的な原因はとても単純で、高校生の時に流行っていたフリースタイルダンジョンが苦手だったからだと思っています。イカつい人たちが罵り合っている、やたら殺伐として怖い番組がなぜあんなに人気だったのか理解できませんでした。それ以降、ラップが全部そう聞こえるようになり、近寄らんとこ……となってしまったのが正直なところです。
あとは、いろいろなヒップホップアーティストの区別がつかなかったことも難しく感じる一因でした。もともと「ここのギターソロかっけー」的な聴き方に慣れていた自分には、ヒップホップにおける個性の主張はややわかりにくく映りました(この疑問点は今回解消します)。
こういった点で、ちょっと前に流行ったLo-Fi HipHopは好んで聴いていたのですが、それ以外のヒップホップはほとんど通ってきませんでした。そのため、事前知識はほとんどゼロの状態です。
参考にした文献
『文化系のためのヒップホップ入門』(以下、『入門』)を大いに参考にしました。ヒップホップの歴史や楽しみ方、ロックとの違いなど、まさに私が知りたいと思っていた内容をわかりやすく教えてくれる素晴らしい入門書でした。
ヒップホップを勉強中なわけだけど、これ評判どおりとっても良い本だった。「文化系」というか、ロックとかは好きなのにヒップホップにはなぜか苦手意識がある、まさに自分のような人間のための入門書という感じで大変ありがたい。 pic.twitter.com/GTwyOZE82X
— 中野ゆざめ (@nyuzame) March 29, 2023
(私のツイートにしては伸びたので、同様のモチベーションを持った方は多いのかも?)
本記事の内容は、ほとんどがこの『入門』+Webの各種ランキング(これとか)やレビュー・評論などで拾い集めた情報から勉強して面白いなあと思ったことのまとめになるので、興味のある方はぜひ原典にもあたってみてください(その方がよいと思います)。
わかったこと
現時点でなるほどなあと思ったことについてまとめます。自分用のメモも兼ねた、非専門家の感想ということをあらかじめご了承ください。
① ヒップホップは「場」の音楽
自分がヒップホップに対してしていた最大の誤読がこの点。ロックが「自分のユニークさを示す『個』の音楽」であるのに対し、ヒップホップは「コミュニティのみんなを喜ばせることを目指す『場』の音楽」であるということ。
すなわち、ヒップホップにおいては「オリジナリティー」もとい「天才性」はそれほど重要視されておらず、むしろ「みんなが共感できる内容をどれだけ巧くラップできるか」「誰も知らないけど良いサンプリングネタをいかに発掘できるか」といった、一種のレギュレーションのある「ゲーム」が主眼に置かれている、ということだそうなのです。
これは、ヒップホップの歴史からも理解できました。その発祥の地となった1970年代のニューヨーク近郊(とりわけ、黒人やラテン系の多い地域)では暴力的な抗争が絶えず、若者たちは身の危険に晒されていたそうです。そんな中、彼らが(自分たちのルーツでもある)ジャマイカにおけるそれを参考に始めた街頭での音楽パーティでも、選曲、MC、ダンスなどが自然と競争=ゲームの側面を持つようになり、暴力によらない抗争の手段として利用されるように。その際、対立する両者のどちらが優位なのかはオーディエンスが決めることになるので、そのバトルのための音楽も独自性よりルールや文法を共有したものになっていったとのこと。これは納得感があります。
この観点に立てば、私が感じていた「ヒップホップは個性がわかりにくい」というのは、モロに聴き方を間違えていたことになります。もともと「場」すなわち「シーン」があり、その中でどうやってみせるか、という行為だったのですから、楽しむには「場」自体に関する知識がある程度前提とされていたというわけです。実際、『入門』の中で歴史的な文脈とともに紹介されていた作品には、以前試しに聴くだけ聴いてみたものも含まれていましたが、その時よりも格段に「すごさ」が分かった気になれました。
また、上記のフリースタイルダンジョン的なものも、同様の視点があれば楽しめたんだろうなと思います。「〇〇と××はライバル関係にあって、自分は〇〇を応援している」的な。プロレスだと思えばよかったのかもな。
(ちなみに、『入門』には続刊が2冊あり、それぞれ2012-14年、15-18年のシーンを振り返る内容になっています。未読ですが、1冊目を読み終えた読者が現行シーンを楽しめるようになるために、続刊としてリアルタイムで解説書を出してくれていたのはありがたいですね。)
② ヒップホップ=ギャング というわけでもない
とはいえ、ただ怖い人がバチバチしているだけの殺伐としたジャンルなのかといえばそういうわけでもなさそう。黎明期からコミュニティを支えたDJであるAfrika Bambaataaは、ヒップホップを構成する要素の一つとして「知識」を挙げていますが、先述のとおり「良いネタをディグって来れるか」が一つの競争になっていたことを踏まえても、ヒップホップの方法論を音楽ジャンルとして深化させようとするある種の「音楽オタク」的方向性は確かに存在するようです。
自分は『入門』を読む前に、検索して出てくるヒップホップ名盤ランキングをとりあえず上から聴いてみる、ということをやっていたのですが、その際にロック耳でもピンと来るアルバムは何枚かありました。特に良かったのが De La Soul の "3 Feet High and Rising" です。
ファンクに留まらないあらゆるジャンルのライブラリから引っ張ってきた大量のサンプリング音源が大胆かつ器用にコラージュされていて、とても聴き応えのあるアルバムでした。歌詞も優しい感じだし。あとで『入門』や各種レビューを読んでみると、「バンドマンにもおすすめ」「ロックファンでもDe La SoulとPublic Enemyまでは聴けた」などのコメントがあり、見透かされているようで恥ずかしかったですけれども。
確かに思い返せば、サンプリングやブレイクビーツのテクニックを活かした音楽はこれまでも好んで聴いてきたわけですが、ポピュラー音楽のフィールドでそれを初めてやったのはヒップホップなんでしたね。「場」を意識したプロレス的な楽しみ方もできる一方、こういう音楽ジャンルとしての味わい方も(ポップス側からヒップホップの要素を利用する形ではなく、ヒップホップに内在する方向性として)ちゃんと存在することを確認できました。
③ 政治との関係
個人的に、ヒップホップはポリティカルな音楽である、というイメージがありました。これは、ヒップホップアーティストが紹介される際に「社会的な抑圧への抵抗」という文脈で語られるのをよく見たからかなと思いますが、この点も少し認識の修正が必要でした。
もちろんそういった政治性を持った楽曲が多いのは確かだそうですが、それは「みんなが共感できる内容をラップする」というルールから生まれた結果であって、ヒップホップ自体がはじめからそこに限定されるわけではない、という認識がより正確(もっとシンプルに「お金が欲しい」みたいな曲も全然ある)らしい。まあ確かに、パンクロックも全部プロテストやってるのかって言ったらそんなことないもんな。
ただし、一般的な傾向として社会的ステータスの低いコミュニティにスタート地点が置かれた音楽である、というのは意識する必要がありそう。『入門』では、「ロックが資本主義社会の中流階級からドロップアウトしようとするのに対し、ヒップホップはむしろ社会へ入っていこうとする音楽である(だから、語っている内容が全然違う)」という興味深いポイントが提示されていましたが、これは根本的な性質の違いとして認識しておく必要があるように思います。
おわりに
以上、門外漢がヒップホップに入門してみた話でした。ずっとわかんねえなあと思っていたジャンルだったので、楽しみ方を知れただけでも自分にとっては大きな一歩です。
ただ、さすがにまだまだ知識が追いついておらず、各人・各グループの識別が依然いまいちつきかねる!のが現状です。とりあえずは数聴いて経験値を稼ぐしかないなと思い、『入門』についている簡単なディスクガイドで紹介されていたものを中心に聴いていっています。修行。
ちなみに、今聴いたものだとDr. Dreの "2001" が非常に良かったです。生楽器サウンドが多めだと私みたいなのでもとっつきやすいのかも。
また最後に、今回こういうことをやってみて、「わからないジャンルをわかりたいとき、やっぱり入門書的なモノはあった方がいい」ということを改めて思いました。例えるならば、第二言語を習得する際、文法を抜きにしてリスニングだけでやろうとしてもなかなか難しいように、楽しみ方や文化が大きく異なるジャンルを、それと知らずに闇雲に聴いていってもたぶんあんまりうまくいかないんだろうと思います。特に、ある程度自分の好みが固まってしまったあとでは。
もちろん、先入観なしに音楽を聴く姿勢もまた重要だとは思いますし、その観点から入門書やディスクガイドの類を敬遠されている方もいるかもしれません。ただそれでも、「どこから手をつければいいのか……」という状態になったときには、第一歩を踏み出す手段として選択してもいいのかなと思いました。
いずれにしても、ここにきてようやくヒップホップと「和解」できそうでよかったなあと思います。また、「音楽についてまとまった知識を仕入れる」という行為も久々で、かつて洋楽ロックを漁り始めた頃を思い出すような楽しさがありました。この調子で、他のわからないジャンルにも挑戦していければ、もう少し「音楽好き」として延命できる気がするので、引き続き頑張ろうと思います。
仲間内でやってるマガジン。こちらもよければ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
