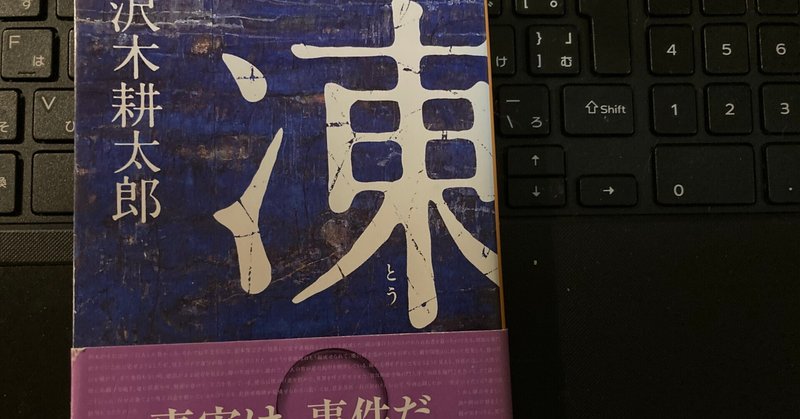
「凍」 沢木耕太郎
初版 2008年11月 新潮文庫
作品紹介
最強のクライマーとの呼び声も高い山野井泰史。世界的名声を得ながら、ストイックなほど厳しい登山を続けている彼が選んだのは、ヒマラヤの難峰ギャチュンカンだった。だが彼は、妻とともにその美しい氷壁に挑み始めたとき、二人を待ち受ける壮絶な闘いの結末を知るはずもなかった―。絶望的状況下、究極の選択。鮮かに浮かび上がる奇跡の登山行と人間の絆、ノンフィクションの極北。講談社ノンフィクション賞受賞。
(アマゾン商品紹介より)
山野井泰史さんといえば、僕が初めて知ったのはNHKドキュメンタリー「夫婦で挑んだ白夜の大岩壁」という番組でした。
凍傷で手足の指の多くを失い、致命的なダメージを負った山野井さんと妙子さん夫婦の登山家が、2007年に、白夜のグリーンランドで標高差1,300メートルの大岩壁に挑む姿を記録したドキュメントです。
この時の印象は、なんというか、のんびりしたハイキングのような感じでした。
それはまた、一線級を退いたクライマーが、記録や名誉とは無縁のところで、しかし、今の自分たちの最大限の限界に挑戦しようとする姿でもありました。
口では小言をぼやきながらも、おたがいに背負ったハンデを補い、支え合いながら、腹の深くで信頼し合い、自分たちの楽しみのためにそこにいる夫婦の姿が印象的でした。
そんな山野井夫婦がまだ先鋭クライマーだった時、その指を失う原因となった、ヒマラヤ、ギャチュンカン峰登攀の記録をメインに、沢木耕太郎が緻密な取材で描き上げたノンフィクション作品が本作「凍」です。
これぞ、純、山岳ノンフィクションです。
前半はクライマー山野井泰史の人物像、経歴、妻、妙子さんとの出会いなどが描かれて行きます。
山野井さんは小学生の時にフランス映画「モンブランへの挽歌」を観て、これだと思い込み、山好きの叔父さんがいたこともあり、小5で北岳を縦走。高校生になると新聞配達のバイトをしながら谷川岳、剣岳、穂高などの難ルート攻略に明け暮れます。高校卒業すると、すぐさまアメリカに渡り、クライミング・バム(不法労働などをしながら、最低限の金を稼ぎ、金が溜まるヨセミテ、コロラドなどの岩登りに明け暮れる浮浪生活者)となり、数々の記録を作ります。やがて、その目標は、ヨーロッパアルプス、ヒマラヤの大岩壁へと移っていき・・と。
ようするに山野井さんは筋金入りのクライマー(垂直岩登り屋)なんですね。
まず、ヒマラヤで最初に成功したのが「チョ・オユー南西壁新ルート単独登頂」でした。チョ・オユーは世界6位の高度の山ですが、8000m峰の中では比較的登りやすいとされている山で、エベレストに登る人が高度順化のトレーニングに登ったりする山です。
しかしそれはノーマルルートの話で、登り方によっては難易度も変わるわけで。山野井さんは誰も登ったことのない壁をソロで登ったわけです。当時ヒマラヤ8000峰の新ルートをソロで開拓した人間は3人しかおらず、その4人目、日本人では初の偉業でした。
山野井さん登攀の選択基準は、高さや一般的な知名度ではなく、壁の難易度。新ルートの開拓にあります。
当時、先鋭クライマーにとっての「絶対の頂」はエベレストにはなく、マカル―西壁でした。
まだだれも登頂したことがない「ヒマラヤ最後の課題」です。
山野井さんはマカル―西壁を目標に掲げます。
入念な準備とトレーニングを重ね満を持して挑戦。
しかし、7300m付近で落石の直撃を受けて敗退。それ以前に今の自分の力量とソロでは登れない壁だったと悟り、以降はその他のヒマラヤ難峰に次々と挑戦していきます。
時にソロで、時に妙子と2人で、時にポーランドの友人と3人で。
しかし敗退が続き・・。(K2峰南南東壁単独無酸素最速登頂などの成功もあるが)
マカル―西壁以降、どこか迷走しているような、晴れない気持ちの中で出会ったのがギャチュンカン峰です。ギャチュンカン峰はヒマラヤ8000m峰14座に僅か数メートル及ばない、高さでいえば15位の山です。「8000m峰14座制覇」とか「7大陸最高峰」とかを掲げる登山家には全く意味のない山で人気もありません。山野井さん自身もノーマークでした。しかし、魅力的な大岩壁があることに気づき、「功名心」に縛られず、純粋に岩登りを楽しめそうな、久々にここだという思いがありました。
後半は、そのギャチュンカン峰登攀の様子がまるで小説のようなダイナミックな展開と緻密な臨場感で描かれていきます。
これ、ホントにノンフィクションか?
いくら取材をしたとはいえ、他人の心理をそんなに明確に言い切れるか?
などと、思いつつもグイグイ引き込まれていきます。
登攀技術の詳細さ、どんな状況でも冷静に対処する心理描写には、圧倒されます。
例えば山岳小説で悪天候に見舞われホワイトアウトするようなところでは身動き取れず、何日も停滞を余儀なくされ、そこが高所なら酸素や食料との戦いとなっていく。
というシーンがよくあるんですが・・
山野井さんはどんなに悪天候だろうと、ホワイトアウトしようと、高度障害で目が見えなくなろうと、幻覚を見ようと、決して停滞はせず、なにがなんでも前に進むんです。
え?マジかよ!と思ってしまいましたが。
山岳小説ならもう絶体絶命のピンチの場面でも、冷静に乗り切る筋道を立てて進み続けるんですよね。
この圧倒的な壁を前にして、登るための一歩を踏み出せるかどうかは、勇気の問題である以上に自分の力量に対する信頼の度合いによる。自分の力量を信じられたとき、押しつぶされそうになる恐怖に耐え、一歩を踏み出すことができるのだ。(本文159Pより)
山野井はさらに降下を続けようとした。眼はまったく見えなくなっている。そこで妙子にハーケンを打たせようとした。妙子の眼も見えなくなっていたが、山野井に比べればまだかすかに見えていたのだ。しかし、もともと、指が短いうえに、残っている指も寒さで凍り、言うことをきかない。(本文242Pより)
もうね、「ストイック」とか「孤高」とか「矜持」とか、そんな言葉をつかって表現することが陳腐に思えます。
ただひたすらに好きな事を追い求める。
そのための準備を地道に積み上げる。
そして挑戦する。
成功しても。驕らない。
失敗しても、最後の最後まであきらめない。
再び立ち上あがる。
過信もせず、慎重になりすぎず、その時の自分の力量を冷静に測り、
経験を信じて、挑戦への一歩を踏み出す。
これ、特別大それたことをしているわけではなく、
人としてかくあるべき本来の姿のように思えます。
しかし、街中で生きる我々は、なかなかそうは生きられていません。
好きな事を追い求める。
たったこの1行がどれだけ難しいか・・・
ところで山野井さんはヒマラヤの遠征資金を、一切スポンサーから支援を受けず、自力で稼いでいます。その主な収入源は冬場の富士山の荷上げの仕事でした。
奥多摩の山奥で自給自足のような生活をしながら、普段の生活費は切り詰めて、収入のほとんどをヒマラヤ遠征資金に充てます。
そういう事情もあり、ソロで登り、夫婦で登り、誰の意向にも左右されず。
好きな山を好きなように登ることができたのでしょう。
それが正しいとか、上とか下とかいうのではなく。
一つの生き方として、私は惹かれます。
という話でした。
