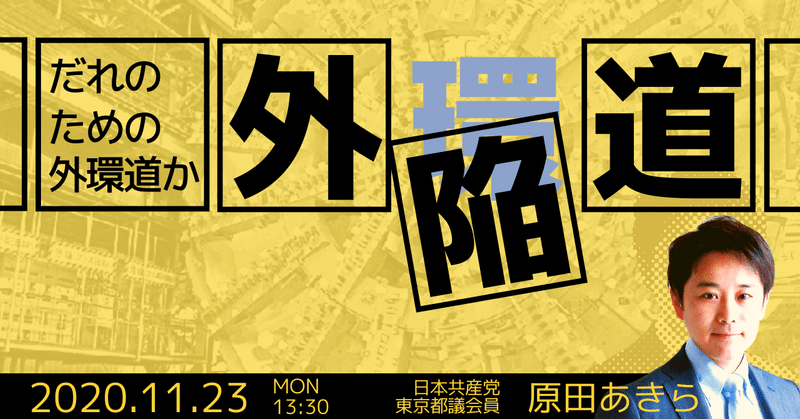
外環道をわかりやすく解説してもらった
ちょっと前の話になりますが、そう…我が家に猫さんが来た日の翌日である11月23日(月・祝)に、調布市で外環道にともなう陥没事故についてのタウンミーティングを開催したんです。その際のドタバタやアレコレはいろいろあるのですが、それは次回に譲って今回は、原田あきら都議によるお話をもとに、外環道工事は何が問題か?をおさらいしていこうと思います。だいたいこちらの動画に書いてあることをなぞっているだけなので、見ていただくのが一番良いのですが、なにせ40分もあるのでこういうのがあってもいいかなと思った次第です。わかりやすさでいうなら動画がベストです✨
1.10月18日の陥没事故は前兆だらけの事故だった
NEXCOの社長は謝罪をしつつも突然の出来事だから予測不可みたいなことを言っていましたが、シールドマシンが発進してからというもの地下水の噴出、酸欠空気の発生、騒音や振動といった地上への影響は前々から発生していて、そのことについて住民のみなさまは不安を訴え、日本共産党都議団や市議団の皆様も抗議し、原因の究明と安全確認、工事の中止を要請していました。でもしなかった。そんな中で発生した事故なのです。だから、NEXCOはこの問題についてしっかり対応する責任があります。
2.NEXCOに対して求めてきたもの
こういう大規模な公共工事では情報公開は欠かせません。モニタリングデータ、管理基準値、屈伸日報、地表面高さの推移および避難計画を住民の方々は求めてきましたが、そのどれもが公開されていません。
避難計画については「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」というパンフレットのようなものを作成しました。が、その中を見るとどのような場合にどういう対応をするのか、どうなったら緊急事態なのか、その緊急事態に何をするのか、ざっくりとしか記載されていないのです…
3.10月18日の陥没事故の話

この時の事故の様子は前のエントリーに書きました。今回は都や事業者の対応の??なポイントを記していきたいと思います
◆ 陥没発見から、担当者が現場に到着するまで3時間以上かかる
◆ 警察と地元自治体に連絡したのは都や事業者ではなく住民だった
◆ 陥没発見から、周辺住民に避難指示するまで4時間かかる
◆ 緊急時に拡声器を使って注意を呼び掛けるはずの緊急車用が走らない
◆ それを原田都議が議会で追及すると、なんと今回の事故は「トンネル工事の安全・安心確保の取組み」上に記載の緊急時には該当していなかった
4.陥没事故を経て改善したこともある
この事故を受けて、都議会で質疑が盛んにおこなわれ、また市議さんや住民のみなさまによる訴えもあり、対応が改善されたこともありました。
◇ 改めて、この地域のボウリング調査を徹底する
◇ 音響トモグラフィを使用して、道路だけでなく住宅街の地中も調査する
◇ GNSS(衛星を使用した計測)を利用して地盤面高さの測量も開始する
ただ、まだ始まったばかりですし、この結果もあますところなく情報公開してくれないと不安は解消されないので、見守っていく必要があると思います
5.空洞発見はどうやっておこったのか
本来は陥没した箇所を調べたかったけど、まだ陥没の影響が残っている場合、機材や人員が落ちてしまう危険性があるからその周辺をしらべることにした。そしたらそこで空洞がみつかった(二か所とも同じ理由)
この記事のたとえが分かりやすいのですが、新幹線の一車両分に相当する空洞が、地下4mにあるわけです。これ…もしどこかのお宅が地下室をつくろうって工事したらズボッと抜けてしまうなんてこと、あるんじゃないですか?

なんと恐ろしい…彼ら(事業者)の万が一にも起きないと言っていたことを軽く超えてきてしまう、本当に危険な状態であるということを理解して真摯に対応してもらいたいです。しかも11月2日の空洞発見時には、その日に発見したにもかかわらずなぜか情報を伏せ、4日に発表するという、まさに「底抜けの隠蔽体質」であることがまた露見してしまったのです。そんなんではもう任せられんですよ。。。(この辺まで動画で言うと15分辺り)
6.都「第一義的には国等事業者」という無責任を正そう
というわけで事業者まかせにしていては不安すぎるので、東京都や調布市世田谷区などの自治体にも主体的に計画に関わってもらって、安全性を確保してほしいのです。というか本来そうあるべきなのです。なぜならば…
◆ 都市計画法 80条
80条 都道府県知事に、報告を求めて勧告もしくは助言をする権限がある
81条 ひどい事業者に対しては事業認可の取り消しを行うことができる
82条 都道府県知事または指定自治体は立ち入り調査権がある
◆ 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)
7条 国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会を組織する
7条の3 協議会は、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる
7条の4 協議会は前項に規定する者以外の者に対しても、協力を依頼できる
7条の5 会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない
これらを見ると、完全に当事者であり、同時に大きな責任を負っている存在だということが確認できると思います。さらに、この外環道という事業に関しては、「東京外環トンネル施工等検討委員会」という第三者?委員会まで組織されているのです。そこでモニタリングデータや掘進日報などの各種データをチェックしているから、安心安全を確保できている、という答弁とされていたというのですが…こんなことが判明しました
◆ メンバーはほとんど事業者の関係者であり、自治体からの参加者はただ一人しかいない(東京都建設局 三環状道路整備推進部長)
◆ その部長は委員会の会議に参加していても、住民側の要求を主張しない
◆ その部長は2年に一度変わり、情熱も専門知識も期待できなさそう
◆ その部長は歴代7名全員が前職国交省の役人である
◆ その部長達は、形式だけの参加にすぎず、国の言い分を伝える役割しか負っていないのでは?
そんなことを追及しているのがこちらの動画になります。はぁ(ため息)
更にこの「東京外環トンネル施工等検討委員会」には大きな問題があります
◆ 委員会の有識者たちは、事業者から安全安心な施工が行われているという報告を受けている→何もデータを見ていない
これぞまさにトンネル委員会ですよ 一刻も早く改善するべき問題だと思います。というかその状態で、よくいままで工事してきたなと戦慄しました…
批判を受けて新たに立ち上げられた、トンネルの構造、地質・水文、施工技術等について、より中立的な立場での確認、検討することを目的として「東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会」もあるのですが、そこもメンバーがもとの委員会とほとんど変わらない、という謎の事態に…
住民の側にたった第三者の有識者会議を作ることが急務だと思います…!
ここまで半分きたので、いったん公開しようかな(*'▽')
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
