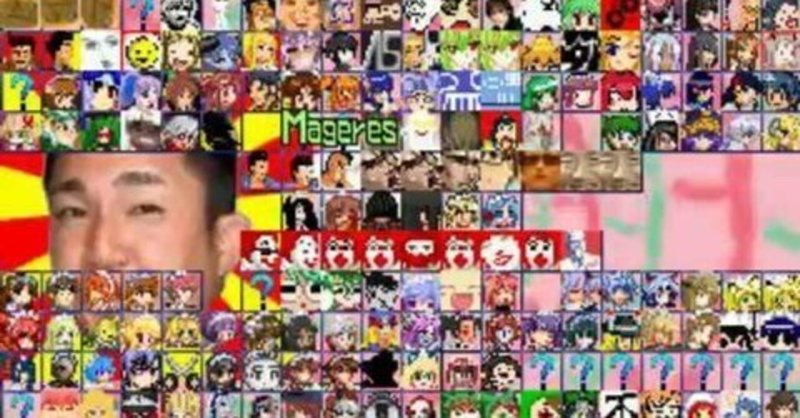
俺と格闘ゲームの話 13 ~同人格ゲー文化、花咲く~
1,マイナーになった格ゲーの世界
格ゲーは俗に90年代後半から段々と落ち着きを取り戻し、00年代には完全に下火になったと言われる。これは今までクソガキが段々と小学生の頃あれほど遊んだ格ゲーに見向きもしなくなっていったのと一緒だ。クソガキも思い入れがなくなった後も細々とやっていたがもうストZERO2とKOF97あたりの記憶を最後にぷつりと糸が切れている。
思い出す程度だと、ストリートファイター3はコンシューマ移植されなかったこと、後KOFは飽きられつつあるのに主人公の草薙京を外したのが割ととどめだったように思う。
SNKに関しては月華の剣士、武力ONEなどの意欲作があったがただでさえゲーセンのないクソ田舎では知られることもなく、コンシューマも餓狼伝説wild ambition、ポリゴン版サムライスピリッツと色々試していたが、それらをやっている人の話を聞いたことがない。
また当時はバーチャファイターの成功とそれに伴う3D格闘ゲーム普及の流れが非常に強く、カプコン、SNKのみならず他のメーカーも軒並みその道を探していたように思う。
バーチャファイターという道を切り開いたセガもファイティングバイパーズなどで進化を目指していく。カプコンだとスターグラディエーター、ジャスティス学園。SNKは前述した餓狼伝説やサムスピ。ナムコ(現バンダイナムコ)は現在3D格ゲーの主流になった鉄拳やソウルキャリバー。タムソフト(販売タカラ)の闘神伝。テクモのDOA。イマジニアのFIST…。
とにかく多種多様の3D格ゲーが出た。RPGばかりだったあのスクウェアでさえトバルNo1、エアガイツなど作っている。
粗製乱造だったために一気に冷え込むことになり、バーチャファイター、鉄拳、DOAが生き残りをかけて戦い、現在の鉄拳一強というスタイルになっていくのだが、それは10年ほど有する。
説明するのもあれだが、2D格ゲーと3D格ゲーの大きな違いを説明しておく。特に現在は2D格ゲーも3Dポリゴンで表現しているからその違いがイマイチピンと来ていない人だって多いはずだ。
簡単に言ってしまえば2Dと3Dの大きな違いは必殺技の有無だ。
2Dはアニメ手法を取り入れていた時代の作品であり、対戦ステージの中でどうキャラクターが面白く立ち回るか、がメインストリームになっている。
例えば現実にはありえない波動拳が飛ぶことが当たり前で、特定のコマンドを入力すれば特定の技が出てくる。それが2D格ゲーの大きな特徴だ。
3Dになると2Dを受けて制作されたこともあってか、そういった特定コマンドの入力による必殺技というよりは、攻撃のコンビネーションの組み合わせで相手と戦っていくスタイルのものがメインストリームとなっている。
そのため攻撃は基本的にパンチとキックのボタンをメインとし、特定の入力をして必殺技を使って、みたいなことは少ない。十字キーで相手の動きを見ながら攻撃を指してコンビネーションを重ねてダメージを与えていく。それが3Dの基本だ。
勿論これはあくまで一番手っ取り早い考え方というものであり、2Dでもコンビネーションを取り入れた作品は多く、特に00年代に大流行したコンボゲーというのは3Dのコンビネーションシステムを強く意識したヴァンパイアシリーズやサムライスピリッツ天草降臨など90年代の3D格ゲーショックに対応した作品を受けたものが多い。
一方で禁煙は3D格ゲーにもストリートファイターの豪鬼や餓狼伝説のギースを自社の格ゲーに組んだり、DOAのジャン・リーのように3Dでも単体の攻撃があったりするなど、必ずしも2Dとは独立しているというわけでもない。
お互いが意識し合う関係なのだ。
でもそんなことプレーしていない人間にはどうでもいい。
むしろ色々ありすぎるうえ、各々の格ゲー観があるから本当にとっつきにくい。
「格ゲー=ストツー→コマンドで必殺技を出すもの」という人がいれば、「格ゲー=バーチャ→コンビネーションで攻撃していくもの」という人がいるため、それが分かり合うのは相当時間を要するのだ。
そういうのもあって、本当に格ゲーというのが色々敷居を高めてしまったのがプレイ人口を減らした遠因の一つなのだ。
2,マイナー=悪いってわけでもない
とはいうものの、マイナーになったからといって火が消えたというわけではない。むしろ妙に濃くなっていた。
当時格ゲーブームにのまれた俺達昭和最後辺りの世代よりもうちょっと前の世代。昭和50年代生まれくらいの、思春期に格ゲーブームにぶち当たった世代にはもう格ゲーが自分の青春というレベルに仕込まれた奴らがいる。
子供の頃「大人になったら格ゲーを作る」と考えていた人間が、ブーム衰退と共に行き場をなくしてしまい、仕方なく社会人をしていた大人が多くいた。
そういう夢折れた思春期ボーイに与えられたアイテムがwindowsなのだ。
それ以前からもマイコンという形でゲーマーの行きつく果てはパソコンだった。これは俺も経験したことないので知識や多分の想像も含まれているのだが、今と比較してもコンシューマ機というのは力がなかった。
クソガキの頃触れたスーファミ用格ゲーなんてのはあくまで格ゲーをやる人用ではなく、俺達のようなキャラゲーとしての格ゲーが好きだったクソガキ用みたいなところがあって、アーケードと比較しても何かしらの違いがあった。それは容量不足からくる省略とかそういったものがあったからだ。俺達や年上のおじさんたちが妙に筐体とかの話をするのはコンシューマ機よりも容量もパワーもあって表現の幅が多かった時代の名残みたいなものがある。
表現の枠を求めていくとコンシューマで出来る事も限られてくる。かといって筐体を置くのは無理だ。
そこでPCー98などのマイコンに行きつく。そこで言語習得し、バイナリを駆使しながらゲームを組んだり、コンシューマ機より圧倒的に演出度が上がったゲームをしていたのだ。この歴史はパソコンが生まれた今昔変わらない。
だが、全然手ごろじゃなかった。
家電店にパソコンが本格的に置かれ始めたのは結構後。windows95の販売を待たなければならなかった。恐らくパソコンも扱っていたとは思うが、さほど大きくは扱われていないように思う。ここは記憶が薄い。むしろゲームソフトやゲーム機の方が面積が多かった記憶が強い。なんだかんだテレビがまず強かった。
そんな感じだったからパソコンがどこの店でも見られるようになったのは00年代を過ぎてから、という記憶がある。これは都会と田舎では大分差があると思うが。
90年代の秋葉原はパソコン自作組はこの辺りを生き抜いた男達の話である。前回話した「ときめきオーバークロック」はこの時代の住人の話だ。
そんな時代の中に格ゲーへの未練を残したまま、手に入りやすいwindowsやappleといった、手に入りやすいパソコンが生まれた。それによって企業が作っていた格ゲーが段々個人や有志の集ったサークルによって開発されて行く。
これで00年代から、同人を中心に格ゲーを作る人々が生まれ始めた。
マイナーになった事と作りやすいツールが整う事で企業から個人、サークルが作る時代にもなったのだ。
3,同人格ゲー台頭
個人やサークルがどこでそれを発表するようになったかと言えば、ご存じ現在はニュースでも取り扱われるようになったコミックマーケットなどの同人即売会。
特に有名なのは渡辺製作所(現フランスパン)が作成した「The QUEEN OF FIGHTERS」シリーズ。これはエロゲ―発から一般まで登ったLeafの作品「To heart」というゲームのキャラクターに格ゲー的要素を振って戦わせた作品。血脈的にはセーラームーン格ゲーのようなものか。ストーリーというよりはキャラクターが波動拳や昇竜拳といった必殺技や、そのキャラクターを象徴するアイテムを必殺技として駆使して戦うパロディ作品だ。
また黄昏フロンティアが作成した「Eternal fighter ZERO」シリーズ。こちらは同じくエロゲ―発のkey作品「kanon」「Air」シリーズのキャラクターを戦わせたパロディ作品。前者と同じく戦わせる意味というよりは知っているキャラクターが対戦格闘ゲームで跳ね回って戦っている作品と思ってもらっていい。
こういった熱意ある若者たちが自分たちでプログラムを組み、各々の「面白いもの」を組み合わせて物を作っていく同人ゲーム時代を担う一つとして格ゲーがあったのだ。
それ以外にも商業的に作っていないものも多々あり、2000年代初頭にふたば☆ちゃんねるで流行ったキャラクターを格ゲーキャラに作り込んで戦わせている元祖才能の無駄遣いと言われる「虹裏格闘ゲーム」
キン肉マン愛が高じすぎて原作に出てきたキャラクターを格ゲー化した2D格ゲーツクールソフト「マッスルファイト」など今でも作られ続けている作品がある。
現在では版権ギリギリなところも含めて「MUGEN」などが有名だが、これらの血を脈々と受け継いでいると言える。

勿論これらの作品には著作権という問題が付きまとっているのだが、それを黙認しているのが同人文化というものでそれら各々の問題は個人が負うべきものであり、言及するつもりはない。
だが、そういった熱意ある若者が多くおり、我々もwindowsを通すことによってその世界に触れる事になっていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
