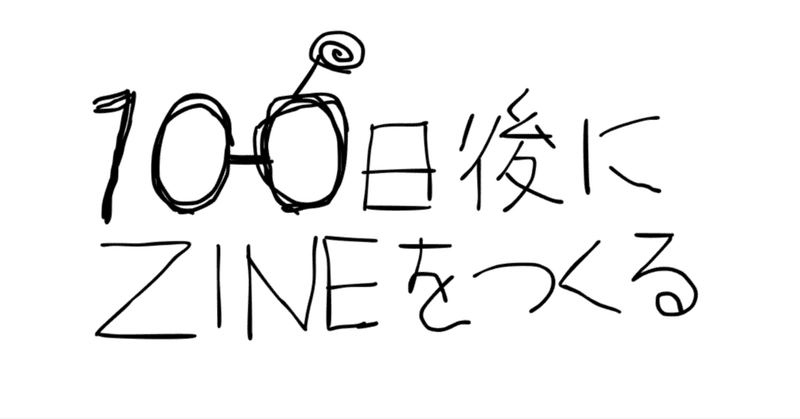
OSO18_100日後にZINEをつくる、78日目
年末に再放送した『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』を観る。
OSO18(読み:オソ・ジュウハチ)
道東で2019年からことしにかけて合計66頭の牛を襲ったオスのヒグマ。最初に牛が襲われた標茶町オソツベツという地名と、当初、足の幅が18cmあるとみられたことから名付けられた。
本来、植物食であるヒグマが牛を襲い続け「怪物ヒグマ」と恐れられたOSO18。人間への警戒心が強く、罠を見抜き、「食べる」以外の目的でも牛を襲っていた。2023年の夏、OSO18が突如牧草地に現れた。逃げる様子も見せずに寝そべっているところを、あっけなく銃殺された。
ものすごいドキュメンタリーだった。堆肥の山を漁る取材班の執念もすごいし、現代の研究所の分析精度にも驚いた。そして、そこから導かれた結論に、なんとも苦い気持ちになる。
人間が守り、増やしてきたエゾシカ。
人間が原生林を切り開き、放牧してきた乳牛。
それらを食べ、肉に依存するようになったOSO18。
一度それを知ってしまうと、自分の命によくないものであっても「依存してしまう」のは、人間に限ったことではなかったのか。
いったん(肉食を)学習してしまうと、それをずっと繰り返す。執着してしまう。行動が変わってしまう動物ですので、そこから抜け出せなくなってしまって、自然本来の行動を失ってしまった。
=省略=
これがもし人の手によって、そうなったんだとしたら、このクマは非常に不幸なクマだったと思います。
人一倍警戒心も強く、罠を見抜く鋭い勘があるにもかかわらず、「肉食」以外の選択肢を失い、野生としての生命力を全うできなかったOSO18。そしてOSO18が死んでも、このまま何も対策をしなければ第2、第3のOSO18が現れる。「怪物」の登場は、生態系におけるバグではなく、人間のつくる仕組みの中で生産されたものだった。
この番組において何よりもゾッとするのは、東京のジビエレストランにOSO18を食べに来たカップル(?)の台詞。
「野生を味わうみたいなもので、いちばん強いものは何かって、OSO18であると。不思議な感じがします。あんまり味に特別感がないところも含めて、ちょっとあっけない最後だなって感じはします。」
「牛の無念を晴らしたぜ!みたいな 笑」
普段ジビエに親しみのないわたしの偏見によると、ジビエって、「自然と共に生きる」とか「命に感謝」とか「SDGsに貢献したい」界隈の方々が好んで食べるものなんだと思っていた。(あと、希少性に興奮する人とか)
しかし、「野生を味わいたい」「強いものを味わいたい」という、そんな感覚があったのか。一体彼はOSO18の肉に、どんな特別な味を期待したのか。そして熊の肉を食べながら「牛の無念を晴らしたぜ!」と笑い合える彼ら。無念の「む」の字も知らないであろう人間が、鶏を食い、豚を食い、牛を食いながら、牛の敵をとるためにヒグマを食べる。
わたしはまだ自分が何に不快になって、何をおぞましいと感じたのか上手に言語化できていない。ただ、OSO18の腫れあがった手と、息絶えた瞳が目に焼き付いている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
