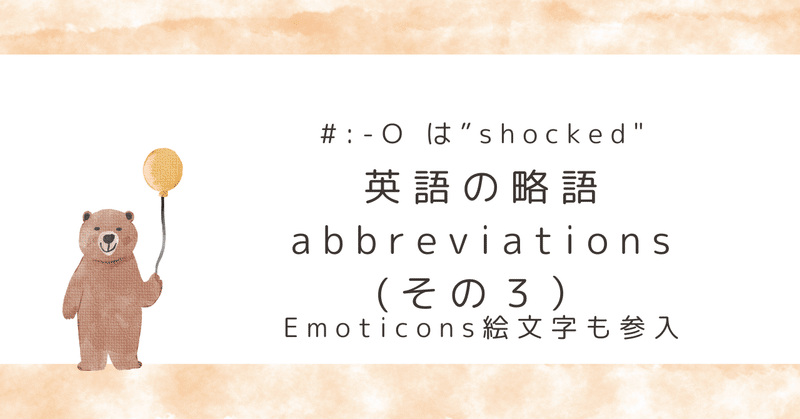
英語の略語abbreviations:頭文字語acronyms, 端折りclippings, 混成語blends(その3)...Emoticonsも参入 #:-O は"shocked "の略?
(その2)の続きです。
現在インタネット上で飛び交っているabbreviationsは?Quirkらの文法書には存在しなかったものが急増する予感
それはともかく、現在インターネット上ではどのようなabbreviationsが飛び交っているのか気になるところです。"Internet"の項目にリストされているabbreviationsを覗いてみましょう。サブ項目の"Blogs" "Chat" "Domain Names" "Emoticons" "Twitter" "Websites"などは、現在の日常コミュニケーションに浸透していますが、Quirkらが上記の文法書を執筆した当時には存在しなかった項目です。しかも始まったばかりで、これからもグローバル規模、爆発的に増え続ける予感がします。特に"Domain Names"のサブ項目ですが、その"Acronyms&Abbreviations"には、本稿執筆中の2018年2月19日現在で178件しかリストされていませんが、実際にはそれでは収まらない数があるであろうことは容易に推定できます。
今後もネット社会が続く限り増え続けるでしょう。同じことは上記の表中の"HTTP"や"MIME"の両サブ項目(*11)についても言えそうです。インターネットがもたらしたグローバル規模の情報化は、明らかに、グローバル英語に大きな変化をもたらしています。これらのサブ項目のabbreviationsの量の増大に伴う質的かつ機能的変化もその一つです。Quirkらが上記の文法書を書いた時は、明らかに語形成(word formation)上、すなわち、形態論的には、abbreviationsはそれ程の例もなく、この膨大な文法書の最後のAppendixの一部を割いて書く程度でした。(*12)
DIYのように文や句からできたacronymsの派生過程
とりわけ目立つのは、Quirkらの分析では[A][i]typeの内の"DIY"に代表されるacronymsの大量発生です。ちなみに、"DIY"の元は"Do it yourself."という文のacronymですが、その派生過程を辿ると、先ずはハイフォンで繋いで"Do-it-yourself"にして一種の複合名詞(a compound noun)に、更に"DIY"というacronym、すなわち、単純名詞(a simple noun)に削ぎ落としたものです。文→複合名詞→単純名詞という派生過程(derivation process)を経ています。特に"Chat"のサブ項目に集めらた"DIY"型acronymsに注目です。速記では話す速度に追いつくために簡素化された略字表記が使われますが、キーボードを叩きながら会話するのですから、abbreviationsが多投されるのは自然の成り行きです。
Chatをクリックすると、最初のページにある"Let’s meet in real life."を略した"(L)MIRL"とか、"Out of here" を略した"OOH"など、文や句をそのままacronym化したものが多々あります。同じように文から派生した"DIY"は機能的には抽象名詞ですが、これらは、元の文や句そのままの文法的機能を保持しています。すなわち、前者は文としての機能、後者は場所を表す副詞的機能を保持しているのです。スピードを求められる"Chat"に特に多そうですが、"Blog" "Twitter" "Websites"のサブ項目にも似たような例が並んでいます。全部細かくチェックできませんでしたが、
“Common Acronyms-Abbreviations and Acronyms- YourDictionary”
"50 Popular Internet Acronyms" In "What is the difference between Abbreviations and Acronyms?",50 Popular Abreviations and Internet Acronyms"
などのサイトに列記されているacronymsがそれらを代表しているものと思います。
数字や絵文字も参入か?日本のemoticnsなどがあまり言及されていない
更に、これらインターネット上のアプリケーションで展開されるacronymsが、文字表記のみならず数字や絵文字や絵で表記されるケースも爆発的に増えていることは興味深いですね。こうした現象を理解するには、言語学、記号論、media論、社会学、文化論、心理学、認知論、AI、脳神経学等々のコラボレーションが必要になるでしょう。Multimedia機器は、かくしてacronymsの世界には多量の"Emoticons"(Emoticons)のサブ項目にリストされているemoticonsが参入しました。これもQuirkらの文法書は触れていません。こうした非言語記号のacronymsは、言語記号のacronymsと質的、機能的にどう違うのでしょうか。インターネットが普及する前から、1960年代後半には若者の間でピースマークのロゴやニコニコ・マークのロゴなどがありました。世界中の若者文化の中でミーム(memes)として、お互いの仲間意識を高める為に爆発的に伝播していきました。これらのサブ項目に派生した言語と非言語のacronymsは、インターネット普及以前のそうしたacronymsを引き継いだものでしょうか、あるいは全く別物なのでしょうか。
余談ですが、この私的サイトは一応世界中にオープンされ書き込み自由のはずです。しかし、"Emoticons"の項目に、日本の若者の間でミーム的に広がり愛用されている、量質ともにリッチで想像力豊かな絵文字がリストされていません。日本のポップ・カルチャーは世界的な人気を持ち、相当数のそれに関連するemoticonsが普及しているはずです。さて、今回は、Quirkらのabbreviationsの3つのカテゴリーの内(1)Acronyms以外の残りの2つのカテゴリー(2)Clippingsと(3)Blendsについてあまり言及できませんでした。前者のclippingsは語句を切るだけですので比較的簡単に作れますが、blendsは意味論的ブレンドと語呂合わせが必要で簡単に作れません。多分clippingsはそこそこ増えても、手間の掛かるblendsはそれほど増えないと予測します。但し、それは英語の場合に限って言えることかもしれません。
漢字と仮名表記の日本語のabbreviationsは英語のそれとは基本的に違う
漢字と仮名表記の日本語では状況が違うでしょう。漢字の音読みとカナはそれぞれ1音節の独立ユニットです。ラテン語のモーラに近く、それぞれがかなり音韻的にも視覚的にも確立しています。英語のabbreviationsの基本となるシラブルはそれに比べると不安定です。しかも日本語では古くから4文字熟語が根付いており、日本語話者はその旋律に沿ってclippingsとblendsを作ることに長けています。多くのテレビ番組などや人気グループ名がこうして簡略化されていますね。例えば、筆者が最近耳にしただけでも「リハーサル」→「リハ」、「ヤフーオークション」→「ヤフオク」、「花より男子」(コミック)→「花男(ハナダン)」等々枚挙にいとまがありません。最後の例はclipping + blendということでしょうか。日本の若者は、acronymsのみならずclippingsとblendsを生成し、同じ文化を共有する仲間の間でミームとして伝播させ、仲間意識を高めています。それが今や世界中に広まりつつあります。
英語の世界、否、言語の世界は変化し続けています。実際に使わなければそれについて行けません。英語も含め、日本語も他の言語も、言語は教室やテキストの中にあるのではなく広大な外にあることが分かると思います。使える言語は参加して使い続けなければ身につきません。今回のabbreviationsという現象を通しても、実際にabbreviationsを理解し使えなければ日常のコミュニケーションに付いていけないということを感じるはずです。それは街の会話から高度の専門領域の意見交換においても同じです。いずれのレベルにおいても多くのabbreviationsが生成され続けています。(2018年2月20日記)
後記 生成AI普及で激増化?
2018年に執筆したものです。現在は生成AIによるChatGTPが普及しはじめました。大変な数のabbreviationsが出現するものと予測できます。
(*11)ここではThe meme typesのことです。“The Complete List of Meme Types”参照。Richard Dawkinsの提唱した、ある特定の文化の中で人から人へ広がって行くアイディア、行動などを指すmemes(the internet memesなど)ではありません。
(*12)筆者は1980年代に欧米約20名の研究者らと共著でA User's Grammar of English: Word, Sentence, Text, Interaction(1989, René Dirven, ed. Verlag Peter Lang, 959 pp.)を出版しました。Word Formation でabbreviationsに触れていません。筆者はModality:English modalの担当で定かではありませんが、議論さえなかったと記憶しています。1980年代中盤当時あまりproductiveな現象ではなかったからです。

上記は掲載時の情報です。予めご了承ください。最新情報は関連のWebページよりご確認ください。
サポートいただけるととても嬉しいです。幼稚園児から社会人まで英語が好きになるよう相談を受けています。いただいたサポートはその為に使わせていただきます。
