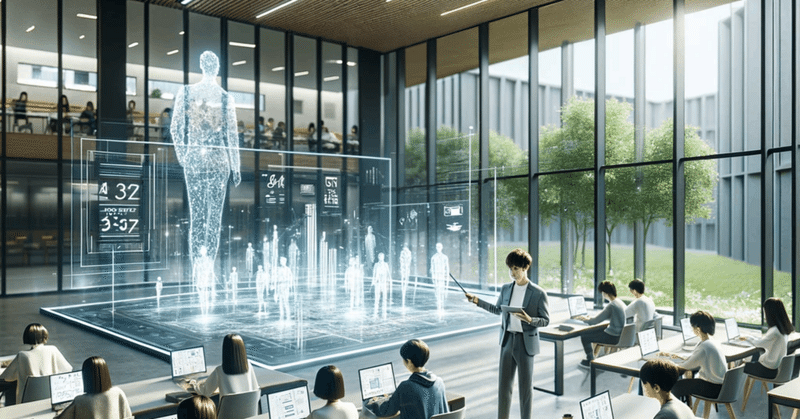
地方大学にいることの強みと弱み
最近,X(旧Twitter)で若手の研究者の発信をよく見かけるようになりました。別の先生も述べておられるように発信が増えることは,地方の大学で孤軍奮闘している若手研究者にとってとても良いことだと思います。なぜなら地方の大学では,社会科学系の学部が一つにまとまっていることが多く,私が専門とする経営学領域においても,教員がほとんどおらず1人か2人ということもうざらにあるからです。
若い研究者の投稿を見て自分が地方の国立大にいた頃の気持ちを思い出したので筆を取ってみた次第です。
1.3つの「焦り」
1-1. 知識ギャップの焦り
初任校として四国の国立大学に赴任した当時,大きく3つの焦りを感じていました。1つは,アクセスできる電子ジャーナルの少なさに起因する「知識ギャップの焦り」です。経営学はあくまでも社会科学系学問の一つにすぎず,閲覧できる電子ジャーナルもかなり限られていました。当時は経営学全般も教えていたことから,自腹でStrategic Management Journal,Administrative Science Quarterly,International Human Resource Management Journal,マーケティングジャーナル,日経ビジネスなどを購入し,多くの文献を文献複写で依頼をしていた記憶があります。
研究予算が必ずしも潤沢でなく,しかも四国という土地柄,学会参加やインタビューを行うためには基本的に飛行機を利用しなければならず,往復の飛行機代でかなりの研究費が持ってかれてしまいます。そうなると上記で挙げた雑誌の購入もなかなか大変でした。
1-2. 時間の焦り
2つ目の焦りは,「時間の焦り」です。あくまでも感覚的な話ですが,地方の方が時間の流れがややゆっくりな感じがしました。逆に都会に行くと時間の動きをかなり早く感じていました。例えば,大都市圏にいる先生の方がメールのレスポンスが早かったりであるとか,何かのお願いに対する対応が早いといった具合です。
その結果,自分の研究ペースが他の同世代の研究者と比べると下がってきていたりであるとか,遅いのではないかといった不安になることがありました。幸いなことに私は,東京に頻繁に出張していたこともありそうした時間のずれに関しては敏感であると同時に,意識的に気をつけた側面はありましたが,もしずっと四国にいた場合,少しずつ気がつかないうちに地方のゆったりとした時間に身をゆだねていたかもしれません。
ただ誤解のないように言っておくと,地方のゆったりとした時間を委ねるということは必ずしも悪いことではありません。じっくりと大きな研究を行うことができます。たくさんの文献を読むことでインプットをたくさんすることもできますし,例えば自分ができる調査手法を広げるといったこともできるかもしれません。
さらに学生も素直で優秀な子が多いです。当時はまだ優秀であっても,何らかの理由により地元にいて欲しいという親の願いかから,都心への進学をせずに地元にとどまって進学をしているというケースが一定数いました。その結果かなり学力も高い子が揃っているケースもありました。
1-3. リサーチサイトの焦り
3つ目の焦りはリサーチサイトの焦りです。ちょうどこの頃『組織科学』の編集幹事という論文の差配をお手伝いする仕事をしていました。そこでもやはり地方の大学に所属している先生は,その地域の企業を事例として論文を書いているケースが散見されました。
特に地方の国公立大学は,「先生」業として県庁や市区町村の仕事も含めた要請もあり,ステータスが高いと言えます。そのためリサーチサイトとしてインタビューの申し込みをすると受け入れていただける確率がかなり高く,事例を書くことも比較的容易であると言えます。
しかし,そこで問題になってくるのがいわゆる「一般化の問題」です。もちろん特定企業のケースを取り上げる以上,その時点で一般化から逸脱しているわけですか,それが地方の中小企業という話になると,査読者を納得させることがより難しくなります。そう考えると地方ではなく,都会にいた方が有名企業へのアクセスがしやすく,ビジネスケースを書くにせよ,事例分析の論文を書くにせよ,都会にいた方がフットワークが軽いなぁと感じることがありました(都心の企業の方が色々な研究者から問い合わせを受けても,そもそもインタビューを許可しないことが多いし,今となっては地方の中小企業であっても,書き方によっては査読者を十分説得できるのではないかと考えています)。
2.自分の研究ポートフォリオを知る
結局僕は,この国公立大学に3年勤務したのち,埼玉県にある私大に移動することになります。この3年の間に準備したことは以下の3つでした。
1. 博士号の取得(単位満期取得退学なので赴任の翌年に博士号取得)
2. 追加で担当しなければならない一般教養科目として
・「人材マネジメント」
・「経営学入門」
を設定し,転職の際に応募できる科目を幅広く設定できるようにしたこと。
(私が赴任した時の科目は「経営組織論」および「経営戦略論」でした)
おかげで次の転職先は「人的資源管理」および「組織行動論」をメインに「経営学入門」を担当することとなりました。
3.自分の研究ポートフォリオを知ること
特に3番目について記載をしておきたいと思います。図は,当時僕が考えていたものを最新版に少しアレンジしたものです。これは,私の博士課程の学生に用いているスライドの1枚で表側は学問領域,表頭はどの内容で論じているのかを表現したものです。例えば,HRMで定量分析の論文がある場合は,そこのセルには**(2024)が記載されることになります。
初任校に奉職するまでにどのセルの論文を埋めているのか,今後どこを埋めていくのかを意識しながら自分の研究を進めていくと行き当たりばったりにならないようになると思います。
さらに言うと,学問領域と分析の中身や手法という2つの軸だけではなく,分析手法(ツール)もあります。例えば定量分析では,SPSS,R,Stataなどがあるでしょうし,テキストマイニングのソフトもあります。そうした時にどこまで自分で分析手法で幅を持たせるかということも考えておく必要があります。

3. では何をすればよいか?
3つの焦りに対してでは何をすればいいのでしょうか?1つは,インプットを高めることに時間を費やすことです。もしくは博士論文を出版するというのも有力な方法の1つです。私は博士論文を出版するまでにとてつもない時間がかかってしまったので,初任校に赴任をしたのであれば,記憶も新しく,時間もあるうちに早々に取り掛かった方が良いと思います。
2つ目はデータアーカイブの活用です。地方の国公立大であったとしても,今はビッグデータもありますし,Pythonをはじめプログラミングを組むことができればスクレイピングによりWeb からデータを取ることができます。
また,HRMやOB(組織行動論)領域で是非おすすめしたいのが,SSJDAのデータアーカイブと,JILPTのデータアーカイブです。SSJDA(Social Science Japan Data Archive)は,東大の社会科学研究所の組織で政府や民間企業あるいは個人が集めたデータを管理し申請者があった個人に貸与している組織になります。JILPTは,労働政策研究・研修機構が過去に行った調査を申請をもとに個人に貸し出しているサイトになります。
SSJDA:https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/infrastructure/
JILPT:https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/archive/datalist.html
特にJILPTのデータはマッチングデータ(例:事業所人事回答+当該事業所の従業員3-5名回答など)が多いので,様々な分析にも耐える力があると思います。
2つ目は,ペースメーカーを作ることです。今にして思えば,学会が同窓会みたいな感じだったのかもしれないです。あとは,ゼミのイベントで他大学との合同ゼミを行っていたことで同世代の研究者と会う機会があったことも大きいかもしれません。合同ゼミが終わると,先生だけで街へ繰り出して最近の研究の話やお互いのゼミ生の話などをしました。特に私は東京の大学院出身なので,神戸大学大学院の先生方と知り合うことができたのは,後々の研究生活においても大変有意義でした。
追記
とはいえ,赴任初年度は授業立ち上げに多くの時間を費やすことになるでしょう。シラバス作成やスライドの準備等,大変だと思います。私の場合,副指導教官に相談したところ,過去の授業で扱った講義スライドを頂くことが出来て,いただいたスライドを基に準備ができました。本当に有難かったです。
ただ,当時の自分に言いたいことは,「もっと地元を楽しめ」ということです。美味しい料理や特産品,観光名所,イベントなど少し肩の力を抜いても良いのではないかとも思います。あとは健康への配慮です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
