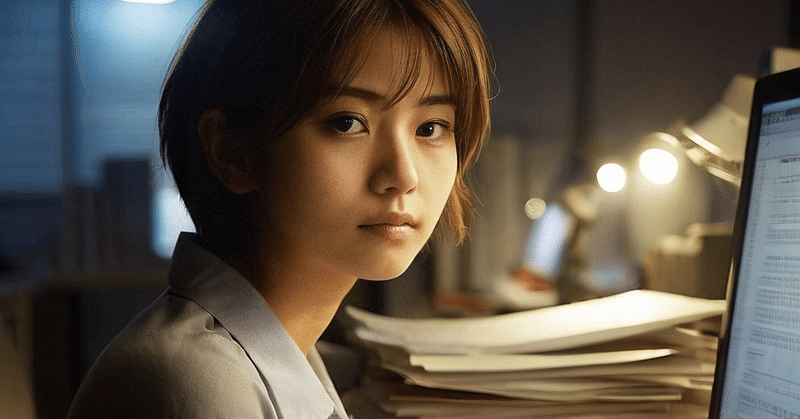
はじめは誰も仕事のことなどわからない
企業における日常活動(仕事の中身)は、教えてもらうことだけでは見えてこないからやっかいだ。
結論から言えば、新しいことをやっているわけであるから当然なのだが、学生時代と違い自分だけが見えていないのではないかと不安が大きくなる。
しかし、誰しもこのような不安感や幻滅感、あるいは焦燥感がある。
私のように見えすぎる(実際は見えていないのだが)と思っていた人間も、仕事に幻滅感をもった。
入社3ヶ月くらいで退職したいと同期に打ち明けた。
当然だが、引きとめられなんとかやっていけた。
同期がいなければ、間違いなくやめた。
仕事とは、学生時代のように単純な活動パターンでないだけに、同期や先輩などを通して「よく話をする」ことが一番だ。
そのうち慣れてくる。
慣れすぎもよくないが、先ず1年、次は3年だ。
キャリアを積んで転職しても上記を口ずさんでいた。
1年すぎると、不思議と3年続く。
また、経験した者からすると、どこの企業へ移ってもあまり変わりない。
目標は高いが、現実は厳しい。
レベルの低い仕事に幻滅するのは、当然なのである。
大事な仕事をいきなり新入社員にやらせる会社はない。
わかってはいたが(本当はわかっていなかった)、私は幻滅した。
毎日20件以上の飛び込み営業。
大学出てする仕事か、と。
馬鹿は、後でわかるのだが、非常に勉強できる機会だった。
人生、自分で勝手に結論だしたらいかんもんがある。
レベルが低い上司もどこにでもいる。
しかし毎日顔を突き合わせるのがたまりません。
あるとき、上司に完璧にほされて精神を病みそうになった。
不運としか言いようがない。
退職するか、適当に合わせてやり過ごすしかない。
上手く専務が気付いてくれて一難を免れたが配転された。
経理の仕事だが、年齢がいってからだったので、こちらも大変だった。
退職するつもりで、人材紹介会社を訪問すると、「その年齢で経理をやらせてもらえるなら3年程度経験してからでもおそくない」と言われ素直に従
った。
個人的には、不運でみじめに思えたが、その後の転職時に営業と経理のキャリアを買われることが多くあった。
経理知識が身についたことで自信を持ちすぎたきらがないでもない。
ほとんどの会社が馬鹿に見えてしまった。
世の中、上手くバランスがとれないものである。
仕事がみえない焦燥感は、私のように総務がやりたいと思ってやっている場合はあまり気にならないが、やりたくない仕事の場合に顕著だ。
当然、営業時代がそうだった。
若いうちであれば、やりたい仕事に移行(転職)という手もあるが、仕事自体は、どんな部署でも、先ずやりたくない仕事が山のようにある。(あった)
転職する場合、もっともやっかいなものは、なんといっても人間関係である。
仕事をやっていくための努力と人間関係は、どんな局面でもついてまわるから、難しく、この状況を乗り越えるための精神力が必須条件だ。
勤務時間の問題は、会社ごと部署ごとにかなり事情が違う。
新入社員時代の最初の3か月くらいは、さっさっと帰社して日報を書いて帰宅していたら、皆が帰る時間まで会社に居ろ、と言われた。
仕方なく帰社時間を遅くしていた。
後でわかったが、先輩達も同様に時間をつぶして帰社していた。
ホワイトカラーの生産性が低いはずである。
担当をもらって自分で業務ができるようになると、直行直帰でメリハリをつけた。
当然だが、仕事あらば早朝から取引先に出向き、夜でも仕事とあらば徹底的に仕事したが、可能な限りスケジュールを立て、早く帰宅できるときはさっさっと直帰した。
営業の場合、仕事しているかどうかは、取引先と結婚していれば女房が一番わかる。
会社の人間でなくとも、誰かが知ってくれているだけでよい。
管理部門へ移行(転職)してからは、新しい会社の立ち上げ業務であったことと、実務を実際に勉強することなどの必要があり、早朝、夜間、徹夜と、私の人生のなかで一番仕事をした。
まだ小さな規模だったので上司、役員すべてが理解してくれていた。
不思議なもので、採用してくれた元社長とは、今日に至るまで長いお付き合いが続いている。
管理部門時代、部下は仕事がない限り早く帰宅させた。
遅くまでやる企業体質は、社員もわかっているもので、それに応じた仕事の進め方をしている。
知らぬは、社長(特にワンマン)ばかりなのである。
このような企業体質でも、可能な限り早く帰宅させ自分も早く帰った。
この場合、仕事の中身で勝負するしかない、と一種の開き直りが必要だ。
結論は、ソニー子会社のようなマネジメントを行わなければ、企業と個人の成長はない。
自由度は高いが、決して早く帰宅するわけではない。
個人が仕事をきちんとマネジメントしているという主体性(一人称)ある仕
事をやっているだけだ。
上司もそのような姿勢をサポートするし、健康などよく心配してくれた。
楽しく自らがやっていたので長時間労働で健康を害するなど皆無である。
私は、確実に成長できた。
もっとも、今日安全衛生法上、会社は従業員の労働時間に応じた健康管理をおこなう必要がある。
私は、強制労働は嫌だが、自由な朗働であれば常にウェルカムだ。
ワンマン社長といっても、こちらが徹底的に仕事をすれば任せるものだ。
これもまた事実である。
要は、自分ということだろう。
管理職の立場で創業経営者などと仕事においてよい関係がもてない場合、なんらかのアクションを起こされる。
降格、配置転換、降給等、解雇(こちらは確実に退職できるからよいが)などの対応を取られた。
これをきっかけに(解雇以外でも)退職した。
理由は、その会社に執着してもビジネスにおけるドライな仕事関係ができないと、まともな成果は決してだせない。
仕事とは、ある面戦場だ。
腹をくくるしかない。
話が脱線した。
話を元に戻そう。
わけがわからない幻滅感や不安感、あるいは焦燥感は、先ず上司や他の人の話を聞いて素直に行動してみることが必要だろう。
若いうちほど、最初、どうしても頭で物事を考えてしまう。
考えること3に対して、行動7くらいの割合で行動を多くした方が良い結果がでる。
スポーツと同じで基本動作ができないのに、やたら本を読んでやってみてもまったくできないのと同じだ。
基本原理を早く体得することだ。
仕事は、頭も使うが、体でおこなうものだ。
営業も管理部門も同じだ。
心配しなくてもだんだん頭を使っていく割合が増えていく。
私は、いつも考えること1に対して行動が9だ。
これはこれで大問題だ。
治療しようとしたが、なかなかできなかった。
すべてやってられない幻滅感や不安感、焦燥感を払しょくするためには、企業のなかで同期や先輩の中で「コイツだ」という人間を捕まえることだ。
多分、私は、このような人たちから必死に仕事や会社について学びながら、なんとか仕事に対する幻滅感や不安感を取り除いてきたように思う。
今、その人たちとの付き合いはない。
人生とは、やはり自分なのだろう。
ただし、そのときどきに支えてもらえる人たちとの出会いは大切にしておくべきだ。
人が仕事で成長していくタイミングには、必ず他人からのサポートがいる、と私は体得できた。
現在では、社内におけるパワハラなどで、社員に過度な対応をしないことが多くなっており、若い人たちが成長していくためには、私たちの時代以上に自分で社内の人間をうまく捕まえて、仕事を知る、あるいは覚える努力がいるだろう。
息子をみていても思う。
入社後、すべての現場部署を担当させてもらい、本来の開発業務へ就いたのは1年後だった。
やはりぶつぶつ文句を言っていた。
その後、技術営業部門へ3年ほど異動し、また本来の開発部門へ戻っているが、技術営業部門へ異動したときには転職を検討していた。
企業からすれば、仕事の現実を学ばせるためのローテーションだが、このことは、入社から10年以上経て効果がでているように思う。
自ら試行錯誤しながら新たなことに挑戦しているからだ。
人間にとって仕事のコアをつくる作業には10年程度かかる、と私は考えている。
この点で息子たちは、仕事を覚えて自ら挑戦していけるスタート台にやっと立ったのだろう。
仕事とは、想像を絶するくらい長い基本と体験の積み重ねだ。
このゴールデンウィークに帰宅していた長男に聞いた。
会社に「この人だ」という人はいる?
二人いる、といった。
しっかりと仕事をやっていける理由のひとつだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
