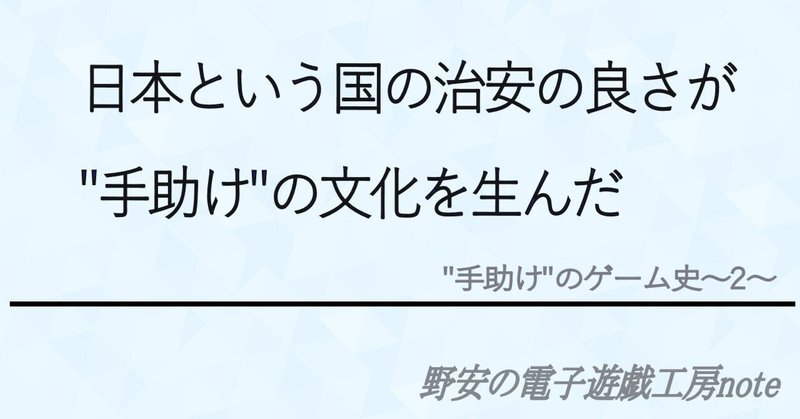
"手助け"のゲーム史~2~ 日本という国の治安の良さが"手助け"の文化を生んだ
上級者が、初心者を手助けしながらプレイする。
そんな仕組みがゲーム内に実装されるようになってきたのは、00年代あたりからだね――という話を、前回のコラムで書きました。
今回は、それよりも前の話です。コントローラーを介しての"手助け"の仕組みがなかった時代から、日本ではゲーマーが互いに"手助け"する文化が醸成されていたよね、という話です。
ものすごく有名な話から始めましょう。
1986年発売の『ドラゴンクエスト』は、プレイヤーが一定時間、何もしない(コントローラーを操作しない状態になる)でいると、画面の隅に「現在のレベル」を表示するウインドーか開きます。
なんのために開くのか。
背後から見ている人が、「いまのレベルを確認できるようにする」ために開くのだ、と言われています。
本当にそういう意図でそのような仕様になったかどうかは知りません。多くのウインドーを開きっぱなしにしておくと画面が文字だらけになり、画面がごちゃごちゃになってしまうので、何もしないときにだけ開くようにしたのかもしれません。
でも結果として、プレイしていない人(ふらりと背後を通りかかった人)がプレイヤーに話しかけ、プレイヤーが会話に応じる(ので、そのときは入力が停止される)と、画面にレベルが表示されるため、そこではこんな会話が発生することになるのです。
「おお。もうレベル〇なんだ」
「うん。△△の町の近くて経験値稼ぎしているところ」
「レベル〇なら、もう次の町に向かってもだいじょうぶだと思うよ」
背後にいる人が、より上級者(すでに先までゲームを進めている人)である場合、その人にレベルという情報が伝わると、的確なアドバイスを送ることが可能になるんですね。
『ドラゴンクエスト』の特徴のひとつは、このような「会話を誘発する」仕組みに長けていることだったりします。プレイした者たちの間で会話が生まれやすくなるよう設計されているんですね。その結果、みんなでアドバイスを送り合い、互いに情報を共有しながらプレイする楽しさが味わえたのです。
ひとりで遊ぶRPGというジャンルにもかかわらず、『ドラゴンクエスト』が大衆にヒットした理由のひとつが、ここにあるのです。
リアルタイムでプレイしていた人には同意してもらえると思うのですが、あの当時、なんか「みんなでプレイしている」という感覚が、たしかにあったんですよ。だから『ドラゴンクエスト』は社会現象と呼ばれるほどのヒットを成し遂げたのです。
こういった、互いに情報を共有することで「みんなでプレイしている」かのような気持ちになり、連帯感みたいなものが生まれることこそが、ゲーム黎明期の日本のゲーム文化の最大の特徴のひとつだと、わたしは思います。
いまでは世界がネットで繋がっていて、みんなで一緒にゲームをプレイするのは当たり前の遊び方になりましたが、ネットが普及する以前はそうじゃなかった。世界中のプレイヤーは、それぞれ個人で、こつこつとゲームをプレイしていたわけですよ。
でも日本は、ちょっとだけ違ったんです。
なぜなら、日本は、めちゃくちゃ治安が良い国だからです。
日本には、かつてゲームセンター文化がありました。各地にたくさんゲームセンターがあったのです。駄菓子屋の店先にゲーム機が置かれていることもありました。休日とか、放課後とかに、そこに小学生や中学生が集ったのです。
これは諸外国では考えられないことです。手元にお金を持っていることが確定している子供たちがたくさん集まるような場所は、あまりに危険すぎて、そうそう街中には作れません。もちろん地域差はあるので、あまり断定的なことは言えないですが。
とはいえ一般的には、海外のゲームセンターは、入場料金制の場所の中とか、デパートなどの一角とかにありました。国際空港とかにも、よく置かれていましたね。英ヒースロー空港で、ターミナル間を繋ぐ通路の途中にゲームが置かれていたのが有名だったように記憶しています。もう40年くらい前の話です。
いずれにせよ、犯罪者が、ふらりと通りかかるようなことないような場所に、アーケードゲームは設置されていたのです。子供が気軽に集まれるように場ではなかったのです。日本以外の国では、それが普通の光景だったのです。
でも日本では、街の中にたくさんゲームセンターが作られました。子供たちがゲームの周囲に群がりました。
すると、そこで出会ったプレイヤーたちは、互いに情報を交換するようになっていきました。このゲームをクリアするコツはこうだよ――といったアドバイスを、互いに教え合うようになったのです。有名なのは『スペースインベーダー』の「名古屋撃ち」とか、『パックマン』の攻略パターンなどですね。(若い世代の人たちは知らないかもしれませんね。検索してみてください)
こうして日本では、ゲームをより楽しむための情報が、プレイヤーからプレイヤーへと口コミで広がっていくようになります。みんなで協力して、互いに"手助け"し合う文化が生まれるんです。
そんなゲーム文化が作られてから、日本には家庭用ゲーム機は登場することになります。1983年にファミコンが発売されます。より厳密に言うと、任天堂は1977年に「カラーテレビゲーム15」(とカラーテレビゲーム6)というゲーム機を発売していますが、そういったところまで話を広げると大変なので、いったん無視しますね。
するとファミコンでも、ゲームセンター時代の"手助け"文化を引き継ぐかのように、いろいろな情報を交換する文化が継続されます。ゲームを楽しむための"手助け"になる情報が、ファミコンを持っている子供たちの間で駆け巡るようになるのです。
こうして生まれたのが「裏技」というカルチャーですね。
そんな裏技カルチャーの火付け役となったのは、やはり『スーパーマリオブラザーズ』の無限増殖でしょう。(こちらも、若い世代の人たちは知らないかもしれませんね。検索してみてください)
こんな裏技を使うと、ゲームがすごく楽しくなるよ! プレイが楽になるよ! といった情報を誰かが発見すると、それがあっという間にゲームユーザーの間で口コミで広がっていくようになったのです。
いずれ、そういった"役に立つ情報"を掲載した攻略本が次々に発行されるようなり、それが発展し、次々にゲーム雑誌が創刊されるようになり、日本には「ゲーム+紙媒体」がタッグを組む、独自のゲーム文化が誕生することになるのですね。
このようにして、大人が知らないうちに、子供たちの間でゲーム情報が駆け巡っていく様子は、ゲームを知らない大人たちにとっては、かなり奇異なものだったようです。
だからこそ、1988年にはこうしてゲーム情報が書け巡ることをテーマにした小説「ノーライフキング」(いとうせいこう・著)が発売され、話題になったりしました。
いずれにせよ、書籍や雑誌の力もあって、日本中の子供たちの間に、ゲームをより楽しむための"手助け"情報が縦横無尽に駆け巡るようになっていった――というのが、ファミコン時代の日本のゲーム文化の最大の特徴だと、わたしは思います。
日本以外の国では、こういった攻略本市場は、ほぼ誕生していないんですよ。まったくないわけじゃないけれど、本のデザインそのものが、かなり違います。(このあたりも、国によって事情が違うので、断言するのは難しいのですが)
いったん、時代を戻します。
ゲームセンター全盛期、ゲームファンたちの間で情報交換が活発になったとき、それらの情報をまとめた同人誌が作られました。いわば攻略本の先駆的存在です。その同人誌が、いまでは伝説として語られる『ゲームフリーク』です。
知っている方も多いでしょうが、知らない方も、その同人誌の名前から想像がつくでしょう。そうです。この同人誌を作っていた人たちが、いずれゲーム開発者になり、『ポケットモンスター』を生み出すことになります。
ゲームセンターというリアル空間に集い、ゲームを楽しむための情報を交換するのって楽しいよね! と心から感じていた人たちが、いずれ大人になり、ゲームという仮想世界の中でモンスターを交換して楽しむ、という遊びを提案したということですね。
それが全世界の子供たちを夢中にさせる大ヒット作となり、ディズニーの総売り上げを超える巨大市場を生み出したのだ――と考えると、なかなかにエモいですよね。
日本は、なぜ『ポケットモンスター』という凄いゲームを生むことができたのか?
そんな問いに対する答えは、それこそ無限にあるのでしょうが、わたしがそう問われたら、日本は治安がいい国だったから『ポケモン』を生むことができたのだと答えるかもしれません。
みんなで互いに"手助け"しあう。情報を交換しあう。そうやってゲームをプレイするのって楽しいよね、という文化があったからこそ、日本から『ポケットモンスター』は生まれたのではないだろうかと。
さて。話が散らかってしまいましたね。
"手助け"のゲーム史というテーマのコラムは、全2回で終了する予定でいましたが、どうにもまとめきれませんでした。もう一回だけ続きます。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
