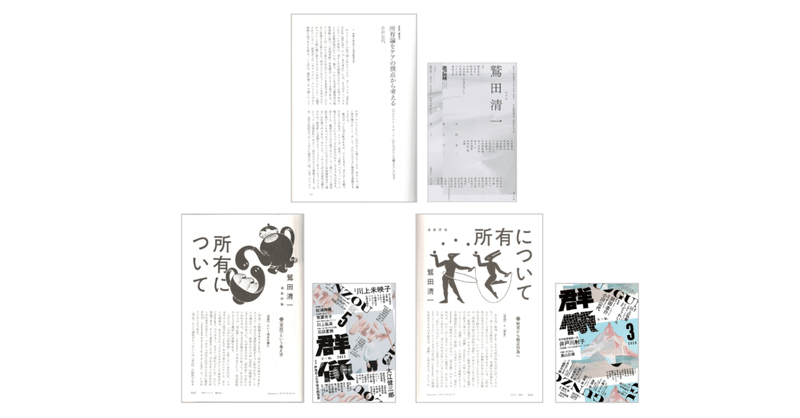
鷲田清一「所有について(群像 2023年3月号/5月号)/小川公代「所有論をケアの視点から考える」(現代思想 2023年5月臨時増刊号 総特集◎鷲田清一)
☆mediopos-3094 2023.5.8
じぶんのもの
ひとのもの
というように
「所有(権)」というのは
自明のことのようだが
決して自明のことではない
鷲田清一によれば
「所有」は両義的であり
「取り替えのきかない譲渡不能な特性、
つまりはあるものの「かけがえのない」あり方」」であるが
「もともと他人への譲渡や交換の可能なもの」でもあるという
所有しているということは
「領界・領空から各人の身体まで」
特定のだれかに「帰属」しているということでもあり
それゆえに譲渡や交換も可能になるのだが
十九世紀フランスの社会主義者
無政府主義の父と言われるプルードンの議論では
「所有とは盗みである」
つまり
「「他者のもの」を横領し、
「わたしのもの」として濫用すること」であり
「みずからは働かずしてそれを詐取ないしは着服すること」
であるがゆえに
所有権が否定されている
「「所有」という事象も「所有権」という概念も、
他のさまざまな事象や概念との、
システマティックな関係の布置によって
はじめてその象りを得る」のであり
人間個人の「才能」といったことにおいてすら
「蓄積された資本であり、それを受け取る者は
その受託者たるにすぎない」というのである
所有しているということは
他との関係において成立しているのであり
決してじぶんだけの世界のなかで
独立して「所有」が成立しているわけではない
じぶんの身体も
臓器移植が行われたりもするように
じぶんが絶対的に所有しているものか
どこからどこまでなのかさえわからない
さらにいえば使っている道具や言葉
そうしたものもそれらは
あくまでも「受託者」として
使っているものであり
むしろそれらは所有している「わたし」よりも
永続的なものであるということができる
その意味でも
「所有(権)」は
その所有の様態によってさまざまではあるだろうが
鷲田清一の示唆しているように
「人びとが「じぶんの所有物」と称しているものは、
じつはその人に託されたもの」であり
「あるものを「じぶんのものとして専有する」のではなく、
まさに「預かっている」」ということだといえる
そしてだからこそ
「そこにはなにがじかの責任が伴う」ことになる
わたしたちの身体もまた
預かったものであり
じぶんの身体を大切にするのも
そこには責任が伴っているからだといえる
鷲田清一の議論にはないがあえていえば
「わたし」が「わたし」であることを
保証しているがゆえに
それだけは「わたし」の所有だといえそうな
心や自我といったものさえも
それらがはたして永続的に所有されるものかどうか
たしかなものではないかもしれない
むしろそこには「所有する者」といった概念を超えた
ありようが存在しているということもできそうである
■小川公代「所有論をケアの視点から考える/
『ロビンソン・クルーソー』から『わたしを離さないで』まで」
(現代思想 2023年5月臨時増刊号 総特集◎鷲田清一―ふれる・まとう・きく―)
■鷲田清一「所有について㉑制度から相互行為へ」
(群像 2023年 05 月号)
■鷲田清一「所有について㉒《受託》という考え方」
(群像 2023年 03 月号)
(小川公代「所有論をケアの視点から考える」より)
「鷲田の説明によれば、「所有」には、取り替えのきかない譲渡不能な特性、つまりはあるものの「かけがえのない」あり方」という意味もあるが、「もともと他人への譲渡や交換の可能なもの」という意味であり、両義的である。」
「「だれかのもの」とは、「だれかの所有物だということ、特定のだれかに「帰属」するものだということである。領界・領空から各人の身体まで、現象的にはおそらくそうである」(鷲田清一「所有について」(『群像』二〇二〇年三月号、一四七頁)。
では、何もかもが「だれかに「帰属」するもの」という認識は普遍的/不変的なのだろうか。いや、そうではないだろう。」
「近代社会の「経済人」が想定する量的な次元での等価交換されるプロプリエテ(=所有、固有性)は幻想であるという鷲田の見地に立って考察してきた。鷲田にとって「愛」というのは、「交通不可能なものを譲渡=所有権剥奪(expropriation)することにとってその多様性を流通させるような、そういう交換」である(鷲田清一『所有と固有』、三六頁)。つまり人間は「交換不可能なみずからの存在の「なんらかの等価物」を示しあうほかない」(同前)。近代社会における「経済人」が見てしまう幻想の外に出るためには、「みずからが与えうるもの」でしか「交換の地平に立つ」ことはできない。鷲田のこのような指摘はまさに、「お茶をいっぱい」差し出すケアの行為に具現されていた。そしてそれは、統一体としての個が解体し、「自と他の境界、身体の内と外が一挙に流動化させられる」契機でもあるのだろう。
近代文学には、自他境界を越えて流れ出し、他なるものを愛しむケアが描かれる瞬間が数多くある。だが、「存在の世話」が発動されるのは、誰かを世話するばかりでなく、自らもケアの対象となることなのかもしれない。」
(鷲田清一「所有について㉑制度から相互行為へ」より)
「《所有〔権〕》の概念の失効ということについては、かつてピエール・ジョゼフ・プルードンが、それが概念としてそもそも不可能なのだと指摘していた。」
「プルードンは〈所有〉をめぐり、一八四〇年の『所有とは何か』でも一八四八年の『貧困の哲学』(・・・)でも、「所有、それは盗みだ!」(・・・)という紋切り型の表現を繰り返している。」
「プルードンによる所有〔権〕の定義は、(・・・)「他者のもの」を横領し、「わたしのもの」として濫用することと、みずからは働かずしてそれを詐取ないしは着服することという二つの契機からなる。そしてそれを理由として、所有〔権〕を否定する。」
「プルードンの議論がわたしたちにより多くの示唆を与えてくれるとすれば、それは「所有とは盗みである」というテーゼとは別に導入された二つの概念によってである。一つは、のちの『貧困の哲学』で提示された「系列」(sèrie)の概念である。プルードンは所有〔権〕について、それを単独の概念、あるいは単独の事象として論じることはできないという。「所有」という事象も「所有権」という概念も、他のさまざまな事象や概念との、システマティックな関係の布置によってはじめてその象りを得るのであって、その布置をプルードンは「系列(セリー)」と呼ぶ。」
「プルードンの言説で注目しておきたいいまひとつの概念は、「受託者」もしくは「用益権者」のそれである。(・・・)プルードンはそこで人間の「才能」について、いかにそれが優れた天性であっても、社会から授かる教育と援助がなければ、あるいは数多くの先行者や手本がなければ開花することはなく、だから個人の「才能」も、「蓄積された資本であり、それを受け取る者はその受託者(dèpositaire)」たるにすぎない」と述べている。」
(鷲田清一「所有について㉒《受託》という考え方」より)
「人びとが「じぶんの所有物」と称しているものは、じつはその人に託された(confiè)ものであるということ。そうした感覚は、あるものを「じぶんのものとして専有する」(s'approprier)のではなく、まさに「預かっている」という感覚である。そして重要なことは、だからそこにはなにがじかの責任が伴うと、つまり「自分に託されたものに責任がある」(・・・)と、いわれていることである。
〈所有〉という関係がじっさいには《受託》の関係であるとすると、当然のこととして所有の主体も「受託者」というポジションに移行することになる。」
「《受託》というこの視点を所有〔権〕論のなかに導入することで、〈所有〉の問題はどのように再設定されることになるのだろうか。」
「さしあたってすぐにそこから導き出される論点は二つある。一つは、あるものを所有していること、つまりはその「所有権」(・・・)を持っていること、つまりは「自由処分権」(・・・)があることとの等値がここでは妥当しないということである。いま一つは、所有する者よりも所有されるもののほうがより永続的に存立するということである。」
「《受託》ということが成り立つのは、所有されるもの、つまりは財産が所有する個人の生の有限の時間を超えているからである。そこでいやでも比較の対象としたくなるのは、手仕事における道具との関係、あるいは表現における言語との関係である。
たとえば大工道具。先輩から譲り受けたものであれ、新調したものであれ、それらを何度もくり返し使うなかで、だれにも軽々しく触れてほしくないし、使ってもらいたくないものになってゆく。その意味では排他的ではある。けれども引退するころになると、たしかに癖があるが、使い込んできたからこそ熟れたそれを、だれかに譲ることも考えるようになる。じぶんの身体の一部になっているそれを手放すのは寂しいものだが、だれかに大事に使ってもらえれば道具を死蔵するよりははるかにいいとも思う。名を継ぐなどの例をあげて述べたのとほぼ同じことが、この道具の場合にも言えそうである。
あるいは言葉。言葉もまたわたしたちが考え出したものではなく、先行する世代から贈られたものである。わたしたちがそれらを口にするなかでじぶんというものを象ってゆく。もちろん、言葉はそれじたいがだれかに用いられなければ存続もしえないが、しかし所有関係とおなじで、使う者よりも使われる言葉のほうがいのちは長い。つまり「永続性」がある。となると、それぞれ独自の流儀やスタイルで表現するわたしたち一人ひとりが言葉の「器」であるわけで、言葉はそういう一人ひとりの使用を機縁として、そうした場面を超えて存続するものであるといえよう。
そのとき、道具を大切にするのも、言葉を大切にするのも、それがじぶんのものだからではなく、まちがいなくみずからの身を養ってきたものだから、そしていずれ別のだれかが使うかもしれないからである。プロパティとは、それぞれの人が事物とのあいだで紡いできた私秘的な関係を護るために、それぞれの人がとるべき公的な責任をさすともいえそうである。そしてさらにそう考えるなら、その先に、この《受託》の「適切さ」(propriety)こそ、 propertyという概念の実質をなすものではないのかとさえ、先走って考えたくなる。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
